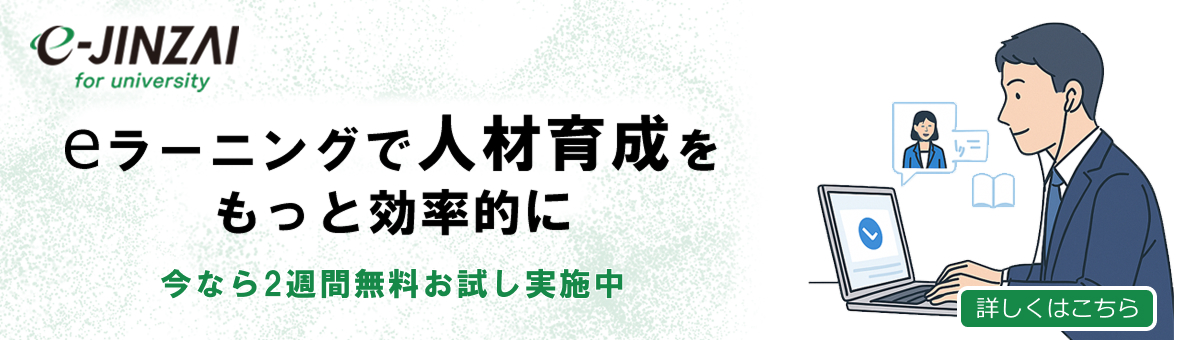【大学職員向け】Z世代学生のコミュニケーションとは

近年、大学における学生支援や教育の現場では、「今の学生」に対する理解がより一層重要になっています。デジタルネイティブ世代として育った彼らは、これまでの学生とは異なる価値観や行動様式を持ち、大学職員との関係性にも新たな課題が生まれています。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世代は、経済的困難、人間関係の希薄化、学習環境の変化など、かつてない困難に直面しました。こうした背景を踏まえ、大学職員としてどのように彼らに寄り添い、支援していくべきかを考える必要があります。
本記事では、大学職員が理解しておくべき「今の学生」の特徴を整理し、それに基づく具体的な対応策とその効果について解説します。
⇒今どき学生とのコミュニケーション術を身に着けるなら『e-JINZAI for university』
目次
今の学生が抱える背景と特徴
コロナ禍がもたらした変化
2020年以降、コロナ禍により多くの学生がアルバイトの機会を失い、経済的に厳しい状況に置かれました。また、サークル活動や学内イベントなどが制限され、人間関係の形成が難しくなったことから、孤立感を抱える学生も増加しています。授業もオンライン化が進み、学修への集中力や健康面に影響を及ぼしました。
その変化は、以下のような側面に表れています。
| 経済状況 | アルバイト減少による収入減、生活費の不足 |
| 人間関係 | 対面活動の減少による友人関係の希薄化 |
| 学修環境 | オンライン授業中心となり、集中力やモチベーション低下 |
安心・安全志向の高まり
このような環境下で育った学生たちは、「安心して過ごせる環境」を求める傾向が強くなりました。挑戦や競争よりも、確実性や安定性を重視する志向が見られ、進路選択や学び方にもその傾向が反映されています。
不確実な社会情勢の中で育ってきたことが、このような志向に拍車をかけています。
学生のコミュニケーションスタイルとは

デジタルファーストの世代
現代の学生は、SNSや動画コンテンツを通じて日常的に情報を収集・発信しています。以下のようなプラットフォームが主な情報源となっています。
- TikTok
- YouTube
- LINEオープンチャット
これらのメディアでは、画像や動画といった視覚的なコンテンツが中心であり、文字よりも「見てわかる」情報が求められます。特にショート動画の普及により、数秒から1分以内で情報を理解するスタイルが一般化しています。
マルチタスキングが日常
スマートフォンやPCを複数同時に使いながら、SNSをチェックし、動画を見ながら課題に取り組むなど、マルチタスキングが日常となっています。
マルチタスキングの特徴と課題は以下の通りです。
| 複数タスクを同時進行 | 情報の見落とし、集中力の分散 |
| 複数デバイスの同時使用 | 学修内容が定着しにくい |
| 効率的なようで非効率な場面 | 優先順位の混乱、スケジュール管理の困難 |
「タイパ」を重視する傾向
「タイムパフォーマンス(タイパ)」とは、かけた時間に対する成果を重視する考え方です。大学職員がメールで長文を送っても読まれないケースが多く、伝える内容をいかに簡潔かつ明瞭にするかが求められます。
【学生が好む情報や対応の傾向】
- 短く、わかりやすいメッセージ
- 結論から先に提示される文章
- すぐに返答があるLINEやチャット
オンラインコミュニティでのつながり
LINEオープンチャットやDiscordなどを活用して、興味・関心でつながるオンラインコミュニティが学生の居場所となっており、以下のような傾向が見られます。
- SNSを通じた匿名性の高い関係に安心を感じる
- 実名・対面での関係は「気疲れする」と感じる傾向
- 対面よりもオンラインの方が自分を出しやすいと感じる
この結果、教職員とのリアルな関係づくりに消極的な学生も増えているのが実情です。
大学職員が直面する課題とは
こうした背景と行動特性を踏まえると、従来の学生対応では対応しきれない新たな課題が発生することになります。大学職員が抱える課題はこれまで以上に多岐にわたることになるのです。
【大学職員の新たな課題】
- メールや掲示での情報提供が届かない
- 対面相談が減り、学生の困りごとに気づきにくい
- レスポンスが遅いと不信感を持たれる
- SNSでの発言が拡散し、対応の内容が評価されやすい
課題を解決するための具体策
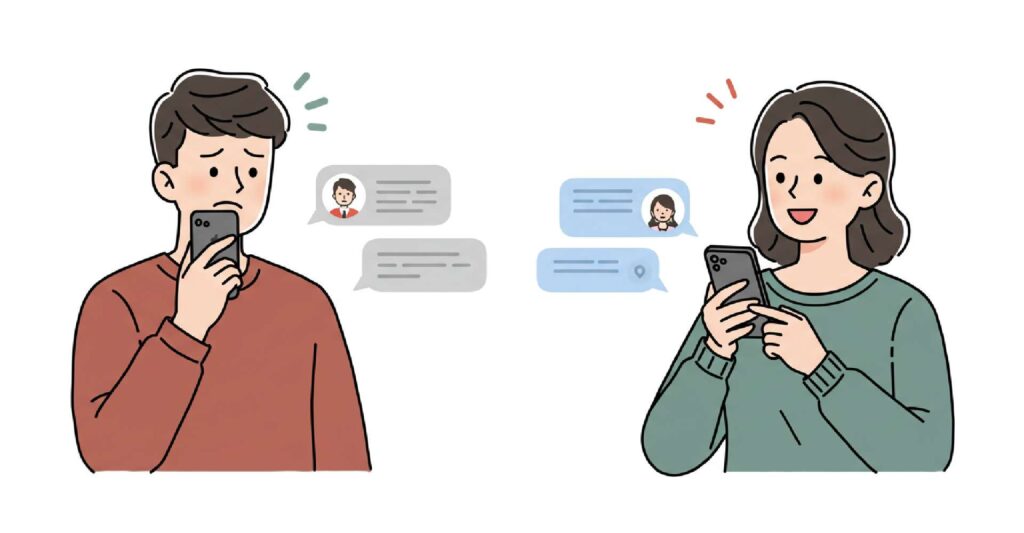
SNSや動画を活用した情報提供
学生の情報収集手段は大きく変化しており、従来の掲示板やメールによる一方的な情報提供では十分に届かないケースが増えています。多くの学生は、日常的にLINEやInstagram、YouTubeといったSNSや動画プラットフォームを利用しており、これらを通じた情報発信がより効果的です。
たとえば、授業のお知らせやイベント情報は、LINE公式アカウントを使って直接通知することで、見落とされるリスクを減らすことができます。また、Instagramを活用すれば、キャンパスの様子やイベントの雰囲気を写真で視覚的に伝えることができ、学生との距離感も縮まります。さらに、キャリア支援や学生生活に関する情報をショート動画にまとめることで、視覚と音声で直感的に伝えることができ、理解度も高まります。
チャットや短文を活用した相談対応
学生との相談には、短文で親しみやすい文面が適しています。以下のポイントに留意しましょう。
- 文末は「!」を使うと印象が柔らかくなる
- ネガティブな連絡は対面か電話で
- 文字数は少なく、わかりやすく
- 内容は第三者が見ても問題ない表現に
対応履歴がSNSで拡散される可能性を意識する必要があります。
デジタルリテラシーの支援
すべての学生が高いITスキルを持っているわけではありません。以下のようなサポートが有効です。
- パソコンや学内システムの使い方を教えるワークショップ
- 利用ガイドを動画やスライドで提供
- 1対1でのフォロー体制を整備
情報格差を減らすことが、支援の第一歩となります。
対面機会の創出と心理的サポート
オンライン授業やリモート生活に慣れた学生の中には、対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ人も少なくありません。しかし、学生の表情や声のトーン、ちょっとしたしぐさなど、非言語的な情報から得られる気づきは、支援の質を大きく左右します。こうした理由から、意識的に対面での交流機会を設けることが、学生理解の第一歩となります。
たとえば、学内イベントや相談会を対面形式で実施することにより、学生が安心して参加できる場をつくることができます。また、日々の対応においては、相手の感情や思考を丁寧に受け止める「積極的傾聴法」を取り入れることで、学生は自分の悩みを言語化しやすくなり、心を開きやすくなります。加えて、認知行動療法の考え方を取り入れることで、学生の中にある思い込みや偏った考えに気づきを促し、前向きな変化をサポートすることが可能になります。
生成AI時代の新たな対応力
生成AIの普及により、学生の学び方や思考方法が変化しています。特にChatGPTなどを活用した「効率的な学習」が注目されています。
大学側が留意すべき点
- AIに頼りすぎないよう、批判的思考を育てる
- 対話型学習を取り入れ、主体的な学習を促す
- AIと人間との役割分担を理解するガイダンスを提供
AI時代に適応した支援を行うには、大学職員自身も継続的な学びが求められます。
課題解決によるメリット
学生支援の現場で起きている課題は、もはや個人の経験や感覚だけで解決できるものではなくなってきています。デジタルネイティブ世代、コロナ禍を経た若者、そして生成AIとともに育つ次の時代の学生たちに向き合うためには、大学職員自身の「アップデート」が必要であり、そのためには、現場に即した研修の導入が不可欠です。研修を受けることでいかのような効果が期待できます。
- 学生対応の質が均質化される
誰が対応しても一定の基準を保てるようになり、学生からの信頼が向上します。 - 教職員間の連携が強化される
共通言語と基本スキルが共有されることで、部署間の連携や引き継ぎがスムーズになります。 - 学生の満足度と定着率が向上する
迅速で的確な支援により、学生は安心して大学生活を送ることができ、離脱リスクも減少します。 - 対応コストの削減につながる
クレームやトラブルの未然防止により、再対応や長期化を防ぎ、業務の効率化が期待できます。 - 職員自身のストレスが軽減する
「どう対応すればいいかわからない」という不安が減り、対応に自信が持てるようになります。
まとめ
「今の学生」は、かつての学生とは異なる価値観や行動様式を持つ新しい世代です。その背景や特性を理解し、彼らに合った方法で関わることが、大学職員としての新たなスタンダードとなりつつあります。
固定観念にとらわれることなく、柔軟に対応を変化させていくことで、学生にとって安心できる学びの環境を提供することができるでしょう。大学職員が「学生の今」に目を向け、支援の質を高めることは、大学全体の魅力や価値を高めることにもつながっていくのです。
e-JINZAIで学生支援スキルを磨く
大学の学生支援部門やキャリア支援部門における担当職員の専門性を磨き上げます。学生支援部門の研修では、日米の学生支援組織と人材育成方法などを学びながら、学生支援担当職員の専門職能を開発することができます。キャリア支援部門の研修では、キャリア支援のデジタライゼーションやオンラインキャリアカウンセリングなどの先進事例などを学びながら、大学のキャリア支援のスペシャリストを育成することができます。
2週間無料お試しはこちら