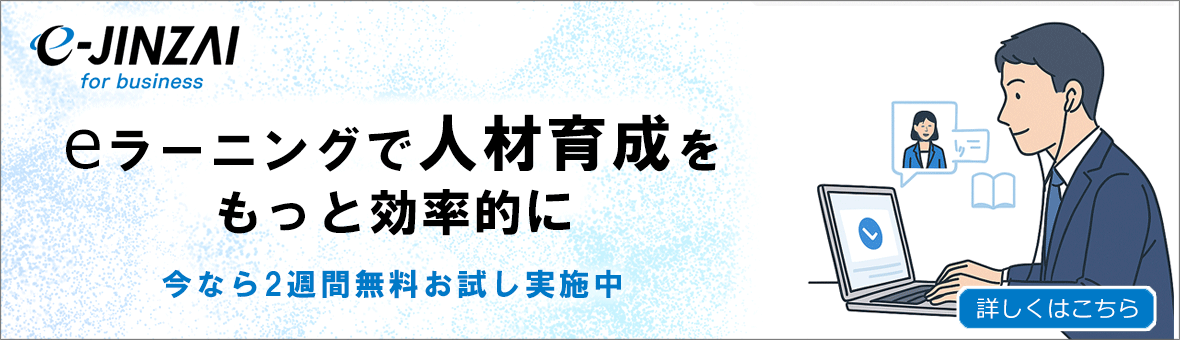戦力化が遅い…その原因は人材育成のズレ?

「新入社員が自立しない」「中堅社員が伸び悩んでいる」「管理職なのに頼りない」──そんな現場の声に、人事として心当たりはありませんか?
育成の必要性は感じているものの、現場の任せきり、もしくは内容が役割とズレていて、社員が求められる力を十分に身につけられていない。結果として、いつまでも戦力化できず、企業としての成長スピードにブレーキがかかっている――。そんな課題を抱える企業は少なくありません。
本記事では、「役割に応じた力を着実に育てる」ことをテーマに、階層ごとに構成された実践型研修の活用方法をご紹介します。現場の育成負担を軽減しつつ、社員の成長を加速させる仕組みを、人事主導でどう整えるか。実例やメリットを交えながら、現実的な解決策をご提案します。
⇒ 戦力化が遅れていませんか?階層別研修で“育てる力”を整える『e-JINZAI for business』
目次
社員が育たない企業の共通点とは

社員がなかなか育たず、戦力化までに時間がかかる。その背景には、多くの企業に共通する育成の問題があります。それは「一人ひとりに合った育成ができていない」「育成が現場任せになっている」「指導が属人的で再現性がない」といった構造的な課題です。人事が全社的な育成の方針や仕組みを持たず、現場の裁量に任せてしまっているケースは非常に多く見られます。
人が辞める会社に共通する特徴
社員が辞める理由の多くは「成長の実感が持てない」「期待されていない」といった感覚に起因します。特に若手社員にとって、自分がどのように評価され、どのようなキャリアパスを歩めるのかが見えない環境では、将来を社内に見出すことができません。また、目の前の業務をこなすだけでフィードバックもなく、「何のために働いているのか」が不明確になると、モチベーションも低下します。
育成が現場任せになっている危険性
OJTに依存した育成体制では、教える側のスキルや経験により育成の質にばらつきが生じます。結果として、同じ社内でも育つ人・育たない人の差が広がり、「優秀な上司のもとでしか育たない」という属人的な組織になってしまいます。人事としては、育成計画やフォロー体制を整え、現場と連携しながら仕組みとして人を育てる体制を構築することが重要です。
育成の質が会社の未来を左右する理由

研修を実施しているのに成果が見えない。社員が成長している実感が持てない。こうした育成の“空回り”状態に陥っている企業では、多くの場合、「誰に・いつ・何を育てるべきか」が明確になっていません。
特に重要なのは、役割や成長段階に応じて適切な学びを提供できているかという点です。たとえば、新人には基本的な仕事の進め方と社会人としての姿勢、中堅にはリーダーシップやチームへの貢献、管理職にはマネジメントと育成の力が求められます。
しかし実際には、それらが混同され、一律の研修を行ってしまうことで、社員が「自分にとって必要な学び」を受け取れないケースが多々あります。
育成の質を高めるとは、「求められる役割に応じたスキル・マインドセットを、適切なタイミングで提供する」ことです。それができれば、社員はスムーズにステップアップし、組織内で自信と責任を持って行動できるようになります。このような視点に立った研修設計こそ、企業の競争力を高め、長期的な成長を支える人材基盤をつくる鍵となるのです。
現場の悩みを解決する研修プログラムとは
「現場では頑張っているのに、なかなか育たない」「どこまで何を教えればいいのかわからない」――そんな悩みを抱える人事やマネージャーにとって、階層ごとに最適化された実践型研修は大きな助けになります。
本章では、新入社員からリーダー層まで、役割ごとに必要なスキルを体系的に身につけられる研修プログラムについてご紹介します。
新入社員向け研修で「定着率アップ」
新入社員には、ビジネスマナーや業務理解に加えて、社会人としての基本姿勢やコミュニケーション力の育成が重要です。本研修では、実践的なワークやロールプレイを通じて学びを深める構成となっており、主体的な振り返りを促すことで、定着と早期戦力化を支援します。成長実感を得られることで、離職率の低下にもつながります。
中堅社員向け研修で「即戦力化」
中堅社員はプレイヤーからリーダーへとステップアップする過渡期にあり、役割変化への対応が求められます。この研修では、対人スキルや自立的な思考力を育成し、組織内での影響力を高める力を養います。自身の強みや課題を見つめ直すワークを通じ、実務への応用力も強化されます。
管理職研修で「組織力強化」
管理職には、成果を上げるだけでなく、部下を育て、チームを牽引する力が求められます。この研修では、1on1の進め方や効果的なフィードバック手法など、実務に直結するスキルを習得。ケーススタディ形式で行動変容を促し、安定したマネジメントを支える力を育てます。
リーダー研修で「変革推進」
変化の激しい時代において、リーダーには先を見据えて組織を導く視座が求められます。本研修では、戦略思考や課題解決力を中心に、次世代リーダーに必要なマインドと行動力を養成します。実践的なワークを通じ、変革を推進する力を現場で発揮できるようにします。
研修を導入することで得られるメリット
育成を外部に委託することに対して、「コストがかかる」「自社の実情に合わないのでは」と不安を感じる人事担当者の方もいるかもしれません。しかし、体系的な研修サービスを活用することは、単に“教える手間を省く”ための手段ではありません。人事主導で戦略的な人材育成を行うための、大きな武器になります。
ここでは、研修を導入することで得られる具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。
属人的な育成からの脱却
育成が現場任せになっていると、上司の経験やスキルによって指導の質が大きく変わってしまい、育つ社員・育たない社員の差が生まれやすくなります。特定の人物に依存した育成体制では、部署間でスキルギャップが広がり、組織全体の底上げが難しくなります。こうした状況を解消するためには、育成方針や教育内容を標準化し、誰が教えても同じレベルの成果が出せるような育成の仕組みづくりが欠かせません。
人事主導でも継続できる育成体制の構築
育成が一時的な取り組みで終わってしまうと、社員の成長は止まり、組織としての成長も頭打ちになります。継続的に育成を行うには、人事主導で全体を見渡し、長期的な計画のもとで育成設計を行うことが必要です。研修の企画、実施、フォローアップまでを一貫して管理できる体制が整えば、現場の協力も得やすくなり、育成文化が社内に定着します。研修が仕組みとして回ることで、人事としても負担を分散させながら効果的な育成が可能になります。
マネジメント層の育成負担を軽減
マネージャーは日々の業務に加えてメンバー育成も担っているため、時間や労力の制約から「教えたいけど教えられない」という声も多く聞かれます。外部研修を活用することで、育成の一部をプロに任せ、負担を軽減することができます。特に、1on1の進め方や部下へのフィードバックの仕方など、実践的な内容を補うことで、マネージャーが自信を持って育成に取り組めるようになり、組織全体のマネジメントレベル向上にもつながります。
まとめ
社員の成長を支える育成体制の構築は、人事にとって重要な経営課題です。特に、役割に応じた力が身につかず、戦力化が遅れている現状は、多くの企業で共通する悩みといえます。
属人的なOJTでは限界があり、育成を仕組みとして整えることが必要です。階層別に最適化された実践型研修を取り入れることで、役割ごとの成長課題に対応でき、現場任せだった育成も標準化されていきます。
社員が「育つ実感」を得ることは、定着率やエンゲージメントの向上にもつながります。
育成を仕組み化し、誰もが育てられる組織へ――。その第一歩として、今こそ研修の見直しを検討してみてはいかがでしょうか?
育成に行き詰まりを感じている人事の方へ
社員が育たない、定着しない──その原因は「一律」の育成にあるかもしれません。 本研修は、新入社員からリーダー層まで階層ごとに最適な学びを提供し、実務に直結するスキルを着実に育てます。個別対応が難しいと感じている今こそ、人事主導で育成を仕組み化するチャンスです。 成長実感を生む本当に使える研修『e-JINZAI』を、まずは無料で体験してみませんか?
2週間無料お試しはこちら