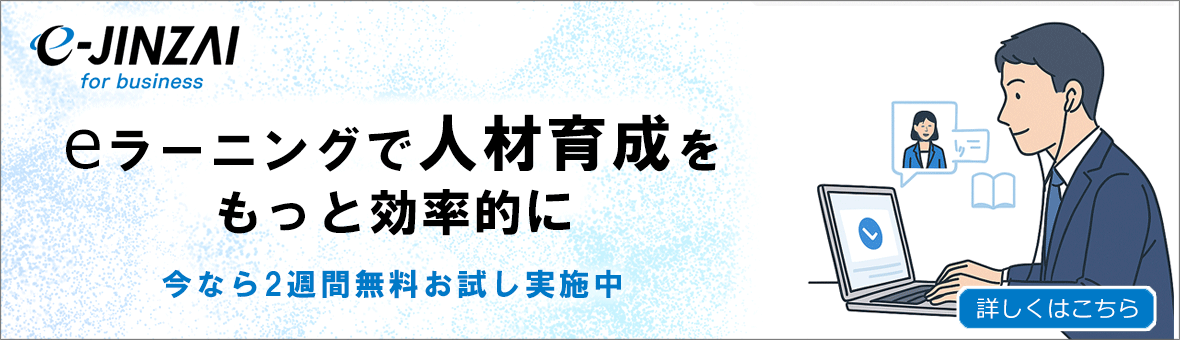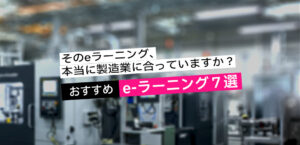通勤手当の支給規定とは?交通手段別の基準や注意点を徹底解説

KEYWORDS 経理
通勤手当は、労働基準法には具体的な規定がなく、企業の裁量に委ねられています。従業員が納得し、企業側の負担も過度に重くならないよう、通勤手当に関する明確なルールを設けることが必要です。
本記事では、人事部・経理部担当者の方向けに、通勤手当の基本的な仕組みや交通手段別の支給基準、注意すべきポイントを解説します。
⇒ 「e-JINZAI for Business」の経理部門向け研修はこちら
目次
通勤手当とは?労働基準法上の取り扱い

通勤手当とは、従業員が職場へ通勤する際にかかる移動費用を企業が負担する制度です。通勤手当は当然支給されるものと認識されることもありますが、実は労働基準法には規定がなく、企業に支給の義務はありません。通勤手当の有無や内容は、各企業の判断に委ねられています。
ただし、法律上は支給しなくても違法にはならないものの、福利厚生の一環として導入する企業が一般的です。従業員満足度の向上や採用時のアピールポイントとなるため、多数の企業が通勤手当を取り入れています。
通勤手当を支給するにあたり、就業規則や雇用契約書などにルールを明記しておくことが重要です。交通手段や通勤距離、支給額の上限、申請方法などを定めることで、従業員とのトラブル防止につながります。また、テレワークを導入する企業のなかでは、出社日数に応じて通勤手当を減額し、代わりに在宅勤務手当として支給するケースもあります。自社の勤務実態に即した通勤手当の規定を整備し、適切に運用することが重要です。
通勤手当の規定を作成する際のポイント
通勤手当に関する規定を整備する際は、支給基準や交通手段ごとの取り扱いについて具体的に定めておきましょう。通勤手当のルールを作るうえで押さえておきたいポイントをご紹介します。
通勤手当の基本的なルールの決め方
通勤手当の規定を整備する際には、支給要件や金額、申請方法などを明確にしておくことが大切です。以下のような項目を盛り込むことで、支給ルールが明確化され分かりやすくなります。
- 基本的な支給要件
- 交通手段別の取り扱い
- 支給金額の算出方法と条件
- 通勤手当支給申請の方法
- 通勤手当の変更・見直しルール
まず、通勤手当を支給する際には、「自宅から職場まで〇km以上で支給対象とする」「中途入社や退職時は日割りで支給する」といった支給基準を明確にしておきましょう。
さらに、利用可能な交通手段についても記載します。例えば、「電車・バスのみ支給対象とする」「徒歩や自転車通勤には支給しない」「マイカー通勤は原則禁止」といったルールを事前に定めておくことがポイント。新幹線を利用する長距離通勤が想定される場合には、別途上限額を設定するケースもあります。
支給方法には「一律支給」と「実費(全額)支給」があります。一律支給は管理がしやすい反面、実際の交通費と差が出る場合に不公平感が生じることがあります。一方、実費支給は従業員ごとの通勤ルートに応じて金額を決定するため公平性は高いものの、管理の手間やコストが増える点に注意が必要です。
バスの通勤手当
バス通勤を認める場合は、支給対象や条件をあらかじめ明確にしておきましょう。バスは電車に比べて短距離の利用が多い傾向にあり、通勤手当の支給にあたっては一定の距離や条件を設けるのがおすすめ。例えば、「自宅~自宅の最寄り駅(会社の最寄り駅~会社)までの距離が2km以上ある場合にバス利用を認める」などと決めておきましょう。
バスの通勤手当の支給方法としては、1か月・3か月・6か月定期などの定期券料金を基準に実費支給するのが主流。上限額を定めておくことで、会社側の負担を減らすことが可能です。
自動車・バイクの通勤手当
自動車・バイクでの通勤手当は、支給を認めると従業員の利便性が上がる一方で、交通事故のリスクが伴う点に注意が必要です。万が一従業員が事故を起こした場合、使用者責任として会社にも損害賠償責任を問われる可能性があります。自動車・バイク通勤による支給を認める場合は、運転免許証や自動車保険証券の写しの提出を依頼しましょう。また、自動車やバイクを置くための駐車スペースを確保するためのコストがかかる点にも留意してください。
通勤手当の算出方法には、ガソリン代をもとに計算する方法と、走行距離をもとに計算する方法があります。燃費による計算方法は車種に依存するため、走行距離に応じた支給が一般的です。走行距離で計算する場合、片道距離×距離単価×勤務日数×2(往復分)といった算出方法で求められます。
自転車の通勤手当
自転車通勤は、基本的にはガソリン代や公共交通機関の運賃が発生しないため、支給しない企業があります。しかし、雨天時に公共交通機関を利用する際の費用負担を軽減するため、自転車通勤者にも通勤手当を支給するという企業も存在します。通勤手当を支給する場合、「自宅から職場までの距離が2km以上」などの条件を設け、距離に応じて計算する方法や、距離に関わらず一律で支給する方法などがあります。
ただし、自動車・バイク通勤と同じく、事故のリスク管理や駐輪スペースの確保が必要です。違法駐輪すると近隣に迷惑をかけてしまうため、従業員には決められた駐輪場に留めるよう指導しましょう。また、賠償責任保険への加入を推奨する、事前申請による許可制にするなどの対策をとることも検討が必要です。
通勤手当を支給する際の注意点

通勤手当に関するルールを策定・支給するときの注意点をご紹介します。
通勤手当は所得税の課税対象(非課税額あり)
通勤手当は、労働基準法上で賃金として取り扱われるため、所得税の課税対象となります。ただし、所得税法では「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で通勤する際の通勤手当が1ヶ月あたり15万円までの場合、非課税であると定められています。例えば、1ヶ月あたりの電車運賃が5万円なら全額非課税です。
注意しておきたいのが、マイカーやバイク、自転車などで通勤している場合。1ヶ月の非課税限度額は一律15万円ではなく、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が異なります。
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの非課税限度額 |
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
通勤距離が2km未満の場合は全額所得税が課税されるため、通勤手当として支給しない企業が多くあります。
通勤手当は社会保険料の計算対象
通勤手当は、たとえ所得税で非課税となった場合でも、社会保険料を計算する際には全額計上する必要があります。公共交通機関の利用で1ヶ月15万円以下であっても、社会保険料の計算には算入するため混同しないように注意しましょう。
なお、営業や出張など業務にかかった「交通費」は、所得税・社会保険料のどちらとも対象外です。
雇用形態に関係なく公平な支給を意識
通勤手当は、雇用形態に関係なく支給されるべき手当です。正社員と非正規社員(パート・アルバイトなど)が同じ業務を行っているにもかかわらず、通勤手当に差があるのは不合理な待遇とされます。
2020年4月に施行された「同一労働同一賃金制度」では、こうした不合理な格差が禁止されており、厚生労働省のガイドラインにおいても、同一の支給を行わなければならないと示されています。
なお、所定労働日数に応じた通勤手当の支給方法(例:定期代相当額の支給/日額交通費を出勤日数に応じて支給)については、勤務実態に応じた合理的な区別とされ、差別的な扱いには該当しません。
通勤手当の不正受給を防ぐための対策
通勤手当の不正受給を防ぐには、申請内容の確認を徹底することが重要です。例えば、実際にはマイカーや自転車、徒歩で通勤しているにもかかわらず、公共交通機関を利用していると偽って申請し、不正に手当を受け取るケースも見られます。
このような不正を防止するためには、申請時に通勤経路や手段、距離をしっかりと把握することが重要です。インターネットの地図アプリや経路検索ツールを活用すれば、通勤距離や交通費の目安を簡単に把握できます。また、定期券や回数券のコピーなど、通勤手段を証明できる書類の提出を求めるルールを設けるのも有効です。
さらに、通勤手当の内容が実態と合っているかどうか、年に1回程度の定期的な見直し・確認を行うのも効果的です。引っ越しによる交通手段の変更など、通勤状況が変わるケースは少なくありません。実態との乖離を防ぐためにも、定期的な確認体制を整えておくことが望ましいでしょう。
まとめ
通勤手当は、労働基準法上では支給は義務付けられておらず、企業の裁量によって決まります。従業員とのトラブルを防ぐためにも、交通手段の取り決めや申請方法などの詳しい規定を設けることが重要です。また、通勤手当の支給内容について、アルバイト・パート・正社員など雇用形態で分けることは禁止されています。通勤手当を正しく支給するためにも、年1回など定期的なチェックを行うのがおすすめです。記事をもとに、通勤手当の支給基準策定や見直しの参考にしてみてください。
経理部門『基礎』研修
e-JINZAI for Businessの経理部門『基礎』研修は、経理部門に配属・異動されて間もない方を対象に、経理パーソンとして必ず知っておかなければならない基礎的知識・スキルを習得するための研修です。簿記の基本から社保・労保の基礎知識まで、動画でわかりやすく学ぶことができます。
2週間無料お試しはこちら