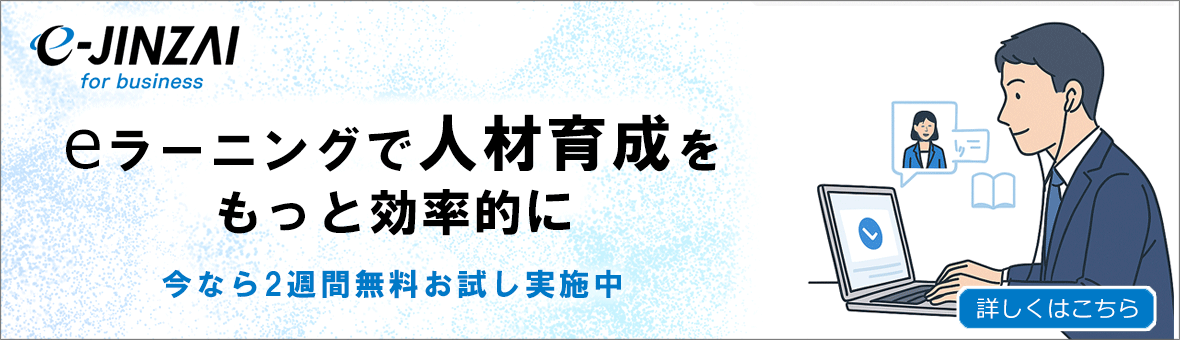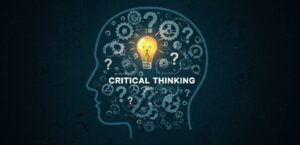リスキリングとは?リカレント教育との違いや助成金を紹介

近年、デジタル化や働き方の多様化が進むなかで、注目を集めているのが「リスキリング」という考え方です。社会やビジネス環境の変化に合わせて、新たなスキルを身につけることは、企業・個人のどちらにとっても欠かせない取り組みとなっています。
本記事では、リスキリングとは何か、リカレント教育との違い、さらには活用できる助成金制度について分かりやすく解説します。
目次
- リスキリングとは?
- リカレント教育との違いとは?
- なぜ今リスキリングが注目されるのか?
- 企業にとってのメリットと課題
- リスキリングの事例
- リスキリングに活用できる主な助成金
- リスキリングを成功させるためのポイント
- まとめ:リスキリングはこれからの働き方の鍵
リスキリングとは?
リスキリングとは、職業能力の再構築、すなわち「新たな業務に対応するために必要なスキルを学び直すこと」を意味します。単なるスキルアップではなく、業務の変化や再配置に対応するための“新しいスキルの獲得”に重点が置かれているのが特徴です。
特に近年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの発展など、テクノロジーの変化にともなって、企業が従業員に新しい業務を任せるケースが増えてきました。リスキリングは、そうした変化に対応する手段として期待されています。
例えば、製造現場の従業員がIT部門に異動する場合、プログラミングやデータ分析のスキルが新たに必要になるといった場面が考えられます。
リカレント教育との違いとは?
似た言葉としてよく使われるのが「リカレント教育」です。どちらも「学び直し」に関する用語ですが、目的やタイミングに違いがあります。
リカレント教育は“キャリアの再設計”
リカレント教育は、学校教育を終えた社会人が、仕事と学習を繰り返す生涯教育の考え方を指します。大学院に通ったり、資格取得のために学習することが含まれ、個人のキャリア形成や再スタートを目的とすることが多いです。
一度仕事を離れて学業に専念するスタイルも多く、自発的かつ中長期的な視点でスキルアップを図ることが特徴です。個人が「なりたい自分」に近づくための、柔軟で主体的な学びと言えるでしょう。
リスキリングは“職場内での再教育”
一方でリスキリングは、現在の職場環境や組織のニーズに応じて、新たな業務を担えるようにするための再教育です。個人の意思で始めるというよりは、企業が主導して従業員に対して実施するケースも多く、より実務に直結した内容になります。
たとえば、事務職からデジタルマーケティング担当へ、製造ラインからデータ分析チームへといった「役割の転換」が前提となることもあります。即戦力として新しいポジションで成果を出せるよう、スピード感のある研修が求められる点も特徴です。
なぜ今リスキリングが注目されるのか?

日本政府もリスキリングの推進に力を入れており、岸田政権が掲げた「人への投資」政策でも大きく取り上げられています。背景には、少子高齢化による労働人口の減少、産業構造の変化、そして技術革新による雇用の変化があります。
中でもDXに対応できる人材が不足している現状は、多くの企業にとって深刻な課題です。業務の自動化やAI活用が進む一方で、それを扱えるスキルを持った人材が不足しているため、社内でのリスキリングによる人材育成が必要とされています。
また、キャリアの長期化も理由の一つです。定年延長や再雇用の流れの中で、一つのスキルだけではキャリアを築きにくくなっており、複数の分野で活躍できるスキルの幅が求められています。
企業にとってのメリットと課題
組織力の強化と人材の流動化への対応
企業が従業員に対してリスキリングを実施することにより、人材を新たな成長分野へ適応させることが可能になります。これは、外部からの人材確保に比べてコストを抑えながら、即戦力として活用できるという点で大きなメリットです。
さらに、自社の業務や文化を理解している従業員を内部で育成することで、業務の引き継ぎや組織の一体感が維持されやすいという利点もあります。部門間の連携を促進し、イノベーションを生む土壌にもつながるのです。
また、従業員のキャリアアップ支援としての側面もあるため、モチベーション向上や定着率の改善にもつながります。成長機会を与えることで、企業に対する信頼感やエンゲージメントも高まり、優秀な人材の流出防止にも貢献します。
課題は「時間」と「継続性」
一方で、日々の業務をこなしながら新たなスキルを学ぶには、時間やエネルギーの確保が難しい場合があります。短期的には生産性の低下を招くリスクもあり、研修制度や学習環境の整備が企業側に求められます。
業務とのバランスを保ちつつ、負担にならない学習スケジュールを設計することがポイントです。例えば、短時間で完結するマイクロラーニングや、業務時間内に学習できる「ラーニングタイム制度」の導入が有効です。
また、継続的な動機づけがなければ学習は中断されがちです。目標設定や進捗管理、評価制度との連動など、制度的な支援とフォロー体制の構築も不可欠となります。
リスキリングの事例
実際に企業がどのようにリスキリングを進めているのかを知ることで、自社での導入イメージが具体化しやすくなります。ここでは、業種や目的が異なる3つのリスキリング事例をご紹介します。
製造業からデジタル分野へのシフト
ある大手製造業では、生産ラインの自動化に伴い、従来の機械オペレーターを対象に、データ分析やIoTに関する基礎知識を身につけるリスキリングを実施しました。
座学だけでなく、現場でのハンズオン研修も取り入れることで、実務に直結したスキルを短期間で習得。従業員は新たな業務にスムーズに移行し、生産性向上にもつながりました。
小売業におけるDX人材の育成
ある大手小売チェーンでは、店舗スタッフを対象に、デジタルマーケティングやECサイト運用のスキルを学ぶプログラムを導入しました。
リスキリングにより、現場スタッフが顧客データを活用して販促を行うようになり、オンラインとオフラインの連携が強化。売上の底上げと従業員のキャリアの選択肢拡大という成果を得ました。
IT企業における非エンジニアの技術習得
IT企業では、営業や人事部門などの非エンジニア職向けに、プログラミングやデータリテラシーの研修を実施。業務理解の精度が向上し、エンジニアとの連携がスムーズになりました。
これにより、プロジェクトの進行スピードが改善されるだけでなく、従業員が自発的に新しい業務へ挑戦する風土が醸成されました。
リスキリングに活用できる主な助成金
日本では、リスキリングを支援するさまざまな助成制度が用意されています。以下は代表的なものです。
人材開発支援助成金
厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金」は、企業が従業員に対して職業訓練を行う際にかかる経費や賃金の一部を支援する制度です。
特に「人材育成支援コース」や「特定訓練コース」は、デジタル技術に関する訓練に対して助成対象となることが多く、リスキリング目的の研修にも活用されています。
事業展開等リスキリング支援コース(2023年度創設)
新たな事業分野へ展開する際に、社員の再教育が必要な企業を対象とした制度です。
訓練経費や受講中の賃金の助成に加え、社外研修を活用する場合にも補助が出るため、中小企業にも利用しやすい制度となっています。
リスキリングを成功させるためのポイント

学ぶ内容は“今”と“将来”に直結したものを選ぶ
業務に直結しない学びでは、せっかく時間を使っても効果が見えにくくなります。現在の業務に役立つか、あるいは将来の異動やキャリアアップにどう活かせるかを意識した設計が必要です。
学ぶテーマが明確であれば、モチベーションも維持しやすくなります。たとえば、営業職がデータ分析やマーケティングの基礎を学ぶことで、提案力や戦略的思考が養われるといったように、実践とのつながりをイメージさせることが鍵です。
自主的な参加を促す環境づくり
企業主導のリスキリングであっても、社員本人の納得感がなければ効果は上がりません。「なぜこのスキルが必要か」「学ぶことでどのように仕事が変わるか」を丁寧に伝え、目的を共有することが重要です。
また、評価制度と連動させることで、学ぶことが昇進や評価につながるという明確な動機付けになります。上司からの積極的な声かけや成功事例の共有など、「やってよかった」と思える空気づくりも大切です。
学習方法は多様に取り入れる
対面研修やオンライン講座、eラーニングなど、学習スタイルは柔軟に選べる時代です。忙しい社会人でも続けられるよう、スキマ時間に学べるツールの導入や、学び合う文化を社内に根付かせる工夫も求められます。
たとえば、10分程度で完結する動画教材や、移動中に聴ける音声コンテンツなどは、手軽に学習を継続する手段として有効です。社内SNSやチャットツールを活用し、学習内容の共有や質問がしやすい仕組みを整えると、学びが活性化します。
⇒ eラーニングを活用したリスキリングは「e-JINZAI for Business」
まとめ:リスキリングはこれからの働き方の鍵
リスキリングは、一時的なトレンドではなく、これからの働き方や組織づくりにおいて「当たり前の取り組み」になっていくでしょう。
変化の激しい社会において、常に新しいスキルを取り入れ、柔軟に適応していく力が、企業にも個人にも求められています。
リスキリングは負担ではなく、自分のキャリアを自分で選び取るための武器でもあります。助成金などの制度も活用しながら、無理なく継続できる形で取り組んでいきましょう。
eラーニングで新たなスキルを身につけませんか?
DX人材の需要や時代の変化に伴い、リスキリングの必要性が高まる昨今。eラーニンングサービスの「e-JINZAI」はスマホがあればいつでも・どこでも好きな時に受講ができます。約20,000本の動画の中から、あなたのキャリアプランに合った学習ジャンルを見つけてください。
2週間無料お試しはこちら