研修は本当に必要?目的や形式、人材育成を成功させるポイントを解説

企業における「人材育成」は、事業の持続的成長を支える重要な経営課題です。その中心的な手段として位置づけられるのが「研修」です。しかし近年、「研修は本当に必要なのか」「成果につながっているのか」と疑問を持つ企業も少なくありません。
本記事では、研修の必要性を改めて整理し、効果を最大化するための設計ポイントや形式の選び方について詳しく解説します。
目次
企業が人材育成で研修を実施する理由

企業が研修を行う背景には、単なるスキルアップ以上の目的があります。研修は、組織文化を醸成し、個人の成長を通じて企業価値を高める「戦略的人材投資」として位置づけられています。
変化するビジネス環境への対応
市場やテクノロジーの変化が激しい現代では、数年前の知識やスキルがすぐに陳腐化します。そのため企業は、社員に対して「常に学び続ける姿勢」を求めざるを得ません。研修を通じて最新の知見や考え方を吸収することで、変化に対応できる柔軟な組織づくりが可能になります。
社員の成長が組織の競争力を高める
社員一人ひとりが専門性を高め、主体的に行動できるようになると、結果的に組織全体の生産性や創造性が向上します。研修は、知識を与える場ではなく、成長を促す「きっかけの場」として機能します。この意味で、研修は経費ではなく投資として捉えるべきものです。
研修の主な種類と目的
一口に研修といっても、その目的や対象によって内容や進め方は大きく異なります。ここでは、企業で一般的に行われている研修をタイプ別に整理し、それぞれの特徴や活用ポイントを見ていきます。
階層別研修
階層別研修は、新入社員・中堅社員・管理職など、役職やキャリア段階に応じて設計されます。
- 新入社員研修:社会人としての基本マナーや組織理解
- 中堅社員研修:後輩育成やリーダシップの強化
- 管理職研修:マネジメントや戦略的思考の醸成
階層別に体系立てることで、社員が成長段階に応じたスキルを身につけられます。
目的別研修
課題解決を目的としたテーマ別の研修です。即効性が高く、現場課題の改善に直結する点が特徴です。
【目的別研修 テーマ一例】
- コンプライアンス研修
- コミュニケーション研修
- ハラスメント研修
- チームビルディング研修
- ロジカルシンキング研修
- アンガーマネジメント研修
- Excel研修
- DX研修
選抜型・公募型研修
ハイパフォーマーや次世代リーダー候補を対象とした選抜研修、または希望者が自ら応募できる公募型研修もあります。主体性を引き出し、キャリア志向を醸成する手法として注目されています。
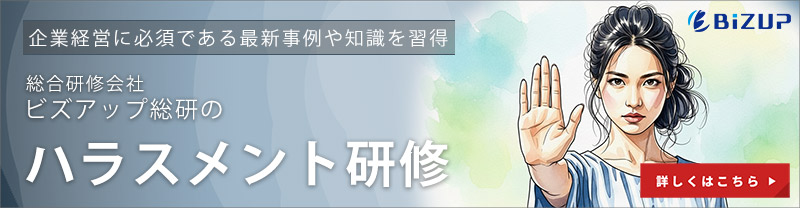
研修の形式とそれぞれの特徴
目的や受講者の属性に応じて、最適な研修形式は異なります。以下では、代表的な形式とその特徴を紹介します。
講師派遣型研修(集合研修)
社内に講師を招き、対面形式で実施する伝統的なスタイルです。グループワークや討議を通じて、受講者同士の相互理解を深められます。チームビルディング効果が高い一方で、日程調整やコスト面の負担が課題です。
eラーニング(オンライン研修)
時間や場所を問わず受講できる利便性が魅力です。動画・テスト・シナリオ教材などを活用し、繰り返し学習が可能です。ただし、自主的な学習を促す仕組みや進捗管理が不可欠です。
公開講座・外部セミナー
他社の参加者と交流し、幅広い視点を得られる形式です。新しい刺激や他社事例に触れる機会として有効ですが、自社課題に落とし込む工夫が求められます。
OJT(On-the-Job Training)
実務を通じて学ぶOJTは、最も実践的な形式です。現場での経験が直接スキルに結びつく一方、指導者の育成が鍵になります。OJTだけでなく、他形式との併用で体系的な育成を目指すことが重要です。
ブレンデッド型研修(複合形式)
オンラインと集合研修を組み合わせ、学習効果と効率を両立させる方法です。基礎知識をeラーニングで習得し、集合研修で議論・実践を行うなど、段階的学習に向いています。コストパフォーマンスが高く、多くの企業で導入が進んでいます。
研修の効果を高めるための設計ポイント
研修を成功させるためには、内容以上に「設計プロセス」が重要です。目的と成果を明確にし、現場に定着する仕組みを構築することで、学びが実務に活かされます。
効果的な研修を設計するための考え方
研修を企画する際、まず押さえるべきは「研修のゴールを成果(行動変化)で定義する」ことです。単なる知識習得ではなく、「部下指導を自発的に行えるようになる」「顧客対応の質を高める」といった行動レベルの目標を設定することで、内容の焦点が定まり、受講者の実践意欲も高まります。
また、研修内容を現場の課題と結びつけることも重要です。現場の実務に活かせない研修は定着しません。人事部門と現場のマネージャーが連携し、今求められているスキル・行動・考え方を明確にすることで、研修の意義が強まります。
さらに、研修は「単発のイベント」ではなく「仕組みとして継続すること」が前提です。フォローアップや評価の仕組みまで含めて設計することで、学びが組織の中に根づき、再現性のある成長を促せます。
成果につながる研修設計の5ステップ
研修設計を具体的に進める際は、以下の5つのステップを押さえておくと効果的です。
| STEP | 項目 | 具体的なアクション |
|---|---|---|
| ① | 目的とゴールを明確化 | 研修の目的を「知識習得」ではなく「行動変化」に設定します。たとえば「部下との1on1を自発的に実施できるようになる」など、成果につながる行動をゴールに据えることが大切です。 |
| ② | 現状と課題を分析 | 対象となる社員のスキルや業務課題を整理し、研修テーマとの関連を明確にします。アンケートや上司面談など、現場の実態把握を通じて真の課題を明確にしましょう。 |
| ③ | 研修内容と手法を設計 | 講義・ワークショップ・ロールプレイなど、学びの定着に適した手法を組み合わせます。最近では、オンライン学習と集合型研修を組み合わせたハイブリッド形式も有効です。 |
| ④ | 実施とフォローアップ | 研修後の行動定着を促すために、上司とのフィードバックや実務での実践課題を取り入れます。実施直後だけでなく、数週間~数か月後のフォローが効果を高めます。 |
| ⑤ | 効果を測定し、改善へ | アンケート・面談・業績データなど複数の指標で効果を測定し、次回以降の研修設計に反映させます。この「設計→実施→評価→改善」のサイクルを継続することで、研修の質が安定し、組織全体の学習力が向上します。 |
まとめ
人材育成において研修は不可欠な手段ですが、目的や設計、形式の選び方によって成果は大きく変わります。
重要なのは、「研修を実施すること」ではなく、「研修を通じてどんな行動変化と成果を生むか」を明確にすることです。自社の課題や社員の特性に合わせ、最適な形式とプロセスを設計することで、研修は真の投資価値を発揮します。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。



