2026年10月からカスハラ対策が企業の義務に:法改正のポイントと実務対応

KEYWORDS ハラスメント
近年、店舗や企業の窓口だけでなく、オンライン上でも過度な要求や暴言などのカスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題として注目されています。厚生労働省は2025年10月、企業にカスハラ対策を義務付ける改正労働施策総合推進法を施行する方針を示しました。
しかし、この法改正は条文が多く、読んだだけではどこから理解すべきか迷う人も少なくありません。本記事では、一般のビジネスパーソンでも把握しやすいように、改正の背景、指針案の内容、企業が取るべき行動を整理して解説します。日常の業務に関係する重要ポイントを中心に、具体的に理解できる構成です。
目次
改正労働施策総合推進法の背景
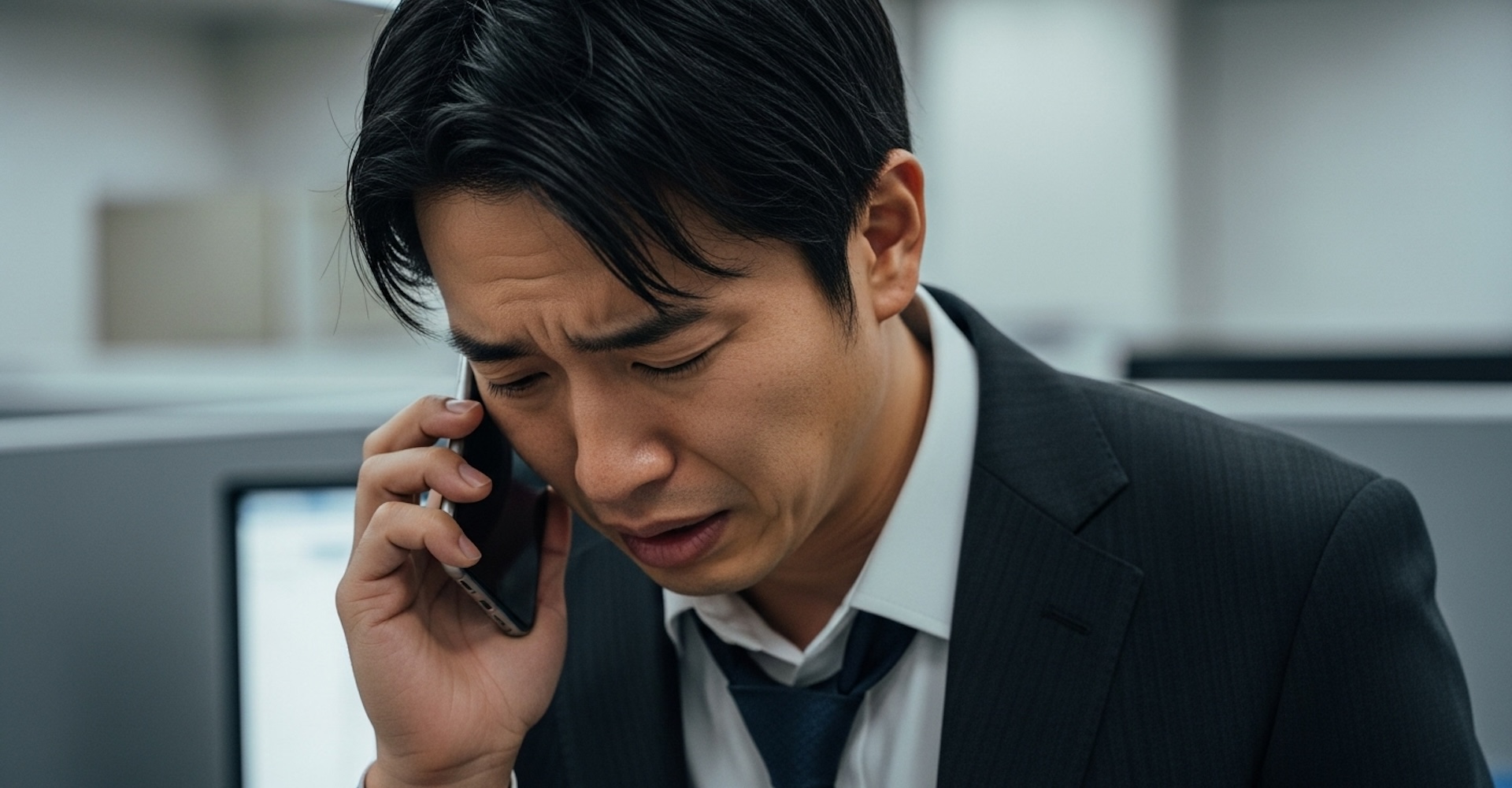
社会問題としてのカスハラ拡大
これまで、職場のハラスメントといえばパワハラやセクハラが中心でした。しかし、厚労省の調査では、接客業・医療・福祉・交通・コールセンターなど、多くの業種でカスハラの被害報告が増加していることが示されています。
さらに、対面だけでなく 電話・メール・SNS を通じても不当な要求や人格否定の言動が発生しており、職場のストレスや離職の原因にもなっています。労働者の健康障害や精神的負担が社会問題化したことを受け、国は今回の法改正に踏み切りました。
2026年10月施行の意味
改正法は 2025年6月11日に公布され、1年6か月以内に施行されるため、厚労省は 2026年10月の施行を予定しています。つまり、企業は2026年秋までに対策体制を整備し、従業員教育を実施する必要があるということです。
改正法で示された「カスハラ対策義務化」のポイント
改正法では、カスタマーハラスメントが 「雇用管理上の措置義務」 として明確に位置づけられました。これにより、企業はパワハラやセクハラと同様に、カスハラについても一定の対策を講じる法的責任を負います。
カスハラの定義
添付された指針(厚生労働省審議会資料)では、カスハラを次の 3 要件をすべて満たすものと定義しています。
- 顧客等の言動であること
- 社会通念上許容される範囲を超えていること
- 労働者の就業環境を害すること
「クレーム=カスハラ」ではなく、正当な申し入れは対象外である点が強調されています。また、障害者が合理的配慮を求める言動などもハラスメントには該当しません。
顧客だけではなく、関係者も含む広い範囲
「顧客等」の範囲には、購入者だけではなく、取引先担当者、広告への問い合わせ者、施設利用者やその家族、近隣住民など企業の事業に関わる多くの人が含まれます。
企業・労働者・顧客すべてに責務が設定
改正法では、企業だけでなく、
- 労働者も他社従業員に対してカスハラを行わない責務
- 顧客等も不当な行為を行わない責務
が定められました。これは「一方的に企業が責任を負う」従来の構図からの大きな変化です。
企業に求められる 5 つの必須措置

改正法に基づき、厚労省指針では企業が必ず講じるべき措置が 5 項目として整理されています。内容をかみ砕いて説明します。
1. 方針の明確化
企業は「カスハラには毅然と対応し、従業員を守る」という方針を明示し、社内報や社内サイト、マニュアルなどで周知する必要があります。
顧客側への掲示も効果的とされており、「ハラスメント行為はお断りします」といった店舗掲示が該当します。
2. 相談体制の整備
従業員が相談しやすいように、窓口の設置や担当者の教育が必要です。
相談内容が「カスハラか判断が微妙」なケースも含め、幅広く対応することが求められています。
3. 事後対応のルール化
相談があった場合、
- 事実確認
- 証拠の確認(録音・録画など)
- 必要に応じ顧客への対応変更
- 被害者のケア
を迅速に行う必要があります。犯罪に該当する場合は警察通報も含まれます。
4. 特に悪質なケースへの抑止措置
たとえば、出入り禁止、サービス提供の停止、警告文の送付など、違法性が高いケースに対応する仕組みを整えることが必要です。
5. プライバシー保護・不利益取り扱い防止
相談した従業員が不利益を受けないよう、就業規則に明記し周知しなければなりません。
特に、性的指向・ジェンダーなどの機微情報の取り扱いには慎重な管理が求められます。


カスタマーハラスメント(カスハラ)の
基礎知識と防止対策のポイント
動画数|3本 総再生時間|94分
近年注目されているカスタマーハラスメント(カスハラ)の基礎知識と、その防止・対応策について学びます。厚生労働省の指針や社会的背景を踏まえ、顧客からの理不尽な言動が従業員に与える影響を正しく理解。具体的なカスハラ事例をもとに、境界線の引き方、対応の基本方針、エスカレーションの判断基準などを整理します。
動画の試聴はこちら現場運用で生じやすい誤解と注意点
カスハラ対策を進める上で、企業や現場が誤解しやすいポイントがいくつかあります。法令や指針の趣旨とずれてしまうと、十分な対策にならないだけでなく、必要な顧客サービスを阻害してしまう場合もあります。
「すべてのクレームがカスハラになる」わけではない
カスハラ対策を考える際に、もっとも誤解が生じやすい点が「クレーム=カスハラ」という認識です。しかし指針では、正当な申入れはカスハラには該当しないと明確に示されています。たとえば、商品に不具合があったために改善を求めたり、説明不足に対して指摘をしたり、サービスの遅れについて理由を尋ねるといった行為は、社会通念上妥当な意見として扱われます。つまり、不満や疑問の表明そのものではなく、「要求の内容や、その伝え方・態度が著しく不当であるとき」に初めてカスハラと判断されるということです。
障害者対応との区別
障害者差別解消法では、障害を理由として不当な差別的取り扱いをしてはならず、必要な合理的配慮を提供する義務が定められています。そのため、障害に伴う困難を取り除くための依頼や、適切な配慮を求める意思表示は、カスハラとはまったく異なる扱いになります。むしろ企業としては、こうした要望に丁寧に応じる必要があります。ここを誤ってしまうと、企業側の不適切対応につながるおそれがあるため、カスハラと合理的配慮の線引きを正しく理解することが重要です。
消費者法制との関係
事業者には消費者契約法をはじめとする多様な法制度のもと、サービスの提供義務や必要な情報を正しく伝える責務が課されています。したがって、顧客からの質問や説明を求める行為を、すべて「迷惑なクレーム」として扱うことはできません。指針はこうした法的責務とのバランスを踏まえたうえで構成されており、カスハラ対策は単に不当行為を排除するだけでなく、企業の「顧客対応力の向上」と不可分であるという考え方が強調されています。
eラーニングによるカスハラ対策の強化
法令の理解や運用ルールの浸透には、従業員教育が不可欠です。特に、下記の理由からeラーニングは効果的です。
実務の「判断基準」を統一できる
カスハラはケースバイケースで判断が難しく、属人的な捉え方になるとトラブルを招きます。eラーニングを通じて、
- どこからが不当行為なのか
- 適切な初動対応は何か
- エスカレーションの基準とは
を組織全体で統一できます。
感情的な場面でも「落ち着いた対応」を促せる
過度な要求や暴言を受けると、従業員は心理的に追い込まれやすく、冷静な対応が困難になります。
教育を通じて対応プロセスを理解しておくことで、動揺を抑え、手順に沿って行動しやすくなります。
法改正後の必須措置に直接貢献する
今回の改正では「方針の周知」「相談体制整備」「事後対応」「抑止策」「従業員保護」が義務化されましたが、これらの運用を支えるのは従業員の知識と理解です。eラーニングは、実務の基盤作りとして最適な手段です。
e-JINZAI lab.のカスハラ対策講座
e-JINZAI lab.の「カスタマーハラスメント(カスハラ)の基礎知識と防止対策のポイント」講座は、近年増加するカスハラを正しく理解し、実務で迷わず対応するために必要な知識を体系的に学べる内容です。厚生労働省が示した指針や社会的背景を踏まえ、カスハラが従業員に与える影響、境界線の考え方、一次対応の基本方針、さらにはエスカレーション判断の要点までを分かりやすく整理。実際の現場で起こりやすい事例をもとに、どこまでが正当な苦情でどこからが不当な言動なのかを見極める力を育て、過剰な我慢や萎縮を防ぐ現実的なスキルを身につけることができます。
さらに本講座では、個人のスキルだけに依存しない「組織的な対応力」を重視しています。管理職や人事が果たす役割、マニュアル整備や相談体制の構築、現場負担を軽減する仕組みづくり、従業員のメンタルケアなど、企業として取り組むべき視点を包括的に解説。職場環境の改善や企業の信頼性向上にも直結する実務型の学びとして、法改正への備えはもちろん、従業員が安心して働ける環境づくりを目指す企業に最適な研修です。
まとめ
2025 年 10 月に施行される改正労働施策総合推進法では、企業にカスタマーハラスメント対策が新たに義務づけられます。
指針では、
- 方針の明確化
- 相談体制
- 事後対応
- 抑止策
- プライバシー保護
など、具体的な要求が詳細に示されています。
カスハラは単なる「迷惑行為」ではなく、労働者の就業環境を害し、離職や健康問題を引き起こす重大な労務リスクです。
同時に、消費者法制や障害者対応とのバランスを踏まえ、正当な申入れとの区別を行う冷静な判断力が求められます。
こうした複雑な要素を踏まえると、従業員が法令と運用ルールを正しく理解するためのeラーニングによる教育は不可欠です。
e-JINZAI lab.などの講座を活用し、企業全体で「安心して働ける環境づくり」を進めることが、これからの組織に求められる姿勢と言えるでしょう。


カスタマーハラスメント(カスハラ)の
基礎知識と防止対策のポイント
動画数|3本 総再生時間|94分
近年注目されているカスタマーハラスメント(カスハラ)の基礎知識と、その防止・対応策について学びます。厚生労働省の指針や社会的背景を踏まえ、顧客からの理不尽な言動が従業員に与える影響を正しく理解。具体的なカスハラ事例をもとに、境界線の引き方、対応の基本方針、エスカレーションの判断基準などを整理します。
動画の試聴はこちら参考資料:職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案 | 厚生労働省
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



