BCP策定の決定版!防災から実務まで網羅する動画研修活用術

「BCP(事業継続計画)を策定したいが、何から手をつければいいのか分からない」 「マニュアルはあるものの、災害時に本当に役立つ自信がない」
多くの企業の総務・防災担当者様が、このような悩みを抱えています。近年、地震や水害だけでなく、感染症リスクやサプライチェーンの分断など、企業を取り巻くリスクは複雑化しています。単なる形式的な書類作成ではなく、「いざという時に本当に動ける計画」が求められているのです。
本記事では、ミネルヴァベリタス株式会社の本田茂樹氏が講師を務めるeラーニング講座の内容をベースに、BCP策定の核心に迫ります。「防災」と「BCP」を切り離さず、車の両輪として学ぶことで、御社の危機管理体制は劇的に強固なものになるはずです。
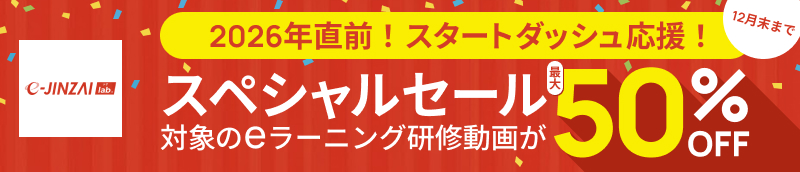
目次
- なぜ今、BCPの見直しが必要なのか
- 【防災編】経営資源を守る「守り」と「代替」の思考法
- 【BCP編】絵に描いた餅にしない!策定の基本ステップ
- 【実践編】サプライチェーン管理と訓練の落とし穴
- 動画で学ぶBCP策定講座:全カリキュラム概要
- まとめ
なぜ今、BCPの見直しが必要なのか
BCPは一度作って終わりではありません。事業環境や想定される被害が変われば、対策もアップデートする必要があります。
被害想定は常に「変わり得る」
過去の想定にとらわれてはいけません。例えば、近年の線状降水帯による豪雨被害や、パンデミックによる出社制限などは、従来の「地震対策中心」の防災計画だけでは対応しきれないケースが増えています。
今回の講座カリキュラムにもある通り、「地震」「水害」「感染症」それぞれで被害の性質は異なります。
- 地震: 突発的破壊。初動の命の安全確保が最優先。
- 水害: 予測可能性がある程度きく。事前の浸水対策や避難判断が鍵。
- 感染症: 人的リソースが長期的に削がれる。出社抑制や代替要員の確保が焦点。
これらに対し、複合的な視点で「被害想定」を見直すことが、実効性のあるBCPへの第一歩です。
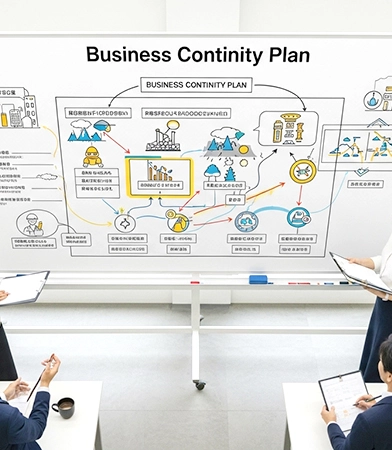

BCP(事業継続計画)の策定と見直しのポイント
動画数|13本 総再生時間|219分
危険物乙4の合格に必要な物理・化学の基礎を体系的に学べる内容です。分子量や比重、物質の状態変化、熱の移動、静電気、化学反応式など頻出分野を図解で理解しやすく解説。初心者でも取り組みやすく、問題演習で短期合格を目指せます。
動画の試聴はこちら【防災編】経営資源を守る「守り」と「代替」の思考法
BCP策定において最も重要な基礎となるのが、従来の「防災対策」との関係性を正しく理解することです。本講座の「防災編」では、この点を非常にクリアに定義しています。
防災対策とBCPは「車の両輪」である理由
「防災」と「BCP」は別物ではありません。これらは相互に補完し合う関係にあります。講座内で語られる重要な概念を整理します。
- 防災(守る): ヒト・モノ・カネ・情報といった「経営資源」そのものが壊れないように守ること。 例:オフィスの耐震化、データのバックアップ、従業員の安否確認システムなど。
- BCP(代替する): 防災対策をしても、どうしても欠けてしまった経営資源を「補う・代替する」ことで事業を続けること。 例:メイン工場が停止した場合の代替生産ライン、テレワークによる業務継続など。
つまり、「徹底して守り(防災)、それでもダメな部分を代替策(BCP)でカバーする」という二段構えこそが、強い組織を作るのです。
経営資源を物理的な被害から「守る」取り組み。
(耐震補強、備蓄、避難訓練など)
欠けた経営資源を他で「補う・代替する」仕組み。
(代替拠点、バックアップ、外部委託など)
命と拠点を守るための初動アクションリスト
災害発生直後の動きが、その後の復旧スピードを決定づけます。講座の「防災編」では、時間軸に沿った具体的なアクションリストを学びます。
- 準備: 平時に自助・共助・公助の観点で拠点をどう守るか準備する。
- 初動: 発災直後、従業員の命を守るために何が必要か(地震、水害、感染症で命の守り方は違います)。
- 復旧: 安全確保後、いかに素早くBCP発動(業務再開)へ移行するか。
特に重要なのは、「地震・水害・感染症で命の守り方が違う」という認識です。一律の避難訓練だけでは対応できないリスクに対し、具体的なシナリオを持つことが求められます。
【BCP編】絵に描いた餅にしない!策定の基本ステップ
「BCPを作ったけれど、分厚いファイルが棚に眠っているだけ……」 そんな事態を避けるために、講座の「BCP編」では、発動可能な計画を作るためのロジックを体系的に解説しています。
用語の整理と大前提:優先順位と代替戦略の考え方
BCP策定で最初につまずくのが、専門用語と「何を優先すべきか」の定義です。本講座では、以下の重要概念を整理することから始めます。
- RTO(目標復旧時間): いつまでに業務を再開させるか。
- MTPD(最大許容停止時間): どのくらい止まると事業が破綻するか。
これらを明確にしないまま策定を進めると、現実離れした計画になりがちです。また、「優先順位の考え方」も重要です。全ての業務を即座に復旧させることは不可能です。 「どの中核事業を最優先で守るか」を選別し、そのために必要なリソース(人・モノ・金・情報)が欠けた場合の「代替戦略」を事前に用意することが、BCPの核心です。
重要業務の把握から発動基準まで(インパクト分析)
具体的な策定プロセスとして、講座では「事業インパクト分析」のイメージを学びます。 災害発生時、自社の被害状況をどう把握し、どのタイミングでBCPを発動するか。その判断基準が曖昧だと、現場は混乱します。
- BCPの発動基準: 地震震度○以上、あるいは大雨警報発令時など、明確なトリガーを設定する。
- 発動時の体制: 誰が指揮を執り、どのような体制で動くか。
これらを「重要業務の洗い出し」とセットで決めておく手順を、動画で分かりやすく解説しています。
【実践編】サプライチェーン管理と訓練の落とし穴
自社の計画が完璧でも、事業が継続できないケースがあります。それが「サプライチェーンの寸断」です。「実践編」では、より実務に即した高度な視点を養います。
自社だけでは守れない?サプライチェーン全体での対策
原材料の調達先が被災したら、製造ラインは止まります。物流が止まれば、商品は届きません。 本講座では、「サプライチェーンの中で考えるべきこと」として以下を提起しています。
- 事業に必要な供給品目情報: 何が止まると自社が止まるのかを把握しているか。
- 在庫の積み増し: ジャスト・イン・タイム(効率化)とリスク管理のバランスをどう考えるか。
取引先のリスクまで視野に入れた対策こそが、現代のBCPには不可欠です。
「避難訓練だけ」はNG!安否確認と立ち上げ訓練の重要性
「うちは毎年避難訓練をしているから大丈夫」と思っていませんか? 実は、避難訓練とBCP訓練は全く別物です。
- 安否確認と要員確認は違う: 「無事です」という報告だけでは足りません。「出社できるか」「業務に従事できるか」という要員確保の視点が必要です。
- 本部立ち上げ訓練: 災害対策本部を実際に設置し、情報を集約し、意思決定をする訓練(机上訓練・実動訓練)を行わないと、本番では機能しません。
講座では、形骸化しないための「意味のある訓練」の例についても触れています。
動画で学ぶBCP策定講座:全カリキュラム概要
今回ご紹介した内容は、ミネルヴァベリタス株式会社の本田茂樹氏によるeラーニング講座で体系的に学ぶことができます。各動画は10分~20分程度に細分化されており、忙しい業務の合間でも学習可能です。
以下に、全3編のカリキュラム詳細をまとめました。
| カテゴリー | 主な講義内容 | 時間目安 |
|---|---|---|
| 防災編 守りと代替の基礎 |
|
計 約70分 |
| BCP編 策定プロセス |
|
計 約80分 |
| 実践編 実務・訓練 |
|
計 約70分 |
まとめ
BCP策定は、一人の担当者がデスクで頭を抱えていても進みません。関係者を巻き込み、共通言語を持って議論することが不可欠です。
本記事でご紹介した「BCP(事業継続計画)の策定と見直しのポイント」講座は、防災の基礎から具体的な策定ステップ、そしてサプライチェーンなどの実務論点までを網羅しており、社内研修や担当者のスキルアップに最適です。
「準備」と「備え」はいつするのか? 災害が起きてからでは遅すぎます。今、この平時のタイミングこそが、組織を強くする最大のチャンスです。ぜひ、この動画教材を活用して、実効性のあるBCP策定の第一歩を踏み出してください。




