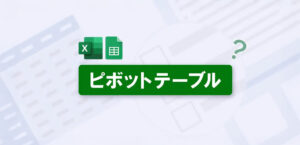花見の場所取りがハラスメントや炎上を招く?会社員が知るべき配慮と対策

春の訪れとともに楽しみになるのが「花見」です。会社の同僚や上司と桜の下で語らう時間を楽しみにしている人も多いでしょう。しかし、近年「花見の場所取り」がハラスメントにつながるケースが指摘されています。業務の一環のように場所取りを指示されたり、不適切な役割分担がされることで、不快な思いをする社員も少なくありません。
では、どのようなケースが問題視されているのでしょうか。また、会社の花見を快適に楽しむためには、どのような配慮が必要なのでしょうか。本記事では、花見の場所取りが引き起こすハラスメントの問題点や、適切な対策について解説します。
花見の場所取りがハラスメントになる理由

業務とは無関係な指示が負担になる
会社の花見の場所取りを、特定の社員に押し付けることは問題となる可能性があります。特に、若手社員や新入社員に対して「新人の仕事だから」と当然のように指示するケースは、業務とは関係のない負担を強いることになりかねません。場所取りのために早朝から出向く、長時間待機する、寒い中で座り続けるといった状況が発生すると、身体的・精神的な負担が大きくなります。
また、業務時間外に場所取りを指示する場合、労働時間として扱われないのかという問題もあります。業務の一環として行わせるならば、適切な対価を支払うべきですが、現実的には「仕事ではないが、やらなければならない雰囲気」が作られていることが少なくありません。
役割分担の偏りが不公平感を生む
場所取りの担当が毎回決まった人に押し付けられるのも、不公平な状況といえます。特に、若手や女性社員ばかりが担当させられる場合、無意識のうちに「都合のいい役割を押し付けている」ことになり、これがハラスメントと捉えられることがあります。
例えば、「女性のほうが気が利くから」「男性のほうが体力があるから」などの理由で、一部の社員だけが場所取りや準備を担当するのは、業務の負担を特定の層に偏らせることになりかねません。花見は会社のレクリエーションの一環であるため、全員が平等に楽しめる環境を整えることが大切です。
断りづらい雰囲気がプレッシャーになる
「場所取りは若手の仕事」「断ったら評価に影響しそう」といった雰囲気が生まれると、社員は精神的なプレッシャーを感じます。特に、上司からの依頼や、慣例として続いている場合は、断ることが難しくなりやすいです。
また、「今年もよろしく」と言われると、過去に場所取りを担当した社員が「自分がやらなければならない」と思い込んでしまうケースもあります。こうした**「暗黙の了解」**が積み重なることで、気付かぬうちにハラスメントの構造が生まれてしまうのです。
ハラスメントにならないための対策
業務時間外の指示が負担になる
会社の花見の場所取りを特定の社員に押し付けることは、大きな負担となるだけでなく、ハラスメントとみなされる可能性があります。特に問題となるのは、業務時間外に場所取りを指示するケースです。例えば、「始業前の早朝から場所を確保しておいてほしい」「勤務後に数時間、場所取りをお願いする」といった指示が、労働時間としてカウントされないまま事実上の業務として扱われることがあります。
業務時間外にもかかわらず、断りづらい雰囲気の中で場所取りを強いられると、社員にとってはサービス残業のような負担になりかねません。また、寒さや長時間の待機による身体的な負担も無視できません。業務とは関係のない時間に、会社のイベントのために個人の時間を割かせることは、本来あるべき働き方から逸脱しているといえます。
仮に会社のイベントとして正式に場所取りを業務の一環とする場合は、時間外手当の支給や代休の取得など、適切な対応が求められます。そうした配慮がないまま、社員が「やるのが当然」と扱われることは、見えないプレッシャーを生み、ハラスメントの温床となる可能性があるのです。
代替案を検討する
近年では、公園によっては「場所取り禁止」のルールを設けているところも増えています。そのため、場所取りにこだわらず、事前予約が可能な会場を選ぶのも一つの方法です。予約制のスペースを利用することで、無理な場所取りをしなくても済みます。
また、花見の形を変えるのも選択肢の一つです。例えば、昼休みの時間に近くの公園で短時間の花見を楽しむ、オンラインで「桜鑑賞会」を開催するなど、参加しやすい形にすることで、ハラスメントのリスクを回避できます。
希望を尊重し、強制しない
場所取りを担当する人を決める際には、本人の希望を尊重し、決して強制しないことが重要です。たとえ業務時間内であっても、本人の意向を無視して無理に押し付けることは、ハラスメントにつながる可能性があります。
また、場所取りをした人に感謝を示すことも大切です。「やってくれて当然」と考えるのではなく、労力に対してしっかりとお礼を伝えることで、不公平感を軽減できます。
ハラスメント研修
ハラスメントは、良好な職場環境を保つために決して許されるものではなく、社員の精神的健康を守るためにも非常に重要なテーマです。 ビズアップ総研では、ハラスメントが企業・団体に及ぼす悪影響を様々な観点で学べる講座を多数ご用意しています。eラーニングで気軽に学べるe-JINZAIの2週間無料お試しID発行も行っておりますので、この機会にぜひご利用ください。
詳細・お申し込みはこちら他のお客さんへの影響にも注意

花見の場所取りは、社内の問題だけでなく、周囲の利用者や社会全体に与える影響にも配慮する必要があります。特に、企業が組織的に広範囲の場所取りを行った場合、一般の花見客の迷惑になり、批判を受ける可能性があることを認識しておかなければなりません。
実際に、ある企業が自社名の入ったレジャーシートを使用し、大量のスペースを事前に確保した結果、SNS上で非難が殺到し、最終的に企業側が謝罪に追い込まれる事態となりました。このように、企業の場所取りは、外部からの目にも触れやすく、社会的な問題になりやすいのです。
また、公園や河川敷などの公共の場では、自治体ごとに場所取りのルールが定められていることが多いため、事前に確認することも重要です。例えば、「当日のみ場所取り可能」「〇時間以上の無人状態は禁止」などの規則がある場合、それを無視すると、トラブルの原因になりかねません。企業のイメージを損なわないためにも、場所取りの方法には十分な注意が必要です。
まとめ
会社の花見は、社員同士の交流を深める良い機会ですが、その準備が特定の人に負担を強いる形になってしまうと、ハラスメントの問題につながることがあります。特に、場所取りを一部の社員に押し付けたり、断りづらい雰囲気を作ることは避けるべきです。
公平な役割分担や代替案の活用、希望を尊重した運営を意識することで、花見を全員が楽しめるイベントにすることができます。「誰かに負担を強いるのではなく、全員で楽しむ」という意識を持ち、健全な職場のレクリエーションを実現していきましょう。