アンガーマネージメントとは【自己診断テストあり】
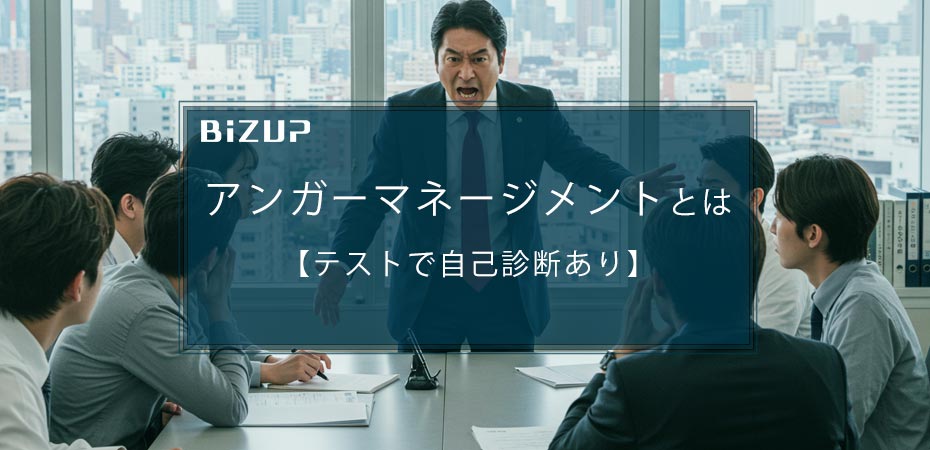
KEYWORDS アンガーマネージメント研修
「イラッとした」「つい感情的に言ってしまった」「なんでこんなに怒りが抑えられないんだろう…」
そんな経験は誰にでもあるはずです。怒りの感情は人間にとって自然な反応ですが、扱い方を間違えると、人間関係や職場の雰囲気、ひいては自分自身の心身にも悪影響を及ぼします。
そこで注目されているのが「アンガーマネジメント」。これは、怒りの感情を理解し、上手にコントロールするための心理トレーニングのことです。本記事では、アンガーマネジメントの基本から実践方法、学び方までを詳しく解説します。
目次
- アンガーマネジメントの定義と歴史
- 怒りのメカニズムを知る
- アンガーマネジメントの基本テクニック
- アンガーマネジメントテスト:あなたの点数は?
- 職場や日常生活におけるアンガーマネジメントの実践
- アンガーマネジメントを学ぶには
- まとめ
アンガーマネジメントの定義と歴史
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、「怒りの感情と上手につきあうための心理トレーニング」のことを指します。私たちは日常生活の中で、上司や部下、家族や友人とのやりとり、あるいは通勤電車の混雑やインターネット上の投稿など、さまざまな場面で怒りを感じることがあります。
その怒りが爆発してしまうと、人間関係が壊れたり、職場の雰囲気が悪化したり、後悔につながる言動を取ってしまったりすることがあります。一方で、怒りを無理に抑え込むこともストレスや体調不良の原因となります。
アンガーマネジメントは、怒りを「なくす」ものではなく、「コントロールする」ことを目的としています。怒りを感じる自分を否定せず、その感情を理解し、適切な形で表現できるようになるためのスキルです。
歴史的背景
アンガーマネジメントは、1970年代のアメリカで誕生しました。心理学者のチャールズ・スペルバーガー博士らが研究を進め、刑務所やカウンセリングの現場などで、「怒りの感情によって問題行動を引き起こしてしまう人々」に対する心理療法として活用されるようになったのが始まりです。
その後、アンガーマネジメントは医療・教育・ビジネスなどさまざまな分野で注目され、アメリカ全土に広がっていきました。現代では、学校教育や企業研修、スポーツ選手のメンタルトレーニングなどにも取り入れられています。
日本にこの概念が紹介されたのは2000年代に入ってからで、日本アンガーマネジメント協会が2011年に設立されて以降、一般向け講座や企業研修が本格的に展開されるようになりました。
なぜ今、注目されているのか?
現代社会では、コミュニケーションの多様化や働き方の変化により、ストレスや摩擦を感じる場面が増えています。とくに職場では、「パワハラ」「感情的な叱責」「無言の怒り」など、怒りが原因のトラブルが後を絶ちません。
また、SNSの普及によって、感情が瞬時に言葉として発信されやすくなり、「ちょっとした怒り」が大きな炎上につながるケースも増えています。こうした背景から、「感情のマネジメントスキル」としてアンガーマネジメントへの関心が高まっているのです。
怒りのメカニズムを知る
怒りは「二次感情」
怒りの感情は、「突然湧いてくる強い感情」のように感じるかもしれませんが、実はそうではありません。怒りは「二次感情」と呼ばれ、その前段階には必ず別の感情(一次感情)が存在しています。
たとえば、以下のような流れです:
- 「約束を破られた」 → 悲しみ・裏切られた気持ち → 怒り
- 「意見を聞いてもらえなかった」 → 寂しさ・無力感 → 怒り
- 「遅刻された」 → 不安・焦り → 怒り
このように、怒りの奥には「わかってほしかった」「尊重してほしかった」といった、人として当然の欲求が隠れていることが多いのです。つまり、怒りは防御反応のようなもので、自分の心を守るために発生するとも言えます。
この構造を理解することで、「自分は今、本当は何に傷ついたのか」「どんな価値観が侵されたと感じたのか」を冷静に分析することができるようになります。
「~すべき」思考が怒りを生む
怒りの原因の多くは、自分の中の「~すべき」という思い込みや期待が裏切られたときに生じます。心理学ではこれを「べき思考(should thinking)」と呼びます。
例えば:
- 上司は部下をちゃんと評価すべき
- 子どもは親の言うことを聞くべき
- 電車は時間通りに来るべき
しかし、現実にはこれらが常に守られるとは限りません。そのギャップが「怒り」という形で表れるのです。つまり、怒りの正体は「自分の理想」と「現実」のズレ」だと言えるでしょう。
この「べき」を緩めることで、怒りの強度を下げることが可能になります。たとえば、「部下は報告をもっと早くしてほしいけど、初めての案件だし仕方ないかもしれない」と考えることで、怒りを抑え、建設的な対話に変えることができます。
怒りのピークは6秒
怒りの感情には、実は明確なピーク時間が存在します。それが「6秒」です。
これは脳の構造に関係しています。怒りを感じた瞬間、脳内では「扁桃体(へんとうたい)」という部位が活性化し、戦うか逃げるかの反応(いわゆる「闘争・逃走反応」)が起こります。しかし、6秒ほど経過すると、「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という理性を司る部分が働き始め、冷静な判断ができるようになります。
つまり、この最初の6秒をどう過ごすかが、アンガーマネジメントの第一歩。深呼吸、カウント、視線を外す、手を組むなど、意識的に「反応しない」時間を作ることで、自分の怒りを冷静にコントロールする準備ができます。

アンガーマネジメントの基本テクニック
アンガーマネジメントでは、怒りに対して反射的に反応するのではなく、一歩立ち止まり、冷静に対処することが重要です。以下に代表的なテクニックを紹介します。
1. 衝動のコントロール
怒りを感じた瞬間、無意識に反応してしまうのが人間の常。しかし、それをワンクッション置くことで衝動的な行動を防ぐことができます。
主な方法:
- ゆっくり10秒数える
- 深呼吸(4秒吸って、4秒止めて、4秒吐く)
- その場を一旦離れる
- 手をぎゅっと握ってからゆっくり開く
これらの行動は、「今すぐ反応しない」という選択肢を自分に与えてくれます。怒りの瞬間にほんの少しだけ間を置くことで、後悔のない行動を選びやすくなるのです。
2. スケールテクニック
これは怒りの大きさを数値で表す方法です。自分の怒りを0〜10で評価してみましょう。
たとえば:
- 0:まったく怒っていない
- 3:少しイラっとするけど許容範囲
- 7:強い怒りを感じている
- 10:爆発寸前!
この数値化によって、「自分は今、どのレベルの怒りにいるのか?」を客観視できるようになります。また、「10段階中5なら、言い方を変えれば穏便に済むかもしれない」といった冷静な選択も可能になります。
3. 怒りのタイプを理解する
怒りには表現の仕方によって以下のようなタイプがあります:
- 攻撃型:言葉や態度で怒りを外に出す(怒鳴る、強く責める)
- 受け身型:怒りを外に出さず、内側にためる(我慢、無視)
- 執着型:過去の怒りを繰り返し思い出す(根に持つ)
- 爆発型:我慢していた怒りが突然爆発する(感情が暴走する)
自分がどのタイプに当てはまるかを知ることで、それぞれに適した対応策を取ることができます。たとえば、受け身型の人は「怒りを言葉で表現する練習」、攻撃型の人は「伝え方の工夫(アイ・メッセージ)」などが有効です。
アンガーマネジメントテスト:あなたの点数は?
以下の10個の質問に対して、あてはまるものを1つ選んでください。
各項目に点数がついていますので、合計点であなたのアンガーマネジメント力を診断します。
| 質問事項 | とてもあてはまる | ややあてはまる | あてはまらない |
| 1. 怒りを感じたらすぐに口に出してしまう | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 2. 怒りを後になってまで引きずることが多い | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 3. 思い通りにいかないと強いストレスを感じる | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 4. 人のミスにすぐイライラしてしまう | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 5. 「なんで自分ばっかり」と感じることが多い | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 6. 怒りをうまく言葉で伝えられていない気がする | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 7. ネガティブな投稿をSNSで発信したことがある | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 8. 怒りを我慢して、爆発してしまうことがある | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 9. 他人の価値観に寛容になれないと感じる | 3点 | 1.5点 | 0点 |
| 10. 怒ってしまった後に後悔することがよくある | 3点 | 1.5点 | 0点 |
合計点で診断!
| 合計点数 | 診断結果 |
|---|---|
| 0〜10点 | アンガーマネジメント上級者 あなたは怒りに振り回されず、冷静に感情を扱う力があります。今後もそのバランス感覚を大切に! |
| 11〜20点 | 安定タイプ 多少イライラすることはあっても、自制が効くタイプ。改善の余地もありますが、基本的には良好な感情コントロールができています。 |
| 21〜25点 | 要注意タイプ 怒りが積もりやすく、表に出すか内にためるかのどちらかに偏る傾向があります。アンガーマネジメントの基礎を学ぶとより安定するでしょう。 |
| 26〜30点 | アンガーマネジメント必須タイプ 怒りが生活や人間関係に影響を与えている可能性があります。怒りの背景や対処法を見直し、少しずつ改善していくことが重要です。 |
おすすめの使い方
- チーム研修や家庭内での会話のきっかけに
- 自己理解を深めるワークとして
- 自分の怒りグセを「見える化」して振り返るツールに
職場や日常生活におけるアンガーマネジメントの実践
職場での活用
たとえば、部下が報連相を怠ったとき、感情的になって叱責するのではなく、「なぜ自分がそれに怒っているのか」を見つめ直します。
- 「自分が大切にしている価値観は?(責任感、時間の大切さ)」
- 「その価値観は相手にも共有されているか?」
- 「怒りをどう伝えれば相手が前向きに受け取れるか?」
このように考えることで、ただ怒るのではなく、建設的な指導や対話につなげることができます。これは上司・部下間に限らず、チーム全体の雰囲気や業務効率にも大きく影響します。
家庭での実践
家庭では、相手に甘えがある分、怒りが爆発しやすい傾向があります。例えば子どもが言うことを聞かないとき、「またか!」とイラ立つのではなく、「今日は自分に余裕がないのかも」と自分自身の状態をチェックしてみることも大切です。
また、「今、どんな気持ち?」と自分に問いかけてみることで、怒りの本質に気づけるようになります。パートナーとの関係でも、「何をどう変えてほしいのか」を具体的に伝えることが関係改善の鍵となります。
SNSやデジタル空間での注意
匿名性が高いSNSでは、怒りを発散しやすくなりがちです。投稿する前に「これは本当に発信するべき内容か?」「一晩寝かせてみよう」といった一呼吸を入れるだけで、炎上リスクを大幅に減らすことができます。
アンガーマネジメントを学ぶには
アンガーマネジメントは、「知っている」だけでは効果が出にくく、日常の中で少しずつ実践していくことが重要です。そのため、自分に合った学び方を選ぶことが成功のカギとなります。ここでは、代表的な学び方である対面式講座とeラーニングについて詳しく解説します。
1. 対面式で講師から学ぶ
特徴とメリット
対面式の講座では、認定講師や専門家が直接指導してくれます。座学だけでなく、ワークショップ形式やグループディスカッション、ロールプレイ(役割演技)を通じて、リアルな感情のやりとりや、実践的なスキルを身につけることができます。
特に以下のような点がメリットです:
- その場で質問・相談できる
→ 自分のケースに合わせたアドバイスがもらえる。 - 感情のやりとりを体験できる
→ 他人の反応を実際に見て学べる。 - モチベーションが保ちやすい
→ 同じ目的を持つ参加者と刺激し合える。
また、アンガーマネジメントの基礎講座は、半日程度の短時間で受講できるものが多く、平日夜や週末に開催されるため、忙しい社会人でも参加しやすくなっています。
デメリット
- 受講料がやや高め(5,000円〜10,000円程度が相場)
- 開催場所や日程が限られているため、地方在住だと受講しにくい
- コロナ禍などで開催が制限される場合もある
こんな人におすすめ!
- 実際に講師や他の受講者と顔を合わせながら学びたい人
- 自分の怒りの傾向を他者の視点からフィードバックしてほしい人
- 職場や家庭での具体的な悩みを持っていて、個別相談もしたい人
2. eラーニングで学ぶ
特徴とメリット
eラーニングは、パソコンやスマートフォンを使って、いつでもどこでも学べるオンライン講座です。動画やスライド、テキストを活用し、基礎知識から応用までを自分のペースで進められるのが最大のメリットです。
最近では、高品質な学習コンテンツが多数登場しています。
メリットは以下の通り:
- 時間と場所に縛られず、自由に受講できる
→ 忙しい社会人や子育て中の方でも安心。 - 費用が比較的安価(2,000円〜5,000円程度のものも)
→ お試し感覚で気軽に始められる。 - 繰り返し視聴が可能
→ 自分が理解できなかった部分を何度でも見直せる。
⇒国内最大級の20,000動画を超える企業向けeラーニングでアンガーマネージメントを学ぶ
デメリット
- 講師との直接のやりとりができない(※一部例外あり)
- 自分で計画的に学ぶ必要があるため、モチベーション維持が課題
- 実践やフィードバックを受ける機会が少ない
こんな人におすすめ!
- 忙しくて決まった時間・場所に通えない人
- 自分のペースで学習を進めたい人
- アンガーマネジメントにまずは気軽に触れてみたい初心者
学びのコツ:両方を組み合わせるのもアリ!
初めはeラーニングで基礎知識を身につけ、興味が深まったら対面講座で実践する、というようにハイブリッド型の学び方も効果的です。最近では、Zoomを使ったオンライン対面講座など、両者の中間に位置するスタイルも増えており、自分に合った柔軟な学び方が選べる時代になっています。
まとめ
怒りの感情は、決して悪いものではありません。それは、自分の価値観や大切にしていることを守ろうとする防衛反応でもあります。ただし、それをどう扱うかによって、人生の質は大きく変わります。
アンガーマネジメントは、「怒らない人になる」ためのものではなく、「怒る必要のあるときには適切に怒り、怒る必要のないときには冷静でいられる」ためのスキルです。
日々の中で少しずつ実践を積み、自分の感情と上手につきあう力を育てていくことで、より良い人間関係、健やかな心のあり方に近づくことができるでしょう。!
ビズアップ総研のアンガーマネージメント研修
「アンガーマネジメント」は、経営層、管理職、一般スタッフなど、現代に働く全ての方に必須スキルになってきています。ビズアップ総研のアンガーマネジメントは、階層別やテーマを絞った内容で提供いたします。
研修の詳細はこちら


