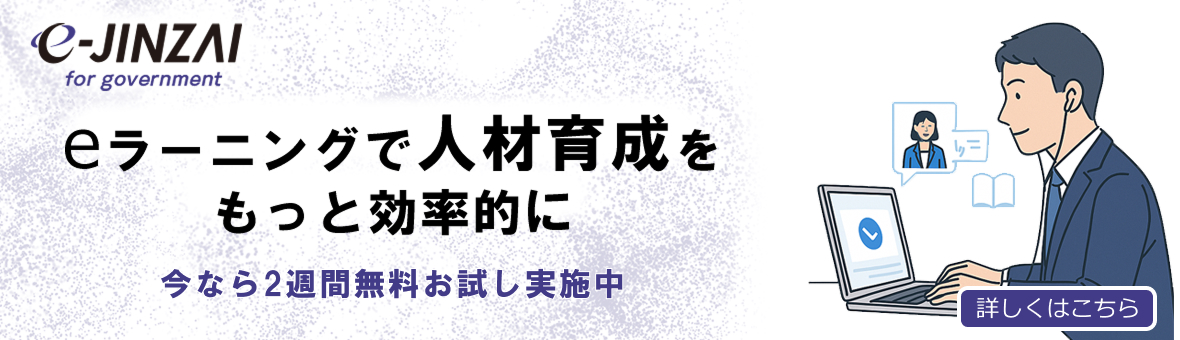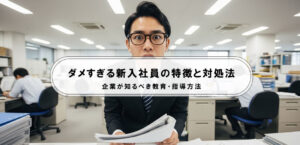その経営、10年後も続けられますか?公営企業に求められる準備と対策

KEYWORDS 自治体
公営企業は、住民の生活を支える基盤として、水道や下水道、病院、交通など多様なサービスを提供しています。こうした事業は民間では対応が難しい一方で、住民に不可欠な役割を果たしているため、安定的かつ持続可能な経営が求められています。
しかし、近年では人口減少の加速、インフラ設備の老朽化、財政の厳しさ、専門人材の不足といった課題が顕在化しており、従来の運営では立ち行かなくなりつつあります。こうした背景の中、各自治体が将来を見据えて中長期的な視点で経営を見直す必要性が高まっています。
本記事では、公営企業を取り巻く経営環境を整理し、今後の経営戦略の方向性と、具体的な課題を解決するために有効な「研修」の役割について詳しくご紹介します。
⇒「10年後も続く公営企業経営」の第一歩|e-JINZAI for government
目次
将来に備えた公営企業のあり方
総務省が提示する「経営戦略策定・改定ガイドライン」では、自治体が公営企業を持続的に経営していくためには、以下のような環境変化に対応した取り組みが不可欠であるとされています。
- 人口の急速な減少と地域の低密度化:水道や下水道の需要が減少し、料金収入の確保が難しくなっています。
- インフラの更新時期の到来:多くの施設が建設から数十年を経ており、更新投資が一斉に必要になっています。
- 人材確保の難しさ:技術系職員の高齢化や人手不足により、計画的な運営が困難になりつつあります。
- 経営悪化のリスク:収支の均衡が崩れることで、必要なサービスの維持が難しくなる可能性があります。
これらの問題に対処するには、長期的な視野での経営方針の設定と、それを実行する仕組みが重要です。
中長期視点で考える経営の方向性

持続可能な運営を目指すには、場当たり的な対処ではなく、中長期的な視点を持った計画的な経営が不可欠です。ここでは、総務省のガイドラインに基づく「経営戦略」と「投資・財政計画」の基本的な考え方を紹介し、その重要性を解説します。
経営戦略とは何か
経営戦略とは、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な計画です。これには、地域の人口動態や施設の老朽化状況を踏まえた上で、今後の運営方針を明確にすることが求められます。
戦略の立案には、経営の現状把握、将来の需要予測、収支の見通し、投資計画など、幅広い観点からの検討が不可欠です。また、議会や住民の理解を得ながら進めることも大切です。
投資・財政計画の役割
経営戦略の中核となるのが「投資・財政計画」です。施設の更新や整備にかかる費用(投資試算)と、それをどのような財源で賄うのか(財源試算)を明確にし、10年以上の長期にわたる収支の均衡を目指します。
この試算には以下の要素が含まれます。
- 設備の現状と劣化状況
- 更新に必要な金額と優先順位
- 財源構成(料金収入、企業債、繰入金など)
- 将来の料金改定の必要性
これらを総合的に考慮し、事業の持続性を確保することが重要です。
現場で見えてきた具体的な課題
実際の自治体現場では、理論だけでは捉えきれない課題が山積しています。下記に主な課題とその具体的な内容を整理しました。
| 課題分類 | 内容概要 |
|---|---|
| 収益構造の悪化 | 人口減少により水道・下水道の利用者が減少。固定費を賄いきれず赤字経営に転落するリスクが増大。 |
| インフラの老朽化 | 昭和期に整備された施設が一斉に更新期を迎え、更新費用の集中が財政を圧迫。 |
| 人材不足と業務の属人化 | 技術職員の退職や採用難により、知識・経験が一部の職員に偏り、継続的運営が困難に。 |
| 経営の見える化不足 | 経営情報が住民や議会に伝わりにくく、料金改定や施設更新に対する合意形成が進まない。 |
特に多く見られる悩み
- 使用者が減っても料金は上げづらい(住民の反発)
- どこから更新を始めればよいか優先順位が決められない
- 業務が属人化し、異動や退職でノウハウが断絶
- 予算説明の際、将来見通しをうまく伝えられない
こうした複合的な課題に対しては、実務的な知識と計画性を持った対策が必要不可欠です。
学びが現場にもたらす変化

これらの課題に対して、担当者個人の知識や経験だけでは限界があります。そこで重要となるのが、体系的に学ぶ機会としての研修です。この章では、研修によって得られる知識・視点・実践力について解説します。
経営戦略の実務を体系的に理解できる
経営戦略を「知っている」だけではなく、「現場で実践できる」レベルまで落とし込むには、実務的な知識が必要です。研修では、総務省のガイドラインに基づく計画の立て方から、実施後の検証、PDCAの運用に至るまで、具体的な手順とポイントを段階的に学ぶことができます。
ケーススタディやワークショップ形式での演習を通じて、単なる座学では得られない実践的な理解が可能になります。また、他自治体の職員との意見交換を通じて、自身の課題を相対化できる点も大きなメリットです。
財務・料金制度の基礎が身につく
経営戦略における料金改定や財源構成の見直しは、住民サービスに直結する重要なテーマです。研修では、地方公営企業法や水道法に基づく料金算定の基本原則、減価償却費や資産維持費の考え方など、財務制度の全体像を理解できます。
また、収支のバランスを保ちながらも、住民にとって納得感のある料金体系を設計するための工夫や、料金改定の際の説明方法も学べるため、実務に直結した知識が身につきます。
広域化・共同化による選択肢の発見
将来的なサービス維持に不安がある自治体ほど、他自治体との連携による「広域化」「共同化」が有効な手段となります。研修では、実際に広域化を進めた先進事例や、PPP/PFIといった民間活用の選択肢についても学ぶことができます。
これにより、「自分の自治体だけではできない」と諦めていた改革も、外部との協働によって実現可能であることに気づけるでしょう。現状を打開するヒントが得られるのは、大きな学びの収穫となります。
自治体にとっての学びの価値
研修で得られる知識や視点は、参加者個人のスキルアップにとどまりません。組織全体の意識改革や、自治体経営の質の向上にもつながる点が大きな魅力です。ここでは、組織・地域にとっての研修の意義を整理します。
経営の視野が広がる
制度や理論にとどまらず、全国の先進事例や他自治体の取り組みを知ることで、自らの業務や自治体を俯瞰的に捉える視野が得られます。研修を通じて「当たり前」と思っていたやり方を見直すきっかけにもなり、イノベーションの種が生まれる可能性もあります。
組織内での共有・説得力が増す
経営戦略や財政計画を提案する際、組織内の理解と協力を得ることは不可欠です。研修で得た根拠ある知識や事例は、上司や同僚、議会への説得材料としても有効です。これにより、政策の合意形成がスムーズに進み、組織内の一体感が高まります。
安定的なサービス提供に繋がる
最終的なゴールは、地域住民に対して持続的かつ安定的にサービスを提供し続けることです。制度・計画・財政・組織など、多角的な視点を持った職員の存在が、経営基盤を強化し、自治体全体のレジリエンスを高めることに繋がります。
まとめ
公営企業を取り巻く経営環境は、これまでにないスピードで変化しています。人口減少や施設の老朽化、財政の厳しさ、専門人材の不足といった課題は、どの自治体でも共通して直面している問題です。これらにどう対応するかは、単なる経営の話にとどまらず、地域の未来をどう築いていくかという大きなテーマでもあります。
その中で、経営戦略の策定は重要な一歩となります。しかし、策定自体が目的ではなく、それをいかに実行に移し、継続的に改善していけるかが問われています。制度を理解し、課題に実務的に対応できる力を持つ人材の育成が欠かせません。
研修は、こうした力を身につける絶好の機会です。実務に即した知識の習得、他自治体との交流、成功事例の学びを通じて、自身と組織の成長を促すことができます。そしてそれが、結果として地域全体の持続可能な発展につながっていくのです。
今こそ、学びを通じて未来の公営企業経営を切り開く一歩を踏み出しましょう。
e-JINZAI for governmentの公営企業運営研修
人口減少に伴う料金収入の減少、施設等の老朽化問題。公営企業の経営基盤の強化、財政マネジメントの向上等に的確に取り組むために必要な公営企業会計を学び、料金改定や広域化・共同化、また、公共施設のファシリティマネジメントとして、アセットマネジメント、ストックマネジメントに関する知識を学んでいただきます。
2週間無料お試しはこちら