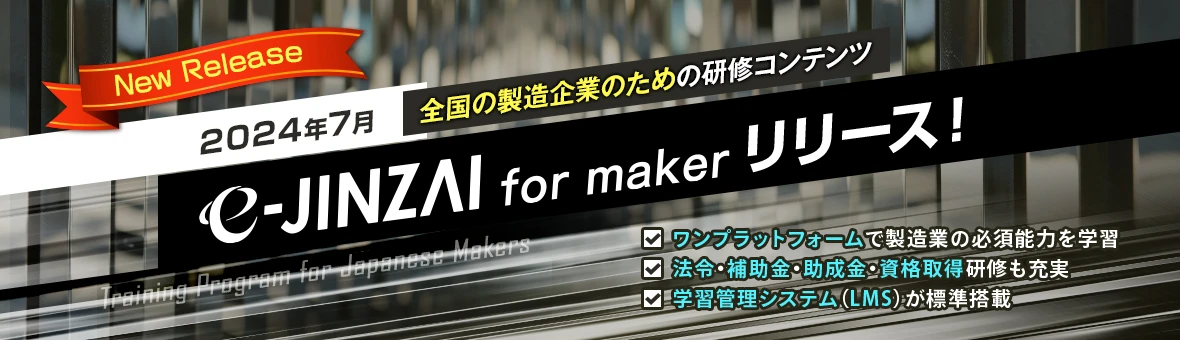セクハラ・パワハラだけじゃない!製造業で注意すべき最新ハラスメントとは

製造業の現場では、品質・納期・コストといった厳格な管理が求められる中で、強い指導や上下関係が重視される職場文化が根付いています。しかし、こうした構造はときに過剰な言動を招き、従業員の精神的負担となる「ハラスメント」につながるリスクをはらんでいます。
本記事では、製造業におけるハラスメントの発生要因と具体的なケース、企業が取るべき対策、そして近年注目される新たなハラスメントの形態まで幅広く取り上げます。働きやすい職場づくりを目指す経営者・人事担当者に向けて、実践的な知識と対応のヒントを提供します。
⇒製造業のハラスメント問題、対策は「e-JINZAI for maker」で
目次
製造業に特有のハラスメント要因とは
ハラスメントはあらゆる業種で発生し得るものですが、製造業には他業界と比較してリスクを高めるいくつかの構造的要因があります。
現場特有の強い指導がトラブルの火種に
製造業の現場では、労働災害を防ぐために迅速で厳しい指導が必要不可欠です。しかし、感情的な言動が日常化すると、それが「指導」と「攻撃」の境界を曖昧にし、受け手によっては強いストレスや恐怖として受け止められます。
とくに新人や派遣社員など、立場の弱い労働者は反論しづらく、指導の名を借りた威圧的行動が横行する場合も少なくありません。
年功序列・上下関係の固定化
製造業では、ベテラン社員が新人に対して一方的な物言いをする場面が見受けられます。年功序列や「体育会系」の職場風土が残る企業ほど、役職や年齢に基づく力関係が強く、これがパワーハラスメントの温床になることがあります。
また、女性や外国人労働者など多様な人材が増えているにもかかわらず、それを受け入れる組織文化の醸成が追いついていない企業では、無意識の差別的言動が発生するリスクもあります。
現場で頻発するハラスメントの実態

製造業で見られる代表的なハラスメントには、パワハラ・セクハラ・マタハラの3つがあります。それぞれの定義と具体的事例を押さえ、問題の本質を理解しておきましょう。
指導の域を越える「パワハラ」
パワハラとは、優越的な立場にある者が、業務の必要性を逸脱して行う言動によって、部下や同僚の就業環境を悪化させる行為を指します。製造業では、以下のような例が典型的です。
- 作業ミスに対して「給料泥棒」「辞めろ」と怒鳴る
- 特定の社員にだけ業務を割り振らない、孤立させる
- 物を投げる、胸ぐらをつかむなどの身体的威圧
これらの言動は、上司の「感情的な怒り」から生まれることが多く、明確な指導目的がないまま繰り返されれば、パワハラに該当します。
偏見や性的言動がもたらす「セクハラ」
セクシュアルハラスメントは、性的な言動により相手を不快にさせたり、職場環境を悪化させたりする行為です。製造現場では、男性中心の職場でありがちな以下のような発言が問題となります。
- 「彼氏つくらないの?」「結婚できないタイプだよね」
- 飲み会で女性にお酌を強要する
- 男性同士のいじりの中で性的な冗談を交わす
これらは本人が冗談のつもりでも、受け手が不快に感じた時点でセクハラになり得ます。性別を問わず、相手の立場に立った配慮が必要です。
妊娠・育児をめぐる「マタハラ・パタハラ」
女性社員が妊娠・出産・育児休業を取得した際、または男性社員が育児休業を申し出た際に、不利益な扱いや嫌がらせを受けるケースがあります。
- 「また休むの?他の人に迷惑」
- 「男のくせに育休なんておかしい」
- 「時短勤務なら責任ある仕事は任せられない」
こうした発言や扱いは、男女雇用機会均等法・育児介護休業法違反にあたり、企業に対する行政指導や訴訟リスクを伴う重大な問題です。
見逃せない!近年増加するハラスメントの新潮流
近年では、従来型のハラスメントに加えて、モラハラやSOGIハラなど新たなハラスメントが問題視されるようになっています。企業はこれらの動きに敏感でなければなりません。
精神的な追い込み「モラルハラスメント」
モラハラとは、暴力ではなく言葉や態度で相手を精神的に追い詰める行為です。具体的には以下のような行動が該当します。
- 挨拶しても無視する
- 他人の前で意図的にため息や皮肉を言う
- 情報を共有せず、孤立させる
表面上は「感情的でない」ため見逃されがちですが、持続的なモラハラはパワハラ以上に深刻な精神的影響を与えることもあります。
性的指向や性自認に基づく「SOGIハラスメント」
LGBTQ+に対する偏見や無理解が原因で発生するのがSOGIハラスメントです。
- 「あの人ゲイらしいよ」などのアウティング
- 「男ならもっと男らしくしろ」などのステレオタイプの押し付け
こうした言動は、本人の尊厳を傷つけるだけでなく、職場全体の人権意識の欠如を露呈します。性自認や性的指向に関する情報は、本人の了承なしに共有してはなりません。
男性や同性間でも起こるハラスメント
セクハラは「男性から女性へ」という固定観念が根強くありますが、実際には逆のケースや同性同士のケースも増えています。
- 女性上司からの性的な冗談に困っている男性部下
- 同性間でのボディタッチや恋愛対象に関する発言
- 男性社員に対して「男のくせに育児するなんて」と否定的な言動
性別や関係性にかかわらず、「受け手がどう感じたか」が重要であり、企業はこれらのケースにも正しく対応できる体制を整える必要があります。
法令で求められる企業の対応義務
日本では、職場のハラスメントを防止するために、複数の法令が整備されています。企業には次のような義務があります。
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
2022年より中小企業も含め、パワハラ防止措置が義務化。 - 男女雇用機会均等法
セクハラ防止措置、妊娠・出産に関する差別禁止。 - 育児・介護休業法
育児・介護に関連する不利益な扱いの禁止。
これらの法令では、「就業規則への明記」「相談窓口の設置」「事後対応の体制整備」が企業に求められています。違反があれば行政指導や訴訟リスクもあるため、コンプライアンス対策の一環としても対策は必須です。
職場を守るための研修と体制整備の効果

製造業の職場では、業務の性質上、厳格な指導や上下関係が重要視される一方で、強い口調や一方的な言動がハラスメントと認識されにくい傾向があります。そのため、ハラスメントを未然に防ぎ、職場環境を改善するには、現場の実情に即した実践的な対策が必要です。
まず重要なのは、管理職や現場リーダーを対象とした研修の実施です。製造現場のリーダーには「安全のために厳しく指導するのは当然」といった価値観が根強く残っていることが多いため、次のような内容を盛り込んだ研修が効果的です。
- 指導とパワハラの違いを理解するケーススタディ
- 言葉の選び方や伝え方を見直すロールプレイ
- 自分の言動を振り返るセルフチェック
こうした研修によって、自覚なく繰り返していた言動を「ハラスメントのリスク」として認識できるようになります。
また、従業員が安心して相談できる体制づくりも不可欠です。製造業では、物理的に現場が分かれている、非正規や派遣社員が多いといった特徴があるため、以下のような配慮が求められます。
- 匿名で利用可能な相談窓口の設置
- 定期的な無記名アンケートの実施
- プライバシーを守る面談対応と記録の管理
さらに、日々の業務の中で**上司と部下がこまめに対話する「1on1ミーティング」**を取り入れることで、小さな不安や違和感の早期発見にもつながります。
加えて、管理職向けには以下のようなスキル研修を継続的に行うことで、職場全体のコミュニケーションの質が向上します。
- 傾聴力を高めるトレーニング
- フィードバックの伝え方を学ぶ実践型講習
- 多様な価値観を理解する意識改革型プログラム
製造業の現場では、業務効率や安全意識だけでなく、「人を大切にする文化」の醸成が、ハラスメント防止に直結します。職場内の信頼関係が深まれば、従業員の安心感が高まり、離職の抑制や生産性向上にもつながります。こうした取り組みは、企業の長期的な成長戦略としても不可欠な要素となるのです。
まとめ
製造業の現場におけるハラスメントは、構造的な課題が背景にあるからこそ、組織的なアプローチが必要です。指導と威圧の境界、性別や立場にとらわれない公平な対応、そして新たなハラスメントへの感度を持つことが、これからの企業に求められています。
従業員の働きやすさは、企業の強さにつながります。今こそ、制度の整備と人の意識改革の両面から、安心して働ける職場づくりを本気で進めるときです。
製造業のハラスメント防止
ハラスメントのトラブルは、ニュースにも取り上げられるほどの社会的な問題です。ハラスメントによって社員が離職してしまうことは、労働力の観点からもブランディングの観点からも悪影響が出てしまいます。ハラスメント問題を未然に防ぐこと、発生してしまっても適切に対処することが、企業にとって重要な課題となっています。本研修では製造業で実際に起こったトラブルなどをベースに、ハラスメントに対する知識を学んでいきます。
2週間無料お試しはこちら