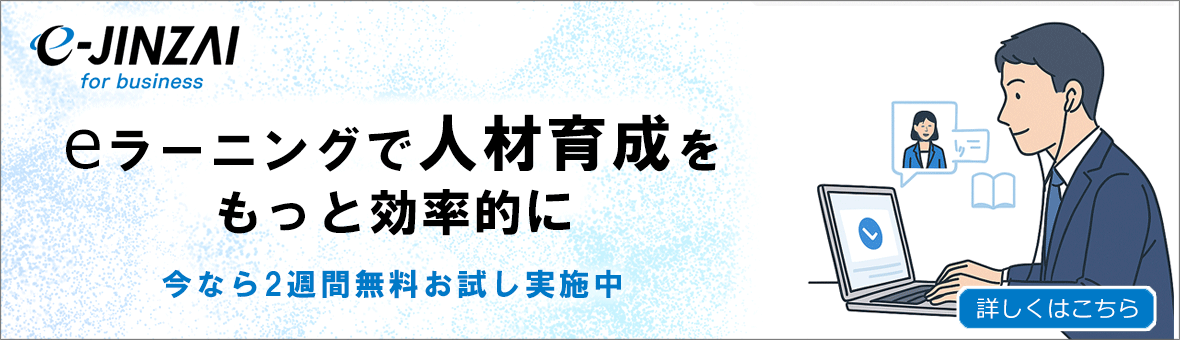御中?様?各位?ビジネス場面での宛名の正しい書き方を徹底解説

KEYWORDS ビジネススキル
ビジネスの場面で手紙や荷物を送る際、「御中」「様」「各位」のどれを使えば良いのか迷った経験はありませんか?適切な敬称を選ばないと、相手に失礼になってしまうこともあるため、正確な使い分けが求められます。
この記事では、企業や企業の個人宛に手紙や荷物を送る際、または返信用封筒に記載する場合の宛名の書き方について、シチュエーションごとに詳しく解説します。
⇒ 社会人にふさわしいビジネスマナーを学ぶなら「e-JINZAI for Business」
目次
宛名の基本ルールとは

まず、宛名を書く際の基本的なルールを押さえておきましょう。宛名には、相手の立場や役職に応じて敬称を付けます。「様」は個人に対する最も一般的な敬称であり、「御中」は組織や部署に使われます。「各位」は複数人に向けて使う表現で、メールや案内状などでよく見かけます。
誤った敬称を使うと、「ビジネスマナーがなっていない」と思われかねませんので、正しい使い方を理解しておくことが大切です。
| 宛先の種類 | 敬称 | 例文 |
|---|---|---|
| 企業や部署 | 御中 | 株式会社〇〇 総務部 御中 |
| 特定の個人 | 様 | 株式会社〇〇 営業部 田中太郎様 |
| 担当者不明 | 御中 | 株式会社〇〇 採用担当 御中 |
| 複数人・全体宛て | 各位 | 株式会社〇〇 従業員各位、営業部各位など |
企業宛に送る場合:御中の使い方
企業や部署に宛てるとき
企業の総務部や人事部といった特定の部署に送る場合、宛名の末尾には「御中」を付けます。たとえば、「株式会社〇〇 総務部 御中」となります。個人名が分からない場合や、特定の担当者がいない場合にもこの形式が適しています。
また、ビジネス文書だけでなく、商品サンプルの送付や請求書の送付にも同様の書式が使われます。郵便物の種類に関係なく、宛名の正確さは信頼に直結します。封筒に記載する際は、略称や省略を避け、正式な社名・部署名で書くことが望ましいです。
このとき、「株式会社〇〇様」「〇〇部様」と書くのは誤りです。企業や部署は個人ではないため、「様」ではなく「御中」が適切です。
宛名と送り主の位置
宛名は封筒の中央に大きく書き、差出人は左下に小さめに記載します。送り主が企業の場合は、社名と部署名、担当者名の順に書くと丁寧です。
この配置は、郵便物の配送時にも重要で、正しい位置に書かれていないと誤配や遅延の原因となります。文字は読みやすい大きさで、楷書体を意識して丁寧に書くと印象が良くなります。宛先が長い場合は、改行しても構いませんが、見やすさを意識してください。
担当者が不明の場合
誰が担当なのか分からない場合は、部署名や役職名の後に「御中」をつけましょう。たとえば、「株式会社〇〇 人事部 採用担当 御中」といった表記です。採用関係の書類などでよく使われる形式です。
「採用ご担当者様」と書いてしまうこともありますが、相手が特定の個人ではない限りは「様」ではなく「御中」が適切です。
企業の個人宛に送る場合:様の使い方
担当者名が分かっているとき
企業に勤務する特定の個人に宛てる場合には、「様」を使用します。たとえば、「株式会社〇〇 営業部 田中太郎様」となります。このとき、「御中」と「様」を併記するのは誤りです。あくまで、宛名の最終行が個人名であれば「様」だけでよいのです。
メールや書類の送付状にも「様」を使用することで、丁寧な印象を与えます。役職がある場合には、「田中太郎 課長 様」と記載しても問題ありません。いずれの場合も、過剰な敬称の使用は避けるべきです。
複数敬称はNG!
「株式会社〇〇 営業部 御中 田中太郎様」のように「御中」と「様」を重ねて書いてしまう方もいますが、これはマナー違反となるため注意しましょう。
複数人に送る場合:各位の使い方
社員全体や取引先全体に向けて
文書や案内状を企業全体、あるいは複数の社員に送る場合は、「各位」を使います。例えば、「株式会社〇〇 従業員各位」や「関係者各位」などが代表例です。ビジネス文書の冒頭で「お客様各位」と書くこともあります。
ただし、封筒の宛名として使うことは少なく、通常は文書の冒頭で使用されます。封筒の場合は「〇〇株式会社 御中」とするのが一般的です。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。
返信用封筒を同封する場合の宛名
相手に返信用封筒を同封する場合は、相手側が記載することを前提にした宛名を印刷しておくと親切です。このときも、「御中」や「様」を正しく使い分ける必要があります。
例えば、企業宛であれば「株式会社〇〇 総務部 御中」、個人名が分かっていれば「田中太郎様」と印刷しておきます。どちらも分からない場合は、「採用担当 御中」などの記載が適切です。
自分の住所や氏名を封筒の裏面に小さく記載しておくことで、相手が間違えずに返信しやすくなります。
自分が返信する場合の注意点
逆に、自分が返信用封筒を使って返送する際にも、宛名の書き方には注意が必要です。受取人が企業や部署であれば「御中」、個人名が明記されていれば「様」を使用しましょう。差出人欄には、自分の名前や住所を丁寧に記載し、特に採用関係など重要な書類の場合は記入漏れがないか確認することが大切です。また、記載内容に誤字脱字があると印象が悪くなるため、丁寧に書くよう心がけましょう。
さらに、返信用封筒に「行」と印刷されている場合には、これを二重線で消し、「御中」または「様」に書き換えるのがマナーです。これは相手に敬意を示すための基本的なルールであり、特にビジネス文書では必須とされています。消し忘れがあると失礼にあたるため、封筒の投函前に必ず確認しましょう。
「行」の扱いについて
ビジネス文書の返信用封筒には、宛名の下に「行」と印刷されていることがありますが、これは受取人の敬称ではなく単なる送付先を示す表現です。そのため、返信の際にはこの「行」を二重線で消し、適切な敬称に書き換えることがマナーとされています。
たとえば、企業や部署であれば「御中」、個人名が記載されている場合は「様」となります。このひと手間が、相手への敬意と丁寧な対応を示す重要なポイントとなります。書き換えを忘れてしまうと、ビジネスマナーが不足していると見なされることがあるため、特に注意が必要です。
郵便物を送るための注意点

郵便物を送る際には、以下の3つの点にも十分注意する必要があります。各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
宛名の正確さを確認する
受取人の氏名や部署名、会社名に誤りがあると、相手に失礼な印象を与えるだけでなく、郵便が正しく届かない可能性もあります。正式名称を必ず確認し、略称や旧名称を使用しないようにしましょう。特に初めて送付する相手の場合は、公式サイトなどで正確な情報を事前に確認するのが望ましいです。
また、宛名に使用する敬称にも注意が必要です。部署名だけでなく、役職名の誤表記も避けましょう。細部まで正確に書くことが信頼につながります。
封筒のレイアウトに配慮する
宛名は封筒の中央に大きく丁寧に書き、差出人の情報は左下に小さく記載するのが基本です。封筒の余白や配置が乱雑だと、見た目の印象が悪くなり、読み取りにくくなることがあります。特にビジネスの場面では、清潔感と整った印象を与えることが重要です。
封筒の色やサイズにも注意を払いましょう。過度に派手な封筒はビジネスには不向きです。また、のり付けや折り方なども丁寧に仕上げることが基本です。
切手と送料の確認を忘れずに
切手の貼り忘れや料金不足は、相手に余計な手間や負担をかけてしまう可能性があります。特に書類の枚数が多い場合は、重さに応じた切手を正しく貼る必要があります。心配な場合は、事前に郵便局で確認することをおすすめします。
速達や書留など、必要に応じたサービスの利用も検討しましょう。特に重要書類を送る際には、追跡や補償のある方法を選ぶことが信頼性につながります。
まとめ
「御中」「様」「各位」は、それぞれ使うべき場面が異なります。相手が誰なのか、どのような立場にいるのかを正しく判断し、適切な敬称を選ぶことが大切です。この記事で紹介したルールを参考にすれば、今後、宛名で迷うこともなくなり、より信頼されるビジネスコミュニケーションが実現できるでしょう。
特に初対面の相手や重要な取引先とのやり取りでは、宛名の正確さが印象を大きく左右します。細かなマナーを守ることで、ビジネスにおける信頼の土台を築くことができます。今後の郵便対応にぜひ役立ててください。
e-JINZAI ライティング研修
ビズアップ総研のライティング研修は、ビジネス文書を作成できるようになるための研修です。新入社員は「ビジネスに求められる文書」について、若手・中堅社員は「適切な文章を作成する能力」について学びます。好きな時に学べる動画学習で、ビジネス文書で使う言葉遣いや「読み手ファースト」な文章の作り方を学びましょう。
2週間無料お試しはこちら