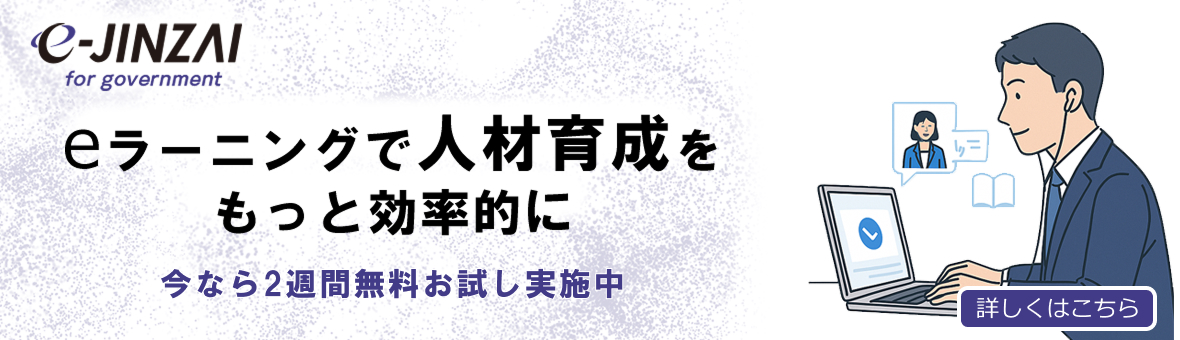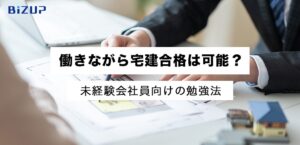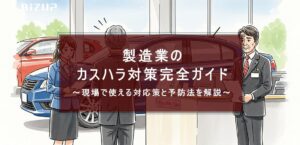【チェックリスト付き】自治体職場の心理的安全性を高める方法

「本音が言えない」「チームの雰囲気が重たい」「新しいアイデアが通らない」──そんな声を、自治体の現場からよく耳にします。人口減少、行政ニーズの多様化、複雑化する業務…変化の波の中で、自治体組織は今、大きな変革の岐路に立たされています。
その解決の鍵を握るのが「心理的安全性」です。職員が安心して意見を交わせる環境が整えば、チームは本来持っている力を発揮し、持続可能な地域行政の実現にもつながります。本記事では、心理的安全性とは何か、その重要性、阻害要因、そして改善のための具体的な方法までを、理論と実践の両面から解説します。
⇒職員が“働き続けたい”と思う自治体へ。e-JINZAI for government
目次
- 心理的安全性とは何か?
- 心理的安全性を阻害する要因
- 職場の心理的安全性を見える化するチェックリスト
- 心理的安全性を高める実践的なアプローチ
- 心理的安全性がもたらす“見える”成果
- 明日から取り組む、小さな第一歩
- まとめ
心理的安全性とは何か?
心理的安全性は、チームや組織の「見えない土壌」とも言える重要な要素です。まずはこの概念が何を意味し、自治体職場においてどのような価値を持つのかを理解することから始めましょう。
定義と背景
心理的安全性(Psychological Safety)は、ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン教授によって提唱された概念で、「自分の意見や気持ちを率直に発言しても非難や不利益を受けることがない状態」を指します。この状態にあるチームでは、メンバーが互いの違いを尊重し、挑戦や改善のための対話が活発に行われる傾向があります。
Google社が行った生産性調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、最も成果を上げていたチームに共通していた要素は“心理的安全性”でした。このことからも、業種や規模を問わず、チームの土台となる要素として注目されています。
自治体における重要性
自治体職場において心理的安全性が注目される背景には、いくつかの社会的要因があります。第一に、業務が複雑化し、属人的な対応では限界があること。第二に、若手職員の定着や多様性の確保といった人材面での課題。そして第三に、住民の期待に応える質の高い行政サービスを持続的に提供する必要性です。
こうした課題に対応するためには、現場からの意見が自由に上がり、柔軟な対応や協働ができる組織文化が不可欠です。そのベースとなるのが、心理的安全性なのです。
心理的安全性を阻害する要因

「心理的安全性が低い」と感じる職場では、なぜそのような状況が生まれるのでしょうか?その背景には、組織の文化や日々のコミュニケーションのあり方が深く関係しています。
主な阻害要因
心理的安全性を損なう要因は、必ずしも目に見えるものばかりではありません。たとえば、ミスをすると即座に叱責されるような風土では、誰もが萎縮してしまい、次第に意見を控えるようになります。あるいは、上司が常に指示を出し、部下の提案を受け入れないような一方通行の関係では、対話の土壌が育ちません。
また、「波風を立てないこと」が評価される文化では、表面上は平穏でも、内面では不満や疲弊が蓄積していきます。さらに、多様な価値観を受け入れない風潮も問題です。例えば、異動者や若手職員のアイデアが「うちでは無理」と否定され続ければ、創造性や改善提案の芽は早々に摘み取られてしまいます。
以下のような状況がある場合、心理的安全性は著しく損なわれます。
- ミスを責める風土:小さな失敗でも過剰に責任を問われることで、職員が萎縮してしまいます。
- 一方通行の上意下達:管理職の指示に異論を唱えにくい雰囲気では、現場からの改善提案が止まります。
- 同調圧力の強さ:「波風を立てるな」という無言の圧力が、職員の主体性を奪います。
- 異質性への排除的態度:若手、女性、外部から来た人が疎外感を覚えることで、多様性が失われます。
このような環境では、業務の改善は進まず、離職や職員のメンタル不調にもつながってしまいます。
職場の心理的安全性を見える化するチェックリスト
「心理的安全性があるかないか」は、目に見える数値では把握しづらいものです。そこで有効なのが、定量的に可視化するためのチェックリストです。
心理的安全性チェックリスト(7項目)
以下の質問に対して、5(あてはまる)〜1(あてはまらない)で自己評価を行うことで、職場の現状を見える化できます。
| No. | チェック項目 | 内容の説明 | 自己評価(5〜1) |
|---|---|---|---|
| 1 | ミスをしても非難されない | チーム内でミスをしても、責められることなく冷静に対応できる環境か | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 2 | 難題について自由に意見を言える | 困難な課題についても、自分の意見を安心して表現できる雰囲気があるか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 3 | 多様な個性が受け入れられている | 年齢・立場・価値観の違いにかかわらず、メンバーの多様性が尊重されているか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 4 | チャレンジが推奨されている | リスクを恐れずに新しい試みに挑戦できる風土があるか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 5 | 助けを求めやすい | 困ったときに周囲に相談したり、協力をお願いできる関係性があるか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 6 | 中傷や攻撃がない | 無視、陰口、攻撃的な言動などがなく、互いを尊重し合っているか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
| 7 | 自分の強みが活かされている | 自分のスキルや経験がチーム内で活用されていると実感できるか | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 |
このチェックは、組織の状態を客観的に捉えるきっかけになります。改善の第一歩は、「何が問題なのか」を明らかにすることから始まります。
心理的安全性を高める実践的なアプローチ

職場環境は一朝一夕では変わりませんが、小さな行動の積み重ねで「心理的に安全な組織文化」はつくることができます。
日常に取り入れられる行動改善
まず始めやすいのは、日々のコミュニケーションの質を高めることです。たとえば、朝の挨拶を丁寧に行うことや、部下の努力に対して「見ているよ」「工夫が伝わってくるよ」といった前向きなフィードバックを意識的に伝えること。これだけでも、職員の安心感とモチベーションが高まります。
そのほか、即実践できる行動を以下に抜粋して紹介します。
- 1on1ミーティング:上司と部下が定期的に対話を行うことで、相互理解と信頼関係が育まれます。
- ポジティブなフィードバック:小さな努力や成長を見逃さず、言葉で伝えることが、自己肯定感を高めます。
- 新人支援の仕組み化:OJTではなく、心理的ケアを重視したフォロー体制の整備がカギです。
eラーニングによる継続的学習
時間や予算の制約がある自治体にとって、eラーニングは柔軟かつ継続的に学びを提供できる有効な手段です。心理的安全性に関する研修動画やチェックワーク付きのコンテンツを活用することで、個々の職員が自分のペースで知識を深められます。
特に、管理職向けのリーダーシップ研修や、若手職員が参加しやすいケーススタディ型のeラーニングは、実践に直結しやすく好評です。これらの教材を活用することで、座学だけでなく、行動変容につながる学びが実現できます。
心理的安全性がもたらす“見える”成果
心理的安全性は「気分的なもの」ではなく、実際に組織にさまざまな成果をもたらします。
以下はその代表的な例です。
・アイデアが出やすくなる:自由に発言できる風土が創造性を高める
・住民対応の質向上:職員の心の余裕が、より丁寧な対応につながる
・ミスや不正の早期発見:正直な情報共有がリスク管理に直結する
・業務の円滑化:助け合いやフォローアップが自然に行われる
これは単なる理想論ではなく、Google社の調査結果や、多くの実務事例でも裏付けられた事実です。
明日から取り組む、小さな第一歩
最後に、心理的安全性を高めるための「小さな第一歩」を書き出してみましょう。大切なのは、続けやすく、誰にでもできることから始めることです。
- 「朝、最初に会った人に笑顔で挨拶する」
- 「1on1ミーティングを月1回始める」
- 「会議で必ず1回、後輩の意見に耳を傾ける」
- 「“ありがとう”を1日1回は言葉にする」
組織を変えるのは、リーダーだけではありません。一人ひとりの行動の積み重ねこそが、心理的安全性のある職場を生み出します。
まとめ
心理的安全性は、自治体職場における「安心して発言できる」「互いを尊重できる」空気をつくる基盤です。年功序列や縦割り文化が残る環境では、若手の声が届きにくく、挑戦や改善が停滞しがちです。しかし、ミスを責めない、違いを認め合う、意見を歓迎する文化が育てば、職員の意欲と連携が自然に高まり、業務の質や住民サービスにも良い影響を与えます。
また、心理的安全性は職員のメンタルヘルスや離職防止にもつながる重要な視点です。小さな実践から始めることで、組織文化は着実に変わっていきます。一人ひとりの行動が、働きやすく、信頼される自治体づくりの一歩となるのです。
自治体の職場環境整備研修
自治体における職場環境の整備は、職員の働きがいを高め、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。多様な人材が能力を発揮できる環境づくりや、柔軟な働き方への対応は、持続可能な行政運営に欠かせません。職場環境を整えることで、職員の定着率やエンゲージメントが向上し、住民サービスの質の維持・向上にもつながります。この研修では、自治体における職場環境整備の基本的な考え方や実践のポイントを解説し、組織の活性化と働きやすさを両立するための視点を養います。
2週間無料お試しはこちら