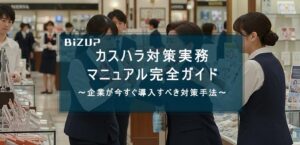【買い切り講座】自治体DX推進対応│現場で使えるDX改革を学ぶ

自治体におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、今や「避けては通れない変革」として全国の自治体に広がりつつあります。多くの自治体がオンライン申請、電子決裁、チャットボットなどの導入を進め、住民サービスの向上や職員の業務効率化に一定の成果を上げてきました。
たとえば、ある中核市では、住民票のコンビニ交付をはじめとした行政サービスのオンライン対応により、住民の待ち時間を大幅に削減。職員にとっても申請受付や書類確認の負担が軽減され、「業務にゆとりができた」と好評を得ています。
しかしその一方で、「導入したが、思ったほど現場で活用されていない」「最初は使っていたが紙に戻ってしまった」といった声も聞かれます。こうした“形骸化”の原因は、ツールの導入が目的化し、本来の業務改革の視点が抜け落ちている点にあります。
本記事では、単なるツール導入ではなく、現場が本当に変わるための「実践的なDX」の進め方を紹介します。住民にとって便利で、職員にとっても働きやすい、そんな未来を目指すヒントをお届けします。


自治体業務の効率化・ペーパーレス化・AI化実践研修
動画数|11本 総再生時間|164分
この研修では、自治体DXを成功に導くためのBPR、AI・RPA、ペーパーレス化の実践方法を体系的に学びます。制度・計画に基づいた戦略と現場実践を事例を交えて習得します。
動画の試聴はこちら目次
なぜ進まない?ペーパーレス化・オンライン化の壁
多くの自治体で、DXのスタートラインとも言える「ペーパーレス化」「オンライン化」が思うように進まない要因には、いくつか共通点があります。
こうした障壁がある中でも、ペーパーレス化やオンライン化を推進して成果を上げている自治体も増えています。たとえば、ある町村では庁内の稟議書をすべて電子化し、年間で2万枚以上の紙の削減を実現しました。さらに、回覧速度が格段に上がったことにより、意思決定の迅速化も同時に達成されています。
このような成功事例からわかるように、課題はあるものの、解決策を講じてひとつずつ乗り越えていくことが可能です。DXは一足飛びではなく、段階的に文化を変えていくプロセスなのです。
業務プロセスの可視化で現場の「納得感」を得る
DXの定着には、現場職員が「この仕組みは自分たちの業務を楽にするものだ」と実感することが不可欠です。そのためにはまず、業務の現状を可視化する作業が必要です。
業務フロー図の作成や、職員へのヒアリング、時間配分の実測などを通じて、「どの業務がどこで滞っているのか」「誰がどのように対応しているのか」を明らかにします。これにより、無駄な工程や重複業務が浮き彫りになり、改善の余地が具体的に見えてきます。
さらに、現場の職員自身が業務のムダや非効率を“自分ごと”としてとらえることで、BPR(業務改革)への理解と納得が深まり、能動的に変革へ参加するようになります。
実際に、ある市では部門ごとに業務の棚卸しを行い、「誰が・いつ・どのように・なぜ」その業務を行っているのかを細かく分析。その結果、年間30時間以上を費やしていた手作業のチェック業務が不要であることが判明し、AIによる自動確認へ移行されました。
この段階での成功体験こそが、「やらされるDX」から「自分たちで創るDX」への転換点になるのです。業務プロセスの可視化は単なる作業ではなく、現場のモチベーションを高め、組織全体に変革の風を吹き込む第一歩となります。
BPRとICT導入で“形だけ”から“定着”へ
業務の可視化によって改革の方向性が見えたら、次はそれに合わせたICT導入が必要です。ここで重要なのは「ツールありき」で進めるのではなく、「業務に合った形で最適なツールを導入する」という発想です。
たとえば、決裁業務を電子化したいのであれば、まずは決裁フローを簡素化し、承認ルートを明確にする必要があります。そのうえで、クラウドベースのワークフローシステムを導入すれば、業務の標準化・迅速化が可能になります。
また、文書共有においても、全庁共通のドキュメント管理システムを整備し、検索性とアクセス権限のルールを整えることで、「どこに保存したか分からない」「勝手に削除された」といったトラブルを未然に防げます。
成功している自治体では、こうしたICT導入の前に必ず「業務設計の見直し」が行われています。この順番を誤らないことが、DX成功の分かれ目と言えるでしょう。
AI・RPAの併用による段階的ステップアップ
定型的で繰り返しが多い業務は、AIやRPAの得意分野です。BPRで明らかになった「手作業が多く、人手に頼っている業務」は、まさに自動化のチャンスです。
たとえば、住民からのよくある質問への対応は、AIチャットボットが活用できます。24時間いつでも問い合わせが可能となり、職員の窓口対応時間が減ることで、より複雑な案件や人にしかできない業務に集中できます。
RPAについても、帳票の自動作成や、他システムへのデータ入力など、これまで人が行っていた「画面の切り替えと転記作業」を代替できます。これにより、作業ミスの削減と処理スピードの向上が期待できます。
多くの自治体では、まず一部業務から試験導入し、成果が出たものを他部門へ横展開しています。この「段階的導入」が、組織内の抵抗感を抑えながら確実に浸透させるポイントです。
研修とルール設計で文化としてのDXを根づかせる
DXは単なるシステムの導入ではなく、働き方や組織文化の変革でもあります。だからこそ、定着には「研修」と「ルール設計」が欠かせません。
まずは、DX推進の背景や目的を全職員に共有する「全体研修」を実施します。次に、実際の業務に即した操作トレーニングや、導入したICTツールの使い方研修を行います。これにより、使い方がわからずに使わなくなるという事態を防げます。
加えて、電子決裁のフォルダ名やファイル形式の統一、クラウド文書の命名ルール、業務日報の入力フォーマットなど、「使い方のルール」を明文化することも重要です。これにより、誰が使っても同じ品質・スピードで業務が遂行できる環境が整います。
成功体験の共有も文化醸成には有効です。たとえば、DXによって削減できた時間や、住民からの感謝の声などを可視化し、庁内で発信することで、他の部門にも良い影響を与えることができます。
他自治体の成功事例と外部評価につなげるコツ
全国では、さまざまな自治体がDX推進において成果を上げています。中には、総務省のモデル事業に採択されたり、メディアで取り上げられたりと、外部からの評価を受けている自治体もあります。
このような評価は、職員のモチベーション向上につながると同時に、住民からの信頼獲得にも大きく寄与します。そこで重要になるのが「成果の見える化」です。
たとえば、導入前後の業務時間や紙使用量の比較、住民満足度の変化、申請処理時間の短縮率など、数値で示せる成果を積極的に発信しましょう。また、SNSや自治体ホームページでの発信も有効です。
他自治体との情報交換の場に参加することもおすすめです。互いのノウハウを共有することで、取り組みの幅が広がり、さらなる改善につながります。
| 指標項目 | 導入前 | 導入後 | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 年間紙使用枚数 | 50,000枚 | 12,000枚 | ▲76% |
| 1件あたりの申請処理時間 | 3日 | 1日 | ▲67% |
| 住民満足度(5段階) | 3.2 | 4.5 | +40% |
| 業務時間の年間削減合計 | – | 450時間 | 新規成果 |
おわりに:市民が「便利になった」と感じるDXとは
自治体DXの最終的なゴールは、住民が「便利になった」「変わった」と実感できることです。そのためには、システムやツールを導入するだけでは不十分です。業務そのものの見直し、文化の醸成、そして職員の意識改革が伴ってはじめて、DXは本当の意味で「定着」します。
今日から始められる一歩は、小さな業務の可視化や、同僚との共有からかもしれません。それが組織全体の流れを変え、やがては自治体としての先進的な取組へとつながるでしょう。
「うちの町、便利になったよね」——そんな住民の声が聞こえてくる未来を、今日から一緒に築いていきましょう。