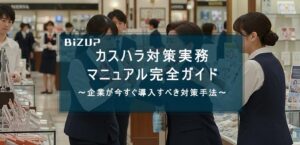働きながら宅建合格!未経験の会社員が最短で受かる勉強法とは
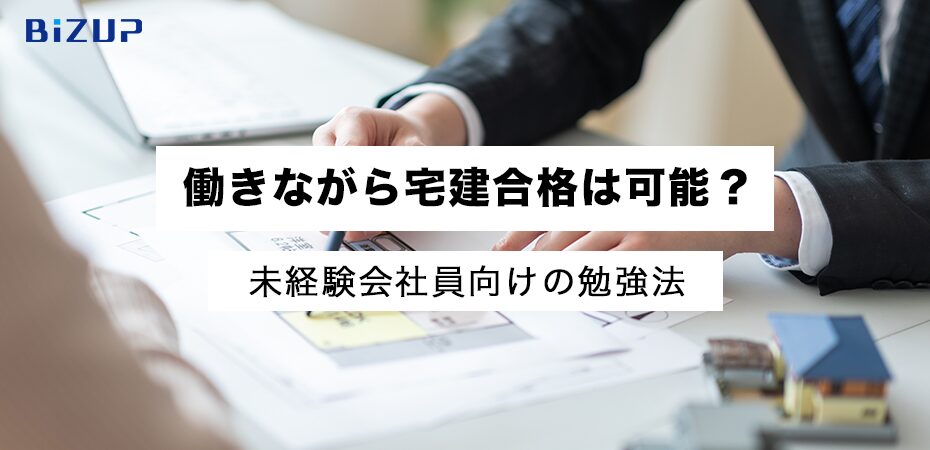
働きながら宅建に合格する――。それは決して夢物語ではありません。特に異業種から不動産業界への転職や、キャリアアップ・副業を視野に入れる方にとって、宅建は最も現実的かつコスパの良い国家資格の一つです。
宅地建物取引士(通称:宅建士)は、法律知識と取引の実務的スキルを証明できる国家資格であり、不動産業界はもちろん、建設・金融・法律関連でも重宝されます。資格手当が支給される職場も多く、転職市場での「武器」になるのは間違いありません。
⇒ 宅建(宅地建物取引士)資格試験対策講座┃e-JINZAI lab.
目次
- 働きながらの宅建勉強で挫折する人の共通点
- 挫折しないための戦略:スマホ学習×eラーニング活用法
- おすすめの宅建オンライン講座3選(2025年版)
- 社会人のための「半年合格」学習モデル(週10〜15時間ペース)
- まとめ:働きながらでも、宅建合格は“戦略”で勝てる
- 関連する記事
働きながらの宅建勉強で挫折する人の共通点

モチベーションが続かない典型パターン
社会人にとって最大の壁は、継続的なモチベーションの維持です。特に試験日まで半年以上ある宅建試験では、初期のやる気が途中で失速してしまうケースが多く見られます。原因は、以下のようなものが多いです:
- 明確な学習スケジュールがない
- 勉強が単調で達成感が薄い
- 学んだ内容が実生活と結びつかない
独学で理解が進まず脱落するケース
宅建は法律問題が多く、独学だと「何をどう覚えるか」が分からないという人も少なくありません。特に異業種から挑戦する場合、「民法」「宅建業法」など初見の概念が多く、間違った理解のまま進んでしまうこともあります。これは、後で模試の点数が伸び悩む原因にもなります。
挫折しないための戦略:スマホ学習×eラーニング活用法
働きながら宅建合格を目指す社会人にとって、講座選びは合否を左右する重要なステップです。とくに限られた時間の中で効率よく学習するためには、1回の講義時間が短く区切られており、通勤中や昼休みなどのスキマ時間でも活用しやすい設計であることが不可欠です。また、単に講義を視聴するだけでなく、試験で問われる出題範囲が体系的に整理されていて、学習に偏りや抜けが生じない構成になっているかどうかも大きなポイントとなります。
スキマ時間で成果を出す学習アプローチ
通勤時間、昼休み、家事の合間…これらを「学習時間」に変えることで、忙しい社会人でも継続的な勉強が可能になります。具体的には以下のような使い方が有効です:
- 通勤中:スマホアプリで一問一答や音声講義
- 昼休み:10分だけ過去問演習
- 就寝前:1単元だけ動画講義視聴
この「細切れ時間の積み重ね」こそが、働きながらでも合格できる大きな鍵です。
短時間集中型eラーニングの効果と活用術
今注目されているのが、1回10〜15分で学べるeラーニング講座です。理解度に応じて何度も繰り返し学べるため、短時間でも知識が定着しやすいのが特徴。スマホ対応や倍速再生機能がある講座なら、さらに効率が上がります。
特に、図解や具体例で説明されるコンテンツは、法律用語に馴染みのない異業種出身者にとって理解の助けになります。
おすすめの宅建オンライン講座3選(2025年版)
働きながら宅建合格を目指す社会人にとって、講座選びは合否を左右する重要なステップです。
とくに限られた時間の中で効率よく学習するためには、1回の講義時間が短く区切られており、通勤中や昼休みなどのスキマ時間でも活用しやすい設計であることが不可欠です。ここからは、忙しい社会人向けに、オンラインで学べる宅建講座を3つ紹介します。
忙しい社会人向け講座の選び方
講座を選ぶ際にチェックすべきポイントは次の通りです:
- 1講義が短時間で完結しているか
- スマホ対応しているか(音声のみ再生も可)
- 過去問や模試、質問対応があるか
- 合格者の実績が明示されているか
特に初学者にとっては、民法や不動産関連法などの難解な法律用語をそのまま丸暗記するのではなく、図解や具体的な事例を交えて視覚的かつ直感的に理解できる講座が効果的です。さらに、市販のテキストや問題集との併用を前提とし、アウトプットを意識した設計であるかどうかも確認しておきたいところです。
こうした講座は、ただ知識を詰め込むのではなく、学習のペースメーカーとしても機能するため、継続的に学習する習慣が自然と身につきやすくなります。
編集部おすすめ:学習スタイル別サービス比較(改訂版)
編集部が選んだおすすめの宅建オンライン講座を学習スタイル別に比較すると、社会人に特に人気なのが「スタディング宅建講座」です。こちらはスマホに完全対応しており、短時間で学べる動画とAIによる復習機能を活用することで、忙しい日常の中でもテンポよく学習を進めることができます。
一方、講師とのやり取りや個別の添削指導を希望する方には「アガルート宅建講座」が適しています。こちらは講義の質が高いことに加えて、理解が浅い分野に対してピンポイントで質問ができる環境が整っており、初学者にとって心強いサポート体制が魅力です。
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| スタディング宅建講座 | スマホ対応・AI復習・時短学習設計 | 忙しい社会人全般 |
| アガルート宅建講座 | 添削指導+講義の質が高い | 過去問に沿って対策をしたい人 |
| e-JINZAI lab. 宅建講座 | 図解・事例・PPTで徹底解説、実務対応◎ | 初学者・実務に役立つ内容を知りたい人 |
そして、図解や事例を豊富に用いた、実務との接続も意識した講義スタイルを求める方には、e-JINZAI lab.の「宅地建物取引士資格試験対策講座」が最も適しています。市販テキストと連動しながら、PPTや動画で要点を補足し、過去問演習と合わせて着実に理解を深められるため、法律を初めて学ぶ方でも合格ラインに達することが十分可能です。


宅建(宅地建物取引士)資格試験対策講座
動画数|76本 総再生時間|1641分
宅地建物取引士資格試験の合格を目指す初学者・既修者向けに構成した実践的な対策講座です。権利関係・宅建業法・法令上の制限・税法など出題分野を体系的に整理し、重要テーマを中心に講義を展開。
動画の試聴はこちら社会人のための「半年合格」学習モデル(週10〜15時間ペース)
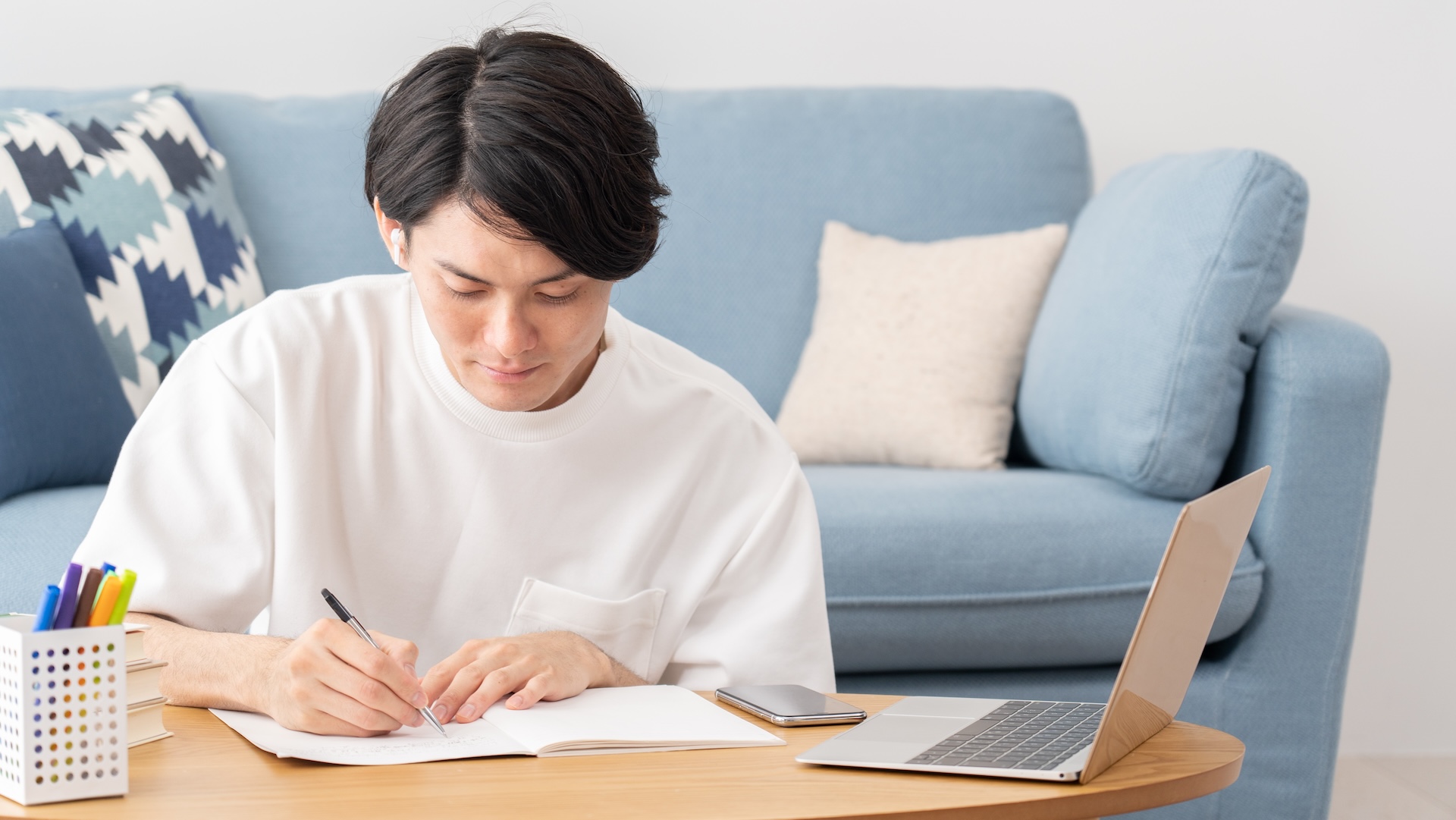
働きながら宅建に合格するには、効率と継続を重視した学習設計が不可欠です。とくに平日はまとまった時間を確保しづらいため、通勤中や休憩時間などのスキマ時間に学習を進めつつ、週末に演習と復習で定着を図るスタイルが効果的です。以下は、e-JINZAI lab.の「宅地建物取引士資格試験対策」を受講した場合の、半年で宅建合格を目指すための学習モデルです。
6か月間の学習スケジュール全体像
| 月数 | 学習範囲 | 学習目的 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 民法の基礎(制限行為能力、意思表示、代理、物権など) | 基礎用語や法的思考の型を身につける |
| 2か月目 | 民法応用(抵当権・債権分野)/借地借家法・登記法など | 実例理解を深めて条文と判例に慣れる |
| 3か月目 | 宅建業法(制度、業務規制、重要事項説明など) | 高配点分野で得点源を構築する |
| 4か月目 | 法令上の制限・税法 | 暗記項目を整理し、数字や制度の理解を深める |
| 5か月目 | 過去問演習・苦手分野の復習 | アウトプットを重視し得点力を磨く |
| 6か月目 | 模試・総復習 | 試験形式に慣れ、実戦力を完成させる |
月別の学習内容と講義活用イメージ
1か月目では、宅建試験の土台となる民法を中心に学びます。たとえば、「制限行為能力者」「意思表示」「代理」など、法律初学者がつまずきやすい概念を、「宅建士試験の傾向と対策(76分)」や「代理・時効(43分)」などの講義を通じて理解します。図解や事例を交えた動画講義を活用することで、文字だけでは理解しづらい論点もスムーズに把握できます。
2か月目では、抵当権や債権分野を中心に、より応用的な民法の理解を深めます。同時に、借地借家法・区分所有法・不動産登記法などの周辺法もこのタイミングで学習します。1講義あたり10〜30分程度なので、平日に1〜2本、週末にまとめて視聴すれば十分にカバー可能です。
3か月目は、配点が最も高い宅建業法の集中学習期間です。「重要事項説明」や「37条書面」など頻出テーマに加え、「手付金」「クーリングオフ」「契約不適合責任の制限」など、得点しやすい知識を確実に習得します。過去問演習もこの時期から取り入れ始め、知識の定着度を測っていきます。
4か月目には、暗記中心の法令上の制限(都市計画法・建築基準法・農地法など)や税法を扱います。出題される法令は多岐にわたりますが、出題傾向が安定しているため、効率的に学習すれば十分得点が可能です。図表や比較リストを自作すると記憶に定着しやすくなります。
5か月目以降は過去問中心のアウトプット期に入り、各分野の理解度を確認しながら、苦手分野を重点的に復習します。6か月目には模擬試験形式で本番を想定した演習を行い、得点力の仕上げを行います。時間配分の調整や解答戦略もこの時期に固めておくと安心です。
週間学習モデル(目安:週10〜15時間)
| 曜日 | 内容 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 月〜金 | 通勤中の音声講義/スマホアプリで一問一答 | 60〜90分/日 |
| 土曜日 | 動画講義2〜3本+過去問演習20〜30問 | 約2〜3時間 |
| 日曜日 | 間違いノートの復習+確認テスト | 約1.5〜2時間 |
このモデルでは、「学習の質」と「継続性」の両立を重視しています。毎日短時間でも教材に触れ、週末に復習と演習を行うことで、知識の定着を図りながら合格レベルまで引き上げていきます。
まとめ:働きながらでも、宅建合格は“戦略”で勝てる
宅建は難易度の高い試験ということもあり、働きながら宅建に挑戦する社会人、とくに異業種出身の方の中には、「働きながらでも合格はできるのだろうか…」と不安に思う方も多いかもしれません。ですが、「スマホ学習」や「短時間eラーニング」といった現代型の勉強法をうまく活用すれば、合格は現実的な目標です。重要なのは、完璧を目指すのではなく「やめずに続ける」ことです。計画的に繰り返し学習を重ねることで、誰でも確実に合格に近づけます。知識の積み重ねが将来のキャリアにもつながることを信じて、勉強を続けてみてください。
関連する記事
- 【2025年最新】宅建とは?試験の難易度や勉強時間を解説
- 宅建取得で年収は上がる?不動産業の給与体系を徹底解剖
- 働きながら宅建合格!異業種会社員が最短で受かる勉強法とは(この記事)