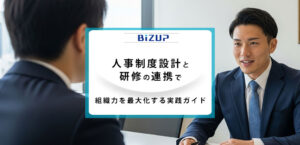納得される人事評価制度を作ろう。360度評価のメリット・注意点を解説!
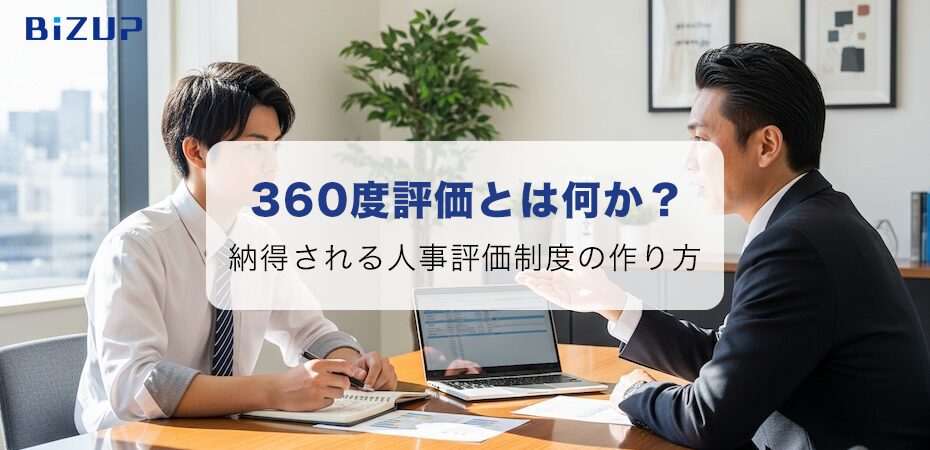
KEYWORDS 人事
「上司からの評価だけでは不公平だ」
「自分のがんばりをもっと正しく見てほしい」
こんな声が、社員の中から聞こえてきたことはありませんか?
近年、人事評価のあり方が大きく変わってきています。
特に注目されているのが、「360度評価(さんびゃくろくじゅうどひょうか)」という方法です。
これは、上司だけでなく、同僚・部下・関係者など、まわりの人全員が「その人の働きぶりを評価する」しくみです。この記事では、「360度評価とは何か?」という基本から、導入するメリットや注意点、活用のコツまでわかりやすく解説します。
目次
こんな悩み、ありませんか?

上司の評価がすべてになっている
「結局、上司に気に入られてるかどうかじゃないの?」
そんな声が社内に出てしまうと、社員のやる気が下がってしまいます。
人事評価が「上司の主観だけ」で行われている場合、どうしても偏りが出てしまうことがあります。
チームでがんばる仕事が多く、個人の貢献が見えづらい
最近の仕事は、1人で完結する仕事よりも、チームで協力する仕事が増えてきています。すると、「誰がどれだけ貢献したのか」が見えにくくなり、正しく評価しにくくなります。
評価される側が納得しにくい
評価された内容に対して、
「それってちゃんと見てたの?」
「そんなふうに思われていたなんて…」
と、社員が納得できずに不満を持ってしまうこともあります。
360度評価とは?
いろんな立場の人が“その人”を評価する方法
360度評価とは、上司だけでなく、同僚・部下・他部署のメンバーなど、複数の関係者が評価する方法です。つまり、“一方向”ではなく、あらゆる角度(=360度)からの視点でその人を見て評価するという考え方です。
たとえば、こんな感じで評価されます
| 評価する人 | 内容の例 |
| 上司 | 業務の成果、目標の達成度など |
| 同僚 | チームワーク、コミュニケーションのとり方 |
| 部下 | リーダーシップ、部下への対応・育成の姿勢 |
| 他部署 | 協力姿勢、他部署への配慮や情報共有 |
このように、普段の仕事ぶりをいろんな視点で見て評価することで、より公平で立体的な評価が可能になります。
360度評価のメリット
1. 多面的な評価で“本当の姿”が見えてくる
人には、上司の前では緊張してしまうけれど、同僚や部下とは自然体で接するという面がありますよね。
360度評価を使えば、さまざまな視点からその人の「普段の行動」や「周囲への影響力」なども見えるようになります。
2. 社員の納得感・信頼感が高まる
「1人の上司の意見だけじゃない」
「いろんな人が見てくれてる」
という安心感があるため、評価に対する納得感が高まりやすくなります。
これにより、人事評価制度全体への信頼が向上し、社員のやる気も引き出しやすくなります。
3. 上司自身が“見られる立場”になる
部下からの評価があることで、上司も「ただ命令するだけ」では通用しません。
部下との接し方や育成への姿勢も評価に反映されるため、マネジメントの質向上にもつながります。

360度評価の注意点・課題
1. 感情的な評価・人気投票になりやすい
具体的な課題例:
- 「いつも明るくあいさつしてくれるから高評価」
→ 実際の仕事の成果やチームへの貢献度とは関係がないのに、“感じがいい人”が評価されやすくなる。 - 「意見をあまり言わないから低評価」
→ 静かにコツコツ仕事をしている社員が本来の働きぶりに関係なくマイナス評価される。 - 「仲がいい同僚だから、悪く書けない」
→ 評価の目的が“客観的な働きぶりの確認”ではなく、人間関係に左右される“人気投票”のようになってしまう。
このように、感情や印象で評価が決まってしまうと、「本当に成果を出している人」が正しく評価されなくなり、社員の不満が高まります。
2. 匿名性がないと本音が出にくい
具体的な課題例:
- 「部下が上司の評価を書くが、あとでバレるかも…と不安」
→ 正直に書けず、本当は困っていることがあっても『問題なし』と回答してしまう。 - 「同じチームの人を評価するけど、評価後も一緒に仕事をするから遠慮してしまう」
→ 「気まずくなるのが嫌だから良い点しか書かない」=本音が評価に反映されない。 - 「後で自分の評価もやり返されるかも…」という不安
→ 評価を攻撃や復讐の手段と勘違いする人が出てくるリスクもあり、制度への信頼が下がる。
匿名性が確保されないと、評価が正しく機能せず、表面的で意味のないものになってしまいます。
3. 評価結果の伝え方がむずかしい
具体的な課題例:
- 「“チームへの貢献が足りない”と書かれていたけど、誰に言われたのかわからずモヤモヤ…」
→ 根拠や背景が不明なまま結果だけ伝わると、不信感が残る。 - 「“協調性が低い”とフィードバックされたが、改善点がわからない」
→ 評価は受けたものの、どう行動を変えればいいのかがわからず、育成につながらない。 - 評価を見て「誰が書いたのか」を詮索し、人間関係がギクシャク
→ 特に人数が少ない職場では、評価者の特定がしやすくなりトラブルの原因になる。
本人への伝え方を間違えると、360度評価が逆効果になり、信頼関係の悪化や制度への不満につながってしまうことがあります。
対策
評価内容をそのまま本人に伝えてしまうと、「誰がこんなことを書いたのか」と不必要なトラブルを招く恐れがあります。そのため、フィードバックは慎重に扱う必要があります。
理想的な対応としては、専門の人事担当者や外部コンサルタントが内容を整理し、客観的にまとめて本人へ伝えることです。その際には、感情的な表現を避け、事実や具体的な行動に基づいたフィードバックを心がけることが大切です。
| 課題 | リスク | 対策のポイント |
| 感情的な評価 | 人気投票化・評価の不公平 | 評価項目を「行動ベース」に明確化する |
| 匿名性の欠如 | 正直な意見が出にくい | 評価は匿名で実施、本人への伝達も配慮 |
| フィードバックの難しさ | 不信感・モチベーション低下 | 評価のまとめ・伝え方は専門家が支援するのが理想 |
360度評価を成功させるためのポイント

評価項目はシンプルに、行動ベースで
評価項目は、できるだけ具体的な行動に基づいて設定することが大切です。
- ×「周囲への配慮がある」
- 〇「困っているメンバーがいたら声をかけてサポートしている」
このように、誰が見ても判断できる表現に言いかえることで、納得感のある評価につながります。
目的をハッキリさせる
「評価のためにやっているのか」
「成長のためのフィードバックなのか」
目的があいまいだと、現場の理解を得るのは難しくなります。まずは、「360度評価は社員の成長や組織の改善のために活用する」という意図を、しっかりと伝えることが重要です。
最初はテスト導入もOK
いきなり全社導入する必要はありません。まずは一部の部署で試験的に実施し、問題点を洗い出して改善しながら少しずつ範囲を広げていく方法がスムーズです。
ビズアップの人事コンサルでできること
「360度評価ってうちの会社に合うのかな?」
「導入しても運用が難しそう…」
そんな悩みを持っている方におすすめなのが、ビズアップの人事コンサルサービスです。
制度の設計から運用支援まで、まるごとサポート
- 自社の風土や組織構造に合った360度評価の設計
- 評価項目の作成、フィードバック方法の支援
- 評価者向け研修や運用マニュアルの作成
- 評価結果の整理と分析、課題の抽出と改善提案
すべて専門のコンサルタントが丁寧にサポートします。
中小企業にもやさしいサービス設計
- 社員数30名〜300名まで幅広く対応
- 「最初に何をすればいいのか」から一緒に考えてくれる
- 専門的な知識がなくてもOK!
はじめて評価制度を見直す企業にもやさしい内容です。
無料相談・お見積もりも受付中!
まずは、「どんなサービスか知りたい」「他社の事例が見たい」という方のために、無料相談&お見積もりが可能です。
まとめ
360度評価は、多くの人の目で“その人の本当の姿”を見つけ、評価につなげるという、今の時代に合った評価制度です。
ただし、しっかりと目的を持ち、評価の方法や伝え方に注意しないと、逆にトラブルの原因にもなりかねません。
「公正で、社員が納得できる評価制度をつくりたい」
そんなときは、人事制度づくりのプロと一緒に進めることが成功の近道です。
あなたの会社にも、本当に意味のある評価制度を。
まずは無料資料請求から始めてみませんか?