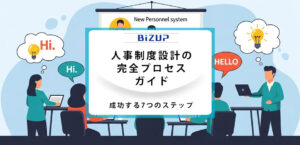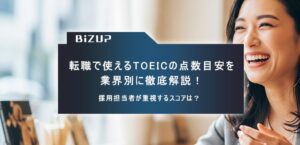年俸制の人事評価、ちゃんとできていますか?~制度の特徴と落とし穴、見直しのヒントをわかりやすく解説~
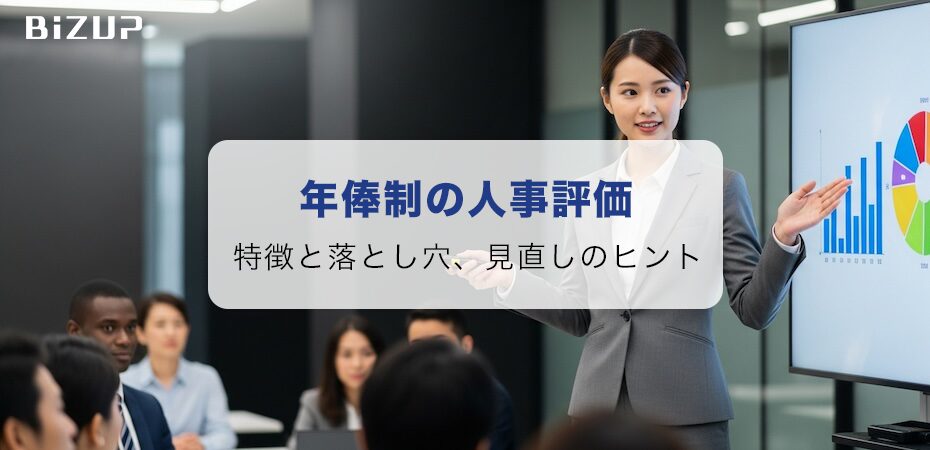
KEYWORDS 人事
「年俸制にしているけど、評価の仕方があいまい…」
「毎年の金額だけ決めていて、評価制度は実質ないに近い」
そんな声を、人事や経営の現場からよく聞きます。
年俸制(ねんぽうせい)は、「毎月の給料」ではなく、1年単位で給与を決める仕組みです。よく「成果主義」「高年収の社員向けの制度」といったイメージがありますが、正しい運用をしなければ、トラブルのもとになることもあります。
この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。
- 年俸制の特徴とよくある誤解
- 年俸制でうまく人事評価をするためのポイント
- 制度運用でよくある課題とその解決策
目次
- 年俸制ってなに?月給制とどう違うの?
- 年俸制のメリットとは?
- よくある誤解と運用上の課題
- 年俸制の人事評価をうまく機能させるポイント
- 具体例で見る課題と解決のイメージ
- ビズアップの人事コンサルでできること
- まとめ
年俸制ってなに?月給制とどう違うの?

年俸制とは
年俸制とは、1年間の給与をあらかじめまとめて決める制度です。
例:「年収600万円」と決めたら、12か月に分けて「1か月50万円」として支給する形です。
この制度は、以下のような人に多く使われます。
- 管理職や専門職など、責任や成果が大きいポジション
- 業績評価に連動した報酬が必要な人
- 外資系企業や成果重視の会社
月給制との違い
| 比較項目 | 年俸制 | 月給制 |
|---|---|---|
| 給与の決め方 | 1年単位でまとめて決定 | 毎月の基本給+手当など |
| 評価のタイミング | 年に1回が多い | 半年ごと、年2回の見直しが多い |
| 成果との連動 | 強く意識される | やや弱いこともある |
| 柔軟性 | 高い(個人契約的) | 安定性がある |
年俸制のメリットとは?
1. 成果に応じた報酬が可能
年俸制は、「成果主義」ととても相性がよい制度です。
つまり、「がんばった人」「成果を出した人」が大きく評価され、収入にも反映しやすいという特徴があります。たとえば、売上目標を大きく超えた営業社員がいれば、翌年の年俸を大幅に上げるなど、メリハリのある報酬設計がしやすくなります。
2. 社員のやる気や責任感が高まる
年俸制では、最初に1年間の金額を決めることで、その年の期待値や役割をしっかり伝えることができます。これは、社員にとっても「自分は会社からどう期待されているか」を明確にする材料になり、やる気や主体性を引き出す効果があります。
3. 管理しやすく、コストが読みやすい
年俸制を導入すると、年間で支払う人件費があらかじめ計算できるので、会社側にとっても人件費の予算管理がしやすくなります。

よくある誤解と運用上の課題
ここまで聞くと、「年俸制って便利で理にかなってる制度だな」と思うかもしれません。でも実際には、運用に失敗している企業も多く、以下のような課題が発生しています。
1. 「年俸=固定給」と思い込む
「年俸で払っている=評価不要」と勘違いすると、社員のモチベーション低下につながります。
ありがちな誤解:
「年俸で払ってるんだから、評価なんていらないよね?」
「年俸制にしたから、毎月一定額でOKでしょ?」
このように年俸制=成果連動ではなく、ただの固定給と勘違いされるケースがあります。結果として社員は「何を頑張れば年俸が上がるのか」が見えず、やる気を失います。
2. 評価基準があいまい
年俸制においても、評価はとても重要です。
ところが、「何を見て評価するのか」がはっきりしていないと、
- なぜ年俸が上がったのか/下がったのか、説明ができない
- 上司の主観で決まっているように見えて、不公平に感じる
- 結果として、優秀な人が辞めてしまう
といった問題が起こります。
3. 年度途中でフィードバックがない
年俸制では「年に1回しか評価しない」という運用が多いため、1年間なにもフィードバックされないまま働く社員が出てきます。
- 「この方向で合ってるのかな?」
- 「何を期待されてるのかわからない」
こうした声が出てきやすくなり、コミュニケーション不足から組織の一体感も薄れていくのです。
4. 賞与との関係が不明確
年俸制では、年収に賞与(ボーナス)を含めるかどうかが企業によって違います。
そのため、社員の中には「ボーナスがもらえると思っていたのに、年俸に含まれていた」といったミスマッチや誤解が生じることも。→こうしたケースでは、制度への信頼が下がりやすくなります。
 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。
年俸制の人事評価をうまく機能させるポイント

1. 評価基準を明確にする
何を評価し、どうやって年俸に反映させるのかを誰にでもわかるように明文化することが大切です。
たとえば:
- 売上や利益などの成果だけでなく
- 行動やチームへの貢献、リーダーシップなども評価に含める
といった形で、複数の観点から評価する設計が有効です。
2. こまめなフィードバック
たとえ年俸が年1回の改定であっても、3か月〜半年ごとに面談を実施して、途中経過を確認するようにしましょう。
- 目標に対する進み具合
- 強み・課題・改善ポイントの確認
- 次のステップに向けたアドバイス
こうしたコミュニケーションが、年俸制度への信頼と納得感を高めます。
3. 社員への制度説明を徹底する
- 「賞与は含まれているのか」
- 「何を達成すれば年俸が上がるのか」
これらを全社員に共有することで、制度への信頼性が高まります。会社の側が「伝えたつもり」でも、社員は理解していないことが多いため、制度説明会やQ&Aの機会を設けることが大切です。
具体例で見る課題と解決のイメージ
たとえば、あるIT企業では年俸制を導入していましたが、年俸額の見直しは社長と幹部数名だけで行われており、現場マネージャーの声が反映されていませんでした。その結果、実際に成果を出していた中堅社員が「評価されていない」と感じて退職してしまい、現場のパフォーマンスが大きく下がったという事例があります。
このようなケースでは、現場のリーダーや社員本人との定期的な面談を通じて、情報をきちんと吸い上げて評価に反映させることが不可欠です。
ビズアップの人事コンサルでできること
年俸制の評価制度づくりで悩んでいる企業には、人事制度の専門家によるサポートが効果的です。
特徴① 制度設計から運用までサポート
- 年俸制に合った評価制度設計
- 評価基準の明文化
- 社員説明用資料・説明会の実施
- 管理職向け研修
「年俸制にしたけど、評価制度が追いついていない」
「成果を反映した年俸の決め方がわからない」
ビズアップの人事コンサルでは、そんなお悩みに、経験豊富なコンサルタントが伴走支援します。
特徴② 中小企業の導入実績が豊富
- 社員数30〜300名規模の企業に対応
- 部分的な見直しから全体設計まで柔軟に対応
- 初めての導入でもわかりやすい支援
「まずは内容を見てみたい」「他社の事例も知りたい」という方には、無料の資料請求とお見積もりサービスをご用意しています。
まとめ
年俸制は成果主義に対応できる柔軟な制度ですが、評価があいまいだと制度が形骸化します。
- 「どんな成果・行動が評価されるのか」
- 「なぜその金額なのか」
これに答えられる制度設計と運用が、社員の信頼とやる気を高めるカギです。
制度設計に不安がある企業は、まず無料相談からスタートしてみてはいかがでしょうか?
ビズアップの人事コンサルティングサービス