基本情報技術者試験に合格するためのアルゴリズム勉強法
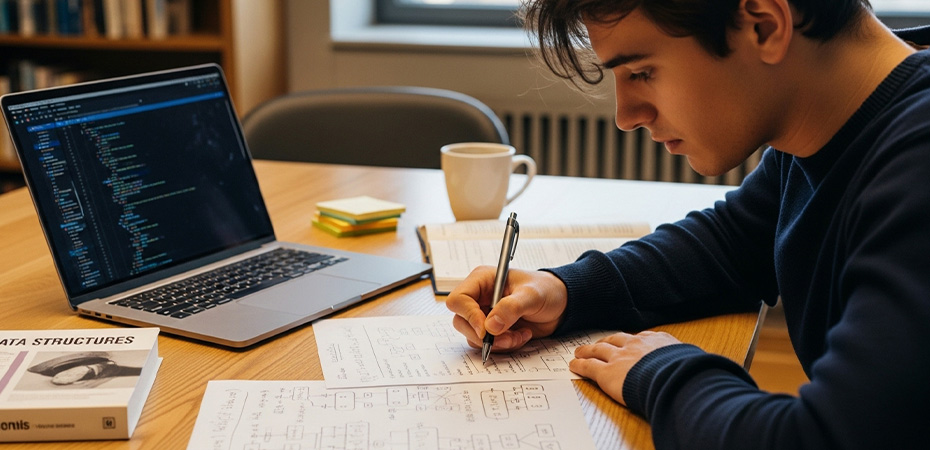
基本情報技術者試験は、ITエンジニアとしての基礎力を測る国家試験です。近年はCBT形式で実施され、年間11万人近い受験者が挑戦しています。合格率はおよそ40%前後と、国家資格の中では比較的高めですが、特に「アルゴリズム分野」で苦戦する受験者が多いのも事実です。
アルゴリズムは、プログラミング的思考力を試す問題として科目Bに多く出題されます。探索やソートのような典型的な手法を理解しなければ正答できず、さらに時間制限の中で効率的に解答するスピードも求められます。つまり、この分野を攻略できるかどうかが合否を分ける大きなポイントになるのです。
この記事では、特につまずきやすいアルゴリズムの勉強法に焦点を当て、効率よく学習を進めるための具体的な方法を紹介します。さらに、添付いただいた「基本情報技術者講座」の内容を踏まえ、eラーニングを活用した実践的な学習ステップも提案します。
目次
- 基本情報技術者試験におけるアルゴリズムの位置づけ
- アルゴリズム攻略のための勉強法
- 効率的な学習ステップ
- eラーニング講座の活用法
- 合格に近づく勉強スケジュール例
- 合格後に広がるキャリアの可能性
- まとめ
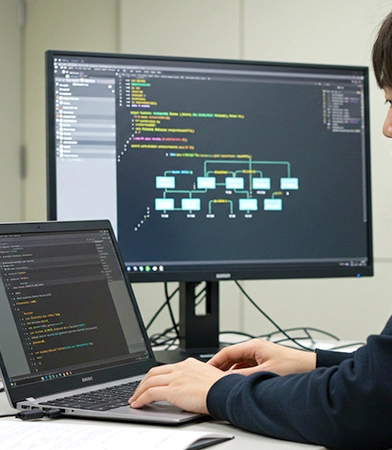

基本情報技術者試験対策講座
動画数|22本 総再生時間|1190分
国家資格「基本情報技術者試験」合格を目指す受講者向けに、基礎理論からアルゴリズム、ネットワーク、セキュリティまで幅広く解説。図解や具体例で理解を深め、頻出テーマと過去問演習で解答力を養成し、実務にも活かせる学習プログラムです。
動画の試聴はこちら基本情報技術者試験におけるアルゴリズムの位置づけ
基本情報技術者試験は大きく科目Aと科目Bに分かれています。科目Aは幅広いIT知識を問う四肢択一式で、科目Bは多肢択一式による応用問題です。
特に科目Bでは、20問中16問がプログラミングとアルゴリズムに関する出題となっています。言い換えれば、アルゴリズム分野での得点が合否を大きく左右するといっても過言ではありません。
なぜ多くの受験者がここで苦戦するのか。その理由は大きく三つあります。
-
抽象度が高く、文章だけではイメージしづらい
探索法やソート法は、数値の操作や比較を何度も繰り返す手順を追う必要があり、頭の中でシミュレーションするのが難しいと感じる人が多いです。
-
数学的な発想が求められる
二分探索やクイックソートなどは、数学的な規則性を理解しなければ本質をつかめません。特にIT未経験者には敷居が高く感じられます。
-
試験時間が限られている
科目Bは60分で20問を解く形式です。1問にかけられる時間は平均3分程度。手順を理解していても、素早く解答できなければ正答率が下がります。
したがって、アルゴリズムの学習は「理解」と「スピード」の両立が欠かせません。
アルゴリズム攻略のための勉強法

基礎理論を押さえる
アルゴリズム問題を理解する前に、まずは基数変換や論理演算といった基礎理論を学習することが重要です。
例えば、二進数の扱いやAND・OR・XORといった論理演算は、アルゴリズムの根本を理解する基盤になります。これを飛ばしてしまうと、問題文を読んでも意味がつかみにくく、応用的な演習でつまずいてしまいます。
アルゴリズムの種類を理解する
試験で頻出となる代表的なアルゴリズムには、大きく「探索」と「ソート」があります。
-
探索アルゴリズム
リニアサーチ(線形探索)、バイナリサーチ(二分探索)、ハッシュ探索など。
-
ソートアルゴリズム
バブルソート、選択ソート、挿入ソート、マージソート、クイックソートなど。
特に二分探索法やクイックソートは過去問でも繰り返し出題されているため、必ず図や擬似コードを使って仕組みを理解しましょう。
疑似言語問題に慣れる
科目Bのアルゴリズム問題は、C言語をベースとした疑似言語で出題されます。プログラミング未経験者にとっては馴染みにくい形式ですが、基本のif文やwhile文を押さえてしまえば応用が利きます。
実際の問題では「配列の操作」や「ループ処理」が多く出題されるため、サンプルコードを読み解く練習を積むことが効果的です。
| 分類 | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 探索アルゴリズム | リニアサーチ/バイナリサーチ/ハッシュ探索 | 目的のデータを探す。二分探索は整列済み配列が前提で高速。 |
| ソートアルゴリズム | バブル/選択/挿入/マージ/クイック | データを並べ替える。クイックやマージは大規模データで有利。 |
| 木・グラフ探索 | 深さ優先(DFS)/幅優先(BFS) | 構造データの走査。到達判定・最短経路の基礎に使う。 |
| データ構造 | スタック/キュー/連結リスト/ヒープ/ハッシュ表 | 操作の計算量(挿入・削除・探索)を意識して選択する。 |
効率的な学習ステップ
ステップ1:全体像をつかむ
まずはテキストや講座の資料を通して、試験範囲の全体像をつかみましょう。ポイントは、最初から完璧に理解しようとしないことです。概要を把握するだけでも、その後の学習効率は大きく向上します。
ステップ2:講座動画で理解を深める
文章だけではイメージが難しいアルゴリズムは、動画や図解で手順を追うことで理解が定着します。添付資料の「基本情報技術者講座」でも、探索法やソート法が図を交えて解説されており、初心者でもステップごとに追いやすい構成になっています。
ステップ3:過去問演習で時間配分を習得
ある程度理解が進んだら、必ず過去問演習に取り組みましょう。科目Bでは1問あたり3分以内で解く意識が必要です。最初は制限時間を設けず、正しく解くことに集中し、徐々にタイマーを使って本番さながらの練習をすると効果的です。
eラーニング講座の活用法

アルゴリズムを効率的に学習するためには、独学に加えてeラーニングを取り入れることが非常に有効です。特に「基本情報技術者講座」のように体系的に整理された教材を利用すると、理解と演習を一貫して進められます。
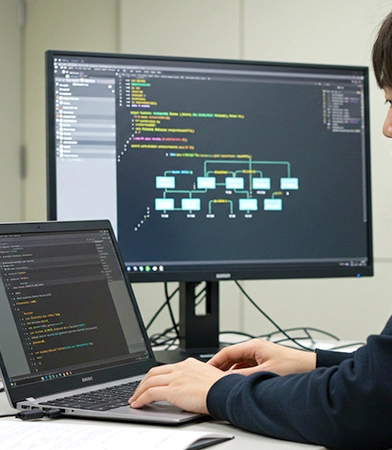

基本情報技術者試験対策講座
動画数|22本 総再生時間|1190分
国家資格「基本情報技術者試験」合格を目指す受講者向けに、基礎理論からアルゴリズム、ネットワーク、セキュリティまで幅広く解説。図解や具体例で理解を深め、頻出テーマと過去問演習で解答力を養成し、実務にも活かせる学習プログラムです。
動画の試聴はこちらアルゴリズム講座
探索法やソート法を中心に、典型的な問題を一つひとつ分解して解説してくれます。文章で読んでも理解が難しい部分も、動画で手順を可視化することで直感的に把握できる点がメリットです。
プログラミング講座
科目Bで出題される疑似言語対策には、プログラミング講座が役立ちます。C言語をベースとした構文に慣れることで、問題文の流れを追いやすくなり、配列やループ処理の正答率が向上します。
基礎理論・基数変換講座
アルゴリズム理解の前提となる論理演算や基数変換を整理できる講座です。試験序盤で出題されるこれらの問題は暗記要素が強く、得点源にしやすいため、効率よく学んでおくことで後半の時間を確保できます。
これらの講座を「基礎理論→アルゴリズム→プログラミング」という流れで受講することで、段階的に理解が深まり、学習効率が大幅に上がります。
合格に近づく勉強スケジュール例
試験合格を目指すなら、3か月を目安に計画的に学習を進めるのがおすすめです。
-
1か月目 基礎固め
基数変換や論理演算を中心に全体像を理解。講座の入門編で基礎を整理。
-
2か月目 演習中心
アルゴリズムやプログラミングの講座を繰り返し受講し、演習問題で理解を確認。
-
3か月目 過去問特訓
過去問を制限時間内で解き、本番同様のスピード感を身につける。苦手分野は動画に戻って復習。
合格後に広がるキャリアの可能性
基本情報技術者試験に合格すると、以下のようなメリットがあります。
-
就職・転職で有利になる
「ITの基礎力を持っている」と企業に示すことができ、選考時のアピールポイントになります。
-
業務で基礎を活かせる
システム開発やプログラミング業務の理解度が上がり、即戦力として評価されやすくなります。
-
上位資格へのステップアップ
応用情報技術者試験や高度情報処理資格に挑戦するための基礎固めとして最適です。
資格取得はゴールではなく、キャリアを広げるための出発点です。合格を通じて「学び続ける習慣」が身につくことも大きな財産となります。
まとめ
基本情報技術者試験の合否を分ける最大のポイントは、科目Bで出題されるアルゴリズム問題です。理解に時間がかかりやすい分野ですが、基礎理論を押さえ、探索やソートの仕組みを動画で学び、過去問で演習を重ねれば確実に得点源に変えられます。
eラーニングを活用すれば、独学では理解しづらい部分も図解や解説動画で補強でき、限られた時間の中で効率的に学習が進められます。自分に合った勉強法を取り入れ、計画的に取り組むことで、合格率40%の壁を乗り越えることは十分に可能です。
「アルゴリズムが苦手だから不安」という方こそ、勉強法を工夫し、eラーニングを味方につけて効率的に合格を目指しましょう。



