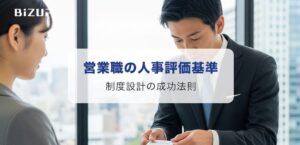QC7つ道具・新QC7つ道具の違いと活用法!QC検定2級合格へ

品質管理の現場では、問題を的確に把握し、改善へつなげるための道具が欠かせません。その代表が「QC7つ道具」と「新QC7つ道具」です。これらはQC検定2級の出題範囲でもあり、受験者にとって避けて通れない重要テーマです。
QC7つ道具は「数値データ」をもとに問題を分析する手法群、新QC7つ道具は「言語データ」を整理して問題解決や発想に活かす手法群です。両者を理解することで、製造現場から企画・設計・営業に至るまで幅広い場面で活用できるようになります。本記事ではそれぞれの特徴と活用法を整理し、学習のポイントを押さえていきます。
⇒ QC検定2級合格を目指すなら|e-JINZAI lab.
目次
QC7つ道具とは
QC7つ道具は、製造現場で収集した数値データを「見える化」し、客観的に問題を特定するための基本的な分析ツールです。
データを可視化する7つの手法
- グラフ:データを視覚化し、全体の傾向を把握する。
- パレート図:不良要因などを大きい順に並べ、重点課題を明確化する。
- ヒストグラム:工程のばらつきを確認し、安定性を評価する。
- 散布図:2つの変数をプロットして相関関係を調べる。
- 管理図:工程が管理状態にあるかを統計的に判断する。
- 特性要因図(フィッシュボーン・チャート):問題の原因を網羅的に整理する。
- チェックシート:データを効率的に収集・記録する。加えて「層別」という考え方を用いることで、時間・場所・設備など条件ごとにデータを分け、原因をより明確にできます。
実務での活用事例
例えば製造ラインで「不良が多発している」とき、まずチェックシートでデータを記録し、パレート図で不良要因の優先度を明確にします。次に特性要因図で要因を体系的に整理し、改善後は管理図で安定性を確認する、といった流れで活用されます。
QC検定2級では、こうした一連のプロセスを理解しているかどうかが問われます。
QC7つ道具の活用プロセス図
データ収集
不良件数を記録する。
主要要因特定
大きな要因を把握する。
原因整理
要因を体系的に整理。
改善実施
対策を実行する。
工程確認
安定を確認する。
新QC7つ道具とは
従来のQC7つ道具は数値データに強い一方で、顧客の声や社内アイデアといった「言語データ」には対応しにくいという課題がありました。この不足を補うために誕生したのが新QC7つ道具です。言語情報を体系的に整理し、問題解決や新しい発想を導き出すための手法群です。
言語データを整理する7つの手法
新QC7つ道具には以下の手法があります。
- 親和図法:多様な意見や情報をグループ化し、課題を明確化する。
- 連関図法:原因と結果が複雑に絡み合う問題を整理し、真因を特定する。
- 系統図法:目的達成のための手段を体系的に展開し、具体策を導く。
- マトリックス図法:複数の要素を行と列に並べ、関連性を整理する。
- アローダイアグラム法:工程の手順や所要時間を図示し、スケジュール管理に活かす。
- PDPC法:ゴールまでに想定される障害と対策を事前に図示し、リスクを回避する。
- マトリックス・データ解析:複数の評価項目を整理してまとめる、新QC7つ道具の中で唯一数値を扱う手法。
実務での活用事例
例えば新製品開発の企画段階では、親和図法で顧客の声を整理し、連関図法でニーズの背景要因を掘り下げます。その後、系統図法で施策を展開し、マトリックス図法で優先順位を決めるといった活用が可能です。営業や企画部門でも広く応用され、従来の数値分析だけでは得られなかった洞察を提供します。
新QC7つ道具の活用フローチャート
親和図法
顧客の声を
整理する。
連関図法
ニーズの背景要因を掘り下げる。
系統図法
施策を体系的に展開する。
マトリックス図法
施策に優先順位をつける。
応用展開
営業や企画部門でも活用。
QC7つ道具と新QC7つ道具の違いと補完関係
QC7つ道具と新QC7つ道具は、いずれも品質管理のために欠かせない手法群ですが、扱うデータの種類と目的が異なります。
- QC7つ道具:数値データを扱い、現場での工程管理や不良削減に強みを持つ。
- 新QC7つ道具:言語データを扱い、企画や設計などの上流工程での発想や改善に活用できる。
例えば製造現場で不良品が多発した場合はQC7つ道具で原因を数値的に分析し、企画段階で顧客ニーズを明確化する場合は新QC7つ道具を用いる、といったようにシーンによって使い分けます。
重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、「両者を補完的に活用すること」です。QC検定2級ではこの関係性を理解し、場面に応じた手法の選択ができるかどうかが問われます。
学習でつまずきやすいポイント

QC7つ道具と新QC7つ道具は一見シンプルに見えますが、学習を進めると多くの受験者が共通の壁に直面します。
混同しやすい手法
まず、似た手法の混同です。散布図と相関係数の関係を理解できなかったり、管理図とヒストグラムを混同してしまうケースは非常に多いです。新QC7つ道具でも、親和図法と特性要因図の区別、系統図法と連関図法の違いなどが分かりにくいポイントです。
- 散布図と相関係数の違いを正しく理解できない。
- 管理図とヒストグラムを混同し、使い分けに迷う。
- 親和図法と特性要因図の役割を混同してしまう。
- 系統図法と連関図法の違いがあいまいになる。
これらは出題頻度も高いため、整理して覚える必要があります。
独学の難しさ
次に、試験範囲の広さです。QC検定2級では統計的な手法から改善活動の事例まで幅広く出題されるため、独学だと「どこに重点を置くべきか」が見えにくくなります。その結果、重要テーマを十分に理解しないまま学習が進み、得点が伸び悩むことがあります。
さらに、実務イメージとの結びつき不足も大きな課題です。教科書的な説明を覚えても、「実際にどんな場面でこの図を作るのか」が分からないと、試験でも応用問題に対応できません。QC7つ道具や新QC7つ道具は、実際に手を動かして図を描いてみることが理解定着の鍵となります。
効率的に学ぶ方法
QC検定2級の学習を効率よく進めるには、単なる暗記ではなく「実務とのつながり」を意識することが不可欠です。
書籍と過去問の活用
まずは市販の参考書や過去問で基本用語や頻出テーマを押さえることが有効です。ただ読むだけでは不十分なので、過去問を解く際には「なぜこの手法を使うのか」「実際の現場ならどう活かせるのか」を考える習慣をつけると理解が深まります。
次に、自分で図を描く演習を取り入れることです。パレート図や散布図を実際に手で作成する、新QC7つ道具の親和図をワークシートに書き出してみるなど、アウトプットを通じて知識を体得することが重要です。
eラーニングという選択肢
さらに、eラーニングの活用も有効です。効率的に体系的な知識を学べるため、独学で理解しにくいポイントを補強できます。例えば QC検定2級対策講座 では、QC7つ道具と新QC7つ道具の使い分けを事例とともに学べるので、試験対策と実務応用の両方に役立ちます。特に忙しい社会人や新入社員にとっては、スキマ時間で効率よく学べる点も大きな魅力です。
まとめ
QC7つ道具は数値データを可視化して現場の改善を支える手法群、新QC7つ道具は言語データを整理して発想や企画に活かす手法群です。両者を正しく理解し、補完的に活用することで、品質管理の幅は大きく広がります。
QC検定2級の学習では、手法ごとの特徴を暗記するだけでなく、実務での使い方や相互の違いを理解することが重要です。学習範囲の広さに戸惑うこともありますが、独学だけでなくeラーニングを取り入れることで効率的に理解を深め、短期間で合格を目指すことができます。
「QC7つ道具」と「新QC7つ道具」をしっかり身につければ、試験対策だけでなく、現場や企画の場でも活躍できる知識とスキルとなるでしょう。