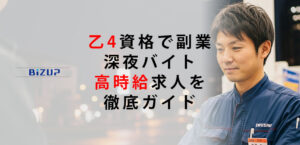宅建取得で年収は上がる?不動産業の給与体系を徹底解剖
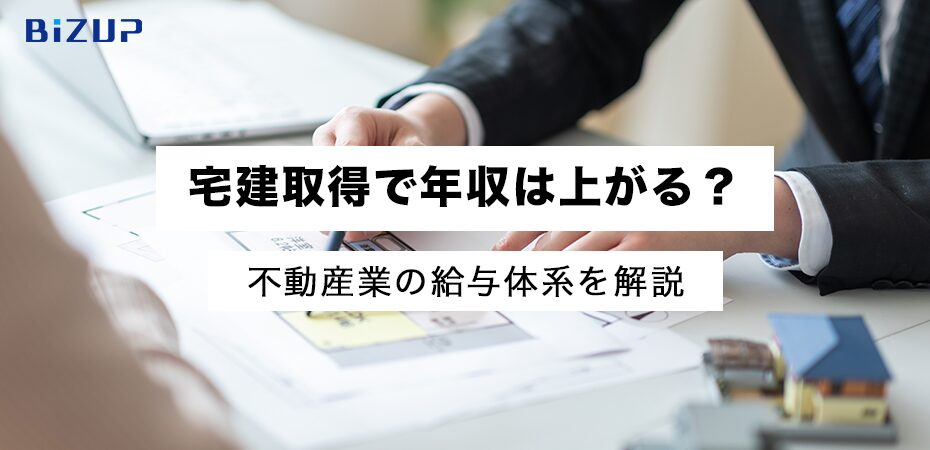
国税庁の『民間給与実態統計調査』(令和4年分)によると、不動産業・物品賃貸業で働く人の平均給料・手当は468.6万円、平均賞与は63.0万円で、年間総額は531.6万円です。対して全業種平均は給料・手当459.5万円、賞与71.4万円、合計530.9万円となっており、給料だけを見ると不動産業が約9万円高いものの、賞与が約8万円少ないため年間総額の差はわずか7千円にとどまります。
とはいえ、この数字だけで「不動産業は平均並み」と結論づけるのは早計です。不動産業の平均年収には、販売仲介・賃貸仲介・管理・開発・投資など多岐にわたる職種が含まれており、会社ごとの歩合給の比率も大きく異なります。とくに仲介営業では 成約件数に応じて歩合が急増するため、高収入の営業職が平均値を押し上げている構造があります。
目次
- 宅建士資格が年収を押し上げる理由
- 不動産会社の給与体系:歩合が平均を引き上げる
- 宅建士が年収を高める5つの要因
- 高収入を狙うためのキャリア戦略
- まとめ:宅建士資格と戦略で年収の上限を引き上げる
- 関連する記事
宅建士資格が年収を押し上げる理由

宅地建物取引業法では、一つの事務所につき「従業者5人につき1人以上」の割合で宅地建物取引士(宅建士)を専任で置くことが義務づけられています。さらに重要事項説明書への記名・押印や契約書への添付など、宅建士にしか行えない独占業務が存在します。この法定業務をこなせる人材が不足すると、会社は営業停止や指導を受ける可能性があるため、宅建士には毎月1~3万円程度の資格手当が付くケースが一般的です。
中小事業者では「社員10人に対して専任宅建士2人」が必要となり、経営者自身が資格を持っていない場合は外部採用で確保することもあります。資格手当+人員調整手当が重なると、同年代の無資格営業より年間30万~50万円ほど収入が上積みされる例も少なくありません。
専任宅建士が不足するとどうなるか
義務人数を下回った場合、行政庁から「業務改善命令」の対象となるうえ、最悪の場合は宅建業免許の停止処分に発展します。人件費を払ってでも宅建士を確保するインセンティブは極めて強く、結果として人材市場での希少価値が賃金に反映されやすいと言えます。
⇒ 宅建(宅地建物取引士)資格試験対策講座┃e-JINZAI lab.
不動産会社の給与体系:歩合が平均を引き上げる
不動産仲介の営業職では、売上高の10~30%前後が歩合として支給されることが多く、月給25万円+歩合給という形が典型です。たとえば3,000万円の中古マンションを仲介し、会社が 3%の仲介手数料(90万円)を得た場合、歩合率20%なら18万円が営業担当者のインセンティブになります。四半期で 5件成約すれば歩合だけで90万円、年間では360万円に達し、基本給と合わせれば700万円超も狙えます。
一方、物件管理部門やバックオフィスでは固定給比率が高く、30代で年収400万円程度という例も珍しくありません。平均年収510万円の裏側には、営業職の高歩合が平均値を押し上げる構造があるのです。
| ポジション | 月給(基本給) | 歩合率 | 年間成約数 ※1 | 歩合収入(概算) ※2 | 想定年収(総額) |
| 売買仲介営業〈新人〉 | 22 万円 | 10 % | 6 件 | 約 54 万円 | 約 318 万円 |
| 売買仲介営業〈平均〉 | 25 万円 | 20 % | 15 件 | 約 270 万円 | 約 570 万円 |
| 売買仲介営業〈トップ〉 | 30 万円 | 30 % | 30 件 | 約 810 万円 | 約 1,170 万円 |
※1 成約件数は中古マンション 1 件あたり売買価格 3,000 万円、仲介手数料 3%を前提に設定しています。
※2 歩合収入は「仲介手数料 90 万円 × 歩合率 × 年間成約数」で算出した概算値です。
宅建士が年収を高める5つの要因

資格手当の付与―月1〜3万円の上乗せが定番
宅建士の資格手当は、2025年時点で月額1万〜3万円が最もポピュラーなレンジです。大手不動産会社では2〜3万円、中小企業でも1〜2万円が支給例として多く、都市部では人材確保を目的に5万円超の高額手当を提示するケースも散見されます。年間換算すると 12万〜36万円の固定収入増となるため、同世代の無資格者と比べて年収差が付きやすいのが実情です。
注意したいのは「手当が高ければ総収入も高い」とは限らない点です。求人によっては手当を手厚くする代わりに基本給を抑える設計もあるため、総額ベースで比較することが大切です。
専任登録による希少価値―従業者5人に1人の法定比率
宅地建物取引業法では、営業所ごとに宅建業従事者5人につき1人以上の「専任宅建士」を置くことが義務づけられています。基準を下回ると2週間以内の補充報告が求められ、それを怠ると業務停止や免許取消のリスクがあります。
人員計画に直結する法定要件ゆえ、企業は欠員を最も恐れるポジションとして専任宅建士を優遇します。中小事業者では役員報酬とは別に資格者へ「人員充足手当」を追加する事例もあり、希少価値がダイレクトに給与へ転嫁されやすい仕組みです。
重要業務の独占―説明義務・契約書添付で存在感
宅建士にしか認められない独占業務は主に3つ。
- 重要事項説明(35条書面)の交付・説明
- 重要事項説明書への記名・押印
- 契約書(37条書面)への記名・押印
これらは売買・賃貸いずれの取引でも不可欠で、オンライン取引(IT 重説・電子契約)が主流になっても省略できません。
契約の最終局面を担う立場は、営業成績にも直結します。実務では「成約ごとに歩合の%を上乗せ」「宅建士が同行した契約にのみ高率インセンティブ」という制度を設ける会社もあり、“独占業務=歩合の加速装置”という構図が高収入につながります。
キャリアの選択肢拡大―管理職や独立開業時の必須条件
多くの不動産会社では、課長・店長クラス昇進の条件に「宅建士必須」を掲げています。昇進が早まることで、基本給テーブルそのものが一段跳ね上がり、役職手当も付与されるため年収ギャップはさらに拡大します。
また、将来的に独立開業を目指す場合、宅建士と宅建業免許の両方が不可欠です。開業準備には会社設立や保証金などで300〜400万円程度が必要とされますが、軌道に乗れば年収1,000万円超も珍しくはありません。
このように、宅建士は「社内昇進」と「独立起業」の二方向でキャリアの階段を開く資格であり、長期的に見ると収入ポテンシャルの差はますます拡大します。
信頼性の可視化―顧客への安心材料となり成約率向上
住宅購入は多くの人にとって人生最大の買い物です。取引相手に「国家資格者が担当する」という安心感を提供できれば、価格交渉を優位に進めたり、紹介客を獲得しやすくなります。結果として成約率が上がり、歩合収入が伸びる──これが数字に現れにくいものの、最終的に年収を押し上げる重要な要因です。
高収入を狙うためのキャリア戦略
宅建士として年収600万円超を目指す場合、第一に仲介営業で歩合の比率が高い会社を選ぶ戦略があります。月間契約件数が伸びる都市部大型店舗では、20 代後半でも800万円を超える事例があります。第二に、賃貸管理と売買仲介を兼営する会社で管理職を狙い、固定給+店舗インセンティブを獲得する方法があります。三つ目は開発会社への転職です。大型案件の用地仕入れ担当は高い専門性と交渉力が求められるため、30代で年収1,000万円を超えるケースも見受けられます。
ただし、高歩合の環境は成果主義が極端になりがちで、成約が途切れた際の収入変動リスクも大きい点に注意が必要です。年間収入を安定させたい場合は、管理部門や投資用物件のアセットマネジメント部門で経験を積むことで、資格手当+事業インセンティブによりバランスの取れた給与を形成できます。


宅建(宅地建物取引士)資格試験対策講座
動画数|76本 総再生時間|1641分
宅地建物取引士資格試験の合格を目指す初学者・既修者向けに構成した実践的な対策講座です。権利関係・宅建業法・法令上の制限・税法など出題分野を体系的に整理し、重要テーマを中心に講義を展開。
動画の試聴はこちらまとめ:宅建士資格と戦略で年収の上限を引き上げる
不動産業の平均年収は、月給・手当の水準が全産業より高い一方で賞与がやや低く、結果として総額ではほぼ横並びというのが最新統計の姿です。ここに宅建士資格の手当(月1〜3万円)が加わることで「毎月の固定収入」が底上げされ、歩合比率の高い営業ポストや高付加価値部門に就いた際の伸びしろも広がります。実際に高年収へ到達するかどうかは、
- 歩合率の高い営業ポストで実績を積む
- 管理・開発など長期視点で付加価値を高める部署へ進む
- 事務所の専任宅建士として不可欠な存在になる
といったキャリア設計と、契約件数を増やすための行動量・交渉力にかかっています。つまり、資格取得だけで収入が跳ね上がるわけではなく、給与システムとポジション選択をどう組み合わせるかが決め手になるのです。
eラーニングで効率よく宅建試験を突破しよう
「働きながらの独学は時間が足りない」「法律条文を読むだけではイメージが湧かない」という悩みがあるなら、動画型のeラーニング講座が強い味方になります。移動中やスキマ時間を活用できるため、通学制の専門学校より柔軟に学習計画を組める点が大きなメリットです。また、難解な条文や制度も講師の図解・事例解説を繰り返し視聴して理解を深められます。
とくにe-JINZAI Lab の「宅地建物取引士資格試験対策講座」は、分野別の短尺動画と図解レジュメで内容を可視化し、初学者でも体系的にインプットできる構成です。サンプル動画は無料公開されていますので、学習スタイルが合うかどうかを確認してから受講を検討できます。
高収入への最短ルートは、宅建士資格の取得 → 自分に合った給与体系とポジション選択 → 契約実績の最大化というステップを着実に進むことです。まずは合格への第一歩として、e ラーニングで効率的に知識を固め、チャンスを引き寄せてください。
関連する記事
- 【2025年最新】宅建とは?試験の難易度や勉強時間を解説
- 宅建取得で年収は上がる?不動産業の給与体系を徹底解剖(この記事)