数字に強くなる!ビジネス数学の基本スキル

「数学」と聞くと、学生時代の難解な数式や試験を思い出す人も多いかもしれません。
しかし、実はビジネスの現場でも数学は密接に関係しています。営業報告書の作成、KPIの分析、原価計算、プレゼン資料の説得力――どれも数字なしには語れません。
本記事では、実務に役立つ6つのビジネス数学スキルを解説し、数字に強いビジネスパーソンになるための第一歩を後押しします。
⇒統計・グラフ・割合…仕事に使える数学をまとめて学べる|e-JINZAI lab.
目次
なぜビジネスに数学が必要なのか?
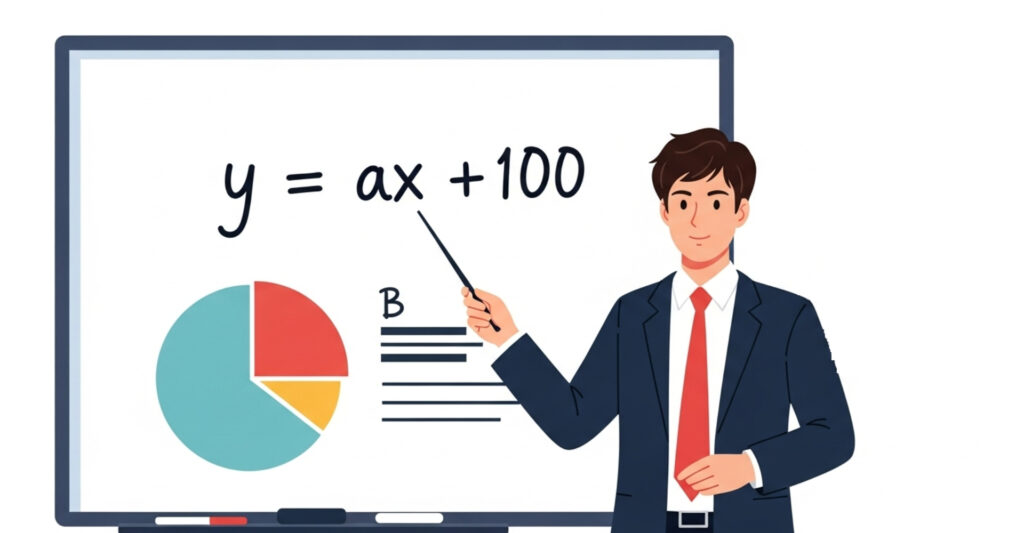
数字を扱うことは、単なる作業ではなく、論理的な思考や意思決定の質を高めるための土台です。ここでは、なぜ「数学的な視点」がビジネスで重要視されるのかを解説します。
感覚だけでは通用しない時代
日々の業務で「なんとなくこうだと思う」といった感覚的な判断をしていませんか?ビジネスの現場では、勘や経験だけに頼る意思決定はリスクを伴います。説得力のある発言や提案には、数値的な裏付けが欠かせません。
意思決定に必要な「数値的根拠」
売上推移、利益率、KPIなど、ビジネスではあらゆるデータが意思決定に関わってきます。これらを正しく読み取り、比較し、活用するには、数学的な視点が必要不可欠です。
ビジネス数学の基本6スキル
ビジネスにおいて頻出する数字の捉え方は、ある程度パターン化されています。ここでは、特に汎用性の高い6つの数学的スキルを、具体例とともに紹介します。
① 割合で全体像を把握する
割合とは、全体に対して「ある部分がどれだけ占めているか」を示す指標です。
たとえば、
- 若手社員の比率
- 営業利益率
- 成約率
などが該当します。
割合 =(注目する量)÷(全体の量)
求めた値に100をかければ、パーセント(%)表示に変換できます。
割合(%)=(注目する量 ÷ 全体の量)× 100
② 変化率で成長や衰退を見抜く
前年比で売上が「上がった・下がった」と言う際、具体的にどれくらいかを示すのが変化率(増加率・成長率)です。
変化率=(変化後の値 − 変化前の値) ÷ 変化前の値
③ 単位あたり量でフェアに比較する
異なる条件の商品やサービスを比較する際には、「単位あたり」に直すことで公正な比較ができます。
単位あたり量は、ある量を基準となる単位で割ることで求められます。
単位あたり量=全体の量 ÷ 単位数
・業者A:3,250円 ÷ 5,000枚 = 0.65円/枚
・業者B:2,040円 ÷ 3,000枚 = 0.68円/枚
よって、業者Aの方が1枚あたりの単価が安く、コスト効率に優れています。
④ グラフで「伝わる資料」を作る
数値データを直感的に伝えるにはグラフの活用が有効です。
- 棒グラフ:項目ごとの比較
- 折れ線グラフ:売上やアクセス数の推移
- 円グラフ:部署ごとの構成比など
目的に合ったグラフを選ぶことで、資料の説得力が格段に高まります。
⑤ 1次関数で売上や費用を見える化
商品の販売数や仕入れ量に応じて発生する費用や売上は、1次関数で表せます。
総費用の式: 費用(y)= 変動費 × 数量(x)+ 固定費
売上の式: 売上(y)= 単価 × 数量(x)
x:販売個数や製造数など変化する要素
固定費:家賃・人件費など数量に関係なく発生する費用
変動費:原材料費や仕入れ単価など数量に応じて増える費用
・費用:2,000 × x + 80,000
・売上:5,000 × x
利益が出る条件は「売上 ≧ 費用」なので、
5,000x ≧ 2,000x + 80,000
3,000x ≧ 80,000
x ≧ 26.66…
よって、利益が出るのは参加者が27人以上となる場合です。
⑥ 平均値と中央値の違いを理解する
「平均年収」などの数値は、実態とずれていることがあります。そこで重要なのが中央値です。
- 平均値はすべての数値の合計をデータの個数で割った値。
→ 外れ値(極端に大きい・小さい値)に影響を受けやすい - 中央値はすべての数値を小さい順に並べたときの真ん中の値。
→ 外れ値の影響を受けず、実態に近い分布の中心を表します
平均値=(データの合計)÷(データの個数)
中央値=データを昇順に並べたときの中央の値(偶数個なら中央2つの平均)
平均値の計算:
(5 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 11 + 45)= 109時間
109 ÷ 9 = 12.1時間
中央値の計算:
真ん中の5番目 → 8時間
考察:
1人だけ極端に多い45時間があるため、平均値は12.1時間と実態より高く出ています。
しかし、中央値は8時間で、大多数の実態をより正確に反映しています。
ビジネス数学を効率よく学ぶには?

「数学は苦手だった…」という方でも、社会人になってから効率よく学び直す方法があります。ここでは、ビジネス数学を身につけるための学習手段と環境を提案します。
まずは基本6スキルを習得
最初から高度な統計や財務分析に挑戦する必要はありません。まずは、この記事で紹介した「割合・変化率・単位あたり量・グラフ・1次関数・平均値と中央値」の6つに絞って理解を深めるのがおすすめです。
これらはExcelやGoogleスプレッドシートの業務でも頻繁に出てくる概念であり、実務との親和性が非常に高い分野です。特に、変化率や単位あたりの考え方は、営業、マーケティング、商品企画、経理と幅広い部署で活用できます。
「基礎をしっかり理解すること」こそが、応用スキルへの一番の近道です。
eラーニングや動画教材でスキマ学習
忙しいビジネスパーソンにとって、時間の確保は最大の課題。
そこでおすすめなのが、eラーニングやYouTubeなどの動画教材を使った「スキマ学習」です。最近では「ビジネス数学」「統計の基礎」などをテーマにした講座が多数登場しており、スマホで気軽に視聴できます。通勤中や昼休みなどの“空き時間”を活用することで、無理なく継続できます。
さらに、演習問題や確認クイズが付属している教材を選ぶと、知識が定着しやすく、実務への応用もスムーズです。
e-JINZAI lab.でも実務で使える数学の基本をコンパクトに学びたい方向けに、「ビジネスに役立つ数学の基礎」講座をご用意しています。初回講座を無料公開中ですので、下記よりご視聴ください!
社内研修に数学講座を導入する動きも
大手企業を中心に、近年では「データリテラシー研修」や「ビジネス数学講座」を社内研修として導入する動きが広がっています。数学に苦手意識を持つ社員が多い一方で、DX推進やデータ分析の基礎として、こうした教育のニーズが高まっているのです。
外部講師を招いた研修や、社内eラーニングプラットフォームを活用したコンテンツ配信など、形態も多様です。職種や役職に応じたカリキュラムが組まれるため、「使える数学」をチーム全体で底上げできるメリットがあります。
まとめ:数学力を武器に、ビジネスの現場で差をつけよう
難しそうに思える数学も、ビジネスの現場に落とし込むととても実用的です。
日々の数字に向き合い、論理的な思考で意思決定ができるようになれば、社内外での信頼や成果にもつながります。
まずは、紹介した6つの基本スキルから始めてみませんか?
数学を味方にすることで、あなたのビジネスキャリアはさらに広がるはずです。



