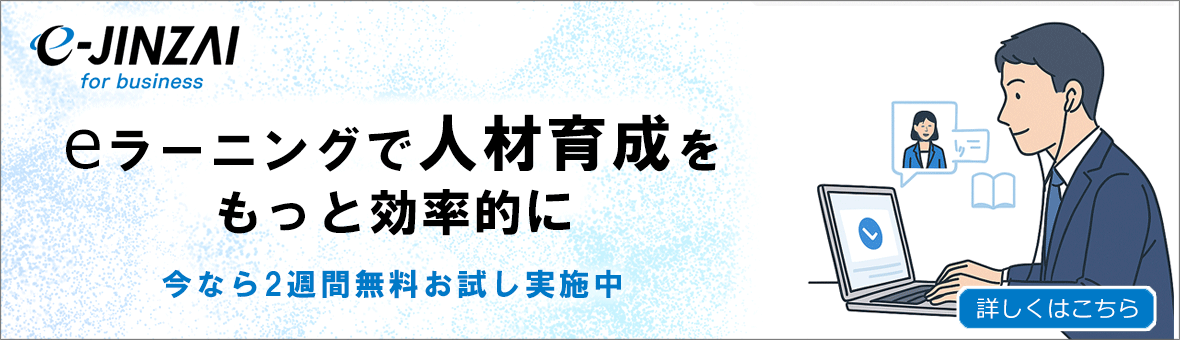就職氷河期とはいつ?原因や影響、支援策までわかりやすく解説

KEYWORDS リスキリング
バブル崩壊後の不況により、新卒採用が極端に冷え込んだ「就職氷河期」。就職氷河期という言葉を聞いたことはあっても、「いつの時期のことか知らない」という方も多いのではないでしょうか。本記事では、就職氷河期がいつ起きたのか、その背景や影響、現在に至るまでの支援策を詳しく解説します。社会問題として今なお語られる就職氷河期について、正しい知識を身につけましょう。
目次
就職氷河期とはいつ?
就職氷河期とは何か、いつの時期を指すのかを紹介します。
就職氷河期は1993年~2004年頃
就職氷河期とは、1993年~2004年頃までの期間で、景気低迷の影響で新卒採用が極端に厳しかった時代を指します。同時期に学校を卒業し、就職活動を行った世代は「就職氷河期世代」と呼ばれています。
「就職氷河期」という言葉が初めて登場したのは、リクルート社の雑誌「就職ジャーナル(1992年11月号)」です。長く続く景気の冷え込みを氷河に例えた造語で、当時の厳しい雇用環境を象徴しています。1994年には流行語大賞に選ばれたことで、就職氷河期という言葉が広く知れ渡りました。
就職氷河期の主な原因はバブル崩壊
就職氷河期が起きた主な原因は、1991年頃から始まったバブル経済の崩壊です。バブル崩壊によって企業の業績は悪化。多くの企業が、人件費を抑えるために新卒採用を大幅に縮小しました。
バブル崩壊後も金融危機やITバブルの崩壊などが続き、たび重なる経済不況により企業の採用意欲は回復しない状況が続きます。1990年代から2000年代初頭にかけての長期不況は、「失われた10年」、さらに20年・30年と呼ばれることもあります。
就職氷河期世代はいつ生まれ?何歳?
就職氷河期世代とは、主に1970年頃から1984年頃に生まれた人々を指し、大学卒業年でいうと1993年〜2006年頃が該当します。年齢は、2025年時点で40代半ばから50代半ばの年齢の方です。
就職氷河期世代は「ロスト・ジェネレーション(ロスジェネ)世代」とも呼ばれ、長期間にわたってキャリア形成が困難だったという特徴があります。なかでも、大学卒業が1999年〜2004年頃の人々は特に内定率が低く、70%台に落ち込んだ年もありました。このような世代は「超氷河期世代」と呼ばれることもあります。
安定した就職が難しかったため、非正規雇用やフリーターなど、不安定な働き方を余儀なくされた人も少なくありません。
就職氷河期の特徴とは?

就職氷河期世代は、ただ「就職が難しかった」だけではありません。厳しい雇用環境の中で社会に出たことで、長期にわたる影響を受けてきました。ここでは、就職氷河期の主な特徴について解説します。
新卒学生の就職困難
就職氷河期の最大の特徴は、新卒学生の就職が極めて困難だったことです。バブル経済期には90%近かった大学生の就職率が、1990年代後半には70%台まで低下。特に2000年頃には、企業の採用意欲が大きく冷え込み、内定を得られないまま卒業する学生も多く見られました。
日本では「新卒一括採用」が一般的であり、新卒時に就職できなかったことが、その後のキャリア形成にも大きく影響するという構造的な問題も発生しています。
非正規雇用の増加
就職氷河期世代は正社員としての就職が難しかったため、非正規雇用(派遣・契約社員・アルバイトなど)で働く若者が急増しました。長引く不況に加えて、1999年の労働者派遣法改正などの影響もあり、企業側が人件費を抑える目的で非正規を選好する動きが強まったことも一因です。
非正規雇用は正社員に比べて賃金が低く、キャリア形成もしにくいため、生涯年収や社会保障の面でも不利になりがちです。結果として、結婚や出産、住宅購入といったライフイベントを諦めざるを得ない人が増え、生活基盤が不安定なまま中高年を迎えている人もいます。
「見捨てたツケ」としての社会への影響
就職氷河期世代への公的支援が本格化したのは、2019年に政府が「就職氷河期世代支援プログラム」を打ち出してからです。2019年より以前は十分な対策が講じられていなかったため、就職機会を逸した多くの人が不安定な雇用状況のまま取り残されていました。
就職氷河期による影響は個人だけにとどまらず、就職世帯を見捨てたツケが社会全体にも波及しています。可処分所得の低下により消費が伸びず、税収が伸び悩むという経済的な損失が発生しました。年金や老後資金の不足、生活保護の受給者増加など、深刻な社会問題へとつながっています。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。
リーマンショック世代との違い
就職氷河期世代とよく比較されるのが、2008年のリーマン・ショック後に就職活動を迎えた「リーマンショック世代」です。リーマンショックとは、2008年9月に米国のリーマン・ブラザーズが破綻したことによる経済危機のことを言います。リーマンショック世代は1984年頃~1990年頃生まれ、大学卒業年度は2009年~2012年頃の方であり、就職氷河期よりも後の世代にあたります。
リーマンショック世代も就職氷河期と同じく、採用抑制や内定取り消しの影響を受けました。しかし、就職氷河期世代よりも景気回復が比較的早かったため、就職率への影響が少なかった点に違いがあります。
就職氷河期世代への支援プログラムとは?
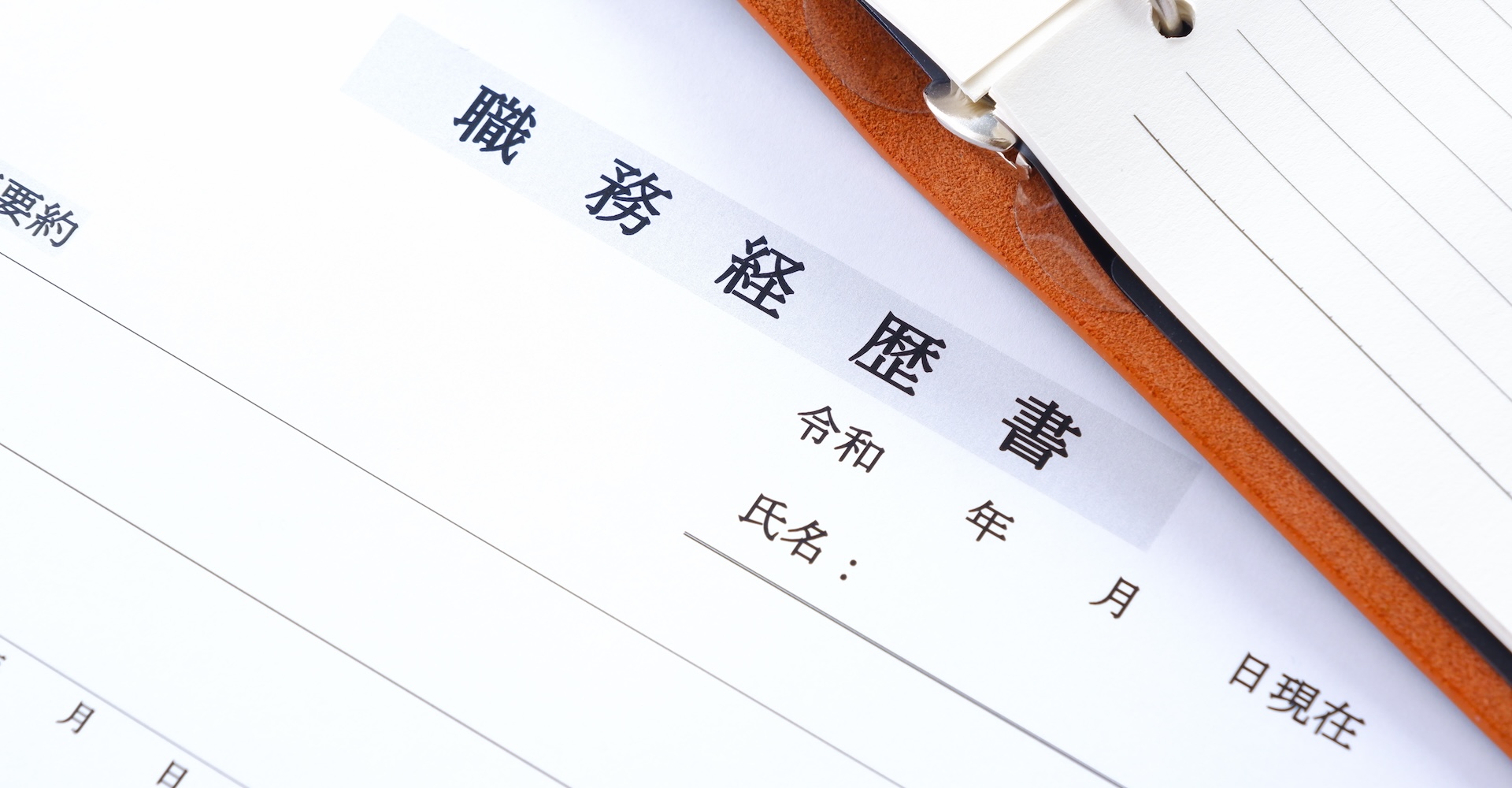
今なお続く就職氷河期世代への影響に対して、政府は就職氷河期世代に対する支援策を打ち出しました。これまでの支援に関する経緯や支援の内容を紹介します。
就職氷河期世代への支援の経緯・実績
内閣府は、2019年に「就職氷河期世代支援プログラム」を創設。3年間の集中支援期間を設け、就職氷河期世代に対して正規雇用への転換や社会参加を支援する取り組みを進めてきました。
支援は2022年以降も継続され、2023~2024年度の2年間を「第二ステージ」として施策の見直しや強化が行われました。2025年にも氷河期世代への支援は継続して行われ、共通の課題を抱える幅広い世代にも支援を拡大しています。
最近では、2025年4月25日に首相官邸において「第1回 就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」が開催。今後の支援方針として次の3本柱が示されました。
- 就労・処遇改善に向けた支援
- 社会参加に向けた段階的支援
- 高齢期を見据えた支援
3本柱を中心とした具体策は2025年6月に取りまとめられ、「骨太方針2025」に反映される予定です。
これまでの施策によって一定の成果も見られており、2019年から2024年の5年間で正規雇用の労働者数は約11万人増加しました。不本意な非正規雇用で働いていた人も約11万人減少するなど、就労環境の改善が着実に進んでいます。また、役職に就く就職氷河期世代も増えつつあり、処遇改善などの効果も出ています。
支援プログラムの対象となる世代・支援内容
「就職氷河期世代支援プログラム」の支援対象となるのは、1993年~2004年頃に学校を卒業した方のなかで、不本意に非正規雇用に就いている方、無業状態となっている方です。また、ひきこもり状態にあるなどの社会との接点が少ない人も対象に含まれています。
具体的な支援内容としては、たとえばハローワークでは就職氷河期世代の専用窓口が設置され、キャリアカウンセリングや職業紹介、定着支援などを行っています。求人のあっせんだけでなく、職業訓練や資格取得支援を通じたリスキリング(学び直し)の機会も提供されています。これにより、即戦力として企業が求めるスキルを身につけ、再就職を果たす人も増えてきました。
ほかにも、社会参加支援として、ひきこもり状態にある方へのカウンセリングや、住居確保給付金の支給といった生活面での支援も実施。さらに、就職氷河期世代の採用に積極的な企業に対しては、助成金を与えるなどの施策も行っています。
まとめ
就職氷河期は1993年~2004年頃にかけて発生し、多くの若者が厳しい就職環境に直面しました。同時期に新卒だった「就職氷河期世代」は、正規雇用の機会に恵まれず、非正規や無業の状態が長期化するケースも少なくありません。こうした背景を受け、政府は近年、就労支援や社会参加を促すプログラムを強化しています。今後も就職氷河期世代の不安を解消し、安定した生活基盤を築くための支援が注目されていくと考えられます。
eラーニングでキャリアアップ
ビズアップ総研のe-JINZAIでは、動画編集や語学、メタバース領域など、ビジネスと自己研鑽に役立つ動画を公開しています。初期費用は無料。ご自身のペースで学べるeラーニングを活用して、隙間時間にリスキリングに取り組んでみませんか?
2週間無料お試しはこちら