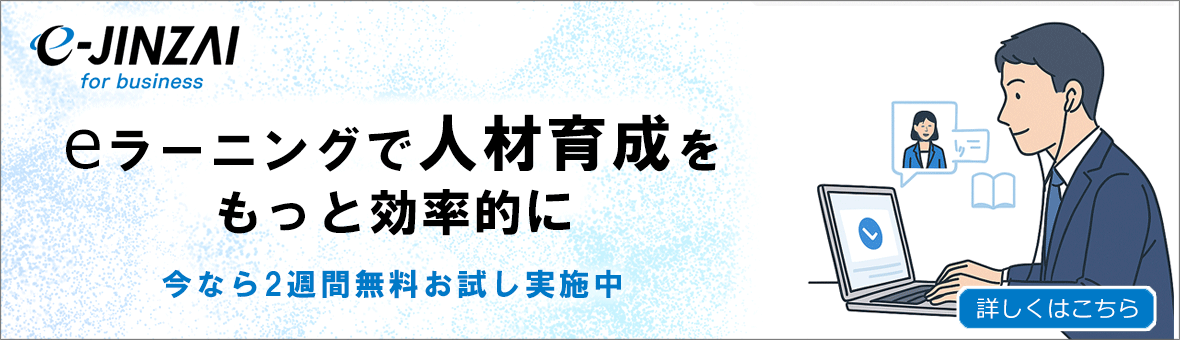内定者研修の法的問題:違法となるケースと注意点
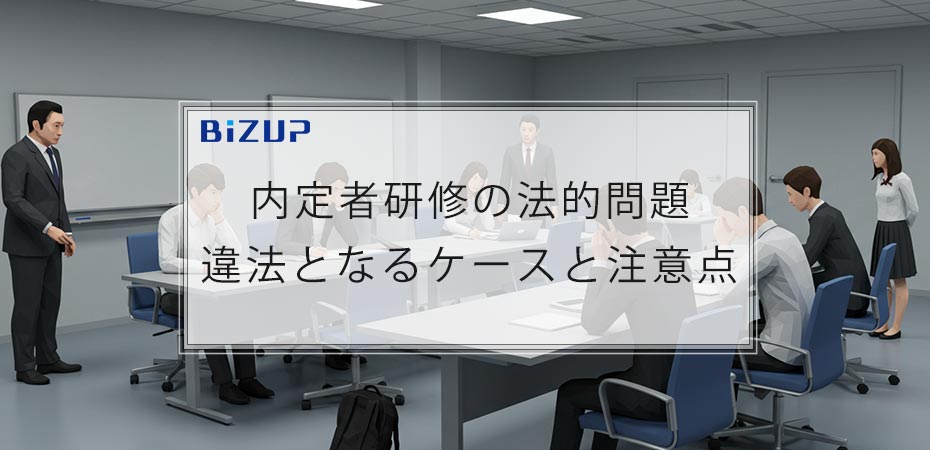
内定者研修(入社前研修)は、多くの企業で導入されている制度です。新卒採用において、入社前に会社との関係を築き、内定者の不安を取り除くための施策として有効ですが、実施の方法を誤ると、法的に「違法」となる可能性があります。
本記事では、企業側が内定者研修を適法に実施するために注意すべきポイントについて、具体例を交えながら解説します。企業としてはもちろん、内定者自身にとっても、自身の権利を守るための理解が重要です。
目次
内定者研修とは?
内定者研修とは、企業が内定を出した学生や求職者に対して、正式な入社日より前に実施する教育や交流のためのプログラムを指します。「内定者向け研修」や「入社前研修」と呼ばれることもあります。
内定者研修の主な目的
- 内定者の不安や疑問を解消し、モチベーションを高める
- 社内文化やビジネスマナーの基礎を習得させる
- 入社後にスムーズに業務に入れるよう準備させる
- 内定辞退を防止し、会社への帰属意識を高める
- 同期とのつながりを作る
内定者研修は、企業と内定者の信頼関係を構築し、入社後のミスマッチを減らすという意味で有益です。ただし、「まだ雇用契約が開始されていない段階である」という点を忘れてはいけません。
内定者研修が「違法」になる主なケース

内定者研修自体は法律で禁止されているわけではありませんが、実施方法によっては法的に問題になる場合があります。
特に、以下のような点には注意が必要です。
ケース1:参加が「事実上の強制」となっている
研修への参加を強制することは、法的リスクが非常に高くなります。内定者はまだ「労働者」ではなく、契約上は就労義務がありません。以下のような言動は「違法」と判断される可能性があります。
- 「研修に参加しなければ内定を取り消す」と脅す
- 「参加しないと評価に響く」と暗に示す
- 名目上は任意だが、実際には参加しないと孤立するような環境を作る
このような場合、企業が指揮命令下に置いている=労働時間とみなされる可能性があり、労働基準法上の問題が生じます。
ケース2:無給で実務を行わせる
内定者に実務に近い研修を行わせ、その時間に給与を支払わない場合、違法とされる可能性があります。
特に以下のような研修は、実質的な「労働」とみなされやすいです。
- 決まった時間・場所に拘束される
- 具体的な業務に関する作業や指示がある
- 上司や社員から指導やフィードバックを受ける
- 成果物の提出が求められる
このような研修には、「賃金支払い義務」が発生する可能性が高いため、有給インターンや契約社員としての雇用形態を取るなどの工夫が求められます。
ケース3:就職活動の妨害(オワハラ)
「オワハラ(就活終われハラスメント)」とは、内定者が他社の選考を辞退するよう圧力をかける行為です。
企業が以下のような形で内定者の選択肢を奪うことは、違法行為に該当する恐れがあります。
- 長期にわたる研修スケジュールを組んで就活時間を奪う
- 「うちに決めたのなら他の選考は断れ」と迫る
- 研修の出席率や課題提出を評価に反映させると示唆する
本来、内定者研修は内定者の成長を促すものであり、囲い込みや他社排除を目的にしてはなりません。
ケース4:パワハラ的な研修
研修の内容が過度な精神的・肉体的負担を伴うものである場合、パワーハラスメントに該当し違法とされることがあります。
たとえば以下のような内容には注意が必要です。
- 「根性」「精神論」ばかりの非合理的な指導
- 社員の前で内定者を叱責・晒しあげる
- 長時間の講義や宿題を課し、学業や生活に支障を与える
- 飲み会など私的イベントへの強制参加
パワハラは、入社前の段階であっても社会的評価を著しく下げるリスクがあるため、企業の信頼を損なう要因になります。
違法にならないために企業が取るべき対応策
「任意参加」であることを明確にする
研修の案内では、「強制ではない」「参加しないことによる不利益は一切ない」ということを明記し、口頭でもその旨をしっかりと説明しましょう。
参加者が「断りやすい空気」を作ることも重要です。
研修の目的を丁寧に伝える
なぜその研修を実施するのか、スキルアップや不安解消など、内定者にとってのメリットを明確に伝えることで、「囲い込み」の疑念を払拭できます。
研修後のアンケートなどを実施し、内定者のフィードバックを集めることも有効です。
業務に関係する研修には「賃金」を支払う
時間拘束や業務指示がある研修については、必ず報酬を支払う体制を整えましょう。
選択肢としては以下のような方法があります:
- 内定者にインターンシップとして参加してもらい、有給とする
- アルバイトや契約社員として一時的に雇用する
- 研修時間に対して日当や報酬を明示して支払う
来社型研修は法的リスクも…eラーニングの活用を
来社型の内定者研修には法的リスクがあるため注意が必要です。
内定者はまだ労働契約が成立していないため、企業が一方的に来社を求め、決まった時間・場所で研修を行うと「労働」とみなされる可能性があります。さらに、「評価に影響する」と示唆したり、内定取り消しの圧力を感じさせる対応は違法とされる恐れもあります。
また、遠方からの移動や学業との両立など、内定者への負担も大きく、感染症や災害へのリスクも考慮すると、対面形式には慎重な対応が求められます。
eラーニングのメリット
- 任意参加であることを強調しやすい
研修内容を動画やオンライン教材として提供することで、強制感なく学習の機会を与えることができます。 - 時間と場所に縛られずに受講可能
学業やアルバイトとの両立がしやすく、内定者の生活に合わせた配慮が可能です。 - 公平な受講環境の提供ができる
欠席や途中参加も許容しやすく、内容の見直しや復習も自由にできます。 - 労働時間とみなされにくい
自由時間に自宅で視聴する形式であれば、企業の「指揮命令下」とは見なされず、賃金支払いの必要性が低くなります。
研修効果を高める工夫も可能
eラーニングといっても、ただ動画を流すだけではありません。たとえば:
- ミニテストで理解度を確認
- 質問フォームやチャットを通じた双方向型のコミュニケーション
- 視聴後の感想やレポート提出で思考を深める
こうした仕組みを取り入れることで、一方通行ではない効果的な学習体験を提供することができます。
⇒ 内定者の閲覧状況を管理者が確認できるe-JINZAI LMSのご紹介

入社までのスケジュールを明示する
不安を抱えやすい内定者にとって、「先が見える計画性」は安心材料になります。スケジュールの透明性を高めることで、過度なストレスや誤解も防げます。
内定者側ができる対応
企業が違法な研修を強行する場合、内定者にも対処手段があります。
- 内容証明郵便で拒否の意思を通知する
→ 証拠として残すことができます。 - 賃金の請求を行う
→ 労働に該当する場合、未払い賃金の請求は合法的権利です。 - 入社自体を再検討する
→ 入社前に問題がある企業は、入社後もトラブルが続く可能性があります。
まとめ:法律を守って「安心な研修」を
内定者研修は、企業と内定者の間で信頼関係を築くための大切な取り組みです。しかし、実施方法を誤れば、「違法行為」となり、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。
違法にならないための4つの注意点を改めてまとめます:
- 研修への参加を強制しない(事実上の強制も含む)
- 実務に関わる研修には必ず賃金を支払う
- 就活の妨害を目的としたスケジュールは避ける
- パワハラ的な研修内容にしない
法令を守りつつ、内定者の成長と安心を第一に考えた研修設計を行うことで、企業と内定者双方にとって価値ある時間となるはずです。
ビズアップ総研の内定者研修
内定者研修には、内定辞退の防止、入社後の早期戦力化という2つの狙いがあります。 本研修では、学生から社会人へのマインド転換を図ることによりこれらを実現しつつ、社会人として働く姿勢や心構え、基本的なビジネスマナーやスキルを習得していきます。
eラーニング2週間お試し