【人事必見】政府も防止要請…就活を無理やり終わらせる「オワハラ」に要注意
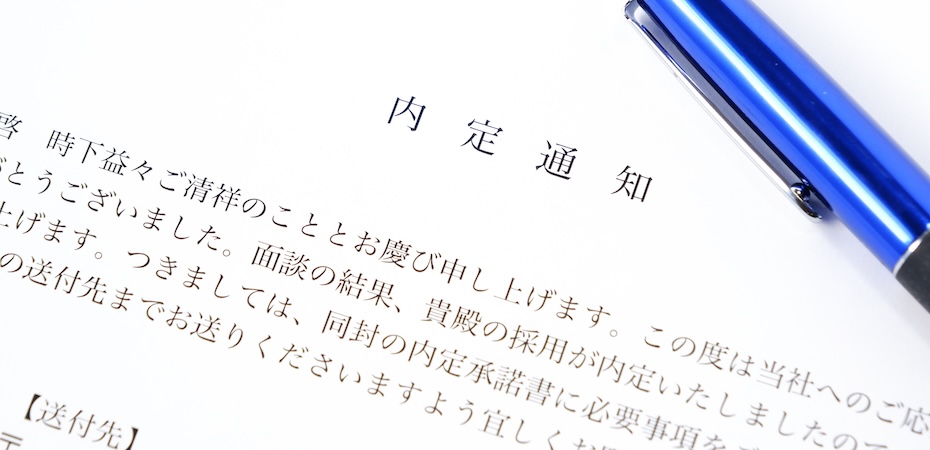
「内定を出すから、就職活動は今日で終わりにしてね」
そんな言葉が、知らず知らずのうちに学生にプレッシャーを与えていませんか?
採用活動が本格化する中で、企業側の焦りや競争心から、学生に対して就職活動の終了を強く促す「オワハラ(就活終われハラスメント)が問題となっています。日本政府や文部科学省なども注意喚起を行っており、一歩間違えば企業の信頼を損ないかねない重大なリスクになりつつあります。
この記事では、オワハラの定義や背景、企業として注意すべきポイントを解説し、学生と信頼関係を築く採用活動のあり方について考えていきます。
目次
- オワハラとは?定義と実態
- 政府も防止を要請、オワハラは“学生の弱みに付け込む行為”と明言
- なぜオワハラが問題視されているのか
- 採用現場で起こりがちなオワハラの例
- オワハラを防ぐために企業ができること
- まとめ:信頼される採用活動こそ、未来の企業をつくる
オワハラとは?定義と実態

「オワハラ」とは、「就活終われハラスメント」の略で、企業が学生に対して就職活動の終了を強く求める、または強要する行為を指します。
例えば、
- 「今ここで承諾書にサインしないと内定は出せない」
- 「他の企業の面接は断ってください」
- 「この場で就活を終わらせると約束できますか?」
といった言動がオワハラに該当します。学生が自分の意思で就職活動を終了するのは自由ですが、企業側が圧力をかけたり、選択肢を奪うような形で就活終了を迫ることは、倫理的にも法律的にも問題視される行為です。
学生は立場的に弱く、将来の不安から企業の言動に従ってしまいやすいため、明確な強制がなくても「断りづらい空気」や「期待に応えなければならないという圧力」もハラスメントにあたる可能性があります。
政府も防止を要請、オワハラは“学生の弱みに付け込む行為”と明言
こうした状況を受けて、政府もついに本格的な動きを見せました。2025年3月21日、政府は来年の就職活動が本格化する現在の大学2年生の採用を巡り、オワハラの防止を徹底するよう経団連など経済団体に要請文を発出しました。
三原じゅん子共生社会担当相は記者会見で、「学生と企業の双方にとって有意義な就職採用活動となるよう、ご協力をお願いしたい」と述べ、文書の中ではオワハラを「就職をしたいという学生の弱みにつけ込んだ行為」と明確に定義しました。
さらに、内定承諾時に保護者の同意を強要することなどを具体例として挙げたうえで、採用活動の日程ルール(説明会は原則3月、選考は6月以降)を順守することも強く求めています。政府による公式な警鐘が鳴らされたことで、オワハラはもはや一部の問題企業だけの話ではなく、すべての企業が対策すべき社会的課題となっています。
なぜオワハラが問題視されているのか
学生の自己決定権の侵害
就職活動は、学生が自身の将来を考え、多様な選択肢の中から最も適した進路を選ぶための大切なプロセスです。オワハラによって他の企業を検討する機会を奪われることは、学生の自己決定権を侵害する行為であり、キャリア選択に深刻な影響を及ぼします。
学生の中には「断ったら内定が取り消されるのではないか」と不安を感じる人も多く、冷静な判断ができなくなることもあります。進路選択は人生に大きな影響を与えるだけに、企業側には配慮ある姿勢が強く求められます。
企業のレピュテーションリスク
SNSや就活情報サイトでは、「〇〇社はオワハラをされた」「選考中に就活終了を強く迫られた」などの体験談が共有され、企業イメージの低下に直結するケースもあります。学生からの不信感は、長期的には応募者減少や離職率の上昇にもつながりかねません。
いったん「ブラック企業」「強引な採用」というレッテルが貼られると、企業ブランディングの回復には多大な労力を要します。特に若手人材の確保が難しくなる中で、こうした悪評は採用活動全体に影を落としかねません。
行政からの警告と対策要請
文部科学省も、企業に対してオワハラの自粛を要請しています。2023年には文科省が全国の大学に通達を出し、「就職活動の自由を妨げる企業の動きには注意するように」と呼びかけるまでに至りました。このような政府レベルでの動きは、オワハラが単なるマナー違反ではなく、社会的な問題として扱われている証拠です。
企業側が無意識に行っている対応でも、法的・倫理的な観点で問題視される可能性があるため、最新の情報を踏まえた対応が欠かせません。
参考:学生の職業選択の自由を侵害する「オワハラ」は行わないでください!!| 文部科学省
人事担当者向け研修
採用面接はもちろん、労働法や労務管理など、人事担当者は学ぶべきことがたくさんあります。ビズアップ総研の人事部門研修では、人事部門向けの研修を職場リーダー、管理職など階層に分けて提供しています。
詳細・お申し込みはこちら採用現場で起こりがちなオワハラの例
内定受諾を強く促す場面
「当社に来てくれるなら、すぐに他の企業を断ってくださいね」といった声かけは、学生にとっては圧力と感じられることがあります。採用担当者は良かれと思って発言しているつもりでも、学生の選択肢を狭めている可能性があることに注意が必要です。
特に就活の初期段階でこうした発言を受けると、学生は「他を見てはいけない」と思い込み、十分な比較検討ができなくなってしまいます。誠実な採用活動を心がけるなら、「他社も見たうえで、当社を選んでもらえたらうれしい」といった言い方が望ましいでしょう。
承諾書の即時提出を求める
「今この場でサインをしてもらわないと、内定が出せません」というような、即決を迫る形の対応も問題視されます。学生が冷静に考える時間や、他社と比較する余地を奪うことは、公平な意思決定を妨げる行為です。
とくに複数企業の選考が重なる時期は、判断材料が揃っていないことも多く、焦って決めたことを後悔する学生もいます。企業側としては、承諾を得るまでに一定の時間を設け、学生の意向を尊重する配慮が求められます。
言外の圧力をかける言い回し
「うちを本命にしてくれたら嬉しいな」「第一志望なら早めに返事がほしい」といった一見柔らかい表現でも、受け取る側の学生によっては「他を見るなというメッセージ」と感じてしまうこともあります。
これは悪意のない世間話のつもりでも、学生にとっては心理的な拘束感につながりやすいのです。言葉の背景にある意図や影響を考え、プレッシャーを与えないように配慮した言い回しを意識しましょう。
「他社も見たうえで納得して選んでいただくことが大事です」という一言が、安心感と信頼を生む場合もあります。
オワハラを防ぐために企業ができること

学生の意思を尊重したコミュニケーション
まず大切なのは、学生が自分のペースで就活を進められるよう、余裕を持ったスケジュール設計と選考プロセスを組むことです。
内定後も、「じっくり考えてもらって構いません」「他社と比較して納得したうえで選んでください」と、選択を尊重する姿勢を明確に伝えることが信頼につながります。学生にとっては、内定をもらった直後ほど判断に迷いが生じやすい時期でもあります。だからこそ、「選ぶ自由がある」と伝えることが、企業への安心感と好印象を与えます。
承諾期限や選考条件の透明化
内定承諾の期限や提出書類については、あらかじめ明確に伝え、学生が安心して判断できる環境を整えることが大切です。
また、複数社との選考が重なる時期には、配慮あるスケジューリングも求められます。
「いつまでに」「何を提出する必要があるのか」を事前に丁寧に説明することで、混乱や誤解を防ぐことができます。
不透明な運用や急な変更は、学生の不安や不信感を招く原因となるため、避けるようにしましょう。
採用担当者への研修と意識付け
オワハラの多くは、悪意ではなく「焦り」や「結果を出したい」という気持ちから生まれています。だからこそ、採用担当者自身がオワハラに関する知識を持ち、無意識の言動が学生にどう受け止められるかを学ぶ機会を設けることが有効です。
特に、若手の採用担当者には「何がNGなのか」が明文化されていないケースも多く、教育の場が必要です。社内で共有できるガイドラインや、実例を学ぶ場があると、未然防止につながります。
まとめ:信頼される採用活動こそ、未来の企業をつくる
採用活動は、学生と企業の最初の接点であり、そこで築かれる信頼が今後の関係性を左右します。たとえ内定辞退されたとしても、誠実な対応をした企業の印象は良く、後の転職や取引、紹介などで思わぬ形でつながることもあります。
就職活動の本質は、学生が自分に合った企業を見つけ、納得して選ぶことです。企業としては、自社を選んでもらうための努力をする一方で、無理に選ばせない姿勢=誠実さが、最終的な評価につながるのではないでしょうか。
オワハラをしないことは、法令順守のためだけでなく、企業としての品格と信頼の証明でもあります。採用担当者の一言が、学生の将来と企業の未来を左右することを、今一度意識しておきたいものです。



