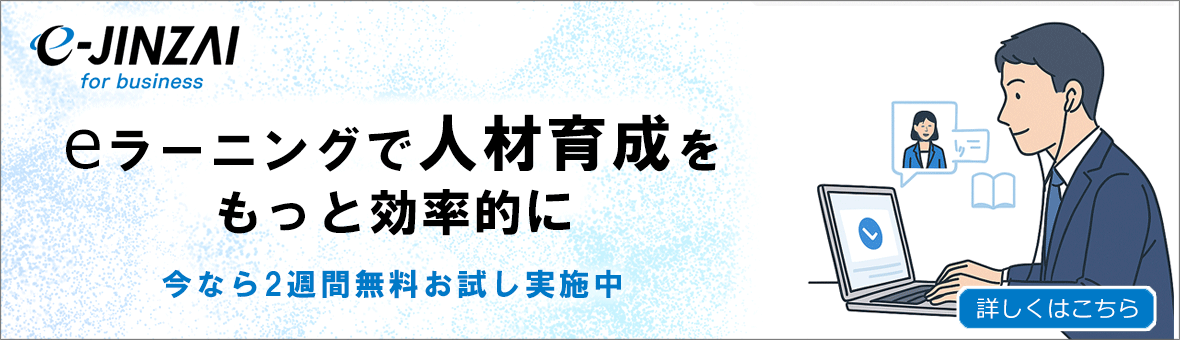社会人なら知っておきたい「冠婚葬祭マナーの基本」

KEYWORDS ビジネススキル
社会人として働く中で、結婚式や葬儀などの「慶弔」の場に立ち会う機会は避けられません。こうした場面では、マナーがその人の品格を映し出します。「服装はこれでいいのか」「祝儀や香典はいくら包むべきか」「どう渡せば失礼にならないか」と不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、社会人に必要な慶事・弔事のマナーを具体的に解説します。事前に知っておくことで、突然の場にも落ち着いて対応でき、信頼される行動が取れるようになります。
⇒「知らなかった」では済まされないマナーを身に着ける「e-JINZAI for business」
目次
慶事のマナーを身につける

結婚式での正しい服装
結婚式は新郎新婦の門出を祝う特別な場であり、出席者もその場にふさわしい装いを求められます。
男性は、黒またはダークグレーのスーツに白シャツ、白やシルバーのネクタイを合わせます。靴は黒の革靴が基本で、靴下も黒を選びます。会社の上司として出席する場合は、準礼装を意識することが大切です。
女性の場合、露出を控えた華やかなドレスやワンピースが適しています。昼の式では光りすぎないマットなアクセサリーを選び、バッグは小ぶりで上品なものにしましょう。肩より長い髪はまとめて清潔感を出すことが大切です。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 基本スタイル | 黒またはダークスーツ 白シャツ、白・シルバーネクタイ | 肌の露出を控えたドレスやワンピース |
| 靴・小物 | 黒の紐付き革靴 黒靴下・ポケットチーフ | パンプス、小ぶりのバッグ マットなアクセサリー |
| 髪型・メイク | 清潔感重視、整髪料で整える | 長髪はまとめ、メイクは華やかに |
避けるべき服装には、全身黒(喪を連想させる)、全身白(花嫁とかぶる)、毛皮や爬虫類素材(殺生を連想させる)、サンダルやブーツなどがあります。
ご祝儀の基本ルール
ご祝儀の金額は、出席者の立場や新郎新婦との関係によって異なります。会社の同僚であれば3万円が一般的です。兄弟姉妹など親族であれば5万円以上が目安となりますが、地域によっても慣習が異なるため、周囲と相談して金額をそろえると安心です。
祝儀袋は、紅白または金銀の水引がついた「結び切り」のものを使用します。表書きには「寿」または「御結婚御祝」と記し、下段に縦書きで氏名を記入します。中包みには旧字体の漢数字で金額を記載し、裏面左下に住所と氏名を書きます。お札は必ず新札を使い、向きをそろえて中包みに入れます。
ふくさに包んで持参し、受付ではふくさから取り出して「本日はおめでとうございます」とひと言添えて渡します。
二次会や贈り物のマナー
結婚式の二次会は、披露宴よりカジュアルですが、場にふさわしい華やかさを意識する必要があります。男性はジャケットに明るいネクタイやポケットチーフを合わせ、女性はパーティードレスや光沢のあるアクセサリーで華やかさを演出します。
二次会の会費は新札で用意し、封筒に入れて持参します。封筒の表に「おめでとうございます」など、短い祝福の言葉を書き添えると心遣いが伝わります。
結婚祝いの贈り物は、式の1週間前までに渡すのが基本です。割れ物は縁起が悪いとされるため避けますが、希望がある場合は丁寧に梱包して贈りましょう。品物には手書きのメッセージを添えると、より丁寧な印象になります。
お返しは「半返し」が基本で、いただいた金額の半分程度の品物を贈ります。お礼状を添えて送ることで、感謝の気持ちをきちんと伝えることができます。
弔事のマナーを理解する

通夜・葬儀の服装と準備
通夜や葬儀では、厳粛な雰囲気にふさわしい服装を心がけましょう。
男性は黒のスーツに白シャツ、黒ネクタイ、黒の靴と靴下を着用します。葬儀では喪服(ブラックフォーマル)を用意するのが一般的です。必要に応じて、ふくさ、数珠、ハンカチ(黒または白)も携帯します。
女性は黒のワンピースやアンサンブルスーツ、黒のストッキング、黒のパンプスを着用します。アクセサリーは一連のパールネックレスなど、控えめなものが適しています。バッグも黒の布製や光沢のない素材を選びましょう。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 基本スタイル | 黒のスーツまたは 喪服白シャツ・黒ネクタイ | 黒のワンピースまたはスーツ 黒のストッキング |
| 靴・小物 | 黒の革靴・黒靴下・数珠・ふくさ | 黒のパンプス・黒のバッグパールの一連ネックレス |
| メイク・髪型 | 整髪・光沢なしの小物 | 派手なメイク・装飾は避ける |
避けるべき服装には、光るアクセサリー、明るい色の服、派手なメイク、殺生を連想させる素材(毛皮、爬虫類)などがあります。
香典の扱いと表書きの注意点
香典の金額も、関係性や立場によって異なります。会社関係者の場合は5,000円〜10,000円、親族であれば10,000円〜30,000円が目安です。香典袋は黒白や双銀、水引が「結び切り」になったものを選びます。
宗教によって表書きが異なるため注意が必要です。仏式では「御香典」や「御霊前」、神式では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」や「御ミサ料」とします。中包みには薄墨で旧字体の漢数字を使い、裏面左下に住所と氏名を記入します。
渡す際は、ふくさから取り出して一礼し、「このたびはご愁傷様でございます」とお悔やみの言葉を添えます。
焼香・参列時の振る舞い
受付では、ふくさを広げて香典を取り出し、芳名帳に記帳します。言葉は控えめにし、会場内では静かに過ごすことが大切です。
焼香の作法は宗教によって異なりますが、一般的には、祭壇の前で一礼→香をつまむ→額に近づける→香炉にくべる→再度一礼という流れです。
退席時には、遺族へ軽く会釈し、静かに会場をあとにします。会食がある場合でも、故人を偲びつつ礼儀正しく振る舞うことが求められます。
法要・法事における配慮
忌日法要と年忌法要の違い
法要には「忌日法要」と「年忌法要」があります。忌日法要は、故人が亡くなってからの日数に応じて行われるもので、初七日・四十九日などがあります。一方、年忌法要は命日を起点に毎年または一定の年数ごとに行う法要で、一周忌・三回忌・七回忌などがあります。
法要は遺族だけでなく、関係者が集まる場でもあるため、準備や心構えが必要です。
香典や服装のマナー
法要の際も香典を持参しますが、金額や袋の書き方は葬儀と同様です。表書きには「御仏前」や「御供物料」など、故人が仏になったことを前提とした表記を使う場合もあります。服装は喪服またはダークスーツ、女性は控えめな装いで出席します。
会食では、和やかな雰囲気の中で故人を偲びつつ、遺族や参加者への心遣いを忘れないようにしましょう。
研修で慶弔時のマナーを実践的に学ぶ
慶弔のマナーは知識として学ぶだけでなく、実際の場面で正しく実践できることが求められます。しかし、日常業務の中ではなかなか学ぶ機会が少なく、不安を抱えたまま本番を迎えてしまうことも少なくありません。
そんな不安を解消する手段のひとつが、研修による体系的な学びです。たとえば、「社会人のための『慶弔時マナー』」では、結婚式や葬儀の場で必要な服装・所作・言葉遣いについて、現場での具体的なシチュエーションを交えて解説されます。
この研修の特長は、単なる形式やルールにとどまらず、「なぜそのマナーが必要なのか」「どのように気持ちを伝えるか」といった背景や意味まで深く理解できる点にあります。オンラインで手軽に受講できるため、業務の合間にも学習しやすく、若手社員や新入社員のビジネスマナー教育にも適しています。
研修を通じて実践力を養うことで、いざという時にも自信を持って行動でき、上司や取引先、遺族・新郎新婦といった関係者に対しても、誠意と信頼を伝えることができます。慶弔のマナーは、その人の印象を大きく左右する重要な場面だからこそ、計画的に学ぶ価値があるのです。
まとめ
慶弔のマナーは、相手を思いやる気持ちを形にしたものであり、社会人としての信頼や評価にもつながります。服装や言葉遣い、ご祝儀・香典の金額や包み方まで、すべてに意味があり、無知のままでは失礼にあたることもあります。
こうした知識は、実際に場面に直面したときに活きるものです。社内でのマナー研修や実践的なトレーニングを通じて、形式だけでなく「なぜそうするのか」という背景まで理解しておくことが大切です。
慌てず落ち着いて対応できるよう、日ごろから慶弔マナーに関心を持ち、自分の振る舞いに磨きをかけておきましょう。
社会人のための「一般教養」研修
慶弔の場にふさわしい服装や言動に不安がある方には、慶弔時マナーを中心とした社会人向けの一般教養研修がおすすめです。冠婚葬祭の基本マナーや、ビジネスに必要な社会常識など、実践的に身につけることができます。職場で信頼される大人の振る舞いを学びましょう。
2週間無料お試しはこちら