職場のちゃん付けはセクハラ?佐川急便判決に見る「言葉の境界線」と昭和的会話の今
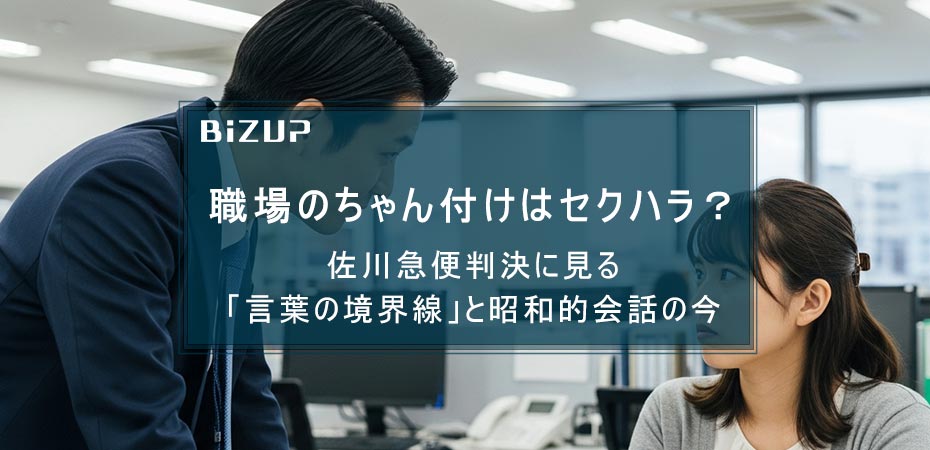
KEYWORDS ハラスメント
「職場のちゃん付けはセクハラなのか?」――そんな問いが全国で議論を呼んでいます。2025年10月、東京地裁は佐川急便の元女性社員が同僚男性から受けた「ちゃん付け」呼びなどの言動をセクハラと認定し、男性に22万円の慰謝料支払いを命じました。このニュースは瞬く間に拡散し、「たかが呼び方で」「時代が息苦しい」といった反発の声と、「仕事は距離感が大切」「言葉の受け手がどう感じるかが全て」という賛同意見が真っ二つに分かれています。
かつて当たり前だった「髪切った?」「今日は可愛いね」といった何気ない言葉も、今では職場では慎重に扱うべき表現とされています。
この記事では、判決の背景や社会的な意義、そしてこれからの時代に求められる“言葉の選び方”について考えていきます。
目次
- 職場のちゃん付けがセクハラ認定された背景
- 昭和の“当たり前”が令和では非常識に?
- 「ちゃん付け文化」とジェンダー意識のズレ
- SNSに見る賛否の分断と“距離感”の再定義
- “悪意がない”では済まされない時代へ
- 信頼を築くための言葉の選び方
- まとめ
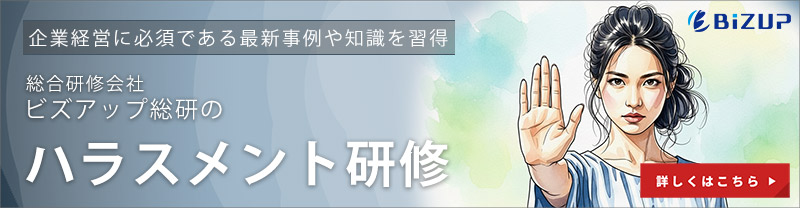
職場のちゃん付けがセクハラ認定された背景
今回の東京地裁の判決は、「ちゃん付け」そのものを問題視したものではなく、言動全体の積み重ねを評価したものです。報道によれば、被告の男性は女性に対して「体形いいね」「かわいい」「よく似合ってる」など、外見を評価するような発言も繰り返していたとされています。これらが職場の業務とは無関係な言葉であり、受け手に心理的負担を与えたと判断されました。
判決では、社会的立場の差や職場の力関係にも着目しています。特に上司や先輩が部下に対して親しげに呼びかけることは、相手が「断りづらい」「違和感を伝えにくい」と感じる構造を生みやすい点が指摘されています。
SNS上では、「ちゃん付けだけでセクハラは行き過ぎ」との声もあれば、「“親しみ”が“圧力”に変わることもある」との理解も広がっています。つまり、同じ言葉でも相手が受け取る意味は時代とともに変化しており、今回の判決はその“線引き”の変化を象徴する出来事と言えるでしょう。
昭和の“当たり前”が令和では非常識に?
昭和や平成初期の職場では、「今日は可愛いね」「髪切った?」「最近元気?」といった軽いコミュニケーションが“人間味のある職場”の象徴とされていました。
しかし、令和の職場ではこれらの発言が「外見への評価」「プライベートへの干渉」と受け取られかねません。多様性が尊重される社会では、“無邪気な一言”が誰かを傷つけるリスクをはらんでいます。
表:時代による職場コミュニケーションの変化
| 時代 | 一般的な会話例 | 当時の印象 | 現代での評価 |
|---|---|---|---|
| 昭和 | 「髪切った?似合うね」 | フレンドリー | 外見評価と受け止められる恐れ |
| 平成 | 「○○ちゃん、今日も元気?」 | 親しみ表現 | 上下関係を軽視する言葉と見なされる可能性 |
| 令和 | 「○○さん、今日もお疲れさまです」 | 丁寧で中立的 | 無難でビジネスライク |
社会全体でコンプライアンス意識が高まる中、ハラスメント研修を実施する企業も増加。厚労省の「職場におけるハラスメント防止指針」では、セクハラを“受け手が不快と感じる性的な言動”と定義しています。
つまり、発言者が悪気なくても、相手が不快に感じればそれがセクハラになる可能性があるということです。
「ちゃん付け文化」とジェンダー意識のズレ
「ちゃん付け」は日本独特の文化的表現で、親しみや温かさを示す呼び方です。しかし職場という公的な場では、性別や立場によって使われ方が偏ることが問題視されています。たとえば、男性社員には「さん付け」、女性社員には「ちゃん付け」という使い分けが無意識に行われるケースがあります。これは「女性を下に見る文化的残滓」として批判されることもあります。
一部の企業では、こうした不均衡を是正するために“呼称ルール”を設けています。たとえば全社員を「さん付け」で統一する、もしくは役職で呼ぶなど、立場を明確にしたルールづくりです。これにより、無意識の偏りをなくし、より公平な職場づくりを進める動きが広がっています。
表:職場での呼称ルールの一例
| 呼称パターン | 問題点 | 改善案 |
|---|---|---|
| 女性のみ「ちゃん付け」 | 性別による不公平感 | 全員「さん付け」に統一 |
| 一部の社員のみニックネーム | 距離感のばらつき | 公平な敬称ルール設定 |
| 役職を省略して呼ぶ | 権限の曖昧化 | 役職・氏名併記で明確化 |
このように、「親しみやすさ」よりも「公平さ」「尊重」が重視される時代へと、職場文化は確実にシフトしています。
SNSに見る賛否の分断と“距離感”の再定義
X(旧Twitter)では、「職場でなれなれしくされるとストレスになる」という産業医の意見が多く支持される一方、「昔ながらのフランクな雰囲気が失われて寂しい」という声もありました。
この対立の背景には、世代間の価値観の違いがあります。昭和世代は「人間関係が円滑になるなら少しの馴れ合いも必要」と考える傾向があるのに対し、Z世代を中心とした若い層は「仕事と個人を明確に分けたい」という意識が強い傾向にあります。
職場における“ちょうどいい距離感”とは何か――その答えはひとつではありません。ただ、共通して言えるのは、相手の立場や感情に敏感であることが信頼を生むという点です。
“悪意がない”では済まされない時代へ
多くの人が「悪気はなかった」「仲の良さの証だった」と弁明しますが、セクハラの判断基準は“発言者の意図”ではなく“受け手の感情”です。産業医の指摘にもあるように、「なれなれしい態度がストレスで体調を崩す」ケースは実際に報告されています。
企業としても、社員が無自覚にトラブルを起こさないよう教育を徹底する必要があります。管理職やリーダー層がまず言葉のリスクを理解し、模範を示すことで、職場の空気は確実に変わっていきます。
また、法的な観点からも注意が必要です。セクハラ行為が認められた場合、企業には「再発防止措置義務」や「被害者保護義務」が生じ、損害賠償だけでなく企業イメージにも影響します。もはや“昔の感覚”で会話をしている余裕はないのです。
信頼を築くための言葉の選び方
セクハラを恐れて無言になるのではなく、信頼を築ける会話に変えていくことが重要です。
たとえば、外見ではなく成果や努力に焦点を当てたフィードバックを意識するだけでも、相手の印象は大きく変わります。
職場で信頼を深める会話例
- 「この資料、すごくわかりやすかったです」
- 「いつもサポート助かってます」
- 「進行どうしましょうか?」と、相手に判断を委ねる表現
こうした会話は“評価”ではなく“尊重”を伝えるものです。小さな言葉の積み重ねが、健全な職場文化を育てていきます。
まとめ
職場での「ちゃん付け」は、親しみを込めたつもりでもセクハラやパワハラと見なされる可能性があります。適切なコミュニケーションの基本は、性別・年齢に関係なく全員を「さん付け」で統一すること、外見ではなく業務の成果や能力に焦点を当てた会話をすることです。企業は定期的な研修やガイドラインの整備を通じて、ハラスメントのない職場環境を作る責任があります。
時代とともに価値観は変化します。「昔は問題なかった」ではなく、「今の時代に合ったコミュニケーション」を心がけることが、すべての人が働きやすい職場を作る第一歩です。
もし不適切な呼び方をされている、または自分の言動が適切か不安な場合は、社内の相談窓口や人事部門に気軽に相談してみてください。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。



