企業を成長に導く法務の力|円滑なコミュニケーションで課題を解決

企業における法務部は、時に「契約書のチェックだけをする部署」や「トラブルが起きたときだけ動く部署」といった、限定的なイメージを持たれがちです。しかし、本来の法務部の役割は、単なるリスク管理にとどまらず、ビジネスの推進をサポートする「頼れるパートナー」となることです。社内の各部署が何か新しい取り組みを始める際に、真っ先に「まず法務部に相談してみよう」と思ってもらえるような関係性を築くことが、企業全体の成長に不可欠となります。本記事では、法務部が抱える課題を明らかにし、その解決策として現場との効果的なコミュニケーション術を解説します。
⇒ 法務部門の課題解決研修|e-JINZAI for business
目次
法務部が抱える課題
法務部が「パートナー」となるためには、いくつかの課題を乗り越える必要があります。
まず挙げられるのが、「存在の認知度」です。法務部の業務内容や役割が社内で十分に知られていない場合、各部署は「こんなことで相談していいのかな?」と躊躇してしまい、法務部との距離感が生まれてしまいます。また、社員が法務部に対して「相談のハードル」を感じていることも大きな課題です。些細なことでも相談しやすい雰囲気がないと、問題が大きくなってから初めて相談されることになり、手遅れになるリスクも高まります。
このような状況を打開し、「まず法務部に相談してみよう」と思ってもらえるようにするためには、現場とのコミュニケーション方法を見直すことが不可欠です。
現場に寄り添うためのコミュニケーション術
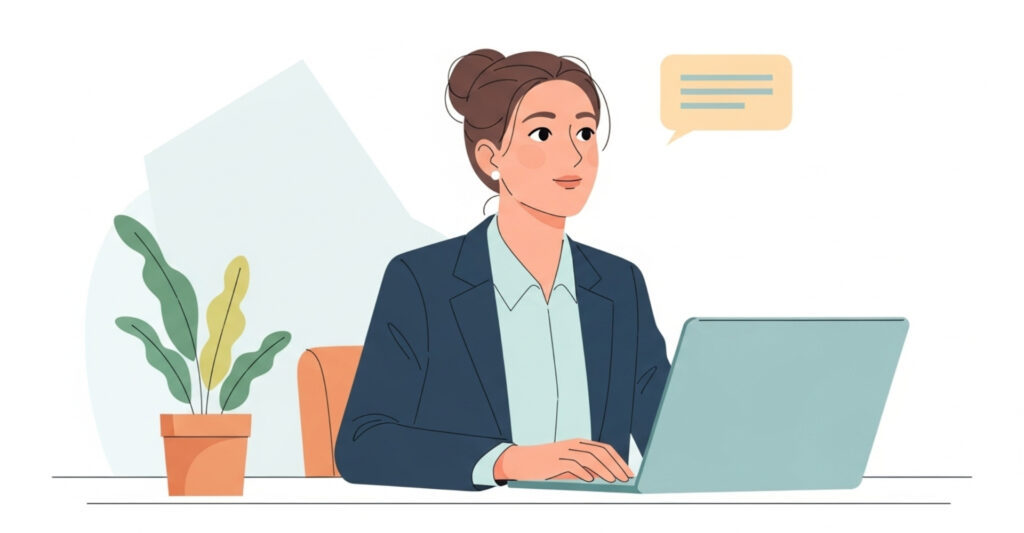
これらの課題を解決し、現場との適度な距離感を保ちながら寄り添うためには、いくつかのコミュニケーション術が有効です。
心構え
まず大切なのは、相談を受ける際の心構えです。
- 「傾聴」の重要性:相談に来る人は、取引先の倒産危機や第三者からの急な問い合わせ、急な契約交渉の進捗など、慌てていることが多いものです。まずは相手の話を最後まで丁寧に聞くことが重要です。話を途中で遮ったり、「要約すると○○ですね?」と先回りしたりせず、相手の言葉に耳を傾けることで安心感を与えることができます。
- 「拡張話法」の活用:相手の話を聞く際には、共感を深めるための「拡張話法」が有効です。感嘆、反復、共感、称賛、質問を使い分けることで、相談者が安心して話せる雰囲気を作り出せます。
- 「完璧な回答」を目指さない:初めから100点満点の回答を出そうとする必要はありません。まずは相談内容を正確に把握し、問題解決に向けた道筋を立てることが第一歩です。相談相手は藁にもすがる思いでいることも多いため、冷静に状況を確認することが重要です。
相談の受け方
相談内容を整理し、解決に導くための具体的な手法も重要です。
- 「見える化」による整理:相談内容を整理する際には、ヒト、モノ、カネ、情報、権利の動きを俯瞰図で書いて「見える化」することが効果的です。図解を通じて相談者と情報を共有することで、お互いの理解が深まります。
- 「道筋を立てる」:相談内容を整理したら、問題解決への道筋を立てます。自分だけでアドバイスできるのか、法務部の上司の確認や他部署との連携が必要か、あるいは社外の専門家や行政への相談も視野に入れるべきかを検討します。
注意すべきポイント
安易な回答が後々のトラブルにつながることもあるため、以下の点に注意が必要です。
- 安易な一般論の危険性:「○○について一般的にどう考えられますか?」という質問に対しては、安易に回答してはいけません。前提となる事実や経緯が異なれば、回答が180度変わることも往々にしてあります。安易な回答は「法務部に確認したらOKだった」という誤ったお墨付きとなり、後々のトラブルの元になる可能性があります。
- 「急いでいる」への対処:相談者が「今、急いでいるので至急見解がほしい」と求めてくる場合でも、すぐに回答を出すべきではありません。見えないリスクが隠されている可能性があり、安易な即答は危険です。
- 「法律用語」をかみ砕く:「法律や判例ではこうなっています」と専門用語を並べても、相談者の納得は得にくいものです。分かりやすいたとえ話を用いるなど、相談者目線の言葉を使うことが重要です。
法務部が目指すべき姿
コミュニケーション術を習得することは、法務部が現場に寄り添うための第一歩です。しかし、さらに一歩進んで事業に貢献するためには、単なる「リスク管理」から「ビジネス推進のパートナー」へとその役割を進化させる必要があります。
法律知識を活かした戦略的な事業サポート
法務部は、事業が立ち上がってから関わるのではなく、企画段階から積極的に参画することが重要です。初期段階から事業計画に目を通し、潜在的な法的リスクを早期に特定・回避することで、事業のスムーズな進行をサポートします。契約書のチェックだけでなく、事業のゴール達成に向けた法的なアドバイスを能動的に提供することで、事業部の信頼を勝ち取ることができます。また、過去の相談事例やトラブルをデータとして蓄積・分析することで、今後のリスクを予測し、より的確な対策を立てることが可能になります。
ナレッジ共有と社内啓発活動
全社員のコンプライアンス意識を高めることも、法務部の重要な役割です。部署ごとの特性に合わせた勉強会を開催したり、最新の法改正情報をニュースレターとして配信したりすることで、社内全体の法務リテラシー向上に貢献します。さらに、契約管理システムなどのツールを導入して業務を効率化すれば、より戦略的な業務に時間を割くことができます。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。
法務部のキャリアパスと育成
法務部の専門性を高め、長期的な成長を促すためには、キャリアパスと育成の仕組みを整えることが不可欠です。
求められるスキルの多様化
現代の法務部員に求められるのは、単なる法律知識だけではありません。事業を深く理解するためのビジネス感覚、現場との信頼関係を築くコミュニケーション能力、そして複雑な問題を解決に導く交渉力など、多岐にわたるスキルが求められます。
実践的な学びと部門内での育成
スキルアップのためには、座学だけでなく、実践的な学びを継続することが重要です。例えば、新任法務部員向けの書籍で心構えを学び、実務解説書で体系的な知識を身につけることが有効です。また、コミュニケーションに関する書籍も、現場との関係構築に役立ちます。
チーム全体で知見を高めていくことも重要です。相談内容を上司や同僚と共有し、様々な視点からフィードバックし合うことで、個々の成長を促すだけでなく、部門全体の対応力を底上げすることができます
法務部との連携を学ぶためのeラーニング
法務部が上記のコミュニケーション術を身につけることはもちろん、他部署の社員も法務部の役割や連携方法を学ぶことで、社内の協力体制をより強化できます。そのための効果的な手段の一つがeラーニングです。時間や場所を選ばずに学習できるeラーニングは、忙しい社員でも取り組みやすい学習方法と言えるでしょう。
法務部門の課題解決に焦点を当てたeラーニング研修では、法律知識だけでなく、現場に寄り添うための心構え、実践的な相談の受け方、そして注意すべきポイントなど、法務部との連携を円滑にするためのノウハウを体系的に学ぶことができます。
まとめ:法務部を「頼れるパートナー」へ
法務部が単なる「リスク管理部門」から、事業を推進する「頼れるパートナー」へと変革することは、企業全体の成長に不可欠です。本記事で紹介したコミュニケーション術を実践し、さらにeラーニングを活用して社内全体で法務部との連携方法を学ぶことで、法務部と各部署との間に信頼関係が築かれます。
これにより、問題が顕在化する前に法務部へ相談する文化が育ち、企業はよりスムーズかつ安全にビジネスを進めることができるでしょう。
課題解決型研修 『法務部門の課題』
法務部門の課題解決型研修では、契約書締結、株主総会や取締役会の運営、競業避止義務、秘密情報保持、コンプライアンス遵守の徹底、法務部門の業務改善や認知度向上、法務部員の社内外折衝方法や継続的学習方法など、法務部門の身近で実際に起こりうるリアリティの高い課題を取り上げます。
2週間無料お試しはこちら


