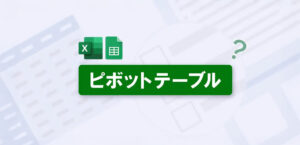災害に強い地域づくりとは?自治体の防災対策の現状と課題

KEYWORDS 自治体
日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発する国です。特に近年では、気候変動の影響により災害の規模が大きくなり、被害が拡大するケースが増えています。こうした状況の中で、地域の防災力を強化し、危機管理体制を整備することが求められています。
本記事では、自治体の防災・危機管理の現状や課題を整理し、地域全体で取り組むべき対策について解説します。過去の災害の教訓を活かし、より災害に強い地域づくりを目指すためのポイントを考えていきましょう。
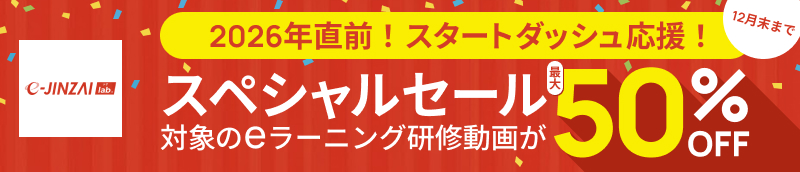
目次
自治体の防災と危機管理の現状

自然災害への対応
日本はこれまでに、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの大規模な地震を経験し、多くの犠牲者を出してきました。加えて、台風や豪雨による水害も頻発し、毎年のように被害が発生しています。被災地では復興が続いているものの、完全な回復には時間がかかる場合も多く、長期間にわたり被災者が不自由な生活を強いられることも少なくありません。
また、自然災害に加えて、新型コロナウイルス感染症のようなパンデミック、自治体の窓口対応でのトラブル、不審者への対応など、新たなリスクも発生しており、自治体の危機管理の重要性が高まっています。
自治体の役割と課題
災害対応において、自治体には次のような役割が求められます。
- 災害発生前の備え:防災計画の策定、住民への防災啓発、ハザードマップの作成
- 災害発生時の対応:避難指示の発令、避難所の開設、支援物資の配布
- 災害後の復旧・復興:被災者支援、インフラの復旧、防災対策の見直し
しかし、多くの自治体では人員や予算の不足、防災計画の更新の遅れ、災害時の対応能力の不足といった課題を抱えています。これらの課題を克服することが、防災・危機管理の強化につながります。
現在の災害対応の課題
自治体職員の負担増加
災害発生時、自治体職員は避難所運営や住民対応など多くの業務を担います。しかし、現状では職員数が不足しており、すべての対応を十分にこなすことが難しいのが実情です。
ある調査によると、自治体職員が災害時に住民から求められる要望の中で最も多かったのは「正確で迅速な情報提供」でした。続いて「避難場所の開設と情報提供」「適切なタイミングでの避難指示」「支援物資の情報提供」などが挙げられています。しかし、これらの要望にすべて応えられると答えた自治体は、全体の42%にとどまり、約6割の自治体は十分な対応ができていないことが明らかになっています。
防災計画やハザードマップの整備不足
災害リスクを住民に周知するためには、地域ごとのハザードマップや防災計画の整備が不可欠です。しかし、ハザードマップが未作成・未公表の自治体も存在し、住民が適切な避難行動を取れない状況が生まれています。
また、防災計画の見直しを行っている自治体は多いものの、財政難などの理由で十分に整備が進んでいない地域もあります。
自主防災組織の活動低迷
多くの自治体では自主防災組織の設置が進められていますが、その活動が十分に機能していないケースも少なくありません。
例えば、高齢化の進行や地域格差により、災害時に十分な支援ができない可能性が指摘されています。また、住民の防災意識が低い地域では、訓練の実施率が低く、いざというときに適切な対応ができないという問題もあります。
e-JINZAI for governmentで学ぶ『防災危機管理行政研修』
ビズアップ総研のオンライン研修では、防災危機管理行政研修を多数ご用意しています。自然災害、重大事故、感染リスク、テロ、サイバー攻撃、武力攻撃の発生事態を想定し、その時、自治体職員はどうすべきか、何ができ、何ができないのかなど、現実的な選択肢を取り上げて学習し、住民の生命、身体、財産を守る危機管理行政に関する専門的知識の習得と災害対応力等の向上を図りましょう。
資料ダウンロードはこちらこれからの防災・危機管理の方向性

近年の災害の大規模化・頻発化に伴い、防災・危機管理の在り方も変化しています。従来の災害対策では、自治体が主体となり、災害発生後の対応に重点を置いてきました。しかし、現在では「防災・減災」という考え方が重視され、事前の準備や地域全体での協力体制の強化が不可欠とされています。今後、より効果的な防災・危機管理を実現するためには、次のような取り組みが求められます。
自治体の防災体制の強化
自治体は災害対応の中心的な役割を担うため、その危機管理体制の強化が不可欠です。しかし、多くの自治体では、防災・危機管理を担当する部署の人員が不足しているほか、専門的な知識を持つ職員が少ないという課題を抱えています。今後は以下のような取り組みを進める必要があります。
- 危機管理専門職の配置
災害対応の専門家(危機管理監や防災士)を自治体に配置し、緊急時の迅速な判断と対応を可能にする。 - 自治体職員の防災研修の充実
災害発生時に適切な対応ができるよう、自治体職員向けの防災訓練や研修を定期的に実施する。 - 他自治体や企業との連携強化
近隣自治体と防災協定を締結し、災害時の相互支援体制を構築する。また、民間企業やNPOと連携し、物資供給や避難所運営を共同で行う体制を整備する。
官民連携の強化
防災対策は自治体だけでなく、企業や地域団体、住民が一体となって取り組むことで、より効果的に機能します。官民連携を強化するために、次のような施策が重要です。
- 企業との連携による物資・人材支援
災害時には、自治体だけで支援を行うのは困難なため、物流業者や食品メーカーと協力して、迅速な物資供給の体制を整える。また、企業のBCP(事業継続計画)と自治体の防災計画を連携させ、職場単位での防災訓練の実施や従業員の地域防災活動への参加を促す。 - NPO・ボランティアとの協力
災害時には、NPOやボランティア団体が避難所の運営や物資配布などを支援することが多い。平時からこれらの団体と連携し、災害時に役割分担を明確にすることで、スムーズな支援活動が可能になる。 - 地域コミュニティの活性化
住民同士が助け合う仕組みを構築するため、町内会や自主防災組織の活動を活発化させる。また、自治体と連携し、防災訓練やワークショップを定期的に開催することで、地域住民の防災意識を高める。
住民の防災意識向上
災害時には、自治体の支援が届くまでに時間がかかることが多いため、住民自身が適切な行動を取れるようにすることが重要です。特に、以下の点について啓発活動を強化する必要があります。
- ハザードマップの活用と周知
地域ごとの災害リスクを住民が正しく理解できるように、ハザードマップの配布や活用方法の説明会を定期的に実施する。 - 「自助・共助」の意識醸成
災害発生時に自分自身や家族を守る「自助」と、近隣住民と協力して助け合う「共助」の重要性を啓発し、具体的な行動指針を示す。 - 高齢者・障がい者支援の強化
要支援者名簿を活用し、避難時に手助けが必要な住民への支援体制を整備する。地域の見守り活動を強化し、災害時のサポートができる体制を構築する。
デジタル技術の活用
近年、災害対応においてデジタル技術の活用が進んでいます。特に、以下の技術を導入することで、災害時の情報伝達や被災者支援の効率化が期待されます。
- AIやビッグデータによる災害予測
気象データや地震観測データをAIで分析し、豪雨や津波、地震の発生を事前に予測するシステムの活用を進める。 - 防災アプリやSNSの活用
スマートフォン向けの防災アプリを活用し、避難情報や災害発生状況をリアルタイムで発信する。また、SNSを活用して、住民同士の情報共有を促進する。 - ドローンやロボットの活用
被災地の被害状況を迅速に把握するために、ドローンによる空撮や自律型ロボットの導入を推進する。これにより、救助活動の迅速化や避難ルートの確保が可能となる。
業務継続計画(BCP)の策定と実施
自治体や企業が災害時に業務を継続できるようにするためには、BCPの策定が不可欠です。しかし、多くの自治体では、BCPが未策定であり、災害発生時に行政機能が停止するリスクを抱えています。今後は以下のような取り組みを進める必要があります。
- 災害対応マニュアルの整備
自治体職員や企業の従業員が災害発生時に適切な対応を取れるように、具体的な行動マニュアルを策定する。 - 代替拠点の確保
災害時に庁舎や企業のオフィスが使用できなくなった場合に備え、代替拠点を確保し、リモートワーク環境を整備する。 - 定期的な訓練とシミュレーション
BCPを策定するだけでなく、定期的に防災訓練を実施し、計画の実効性を検証することが重要である。
まとめ
災害に強い地域をつくるためには、自治体だけでなく、住民や企業、地域団体が協力して防災・危機管理に取り組むことが不可欠です。防災計画の整備や自主防災組織の強化、デジタル技術の活用など、多角的なアプローチが求められます。
「自分の命は自分で守る」という意識を持ち、地域全体で防災力を高めることが、未来の安全につながります。今こそ、災害への備えを見直し、行動を起こしましょう。