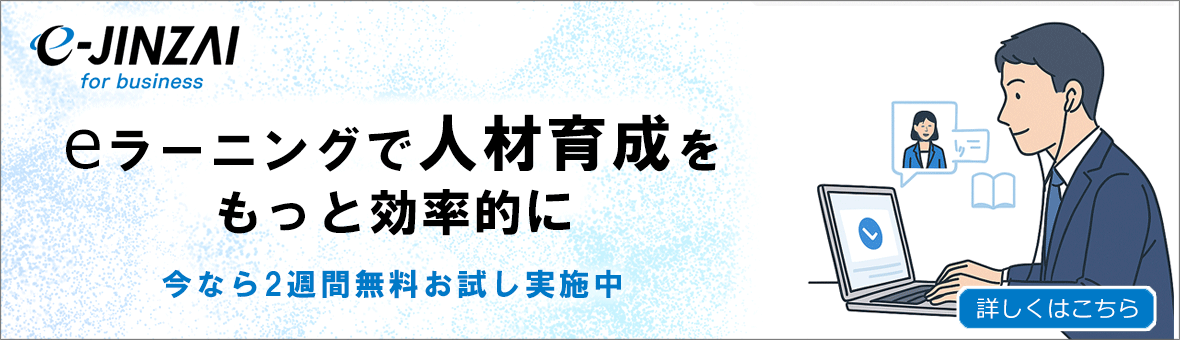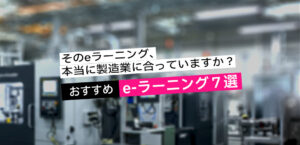DXに強い会社は、全社員に「リテラシー標準」を叩き込む

企業の競争力を左右する要素として、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進がますます重要視されています。DXはもはや一部のIT企業や先進的な業種に限ったものではなく、製造業、小売業、サービス業、あらゆる業界で求められる標準的な取り組みとなりつつあります。
その中で、多くの企業がすでに「DXリテラシー標準」の存在を知っていることでしょう。経済産業省が提示したこの指標は、DXを担うすべてのビジネスパーソンにとって必要な基礎力を定義しています。ところが、実際にそれを自社にどう取り入れるか、どこから始めればよいかについては、多くの企業が迷い、立ち止まっているのが現状です。
⇒ 全社員に必須のDXリテラシー標準研修はこちらから┃e-JINZAI for business
目次
- DXリテラシー標準があっても進まない理由
- DXリテラシーを全社で活かすために必要な視点
- 各部門が抱えるDX推進のリアルな壁
- DXリテラシー標準研修が解決に導く理由
- この研修を選ぶべき3つのポイント
- まとめ:次に動くのは、知っているあなた
DXリテラシー標準があっても進まない理由
「DXリテラシー標準」は、企業が全社員に必要なデジタル基礎力を共有するための道標として設計されています。しかし、指針があっても、社内のDXがなかなか進まない、効果が見えないという声は少なくありません。その背景には、組織内に潜むいくつかの“見えにくい障壁”が存在しています。
共通言語の不足が連携を妨げる
DXを全社的に進めようとするとき、IT部門と営業、マーケティング、人事など、異なる部門間でのコミュニケーションが重要になります。しかし、DXに関する用語や考え方がバラバラだと、議論が噛み合わず、現場では「結局何をすればいいのか」が不明瞭になります。共通言語がないまま進めるDXは、部門ごとの単発的な改善にとどまり、全社的な変革にはつながりにくいのです。
理解はしているが、実行に移せない現場
「DXの必要性は理解している」「リテラシーの強化が必要なこともわかっている」――こうした認識は社内に広がりつつあります。それでも実行に移せないのは、個々の社員が「自分にどう関係するのか」がピンときていないからです。情報はあるのに、具体的な行動に落とし込めていない。このギャップこそ、DX推進が停滞する大きな原因です。
「研修=一部の人だけ」の誤解
DX研修は「IT部門向け」「管理職向け」といったイメージを持たれやすく、一般社員や営業、人事などには無関係と思われがちです。しかしDXリテラシー標準は、すべての職種が対象であり、「全員がDX人材になる」ことを前提としたフレームワークです。この誤解が、組織全体の足並みを乱す要因となっています。
DXリテラシーを全社で活かすために必要な視点
DXリテラシー標準を知っていても、真に組織に根づかせるには、単なる知識の共有では足りません。「実行できるかどうか」が、企業のDXを成功に導く鍵になります。そのためには、以下の2つの視点が不可欠です。
一人ひとりの「自分ごと化」がカギ
リテラシーを高めるには、「自分の仕事にどのようにDXが関わるのか」を理解する必要があります。たとえば、営業職がデータを活用して提案力を上げる、人事が社員のスキルを見える化して育成戦略を立てる――こうした具体的な文脈の中で、DXリテラシーを学ぶことが求められます。抽象的な理論だけでは、現場の行動は変わりません。
部門横断で基礎を揃える意味
企業全体のDXを推進するには、部門間の「認識のズレ」を解消し、足並みを揃えることが重要です。そのために必要なのが、「全社員が同じ基礎を共有する」こと。これにより、IT部門と非IT部門、経営層と現場といった異なる立場の人々が、共通のフレームワークで議論し、協力できるようになります。DXリテラシー標準研修は、この“共通の土台”を築く上で有効です。
各部門が抱えるDX推進のリアルな壁
DXリテラシーの必要性を理解していても、各部門ごとに異なる課題を抱えています。ここでは代表的な職種ごとに、どのような壁があるのかを見ていきます。
IT部門:経営との言語ギャップ
技術に詳しいIT部門は、DXの実務を支える中核です。しかし、経営層との間に“言葉のズレ”が生じやすいのも事実です。技術的に実現可能なアイデアも、経営の視点での理解や投資判断に結びつけられなければ、現場止まりで終わってしまいます。経営的視点とビジネスへのインパクトを語れるIT人材の育成が求められています。
営業・マーケティング:データ活用に自信がない
営業やマーケティングの現場では、顧客ニーズの多様化に対応するため、データ活用の重要性が高まっています。しかし、分析ツールの操作やデータの見方に不安を感じている人も多く、「活用したいのに活かしきれない」という状況に陥りがちです。リテラシーの底上げが、成果に直結する分野です。
経営・人事:育成方針が定まらない
DXの推進役となるべき経営層や人事部門にとっては、「誰を育てればいいのか」「どう評価すればいいのか」といった方針の不透明さが課題です。リテラシー標準を基準とすれば、人材要件を明確化し、育成・評価の軸を社内に浸透させることが可能になります。
DXリテラシー標準研修が解決に導く理由
DXリテラシー標準は、経済産業省が策定した「DX推進スキル標準(DSS)」の一部として定められたもので、企業におけるDX人材育成を体系的に進めるための国家的フレームワークです。全社員に求められる基礎知識を「リテラシー標準」、企画・実行を担う人材には「推進スキル標準」と、段階的に定義されています。このような明確な基準に基づいた研修を導入することで、社内教育に一貫性が生まれ、DX推進を加速させる土台が整います。
DSSには、大きく分けて以下の2つのカテゴリがあります。

つまり、DXリテラシー標準は、DX人材育成の“第一ステップ”として、全社員が押さえるべき土台です。その上に、プロジェクトを牽引する人材の育成が続きます。このように、経産省が国家施策として明文化しているスキル標準をもとに、自社の育成戦略を組み立てることで、人材開発に一貫性と説得力が生まれます。
全社で“共通の土台”を築くために
DXリテラシー標準は、単なる基礎知識の共有ではなく、企業のDX体制づくりにおける“共通土台”です。
この基礎を全社員で共有することで、どのような人材が育ち、どのような役割に発展していくのか──。
経済産業省が示す「DX推進スキル標準」に基づき、その関係性を図に整理しました。
【DXリテラシー標準】
── 全ての社員が身につけるべきDXの基礎力 ──

DXの基礎を身につけた人材がステップアップ
▼
 企画・構想 企画・構想 | ビジネスアーキテクト 目的から業務変革を導く | |
 分析・活用 分析・活用 | データサイエンティスト データで業務を最適化 | サイバーセキュリティ セキュリティ環境を構築・守る |
 技術設計 技術設計 | ソフトウェアエンジニア システムの設計・実装・運用 | デザイナー ユーザー視点で体験をデザイン |
※ 出典:経済産業省「DX推進スキル標準」より再構成
ご覧の通り、DXリテラシー標準は、すべての職種が共通して身につけるべきDXの基礎力として位置づけられています。ビジネスアーキテクトやデータサイエンティストといった専門人材も、この基礎の上に育成されていきます。
つまり、「DXを推進できる人材がほしい」と考える企業こそ、まずは全社員にリテラシーを根付かせることが最優先です。今回ご紹介している「DXリテラシー標準研修」は、この基礎力を短期間で社内に定着させ、企画・分析・設計それぞれのステップに進む人材を育てるための出発点になります。
職種別の理解と実践を促す構成
本研修では、職種ごとの役割や視点に基づいたカリキュラムが用意されています。IT、営業、マーケティング、人事、経営など、それぞれが自分の立場で「DXをどう理解し、どう行動に結びつけるべきか」を明確に学べます。そのため、単なる“共通理解”にとどまらず、日々の業務に直結した実践力を高めることができます。
たとえば営業職向けのカリキュラムでは、顧客データの分析やデジタルツールを活用した提案力強化にフォーカスし、マーケティング部門向けには、データ戦略や施策のPDCAに基づく意思決定力が強化される内容です。このように、それぞれの業務文脈に合わせた設計だからこそ、納得感が高く、学びが行動につながります。
社内全体のDX意識を揃える設計
部門によってDXへの関心度や理解度に差があると、推進プロジェクトが前に進みにくくなります。本研修は、あらゆるレベルの社員が同じフレームワークで学べるよう設計されており、共通言語と共通理解を醸成することができます。
特に、研修を通じて「全員がDXに関わる主体である」という認識が浸透することで、単なる知識の習得にとどまらず、自発的な行動と連携が生まれます。これは、組織横断のプロジェクトや新たな価値創出につながる“土壌”をつくる大きな力となります。
この研修を選ぶべき3つのポイント
DX研修は多く存在しますが、「DXリテラシー標準研修」には、他にはない3つの明確な選定理由があります。以下のポイントを押さえることで、導入判断の参考になるはずです。
公的ガイドライン準拠の信頼性
本研修は、経済産業省とIPAが共同で策定した「DXリテラシー標準」に準拠したカリキュラムを採用しています。内容の信頼性と整合性が高く、政府の方針とも連動しているため、社内での導入時にも説得力があります。
また、公的な枠組みに基づいていることで、評価基準の明確化や育成方針の統一が可能になり、人事制度やスキル評価にも活用しやすくなります。
誰にでも理解できるシンプル設計
専門的な知識やITスキルに関係なく、すべての職種が学びやすい構成となっています。難解な用語は避けられ、わかりやすい言葉と実践例が中心なので、普段DXに関わる機会が少ない職種でも、無理なく理解し、自分の業務と結びつけることができます。この“わかりやすさ”が、研修の効果を最大化し、現場での実践につながっていくのです。
オンライン対応で全社導入しやすい
全社的に受講させたい研修で最もハードルになるのが、「物理的な制約」です。しかしこの研修は、オンラインでの受講に完全対応しており、場所や時間に縛られずに全社員に展開することができます。在宅勤務が多い企業や、複数拠点を持つ企業でも、均等に質の高い教育を提供できる点は、大きな導入メリットです。
まとめ:次に動くのは、知っているあなた
「DXリテラシー標準」の存在を知っている。
その重要性も、全社での活用が必要なことも、理解している。
それでも前に進めないなら、今こそ“行動”に移すタイミングです。DXは、もはや一部の部門に任せておけばよい課題ではなく、すべての社員が主体的に関わるべきテーマです。
本研修は、知識を得るだけでなく、「自分の業務にどう活かすか」を明確にし、行動につなげる実践型の学びを提供します。まずはこの研修を通じて、社内のDX推進力を一段階引き上げる基盤を整えてみてはいかがでしょうか。
未来の成長に向けて、次に動くのは、“知っているだけ”ではなく、“実践できる”組織です。
DXリテラシー標準研修のご案内
経済産業省とIPAが策定した「DXリテラシー標準」に準拠した、全社員向けの研修プログラムです。IT、営業、人事、マーケティング、経営などあらゆる職種に対応し、DXの基礎知識から行動変容までをサポートします。DXを“自分ごと”として捉え、全社での推進力を育むための第一歩としてご活用ください。
2週間無料お試しはこちら