26年ぶりの全面改正「人材育成・確保基本方針策定指針」が示す地方行政の未来
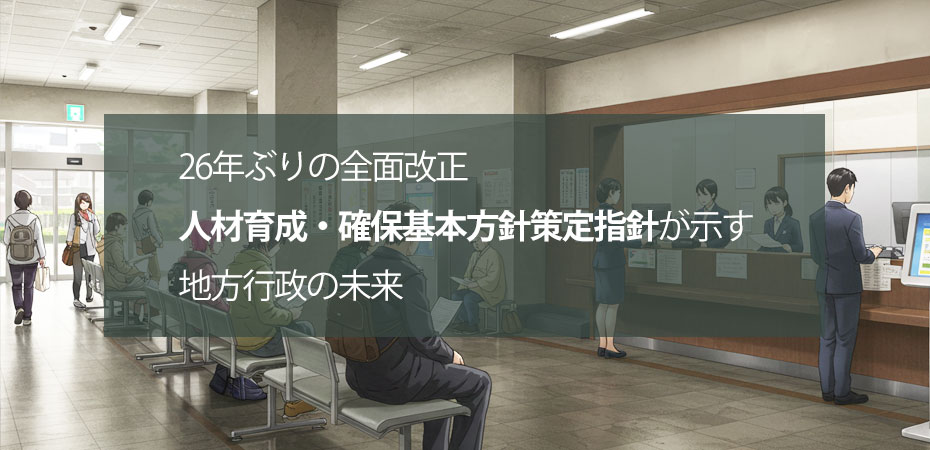
KEYWORDS 自治体
令和5年12月、総務省は「人材育成・確保基本方針策定指針」を公表した。前回の指針は平成9年に示されたものであり、実に26年ぶりの全面改正となる。今回の改正は、少子高齢化やデジタル社会の進展など、地方公共団体を取り巻く環境の劇的な変化に対応するものだ。以下では、本指針の主な要点や改正のポイント、各項目の具体的な内容について紹介する。
⇒新しい人材育成・確保基本方針策定指針に対応した「自治体向けeラーニング」について
⇒総務省人材育成・確保基本方針策定指針(PDF)
目次
改正の背景と趣旨
今回の指針は、自治体を取り巻く急速な環境変化に対応するために改正されたものです。少子高齢化の進行により若年労働力の絶対数が減少する一方で、住民のニーズや行政課題は多様化・高度化しています。また、感染症や災害といった新たなリスクへの対応、行政のデジタル化も求められています。
こうした中で、自治体が持続的に住民サービスを提供していくためには、優秀な人材の確保と、職員一人ひとりが能力を発揮できる育成環境の整備が欠かせません。そのため今回の改正では、人材「育成」に加えて「確保」や「職場環境の整備」といった総合的な視点から、実効性のある方針づくりが求められています。
主な変更点と新たな考え方
求められる職員像の明確化
各自治体が直面する行政課題や地域の特性を踏まえ、どのような人材を育て、どのような能力を備えた職員が必要なのかを明確にします。これにより、育成の方向性が具体化され、職員自身もキャリア形成の参考にすることができます。
中長期的な計画との連携
人材育成の方針は、自治体の中長期的な計画と連動させることが求められます。地域ビジョンの実現に必要な人材を見据え、戦略的に育成と確保を行う必要があります。
全庁的な推進体制の構築
人材政策は人事部門だけで担うものではなく、財政・組織・DX部門など全庁的な連携体制のもとで推進することが重要です。特に首長や経営層がリーダーシップを発揮することが求められます。
都道府県と市町村の連携強化
小規模自治体では人材育成・確保が難しい場合があるため、都道府県が広域的な研修や支援体制を整備し、市町村を支える役割を果たすことが期待されています。
人材育成の具体策

リスキリングとスキルアップの推進
DXやGXといった新たな政策課題に対応するため、リスキリング(新しい知識の習得)とスキルアップ(既存能力の向上)を重視した育成プログラムの整備が必要です。各職種・階層ごとのプログラムを用意し、計画的な学習の機会を提供します。
多様な学習機会の確保
OJTをはじめ、eラーニングや外部研修、大学への派遣、民間企業との人事交流など、学びの方法を多様化することが推奨されています。また、自主研究や資格取得の支援など、職員の自発的な学習意欲を後押しする環境づくりも大切です。
人材育成と人事制度の連携
職員が獲得した知識・技能を業務に活かすとともに、それを人事評価や人材配置に反映させる仕組みの構築が求められています。キャリアパスの明示やメンター制度、1on1ミーティングの導入など、キャリア形成支援も重要な要素です。
人材確保のための取組
公務の魅力発信
SNSやインターンシップ、職場見学などを通じて、地方公務員として働くことのやりがいや専門性を発信することが推奨されています。特に技術職や専門職については、実際の業務内容に基づいた情報提供が必要です。
多様な採用手法の導入
通年募集や年齢制限の緩和、SPIの導入、WEB面接など、受験者にとって負担の少ない採用制度を整備することで、多様な人材の確保を図ります。経験者採用や任期付職員の活用など、多様なルートを組み合わせることが鍵となります。
職場環境の整備
働きやすさの向上
テレワークやフレックスタイム制の導入、育児・介護と仕事の両立支援、長時間労働の是正など、ライフステージに応じた柔軟な働き方の推進が重要です。
メンタルヘルスとハラスメント対策
心身の健康を保つための取り組みや、ハラスメント防止策の実効性確保が求められています。安心して働ける職場環境を整えることが、職員の能力発揮につながります。
デジタル人材の育成・確保
今回の改正で特に強調されたのが、デジタル人材に関する方針です。行政のDXを進める上で、次のような人材像が示されています。
デジタル人材の類型
- 高度専門人材:システム設計やデータ分析に精通し、DX戦略をリードする人材
- DX推進リーダー:業務現場と専門家の橋渡し役として、現場のDXを牽引する人材
- 一般行政職員:デジタルツールを日常的に活用し、効率的に業務を遂行する人材
人材ごとの育成戦略
育成対象の人材像ごとに必要なスキルと人数を把握し、育成計画と数値目標を策定することが推奨されています。外部人材の登用や、複数団体による共同確保なども視野に入れた柔軟な対応が求められます。
まとめ:人材戦略のアップデートに向けて──学びの場をどう整えるか
令和5年に公表された新たな「人材育成・確保基本方針策定指針」は、自治体が将来に向けてどのような組織を構築すべきか、その方向性を明確に示しています。求められるのは、個々の職員の成長を促し、組織として持続可能な力を育てること。そして、職員一人ひとりが地域課題の解決に主体的に取り組める環境づくりです。
こうした変化に対応するためには、育成施策の見直しとともに、職員の学びを支える具体的な仕組みや環境の整備が不可欠です。
そこでご紹介したいのが、自治体向けeラーニング研修サービス「e-JINZAI for government」です。
今般のリニューアルでは、令和5年の新指針に完全対応し、指針で示された重要ポイントをカバーする研修群を新設しています。全職員に必要なビジネススキルを体系的に学べるほか、福祉職や技術職向けの専門研修、さらに「ナッジ」「ヤングケアラー」「女性活躍」といった先端行政テーマを扱うプログラムも拡充されており、あらゆる人材層にとって有益なコンテンツがそろっています。
行政課題を的確に捉え、広い見識と高い職業倫理観をもった人材を育てたいとお考えのご担当者様にとって、導入価値の高い研修プラットフォームです。
株式会社ビズアップ総研では、eラーニング「e-JINZAI」シリーズをはじめ、公開講座や講師派遣など多様な形で研修をご提供しております。学ぶ楽しさと働く喜びを通して、自治体職員の成長と地域の未来を応援します。
⇒国内最大級のオンライン自治体専門研修「e-JINZAI for government」
リニューアルポイント:
- ナッジ・ヤングケアラー・女性活躍など先端テーマ研修の提供
- 総務省「人材育成・確保基本方針策定指針」に完全対応
- 自治体全職員向けビジネススキル研修の新設
- 福祉職・技術職向け専門コンテンツの拡充
人材育成・確保基本方針策定指針に対応したeラーニング
今般のリニューアルでは、令和5年に26年ぶりに総務省から公表された新たな「人材育成・確保基本方針策定指針」に完全対応するとともに、全職員に必要なビジネススキルの網羅、専門性の高い福祉職・技術職向けコンテンツの設置、ナッジやヤングケアラー、女性活躍推進といった行政トレンドをおさえたテーマを組み込んだ研修を多数ご用意。 行政課題を解決する専門的知識とスキルを身につけ、広い見識と高い職業倫理観をもった職員の育成を実現し、行政運営の最大効率化、すべての住民福祉の向上、地域経済振興・地方創生の推進、より質の高い行政サービスの提供を力強く支援します。
e-JINZAI for governmentの詳細はこちら


