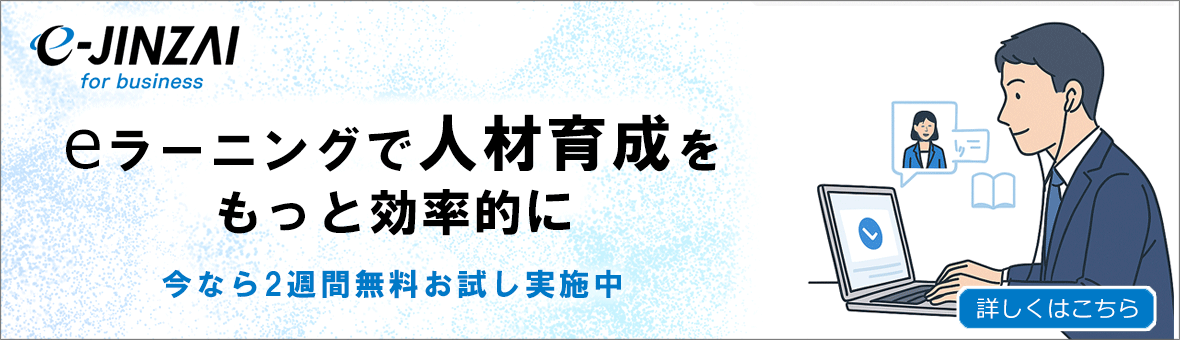【働く人のストレス対策】メンタルヘルスを整えるセルフケアのはじめ方

現代の働く人にとって、ストレスは避けて通れないものです。職場での業務量の増加や人間関係の悩みに加えて、家庭での育児や介護、健康面の不安など、多くの要因が複雑に絡み合っています。これらのストレスを「自分の弱さ」と誤解し、無理を重ねてしまう人も少なくありません。しかし、ストレスを感じるのは自然な反応であり、むしろ適切に向き合うことができれば、心の健康を保ち、前向きな毎日を送ることができます。
本記事では、ストレスを「悪者」にするのではなく、正しく理解し、上手にコントロールしていくための具体的なセルフケアの方法をご紹介します。自分自身との向き合い方、感情を整理する手段、そして必要に応じて誰かに頼ることの大切さまで、日々の生活にすぐに取り入れられる実践的なヒントをお届けします。
⇒ ひとりでがんばる前に、「e-JINZAI for business」で学べる心のケアを
目次
- ストレスを正しく理解する
- 職場でのストレス要因とは
- セルフケアの第一歩「自分と向き合う」
- 誰かに相談することの大切さ
- 前向きな習慣がレジリエンスを育てる
- セルフケアだけでは難しいと感じたら
- 研修で得られる5つのメリット
- まとめ
ストレスを正しく理解する
まずは、ストレスとは何かを知ることが重要です。ただ避けるのではなく、その役割を理解することから、セルフケアは始まります。
ストレスは敵ではない
私たちは「ストレス=悪いもの」と捉えがちですが、実はストレスには「良いストレス(快ストレス)」と「悪いストレス(不快ストレス)」の2種類があります。快ストレスは適度な緊張感を生み、集中力やモチベーションの向上に役立ちます。一方、不快ストレスは長期間にわたり心や体に負担をかける状態で、無視すると不調や疾患の原因となることもあります。
ストレスとは、心の状態を知らせてくれる大切な「信号」なのです。まずはその信号に気づき、状態を見極めることが大切です。
ストレスのサインに気づく
ストレスがたまってくると、次のようなサインが現れることがあります。
- 眠りが浅い、寝つけない
- 胃痛や頭痛などの身体症状
- イライラする、気分が落ち込む
- 集中力が続かない
- ケアレスミスが増える
これらのサインに早く気づくことで、セルフケアにつなげることができます。
職場でのストレス要因とは
人間関係と業務負荷
職場におけるストレスの大きな要因は、人間関係と仕事の量や質です。上司との意思疎通がうまくいかない、部下への指導に自信が持てない、同僚とのちょっとした誤解が積み重なるなど、些細なことでも大きなストレスにつながります。また、終わりの見えないタスクや期限に追われる日々が、心の余裕を奪っていきます。
プライベートと仕事のはざまで
近年では、家庭の問題が職場に影響を与えることも珍しくありません。育児や介護、家族の病気など、生活の中の課題が精神的な負担となり、仕事にも影響を及ぼすケースが増えています。ストレスの要因は一つではなく、複数の問題が重なって起きていることが多いのです。
セルフケアの第一歩「自分と向き合う」
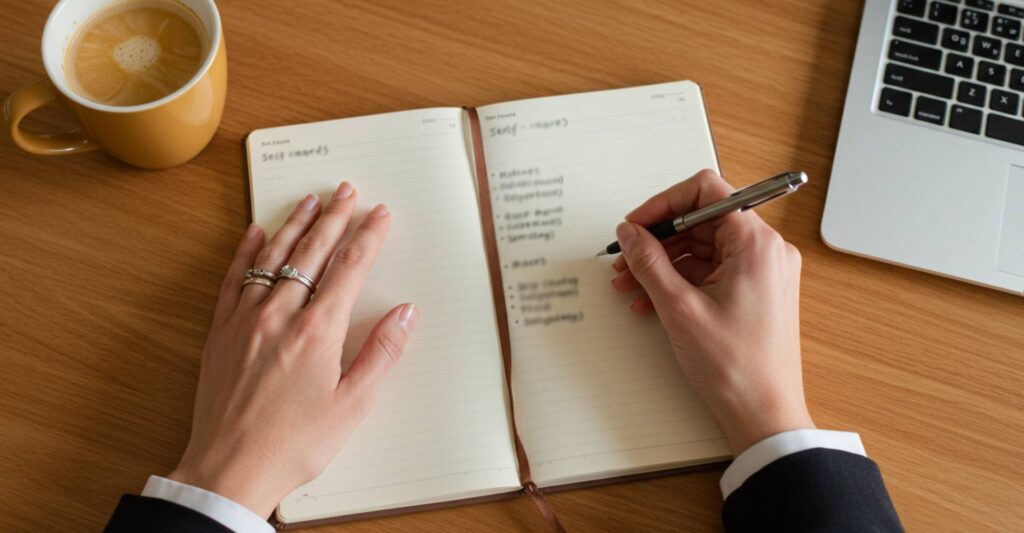
ストレスメモを書いてみる
ストレスに気づくためには、「感情を言葉にする」ことが有効です。おすすめの方法が、ストレスメモの活用です。ストレスを感じた出来事と、そのときの気持ちを手帳やノートに具体的に書き出してみましょう。例えば、「上司に意見を否定されてイライラした」「朝、家族と口論して落ち込んだ」など、状況と感情を記録することが大切です。
例えば、以下のように書いてみましょう。
例:
「13:00 会議。話し方に自信がなく、うまく伝えられずイライラ。相手の反応が冷たく感じて、落ち込んだ。」
このように、状況・気持ち・反応をセットで書くと、自分のストレスパターンが見えやすくなります。
この行為は、1980年代に提唱された心理学的手法「エクスプレッシブ・ライティング(筆記開示)」に基づいたもので、感情を可視化することで客観的に自分の状態を把握できるようになります。
自分の思考のクセに気づく
ストレスメモを振り返ると、「自分がどういうときにストレスを感じやすいか」という傾向が見えてきます。たとえば、「会議で話すことにプレッシャーを感じる」「否定されると過敏に反応する」など、自分の思考のパターンを把握することで、感情の波に飲まれにくくなります。
この「自己理解」は、レジリエンス(回復力)を高める上でも非常に重要な要素です。
誰かに相談することの大切さ
自分の心を守るためには、ときに「誰かを頼ること」も必要です。一人で抱え込まず、周囲の力を借りる選択肢を持ちましょう。
ひとりで抱え込まない
すべてを自分ひとりで解決しようとすると、ストレスはどんどん蓄積されていきます。特に、介護や持病など、自分の努力ではどうにもならないことに直面したときには、周囲のサポートを受けることが必要です。
職場の同僚、信頼できる友人、あるいは専門家に相談することは、「弱さの表れ」ではなく、自分を守るための大切な行動です。
相談にも「整理」が必要
人が悩んでいるときには、大きく2つの心理状態があります。一つは「困っている状態」で、具体的な問題の解決方法を知りたいケース。もう一つは「悩んでいる状態」で、何に悩んでいるか自分でもはっきりせず、モヤモヤしている状態です。
相談するときは、この違いを意識し、「自分が何に困っているのか」「何がモヤモヤの原因なのか」を整理しておくと、相手にとっても伝わりやすくなり、より有効なサポートを受けやすくなります。
前向きな習慣がレジリエンスを育てる
良かったことメモのすすめ
ストレスを軽減するには、ネガティブな出来事だけでなく、「良かったこと」にも目を向けることが効果的です。たとえば、「上司に感謝された」「お昼に好きなものを食べられた」など、日常の中で感じたポジティブなことをメモに残しておくと、自己肯定感が高まり、ストレスに対する耐性がついていきます。
例:
「お昼に好きなパスタを食べてリフレッシュできた。午後の会議では、部長に“わかりやすかった”と褒められて嬉しかった。」
ポジティブな経験も書き留めることで、自己肯定感が自然に育ちます。
小さなセルフケアが未来を変える
セルフケアとは、特別なことではありません。仕事の合間にストレッチをしたり、夜にゆっくり入浴したり、趣味の時間を大切にしたりと、自分の心と体をいたわる時間を意識して取り入れてみましょう。こうした習慣の積み重ねが、将来的に大きなストレス耐性となって表れてくるのです。
セルフケアだけでは難しいと感じたら
セルフケアの習慣を取り入れることで、ストレスとの付き合い方は少しずつ変わっていきます。しかし、すべてのストレスが「自分の努力だけ」で乗り越えられるわけではありません。実際、真面目で責任感の強い人ほど、「自分で何とかしなければ」と抱え込み、心身の限界を迎えてしまうこともあります。
仕事の負荷や人間関係、ライフイベントなど、ストレスの要因が複雑に絡み合っていると、自分一人で状況を整理したり、冷静に対処するのは難しくなります。セルフケアを試しても、「やっぱりうまくいかない」「気持ちが晴れない」と感じるときは、それが悪いわけではありません。それは、今の自分に必要なのが“個人の努力”ではなく“周囲のサポート”だというサインかもしれないのです。
ストレスと上手につき合っていくためには、セルフケアと外部からの支援のバランスがとても重要です。自分をいたわる小さな習慣に加えて、職場や組織として「ストレスケアを支える環境」が整っていることで、心の健康はさらに安定します。次のセクションでは、そうした職場のサポートの一つである「研修」が、どのように働く人の力になるのかをご紹介します。
研修で得られる5つのメリット

個人のセルフケアに限界を感じたとき、次にできることの一つが「学びの場に参加する」ことです。ストレスと向き合うための知識やスキルを体系的に学べる研修は、自分自身を深く理解し、心の扱い方を知るための有効な手段です。以下に挙げるのは、セルフケア研修を受けることで得られる主なメリットです。
- ストレスへの理解が深まる
日々感じているモヤモヤや不調が、どこから来ているのかを明確に理解できるようになります。漠然とした不安が、「あ、これはこういう仕組みで起きているんだ」と分かるだけでも、心の負担はぐっと軽くなります。 - 感情の整理ができるようになる
ストレスがたまると、気持ちをうまく言葉にできなくなりがちです。研修では、感情を言語化するためのワークや方法を学ぶことができ、自分の内面を整理する力が高まります。 - 相談する力が身につく
「誰かに頼る」ことは簡単なようでいて、実は多くの人が苦手にしています。研修では、相談する際の心構えや、伝え方のポイントを学ぶことができ、他者との関係構築にも良い影響を与えます。 - 思考のクセに気づける
ストレスの背景には、「こうあるべき」「失敗してはいけない」といった思い込みがあることも。研修では、自分の思考パターンに気づくきっかけが得られ、無意識のクセを手放すことができるようになります。 - 日常生活への応用ができる
研修で得た気づきや方法は、職場だけでなく家庭やプライベートでも活かすことができます。自分の感情と向き合い、前向きにリカバリーできる力は、人生全体の質を高める大きな資産になるでしょう。
まとめ
ストレスは、私たちが日々の生活や仕事に真剣に取り組んでいる証でもあります。しかし、それを放置したままにしておくと、心身に大きな負担をかけてしまい、気づかないうちにパフォーマンスや人間関係に影響が出ることもあります。だからこそ、ストレスとうまく付き合う「セルフケア」の習慣が重要なのです。
まずは、自分の感じているストレスに気づくこと。そしてその感情を否定せず、紙に書き出したり、信頼できる人に話したりして、少しずつ整理していくこと。それが、心を整え、回復力(レジリエンス)を育てる第一歩になります。日々の中で小さな「良かったこと」を見つける習慣も、自己肯定感を高め、ストレスへの耐性を強くしてくれます。
セルフケアは特別なスキルではありません。今日からできる小さな工夫の積み重ねが、あなたの未来を明るく変えていきます。誰かに頼ることも、自分を守る大切な選択です。心の健康を守る力を育てながら、自分らしく、そして安心して働き続けるための一歩を踏み出してみましょう。
メンタルヘルス研修
日々の多忙な業務や社内での人間関係など、様々な要因からストレスを抱え、心身の不調により休職や離職に発展するケースは増加傾向にあります。個人および組織がメンタルヘルスに対する正しい知識を持ち、柔軟な対応ができるようになることは、大きな問題への発展を防止することに繋がります。本研修では、一般向け・人事向けと異なる観点から研修をそれぞれ用意しており、メンタルヘルスの向上や組織で問題が発生した際の対応方法などについて学習することができます。ストレス社会を健康的に過ごす知識を身につけましょう。
詳細・お申し込みはこちら