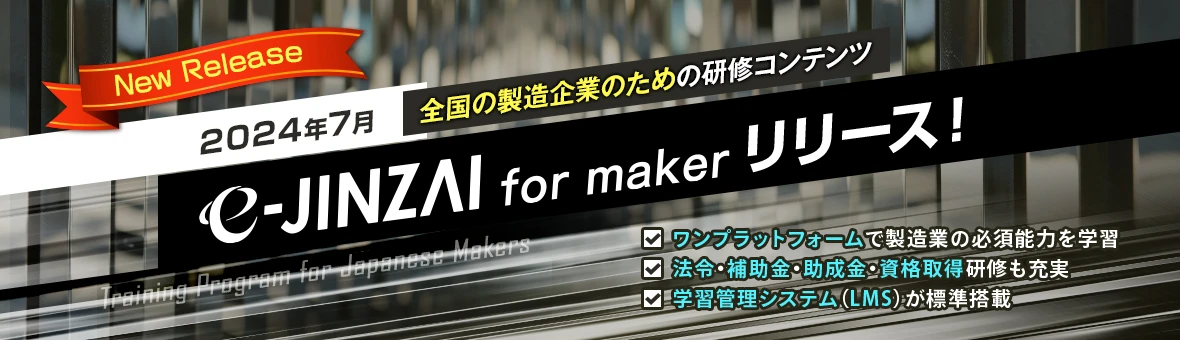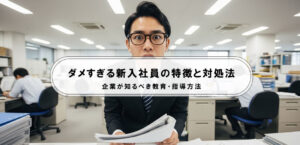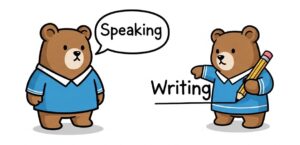属人化が進むなら、技術承継の見える化を

KEYWORDS 製造業・メーカー
製造業の多くの現場で、今まさに深刻な問題となっているのが、熟練技能者の高齢化と若手人材の不足です。現場に長年蓄積されてきた技術やノウハウの多くが、属人的な形で保持されており、マニュアルだけでは到底カバーしきれない暗黙知として存在しています。これらをいかに次世代へ継承し、組織として活かし続けていくかは、企業存続にも関わる重大なテーマです。
この記事では、技術承継がなぜ今、求められているのかを整理し、具体的な承継の進め方、そして研修による支援の可能性までを体系的に解説します。
⇒「見て覚えろ」から「見せて育てる」へ。現場のノウハウを次世代につなげる|e-JINZAI for maker
目次
技術承継が求められる理由

日本の製造業は、高い品質や丁寧な仕上がりを特徴としてきました。その源泉は、現場に蓄積された熟練者の技術力にあります。しかし、その多くが「言葉では伝えにくい」「マニュアルに書けない」性質を持つ暗黙知であり、個々の経験の中に埋もれています。
このままでは、ベテラン社員の定年退職とともに貴重な知識が失われ、現場の力が一気に低下するリスクがあります。製品不良の増加、設備トラブルの対応力の低下、若手の離職――その影響は多岐にわたるでしょう。
なぜ組織的承継が今必要なのか?
以下のような構造的背景が、技術承継の必要性を高めています。
- 熟練者の大量退職が目前に迫っている
- 技術の属人化が進み、再現性のない作業が増えている
- 若手の定着率が低く、育成の効果が得られにくい
- 製品品質や現場対応力の維持が難しくなっている
暗黙知を形式知に変換し、誰もが理解し再現できるようにするには、時間と仕組み、そして全社的な取り組みが必要です。
現場に存在する課題
実際の現場では、技術承継が思うように進まない理由がいくつもあります。
たとえば、ある中小企業では、熟練の職人が新人に作業を教える際、「見て覚えろ」が未だに根強く残っています。何年もかけてようやく身につく作業も、そもそも何を見て、どこに注意すればいいのかが明示されていないため、新人は理解しきれず、ミスや不良が発生してしまうのです。
また、教える側も「どうやって教えたらいいのか分からない」「自分のやり方を説明するのが難しい」と感じており、結果として場当たり的な指導に終始してしまうケースが少なくありません。
現場は常に忙しく、教育に割ける時間も限られています。そのため、長期的な育成計画を立てられないまま、貴重なノウハウが日々失われているのが現実です。
技術承継の進め方と5つの手法

技術承継を円滑に進めるには、現場任せではなく、体系的かつ戦略的な方法論に基づいた取り組みが不可欠です。この章では、承継を機能させるために有効とされる5つの手法をご紹介します。
職業能力の可視化
技能や技術を効果的に伝えるには、「何を、どのレベルで、どのように教えるか」を明確にする必要があります。
その出発点となるのが「仕事マップ」の作成です。仕事マップでは、各作業工程を職務単位に分解し、それぞれに必要な知識・技能・態度を整理します。さらに、各能力を5段階(初心者~熟達者)にレベル分けすることで、教育対象者がどの位置にいて、どこを目指すべきかが明確になります。
この構造化によって、属人的な育成から脱却し、計画的・戦略的な教育体制が構築できます。
作業改善による標準化
作業改善は、技術承継の大きな足がかりになります。たとえば、治具や工程を見直すことで、従来は熟練者でなければ対応できなかった工程が、若手でもこなせるようになります。
- 内段取りの外段取り化による効率化
- 治具改善で作業のばらつきを減らす
- 作業手順書や改善記録を教材化
- 改善活動そのものが技能の共有機会になる
改善の過程を記録・共有すること自体が、技能の可視化・継承に直結します。
モデリングで暗黙知を再現
技能の多くは「見て学ぶ」ことで習得されてきました。モデリングはこの方法を意図的・体系的に活用する手法です。
熟練者の作業を動画に収め、どのような動作をしているのかを細かく分析し、言語化・図解化します。そのうえで、若手が実際に真似をしながら、少しずつ改善を加えていくプロセスを経ることで、単なる模倣にとどまらない「理解」を伴った技能が定着します。
「なぜその順番で作業するのか」「どの瞬間に判断しているのか」などを対話を通じて引き出すことで、暗黙知を再現可能な知識へと変えていくのです。
実践知の補強と共有
製造現場では、設備の微妙な違いや環境条件によって、作業の結果が左右されることがあります。そうした状況で必要になるのが「実践知」です。
たとえば、夏場と冬場で機械の温度が変わるため、微調整が必要になるようなケースです。これは一見すると属人的な感覚ですが、経験を積めば誰でも理解できる知識として整理することができます。
補強知識として、「現象の背景にある理由」や「典型的なトラブル例」「判断基準」を追加情報として整理することで、若手が短期間で“現場感”を得られるようになります。
支援システムとデジタルOJT
近年では、ICT技術を活用した技術承継の仕組みも注目されています。
- 視線解析や動線記録で熟練者の判断を可視化
- 動画教材、シミュレーター、VRなどで遠隔・反復学習
- デジタルOJTにより、属人性を排除し、教育の均質化が可能
こうした技術の活用により、技能継承の効率化と標準化が一気に進んでいます。
研修による支援の可能性
技術承継は現場だけで完結するものではありません。体系的な教育が必要な場面では、集合研修やワークショップなどの形式教育が大きな効果を発揮します。ここでは、研修をどのように設計・活用するかを見ていきます。
若手の育成に効く研修設計
技術承継を円滑に進めるには、OJTだけでなく、OFF-JT(集合研修)の活用が欠かせません。研修の強みは、「なぜこの作業が重要なのか」「どうすれば応用できるのか」といった全体像を捉える視点を与えることにあります。
特に有効なのは、「成功体験を積める設計」です。小さな達成感が自信を生み、自己効力感が育まれることで、継続的な学習意欲が高まります。また、ピアレビューやディスカッション形式を取り入れることで、学びの定着も図れます。
OJTとの役割分担
OJTは現場での即戦力を育てる実践的な手段ですが、体系的な知識を伝えるのには限界があります。一方、研修では知識の整理や応用力の強化が可能です。
- OJT:実作業を通じた体験と実践知の習得
- OFF-JT:背景知識や理論、標準手順の理解
- 組み合わせることで「理解→実践→改善」の循環を構築
両者の役割を明確に分担し、連動させることで、より高い教育効果が期待できます。
技術承継を根づかせるための組織づくり
技術承継は、現場任せにしていては進みません。組織全体で取り組むべき課題です。
まず重要なのは、教育を担当する人材の評価制度を整えることです。「教えること」に対して正当な評価がなされなければ、持続的な承継は期待できません。
また、「守破離」の考え方も有効です。最初は手本を忠実に守る「守」、次に自分なりの工夫を加える「破」、最終的には独自の方法を確立する「離」という段階を設けることで、自然な成長と技術の深化が促されます。
経営層の関与も不可欠です。育成が企業の未来を左右する投資であると認識し、リソースと時間を確保する姿勢が求められます。
まとめ
ものづくりの現場では、技術の蓄積が何よりの財産です。しかし、それが属人的なままであれば、継続性は失われ、企業の競争力にも陰りが見えることになります。
技術承継を単なる作業の引き継ぎではなく、組織の知を未来へつなぐプロセスとして捉え、戦略的に推進することが求められます。可視化、仕組み化、教育支援、そしてデジタル技術の活用を通じて、暗黙知を組織知へと変えていく。それが、これからの製造業における持続的な成長の鍵となるのです。
e-JINZAI for makerの技能伝承研修
多くの日本企業は人手不足の課題を抱えており、なかでも製造業においては、人手不足に加え「技能伝承」「技術継承」が進まないことが、より深刻な問題と言われています。「技能伝承」は特に製造業において、企業が存続し続けるためには必要不可欠ですが、このような課題の対策に関して、研修や情報開示があまり行われていないのが現状です。本研修では、技術伝承の概要から製造業における課題とその対策について解説します。
2週間無料お試しはこちら