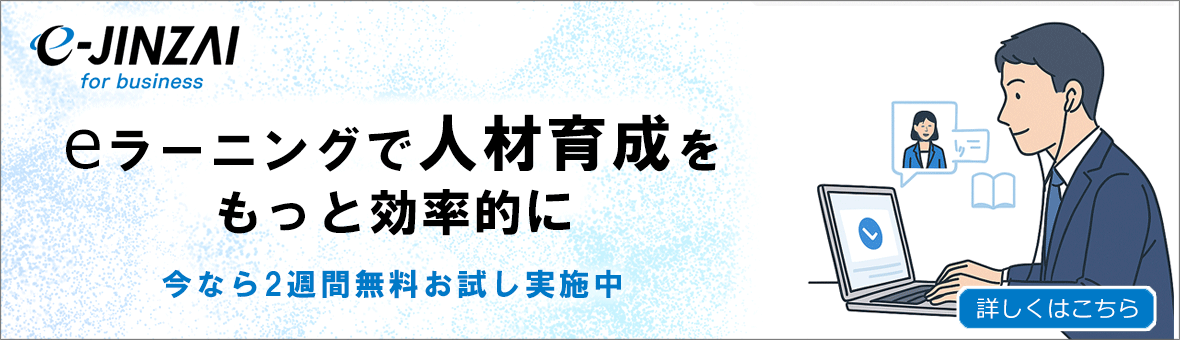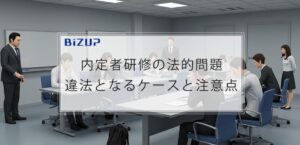人材育成の仕事内容とは?基本的な考え方や業務内容、成功事例を紹介!

人材育成は、企業が業績向上のための目標達成をテーマに、優秀な人材を育てる考え方です。現実的に人材不足に悩む企業は多く、そのため人材育成が占める重要性は大きいものといえるでしょう。
本記事では、人材育成をおこなう部署の仕事内容、具体的な方法や考え方、事例を解説します。
⇒ 効果的な人材育成の手法を学ぶなら『e-JINZAI for Business』
目次
人材育成とはとはなにか

人材育成とは、文字通り「企業ごとに優れた従業員を育成する」ことを指します。仕事内容への向き合い方や能力が高く、その成果として企業の成長や発展に貢献できる人材を育てていくことと、その役割を担った部署、担当者が必要です。
即戦力を求める傾向が多い中で、比較的中長期的に人材育成はおこなわれます。多少の時間を考慮しても、将来的な業績向上につなげることを目的とした考え方です。
現行の人材のスキルを認めて、さらに生産性向上のために磨き上げられれば理想的ですが、人手不足の課題もあってなかなか進展しない企業もあります。人材を育てる以前に、人材育成についての知識やノウハウの優れた人物や方法が問われているのが現状です。
人材育成の重要性
では、なぜ人材育成の重要度が高まっているのでしょうか。
その背景としては、大きく2つ考えられます。
- テクノロジーの進化と市場の均質化
- 人材不足
テクノロジーが進化し、仕事内容が自動化することは当然となってきました。ある程精度の高いサービス提供は、どの企業でも可能になりつつあります。そのため、企業が自社の技術力や価格による競争でライバルに勝つことは徐々に難しくなってきました。改めて多くの企業が、差別化を図るための要素として注目し直しているのが人材です。
そして、人材育成の必要性で最も大きな理由は、人材不足により運営の円滑さを失いつつある点が大きいでしょう。人口減少の煽りを受けて、もはやどの業種・業界も、今後は人材不足が続くものと考えられています。
優れた人材獲得が激化すると予想され、とにかく今いる現行のスタッフ一人ひとりのスキル向上を考え、生産性を上向きにすることも企業課題になってきたからです。
人材育成の目的
人材育成をおこなう目的とは、企業活動の目的と密接な関係性があります。それは「組織や事業の存続」と「組織戦略の達成」の2つです。これらの観点から人材育成およびその仕事内容も決定されていきます。組織や事業の存続のためには優秀な人材が必要です。
その人材が活躍できる土壌があってこそ、初めて組織維持が可能となります。転職市場が盛んであることは社会経済的にも有効的です。しかし、あまりにも流動的すぎると、企業組織自体の問題も浮上していくでしょう。
スタッフが定着せず常に求人ばかりする企業が、よい業績を収める事例はありません。人材育成に注力してスタッフのモチベーション維持を重視することで、仕事の幅が広がり、個人の生産性も向上し、優秀な人材が離職することを防止できる期待があります。
また、組織戦略を達成するには、以下の内容を踏まえておく必要があるでしょう。
- プロとしての知識・スキルを身につける
- 技術革新や最新事情への理解とスキルを吸収する
- 変化へ自律的に行動する
これらを達成するには、個人の成長が最重要項目になりますが、企業側からの積極的サポートも不可欠です。そのために、人材育成の担う役割が成立しています。
人材育成と人材開発の違い
よく人材育成と比較されるのが「人材開発」というキーワードです。人材育成と人材開発には、どのように仕事内容に差があるのでしょうか。
ここでは、人材育成と人材開発の違いを解説していきましょう。
育成は基本強化で開発はスキルアップ
まず人材育成という言葉を使用する場合、職種によって必要となる基本知識とスキルを習得させる目標を置いて実践することを指します。その一方で、人材開発とは、組織全体を底上げするためのスキルアップが目的です。
人材育成と人材開発の2つは同義語であり、大きな違いがなく用いられることもあります。強いて違いがあるとしたら以下のような区分です。
人材育成
- 対象者が新入社員、若手社員など
- 目的は業務遂行に必要なスキルの習得
- 方法は集合研修・ジョブローテーションなど
- タイミングは入社・異動・昇格など直後
人材開発
- 対象は者は全社員
- 目的は組織力のさらなる強化
- 方法は社内研修・外部講座など
- タイミングは随時もしくは必要に応じた場合
人材育成と人材開発にかかる時間
人材育成と人材開発の違いにはかかる時間の考慮が必要です。人材育成は、おもに新入社員などの不慣れな立場のスタッフに向けられるため、長期間実施されます。
その一方、人材開発については短期間で集中的な研修やトレーニングを実施する傾向です。ただし、設定したゴールへの到達までの実際の長さは、内容や手法によって異なります。
人材育成がなぜ企業に必要なのか
現在のビジネス全般では、人材育成こそ企業ビジョンを達成するための要素の1つとなってきました。
では、なぜ人材育成が早急に必要だと問われ始めたのでしょうか。人材育成が必要な背景に着目しなくてはなりません。
生産性向上
人材育成を達成すると、生産性向上につながりやすいからです。スタッフが成長して業務時間への労力が削減できるでしょう。効率と質の向上にもつながります。限られた人員や資源を生かしながら成果を生み出すのに、今や人材育成が欠かせなくなりました。
また、削減できるコストが多くなれば、それだけスタッフの生活改善にも充てられるメリットができます。
業績向上
人材育成をおこなってスタッフが成長すれば、企業の目標に向けて主体的に行動するようになります。適切な判断や行動が可能となり、企業の業績につながるでしょう。
もし自分がするべき仕事を理解できず、ただ受け身なままのスタッフでは、業績向上は望めません。自主性を持って仕事に取り組める人材を育てることが重要です。
経営戦略実現
人材を育てることは、経営戦略の実現にも直結するでしょう。ただ仕事ができればよいわけではなく、その都度の企業の戦略目標を一緒に達成できるマインドのある人物を育てることが本来の目的です。
人材育成によって目標達成に向けての行動指針を決定し、自主的・自律的な考えに基づく人物が育てば、組織経営の実現度が高まります。
人材育成のおもな手法

人材育成の手法は、いくつも考えられます。
そこでここでは、ポピュラーな8つの手法を厳選して解説していきましょう。
OJT(On the Job Training)
OJTとは、企業内教育の手法として頻繁に採用されています。上司や先輩社員の実務を通じて、知識やスキルを部下・後輩に実践形式で教える方法です。仕事内容の主旨は現場で経験を積みながら学べるため、とくに即戦力重視の人材育成にて活用される機会が目立っています。
OFFJT(Off the Job Training)
OFFJTとは、座学によるビジネススキルなどを体系的に学ぶ研修のことを指します。この中に、eラーニング・集合研修・通信教育が含まれます。
eラーニング
eラーニングとは、インターネット回線を利用した研修方法全般を指します。メリットは、時間・場所の拘束がなく多人数で同時に受講ができて、1人あたりの受講コストを抑えることができる点です。
スタッフが好きな時間に学べ、業務に支障をきたすことがない自由度の高さも魅力になるでしょう。
内部集合研修
内部集合研修とは、企業内部にて講師を選出し、実務スキルや知識を学ばせる研修です。実践に基づいた業務の専門知識やスキルを、現場目線から習得できます。
また、リアルな対面式なので、受講者同士の意見交換も可能です。
外部集合研修
外部集合研修とは、企業内ではなく外部からエキスパート講師を招き、専門的スキルや知識を学ぶ研修を指します。具体的な仕事内容の実践感覚はありませんが、社内で見落としがちな客観的知識を体系的に学べることがメリットです。
自己啓発
自己啓発とは、本人の意志による人材育成の手法です。
外部でおこなわれているセミナーや通信教育への受講、ビジネス書籍での学習、国家資格取得などを斡旋して、スタッフの自主性を尊重した手法を指します。
目標管理制度(MBO)
目標管理精度は、「MBO(Management By Objectives)」とも呼ばれる手法です。
スタッフ各人の目標と企業目標とを連動させ、そのまま成長を促しながら管理もともなうように工夫されています。自分の目標達成によって企業に貢献できる仕組みなので、参画意識や主体性を養うことができるでしょう。
ジョブローテーション
ジョブローテーションとは、期間を設け実践的に複数の業務や部署を経験させる手法です。多用な仕事を経験できるため、社内全体の理解を深められます。
部署間を越えて円滑なコミュニケーションができるようにもなるでしょう。
人材育成のおもな仕事内容の手順
企業が効果的な人材育成を成功させるためには、事前準備が重要となるでしょう。
事前準備とはしっかりとした段階を踏みながら、人材育成の手順を確立させることです。
ここでは、おもな人材育成のための仕事内容の手順を解説します。
自社課題の把握
人材育成をする以前に、自社課題がどこにあるのかを把握しておく必要があるでしょう。今どのような人材が必要で、業務上の問題解消するべきかを検討します。
そのための準備としては、現場でのヒアリングは欠かせず、現状把握から逃避しない姿勢が大切です。該当した部署の管理職だけを対象にするのではなく、一般的なスタッフや新入社員から幅広くヒアリングしましょう。
目標の明確化
人材育成の目的を明確化します。どのような人材をいつまでに何人育てるのかなど具体的な設定です。
現状とのギャップも確認し、方向性を検討していきます。人事担当者と経営者が交えながら検討する必要性があるでしょう。
スキルマップの作成
スキルマップとは、取得してほしいスキル・能力を一覧表にしたものです。入社時から役職に就くまでに獲得するスキルは何かを設定し、全体像を把握しやすいように工夫します。
スキルマップ方法は、以下のような順序になるでしょう
- 必要スキルの洗い出し
- 年次・役職別での仕分け
- 整理・修正の上で決定
育成方法の決定
最後に育成方法の決定です。
現場への負担や費用対効果も考慮しながら、本来の業務への支障が出ない範囲でおこなうことがポイントになるでしょう。コストが必要以上にかかると予測されたら、eラーニングや通信教育などの活用が可能かを検討します。
人材育成のおもな事例
実際に人材育成で成功している企業とは、どのような方法で取り組んできたのでしょうか。ここでは、人材育成に成功した事例・シチュエーションを解説します。
スターバックスコーヒージャパン株式会社
世界規模でコーヒーストアを経営するスターバックスコーヒーでは、ドリンクのレシピなど品質に対する厳格なルールが定められています。
ところが、接客のサービスマニュアルは一切策定されていないことが特徴です。マニュアルでスタッフを拘束するのではなく、権限を与えることでミッションに従いスタッフ自らが考えることを推奨しています。
新人店舗のオペレーションを学ぶ際も、正社員、アルバイトなどの雇用形態や仕事内容の区別をせずに、全スタッフが教育プログラムを共有するシステムです。あくまでもスタッフの行動を重視し、信頼していることを意味しています。
サントリーホールディングス株式会社
サントリーホールディングス株式会社の人材育成では、社歴や国籍による差別をせず新しいアイデアを重視するのが特徴です。例えば、企業内大学として「サントリー大学(人材育成の総称)」が設立されています。
また、「MySU」(マイ・エス・ユー、My Suntory University)というプラットフォームを導入し、受講やイベント参加が気軽にできる仕組みです。他にも「有言実行やってみなはれ大賞」という表彰式が創設されました。
世界中から400チーム以上がエントリーした記録もあり、自主性を重視した発想を創出する仕組みを取り入れています。
まとめ
人材育成の仕事内容は、企業が自社の戦略を実現させる意味でも重要な行動です。
経営戦略の実現性を高める人材を健全な方法で育てることで、現行の課題解決ができて、将来的な能力開発にも関わっていきます。
ただし一朝一夕で確立できるものではなく、中長期的な視点で構築していく必要があるでしょう。まずは、各部署の現場で何が起こっているのかを、客観的に把握し、問題点などを洗い出すことが大切です。
人材育成を学ぶならe-JINZAI for Businesss
人材育成は、企業が業績向上のために必須の業務です。ビズアップ総研の人材開発研修では、人材育成戦略の立て方や研修計画の立案、効果測定など、人材育成担当者に必須の知識を学ぶことができます。
2週間無料お試しはこちら