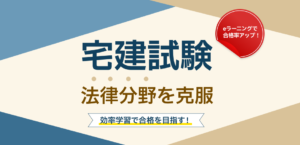国家公務員倫理法とは?倫理規程の内容と違反事例を徹底解説

KEYWORDS 公務員
国家公務員倫理法は、公務員の職務の公正性と透明性を確保するために1999年に制定された重要な法律です。この法律と国家公務員倫理規程により、公務員が守るべき行動規範が明確に定められています。
近年、公務員の不祥事が報道されるたびに、「倫理法違反ではないのか」という声が上がります。しかし、実際にどのような行為が禁止されているのか、違反するとどうなるのか、正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、国家公務員倫理法と倫理規程の基本内容から、具体的な禁止事項、罰則、実際の違反事例まで、公務員を目指す方や現職の方、あるいは公務員と接する機会のある民間企業の方にも役立つ情報を網羅的に解説します。
目次
- 国家公務員倫理法の基本概要と制定背景
- 国家公務員倫理規程の具体的内容
- 禁止される具体的な行為
- 違反した場合の罰則と処分
- 実際の違反事例から学ぶ
- 倫理審査会と監督体制
- 公務員を目指す方・現職の方へのアドバイス
- まとめ


自治体職員のための行政法
動画数|25本 総再生時間|459分
自治体職員として業務を遂行する上で欠かせない「行政手続法」について、実務に直結する視点から学びます。申請に対する処分、不利益処分、行政指導の3領域を中心に、法令の条文だけでなく、実際のケースを用いてその意義や運用上の注意点を具体的に解説。
動画の試聴はこちら国家公務員倫理法の基本概要と制定背景
国家公務員倫理法は、1999年(平成11年)8月に制定され、2000年4月1日から施行された法律です。
制定の背景には、1990年代後半に相次いで発覚した官僚の接待汚職事件や、大蔵省(現・財務省)の「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」など、公務員の倫理観が問われる不祥事がありました。
法律制定の目的と理念
国家公務員倫理法の第1条では、法律の目的を明確に定めています。この法律は、国家公務員が職務に関して利害関係者から金銭や物品を受け取ることを規制し、職務の公正性の確保と行政に対する国民の信頼を保つことを目指しています。
単に違法行為を処罰するだけでなく、「疑念を抱かれるような行為の防止」という予防的な観点が重視されているのが特徴です。つまり、実際に職務に影響がなくても、国民から見て不適切と思われる行為そのものを避けることが求められています。
適用対象となる職員の範囲
国家公務員倫理法の適用対象は、一般職の国家公務員全員です。具体的には、各省庁の職員、国税職員、自衛隊の事務官などが含まれます。ただし、特別職(内閣総理大臣、国務大臣、裁判官など)や防衛省の自衛官は対象外です。
国家公務員倫理規程の具体的内容
国家公務員倫理規程は、倫理法第5条に基づいて人事院が制定した政令です。倫理法が定める原則をより具体化し、公務員が日常業務で守るべき行動基準を詳細に規定しています。
倫理規程で定められた5つの倫理原則
倫理規程第3条では、すべての職員が遵守すべき5つの基本原則を定めています。
- 国民全体の奉仕者性:一部の者の利益のためではなく、常に国民全体の利益のために職務を遂行する
- 職務の公正性:職務上の権限を濫用せず、公正に職務を執行する
- 清廉性の保持:自己の利益を図る目的で職務を行ってはならない
- 公正性への疑念防止:国民から疑念を持たれるような行為をしない
- 品位の保持:職務の内外を問わず、公務員としての品位を保つ
これらの原則は抽象的に見えますが、次に説明する具体的な禁止行為の基礎となっています。
利害関係者の定義
倫理規程における「利害関係者」とは、職員の職務に利害関係を有する個人や法人を指します。具体的には、許認可等の相手方、補助金等の交付先、検査・監督の対象となる事業者、契約の相手方などが該当します。
この定義は非常に重要で、多くの規制が「利害関係者」との関係で適用されます。
禁止される具体的な行為

国家公務員倫理規程では、公務員が利害関係者との間で行ってはならない具体的な行為を列挙しています。これらは「禁止行為」として厳格に制限されています。
金銭・物品等の贈与の禁止
利害関係者から金銭、物品その他の財産上の利益の供与を受けることは原則として禁止されています。これには、贈答品、お中元・お歳暮、金券、高額な土産物などが含まれます。
ただし、以下のような例外があります:
- 宣伝用物品や記念品で広く一般に配布されるもの
- 多数の者が出席する立食パーティーでの茶菓
- 職務として出席する式典での記念品(一定の範囲内)
飲食接待に関する規制
【表1:飲食接待の規制内容】
| 区分 | 内容 | 報告義務 |
|---|---|---|
| 利害関係者との飲食 | 1万円以下は可能(一部例外あり) | 5,000円超は事後報告 |
| 利害関係者以外との飲食 | 制限なし(ただし倫理原則は適用) | 基本的に不要 |
| 割り勘での飲食 | 自己負担が明確であれば可能 | 不要 |
利害関係者と飲食をする場合、一人当たりの費用が1万円を超える場合は原則禁止です。5,000円を超える場合は事後に報告書の提出が必要となります。
その他の禁止行為
以下のような行為も倫理規程で明確に禁止されています:
- 無償での役務提供:利害関係者から無償で役務の提供を受けること
- 不動産取引:利害関係者と不動産売買などの取引を行うこと
- 金銭の貸借:利害関係者から金銭を借り入れること
- 株取引等:利害関係者が関係する未公開情報に基づく株取引
- 無償の便宜供与:ゴルフ、旅行など遊技・遊興での便宜供与
違反した場合の罰則と処分
国家公務員倫理法や倫理規程に違反した場合、段階的な処分が科されます。処分の重さは違反の内容や悪質性によって異なります。
倫理法違反の刑事罰
特に悪質な違反については、刑事罰の対象となります。
【表2:倫理法違反の刑事罰】
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 利害関係者からの金銭・物品の収受(職務関連) | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 禁止行為の要求・約束 | 同上 |
| 虚偽の報告 | 30万円以下の罰金 |
懲戒処分と行政処分
刑事罰とは別に、国家公務員法に基づく懲戒処分が科されます。懲戒処分には重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4種類があります。
倫理法違反の場合、多くのケースで免職や停職といった重い処分が科されています。また、倫理監督官による監督上の措置として、口頭での注意や文書による厳重注意が行われることもあります。
退職後の影響
倫理法違反が発覚した時点で既に退職している場合でも、退職金の一部返納を求められたり、刑事訴追の対象となったりする可能性があります。実際、退職後に違反が発覚して処分を受けた事例も複数存在します。
実際の違反事例から学ぶ
過去の違反事例を知ることで、どのような行為が問題となるのかをより具体的に理解できます。
高額接待による違反事例
2017年には、財務省の複数の幹部職員が学校法人関係者から高額な飲食接待を受けていたことが発覚しました。この事例では、職員が利害関係者から1回あたり数万円に及ぶ飲食の提供を受けており、明確な倫理規程違反として処分されました。
また、2015年にはNHKの複数の職員が、番組制作会社から繰り返し飲食接待を受けていたことが判明し、懲戒処分となりました。
物品供与による違反事例
国土交通省の職員が、建設業者から高額な贈答品を受け取っていた事例があります。お中元やお歳暮という名目であっても、利害関係者からの贈答は原則禁止であり、この職員は減給処分を受けました。
報告義務違反の事例
【表3:報告義務違反の主な事例】
| 年度 | 省庁 | 違反内容 | 処分 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 厚生労働省 | 利害関係者との飲食未報告(複数回) | 減給6ヶ月 |
| 2020年 | 経済産業省 | 株取引報告書の虚偽記載 | 戒告 |
| 2021年 | 環境省 | 贈答品受領の未報告 | 減給3ヶ月 |
これらの事例に共通するのは、「バレなければ良い」という安易な考えが重大な結果を招いたということです。
倫理審査会と監督体制
国家公務員の倫理保持を確保するため、人事院に国家公務員倫理審査会が設置されています。
倫理審査会の役割と権限
倫理審査会は、倫理法・倫理規程の運用に関する重要事項を審議し、各省庁への指導や職員からの相談対応を行います。また、重大な違反事例については調査権限を持ち、必要に応じて処分勧告を行うことができます。
審査会は人事院総裁が任命する5人の委員で構成され、弁護士、大学教授、民間企業の経営者など外部有識者が中心となっています。
各省庁の倫理監督官制度
各府省には「倫理監督官」と「倫理管理監督官」が配置されています。倫理監督官は通常、官房長や局長クラスが担当し、所属職員の倫理保持に関する指導・監督を行います。
職員からの相談窓口としての機能も持ち、「この行為は倫理規程に違反するか」といった日常的な疑問に答える体制が整っています。
報告・公開制度
幹部職員(本省の課長級以上など)は、毎年、株式や不動産などの資産、兼業の状況を記載した「資産等報告書」を提出しなければなりません。また、一定額以上の利害関係者との飲食については「贈与等報告書」の提出が義務付けられています。
これらの報告書は透明性確保のため、一部が公開される仕組みになっています。
公務員を目指す方・現職の方へのアドバイス
国家公務員倫理法と倫理規程を正しく理解し、日々の業務で実践することが重要です。
「グレーゾーン」への対処法
実務では、明確に白黒がつけられない「グレーゾーン」に遭遇することがあります。たとえば、「この企業は利害関係者に当たるのか」「この金額は報告義務があるのか」といった疑問です。
こうした場合は、自己判断せず必ず倫理監督官や人事担当者に相談することをお勧めします。「これくらいなら大丈夫だろう」という甘い判断が、後に重大な問題となった事例は数多くあります。
民間企業側が知っておくべきこと
公務員と接する機会のある民間企業の方も、倫理法・倫理規程の内容を理解しておくことが重要です。善意で行った接待や贈答が、相手方の公務員を処分の対象としてしまう可能性があります。
特に、以下の点に注意が必要です:
- 1万円を超える飲食接待は避ける
- お中元・お歳暮などの贈答を控える
- ゴルフや旅行などへの誘いは慎重に判断する
- 費用負担が明確な形での会食を心がける
倫理観を高めるための日常的な心がけ
形式的なルール遵守だけでなく、公務員としての使命感と倫理観を持つことが根本的に重要です。「国民全体の奉仕者である」という自覚を常に持ち、自分の行動が国民からどう見えるかを意識することが求められます。
各府省では定期的に倫理研修が実施されています。こうした機会を活用し、継続的に倫理意識を高める努力が大切です。
まとめ
国家公務員倫理法と国家公務員倫理規程は、公務の公正性と透明性を確保し、国民の信頼を守るための重要な法制度です。利害関係者との金銭・物品の授受、高額な飲食接待、不動産取引などが具体的に禁止され、違反した場合は懲戒処分や刑事罰の対象となります。
過去の違反事例を見ると、「これくらいなら問題ない」という安易な判断が重大な結果を招いています。グレーゾーンに直面した際は、必ず倫理監督官や人事担当者に相談することが重要です。
公務員を目指す方は、試験合格だけでなく、高い倫理観を持つことが求められています。また、現職の方は日々の業務において倫理法・倫理規程を意識し、国民の信頼に応える行動を心がけましょう。
今後のキャリアに倫理的な判断力を活かすため、定期的に倫理研修を受講し、最新の事例や解釈を学び続けることをお勧めします。