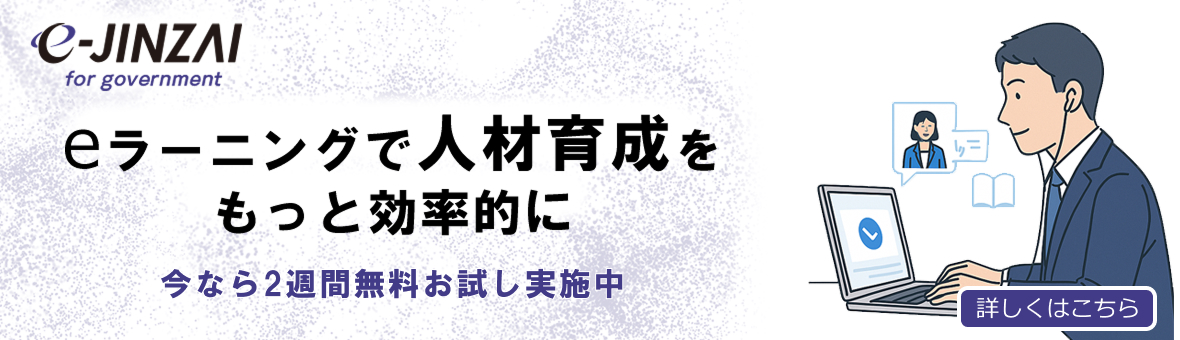国家公務員と地方公務員の退職金制度を徹底比較

KEYWORDS 公務員
退職金の仕組みを正しく理解していますか?
公務員として長年働いてきた皆さん、あるいはこれから公務員を目指す方々にとって、退職金は将来設計における重要な要素です。しかし、国家公務員と地方公務員では制度に違いがあるのをご存知でしょうか?
退職手当の計算方法は一見複雑に見えますが、基本的な構造を理解すれば、自分がどれくらいの退職金を受け取れるのか予測することができます。この記事では、国家公務員退職手当法と地方自治法に基づく退職手当制度を、具体的な計算例を交えながら詳しく解説していきます。
特に、定年退職、早期退職募集制度、自己都合退職など、退職理由によって大きく異なる支給額について、実際の数字を用いてシミュレーションしていきます。退職後の生活設計を立てる上で、この情報は必ず役立つはずです。
目次
- 退職金の仕組みを正しく理解していますか?
- 国家公務員と地方公務員の退職手当制度の法的根拠
- 退職手当の基本的な計算構造
- 退職理由別・勤続年数別の支給率詳細
- 国家公務員と地方公務員の退職金の実態比較
- 退職手当に関する税金と手取額
- 退職後の生活設計と退職手当の活用
- まとめ:退職手当制度の理解が未来を拓く
⇒自治体向けにカスタマイズされたe-ラーニング研修動画はこちら
国家公務員と地方公務員の退職手当制度の法的根拠
国家公務員の退職手当制度
国家公務員の退職手当は、昭和28年に制定された「国家公務員退職手当法」によって規定されています。この法律は、国家公務員が退職する際に受け取る手当の基準を明確に定めており、全ての国家公務員に適用されます。
退職手当制度の目的は、長年にわたる勤務への報償と、退職後の生活の安定を図ることにあります。平成30年には制度改正が行われ、現在の支給率が適用されています。
地方公務員の退職手当制度の特徴
地方公務員の退職手当については、地方自治法の規定により、各地方公共団体が条例で定めることとされています。つまり、基本的には各自治体が独自に決定する仕組みです。
多くの自治体が国家公務員退職手当法の枠組みを参考に条例を作っています。そのため、総務省では国家公務員退職手当法に準じた「職員の退職手当に関する条例案」を作成し、各地方公共団体に示しています。
実際には、ほとんどの地方公共団体がこの条例案に従っており、国家公務員と地方公務員の退職手当制度は基本的に同じ構造となっています。ただし、企業職員や単純労務職員については別の扱いとなり、団体交渉の対象として給与や退職手当が決定されます。
退職手当の基本的な計算構造
退職手当額の算定式
退職手当の計算は、次の基本式に基づいて行われます。
退職手当額 = 基本額 + 調整額
さらに、それぞれの要素は以下のように計算されます。
基本額 = 退職手当算定基礎となる給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率
勤続年数や退職理由に応じた支給率が適用されます。
調整額
調整額は、過去の給与変動や物価変動に応じた補正として加算されます。上限は60月分までとされています。具体的な計算方法は国家公務員法と地方自治体の条例により異なる場合があります。
この構造は国家公務員・地方公務員ともに基本的に共通しており、要素ごとに分けて理解することで、自分の退職手当を概算することが可能です。
退職金計算における主要要素
| 計算要素 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 退職日の給料月額 | 退職日における俸給月額 | 扶養手当、地域手当等は含まれない場合がある |
| 支給率 | 退職理由と勤続年数で決定 | 定年退職が最も高率 |
| 調整額 | 在職中の職責に応じた加算 | 管理職等の期間が影響 |
給料月額とは何か
給料月額とは、退職日における俸給月額のことを指します。国家公務員の場合、基本給である俸給が基準となり、原則として扶養手当や地域手当などの諸手当は含まれません。
ただし、定年が61歳から65歳に段階的に引き上げられる措置に伴い、60歳以降は俸給月額が70%に調整されるため、退職日の実際の俸給月額と退職手当計算の基礎となる月額が異なる場合があります。この点は退職手当を計算する上で重要なポイントです。
調整額の仕組み
調整額は、在職期間中の職務の複雑さや責任の度合いを反映させるための制度です。具体的には、在職中の各月ごとに「調整月額」が設定されており、その中で額が大きいものから60月分を合計した金額が調整額となります。
管理職として長期間勤務した場合や、より高い級で勤務した期間が長い場合、調整額が増加します。この制度により、単に勤続年数だけでなく、どのような職務を担ってきたかも退職手当に反映される仕組みとなっています。
退職理由別・勤続年数別の支給率詳細
退職手当の支給率は、退職理由と勤続年数によって大きく異なります。ここでは主な退職理由ごとの支給率を詳しく見ていきましょう。
退職理由による支給率の違い
退職理由は主に以下の3つに区分されます。
- 定年退職・勧奨退職:最も支給率が高い
- 整理退職:組織改編等による退職
- 自己都合退職:本人の意思による退職
国家公務員と地方公務員の退職金の実態比較
制度の共通点
前述の通り、地方公務員の退職手当制度は国家公務員に準じているため、基本的な計算構造は同じです。支給率や調整額の考え方も共通しており、勤続年数と退職理由が同じであれば、ほぼ同額の退職手当が支給されます。
地方公共団体による違い
ただし、地方公共団体によっては、独自の加算措置や特例を設けている場合があります。例えば、財政状況が良好な自治体では、条例案を上回る支給率を設定しているケースもあります。
逆に、財政状況が厳しい自治体では、退職手当の支給率を一時的に引き下げる措置が取られることもあります。自分が所属する自治体の条例を確認することが重要です。
企業職員・単純労務職員の特例
地方公営企業法が適用される企業職員や、地方公務員法第57条に規定される単純労務職員については、退職手当を含む給与条件が団体交渉の対象となります。
これらの職員の退職手当は、一般の地方公務員とは異なる基準で決定される場合があります。地方公営企業法第38条では、給与の種類及び基準は条例で定めるとされていますが、具体的な額は労使交渉によって決まります。
そのため、同じ自治体内でも、一般職員と企業職員・単純労務職員では退職手当の額が異なることがあります。
退職手当に関する税金と手取額
退職所得控除の仕組み
退職手当には、退職所得控除という税制上の優遇措置があります。勤続年数に応じて控除額が設定されており、多くの場合、退職手当の大部分が非課税となります。
退職所得控除額の計算
勤続年数38年の場合(例):退職所得控除額=800万円+70万円×(38−20)
38 − 20 = 18
70万円 × 18 = 1,260万円
800万円 + 1,260万円 = 2,060万円
退職所得の計算
退職所得は次の式で計算されます。
退職所得 =(退職手当額-退職所得控除額)×1/2
前述のケース1(退職手当2,035万円、勤続38年)の場合:
- 退職所得控除額:2,060万円
- 課税対象額:2,035万円-2,060万円=0円(マイナスは0とする)
このケースでは、退職手当が全額非課税となります。
手取額のシミュレーション
退職手当の手取額は、所得税・復興特別所得税・住民税を差し引いた金額となります。ただし、退職所得控除が大きいため、多くの公務員の場合、税負担は比較的軽くなります。
仮に課税対象となる退職所得が発生した場合でも、給与所得と異なり1/2課税の優遇措置があるため、税率は低く抑えられます。
人事院のホームページでは、退職手当手取額計算書のシミュレーションツールが提供されており、具体的な手取額を確認することができます。
退職後の生活設計と退職手当の活用

退職後の収入と支出のバランス
退職後は、公的年金が主な収入源となります。しかし、年金の受給開始まで期間がある場合や、年金だけでは生活費が不足する場合、退職手当が重要な役割を果たします。
総務省の統計によれば、定年退職後の生活費は月額約25万円~30万円程度が平均とされています。一方、公的年金の平均受給額は月額約15万円~20万円程度です。この差額をどのように補うかが、退職後の生活設計の鍵となります。
退職手当の賢い使い方
退職手当は一時金として支給されるため、計画的な活用が求められます。以下のような使途が考えられます。
1. 生活予備費として確保 退職後の生活費不足に備えて、一定額を預貯金として確保します。目安としては、生活費の2~3年分程度を流動性の高い資産として保有することが推奨されます。
2. 住宅ローンの繰上返済 住宅ローンが残っている場合、退職手当で完済することで、退職後の固定支出を大幅に削減できます。ただし、手元資金とのバランスを考慮する必要があります。
3. 資産運用 すぐに必要としない資金は、適切なリスク管理のもとで運用することも選択肢です。ただし、退職金を狙った詐欺や高リスク商品への勧誘には十分注意が必要です。
4. 介護・医療費への備え 将来の介護や医療費に備えて、一定額を確保しておくことも重要です。公的な介護保険制度がありますが、自己負担分や介護保険の対象外となるサービスもあります。
退職金の活用方法と推奨割合
| 活用方法 | 推奨割合 | 優先度 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 生活予備費 | 30–40% | 高 | 流動性の高い預貯金で確保。住宅ローン返済状況に応じて調整。 |
| 資産運用 | 20–30% | 中 | 高金利環境に注意し、リスク管理を徹底。 |
| 介護・医療費積立 | 10–20% | 中 | 将来を見据え、長期的な視点で確保。 |
| その他(趣味等) | 10–20% | 低 | 生活の質の維持を意識し、無理のない範囲で。 |
まとめ:退職手当制度の理解が未来を拓く
国家公務員と地方公務員の退職手当制度は、長年の勤務に対する報償であり、退職後の生活を支える重要な基盤です。制度の基本構造である「基本額+調整額」という計算式は、一見複雑ですが、退職日の給料月額、勤続年数、退職理由という3つの要素で決まります。
特に重要なポイントは、退職理由によって支給率が大きく異なることです。定年退職の場合、勤続35年以上で59.28月分と給料月額の約5年分が支給される一方、自己都合退職では47.5月分と約1年分の差が生じます。この違いを理解した上で、キャリアプランを考えることが大切です。
今日から、あなたも自分の退職手当がいくらになるのか、計算してみませんか?そして、職場での研修実施を提案してみることも検討してください。将来への備えは、早ければ早いほど選択肢が広がります。あなたの充実した退職後の生活のために、今できることから始めましょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。