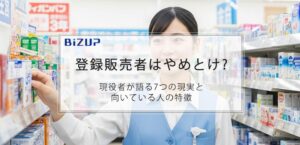学修成果を可視化する大学改革──教育の質を高める新しい視点

KEYWORDS 大学
いま、全国の大学で「学修成果の可視化」が急速に進められています。背景には、文部科学省が示した「教学マネジメント指針」による教育の質保証の流れがあります。学生の学びをいかに把握し、大学としてどう説明し、どのように改善へつなげるか——これは教育現場の最前線に立つ教職員にとって避けて通れないテーマです。
しかし実際には、学修成果の測定やデータの可視化が進んでも、それを教育改善に活かしきれていない大学が少なくありません。数値を集めること自体が目的化し、現場の教員や職員が「なぜ可視化が必要なのか」を共有できていないケースも見られます。
この課題を整理し、体系的に理解する手段として注目されているのが、愛媛大学の中井俊樹教授が監修したeラーニング講座「学修成果の把握と可視化」です。本記事では、講座の内容をもとに、学修成果の可視化が求められる理由と、大学が実践できる改善の方向性を整理します。


“いま”全大学に求められる学修成果の把握と可視化
動画数|4本 総再生時間|101分
本研修では、学修成果の把握と可視化を基礎から実践まで学び、教学マネジメント確立に必要な評価方法と、教育改善へ活かす実践力を身につけます。
動画の試聴はこちら目次
- なぜ「学修成果の可視化」が必要なのか
- 3つのレベルで見る学修成果の把握と可視化
- 学修成果の可視化から「活用」へ
- ハード面とソフト面の両輪で進める改善
- データを意味ある情報に変える
- 改善サイクル(PDCA)を動かす仕掛け
- eラーニングで体系的に学ぶ「学修成果の把握と可視化」
- まとめ
なぜ「学修成果の可視化」が必要なのか
政策と質保証の転換
これまで日本の大学は、入試選抜や設置基準などの「事前規制」で教育の質を確保してきました。しかし、グローバル化や学習者の多様化により、こうした仕組みだけでは教育の成果を十分に説明できなくなっています。
そこで注目されているのが「教学マネジメント」という考え方です。大学が自らの教育目的を達成するために、学修成果を把握し、改善へとつなげる体制を整えることが求められています。つまり「学修成果の可視化」は、大学が社会に対して説明責任を果たすだけでなく、教育の質を自律的に高めるための手段なのです。
大学現場の実情と課題
とはいえ、現場では次のような課題が目立ちます。
- データを収集しても活用につながらない
- 教職員間で目的意識が共有されない
- 成果測定が「目的化」し、教育改善に反映されない
学修成果の把握と可視化はゴールではなくスタートです。重要なのは、「何を測るか」よりも「測った結果をどう活かすか」。この視点を共有できるかどうかが、質保証の成否を分けます。
3つのレベルで見る学修成果の把握と可視化
学修成果の可視化は、一律の方法では機能しません。大学全体、学位プログラム、授業科目という3つのレベルを明確に分け、それぞれに合った方法で行うことが効果的です。
大学全体レベル
大学全体では、教育理念に基づく共通の学修成果指標を設定し、全学的な内部質保証体制を整備することが重要です。例えば、全学共通DP(ディプロマ・ポリシー)や共通教育の成果調査など、学修成果を一貫した視点で確認する仕組みを整えることが、大学の説明責任を支えます。
学位プログラムレベル
学位プログラムでは、卒業認定・学位授与の方針に基づき、学生がどのような資質・能力を身につけたかを多面的に評価します。成績評価だけでなく、修業年限内卒業率、満足度、外部試験スコア、進路決定率、卒業論文の質などを総合的に見ていくことが必要です。
授業科目レベル
授業科目のレベルでは、各授業の到達目標を明確にし、その達成度を根拠に基づいて評価します。評価方法や基準を明示することで、学生にとっても「何ができるようになったか」を実感しやすくなり、授業改善にも直結します。


“いま”全大学に求められる学修成果の把握と可視化
動画数|4本 総再生時間|101分
本研修では、学修成果の把握と可視化を基礎から実践まで学び、教学マネジメント確立に必要な評価方法と、教育改善へ活かす実践力を身につけます。
動画の試聴はこちら学修成果の可視化から「活用」へ
学修成果の可視化が整っても、教育改善へつながらなければ意味がありません。
多くの大学では、成果データを「報告書」で止めてしまい、学内での共有や具体的な改善にまで至らないことがあります。真に機能する教学マネジメントを実現するためには、「把握」と「分析」だけでなく、“活用”の設計が欠かせません。
たとえば、学修成果データを学生本人にフィードバックすれば、自己評価や目標設定のきっかけになります。授業担当者が共有すれば、教育内容や評価基準の見直しに役立ちます。そして大学全体で分析すれば、学位プログラムやカリキュラムの再設計へと発展します。
重要なのは、成果データを“数値”としてではなく、“学びを深める情報”として扱う視点です。
ハード面とソフト面の両輪で進める改善
学修成果の可視化を継続的に機能させるには、制度設計(ハード面)と人の意識(ソフト面)の両方が欠かせません。
| 側面 | 主な取り組み内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| ハード面 |
・制度・規程の整備 ・評価手順やアセスメントプランの策定 ・情報共有システムの導入 |
運用の仕組みを確立し、継続的な質保証を支える |
| ソフト面 |
・教職員の意識改革と共通理解の醸成 ・成果データの活用力向上 ・学修成果を共有する文化の形成 |
改善を現場で支え、組織文化として根付かせる |
学修成果の可視化を持続的に機能させるには、制度やツールの整備だけでは不十分です。たとえば、アセスメントプランを策定しても、それを使いこなす力や、成果を教育改善につなげる意識が組織内に育たなければ、実質的な変化は起こりません。
ハード面は仕組みを「見える形」に整えるための基盤であり、ソフト面はそれを「生かす力」を育てる要素です。
両者が相互に機能することで、学修成果の分析や共有がスムーズになり、意思決定や教育改革のスピードが格段に上がります。
特に、データを扱う職員と授業を担当する教員の連携が進むと、学修成果の情報が「評価のため」から「教育の改善のため」に転換され、学びの質を底上げする循環が生まれます。
データを意味ある情報に変える
多くの大学では、アンケート結果や成績統計などの「データ」は大量に存在しています。
しかし、それらをただ提示するだけでは教育改善の材料にはなりません。データには「意味づけ」を与える必要があります。
具体的には、
- 過去との比較:年次推移で改善度を可視化
- 他学部・他大学との比較:相対的な位置を把握
- 基準との照合:大学が定めた水準を基準にする
こうした比較・基準の設定によって、データは単なる数字ではなく、判断と行動を導く情報に変わります。
また、成果データを可視化するツールとして、レーダーチャートやカリキュラムマップを活用する大学も増えています。学生は自分の成長を視覚的に把握でき、教職員は教育内容の偏りや改善点を一目で確認できます。
改善サイクル(PDCA)を動かす仕掛け
| 段階 | 主な活動 | 目的 |
|---|---|---|
| Plan(計画) | 学修成果指標の設定、方針策定 | 評価の目的を明確化 |
| Do(実施) | 授業・学位プログラムの運用 | 教育活動の実施 |
| Check(評価) | 成果データの分析・可視化 | 現状を把握し課題を抽出 |
| Act(改善) | 教育内容・支援体制の見直し | 教育の質を継続的に向上 |
学修成果の可視化の目的は、データの「収集」ではなく「循環」にあります。
Plan(計画)→Do(実施)→Check(評価)→Act(改善)のサイクルを回し続けることで、教育の質は徐々に高まります。
このとき注意すべきは、「改善は毎年大きく変えるものではない」という点です。カリキュラムやDP(ディプロマ・ポリシー)の効果を確認できるのは、数年単位の長期的な視点が必要です。授業科目レベルでは短いスパンで改善し、学位プログラムや大学全体では中期的に見直す——この異なるスピード感を意識した運用が求められます。
さらに、成果を共有する場を設けることも大切です。単なる報告ではなく、「次に何を変えるか」「どんな支援が必要か」を対話する機会をつくることで、学修成果のデータが教育現場の改善力に変わります。
eラーニングで体系的に学ぶ「学修成果の把握と可視化」

学修成果の可視化は、単にツールを導入すれば完結するものではありません。
必要なのは、教育目的・評価基準・組織運営を総合的に理解することです。そこで近年注目されているのが、eラーニングによる体系的な学びです。
eラーニング講座では、
- 学修成果の可視化の意義
- 3つのレベルでの把握方法
- 成果データの活用とフィードバック
- ハード・ソフト両面からの改善手法
などを体系的に学べます。オンデマンド形式のため、業務の合間にも受講でき、全国どこからでも最新の知見を得ることが可能です。大学教職員にとっては、実務に直結する研修として活用しやすい点が大きな魅力です。
まとめ
学修成果の把握と可視化は、大学教育の質を高めるための「出発点」です。
重要なのは、数値を並べることではなく、その結果をどのように教育改善へとつなげるか。制度(ハード)と意識(ソフト)の両面から仕組みを整え、成果を学生・教職員・大学全体の成長に結びつけていくことが求められます。
まずは、自大学の学修成果の現状を点検し、どのように可視化・活用できるかを考えることから始めてみましょう。そして、eラーニングを通じて基礎から体系的に学ぶことで、教育の質保証を自らの手で進める力が育ちます。