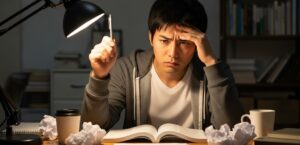ロジハラ(ロジカルハラスメント)とは?背景と取り組むべき防止策を解説

KEYWORDS ハラスメント
「正しいことを言っているだけなのに、なぜか相手が傷つく」「論理的に説明しても納得してもらえない」。
そんな職場のすれ違いから生まれる新しい問題が、ロジカルハラスメント(ロジハラ)です。
ロジハラは、論理的思考が行き過ぎて人を追い詰めてしまう行為。パワハラやモラハラと異なり、「正論」であるために気づかれにくく、企業にとっても見過ごされがちな課題です。
本記事では、ロジハラの特徴と心理背景、そして企業・組織として何ができるのかを解説します。
目次
ロジカルハラスメント(ロジハラ)とは

ロジハラという言葉は近年注目を集めていますが、その本質を正確に理解している人は少なくありません。ここでは、ロジハラの定義と、その行為がどのように職場で起こりやすいのかを整理します。
ロジハラの定義と特徴
ロジハラとは、論理的な言葉や正論を使って相手を精神的に追い詰める行為です。「理屈では正しい」ことを盾に、相手の感情や立場を軽視することで、心理的な圧力を与えてしまいます。問題なのは、加害者自身が「自分は正しい」と信じているため、ハラスメントの意識を持ちにくいことです。
たとえば、「感情的にならず事実で話して」「説明が筋通っていない」といった発言。一見正論のようでいて、相手の意見を封じ込める言葉として働くことがあります。このような発言が続くと、部下や同僚は発言を控えるようになり、チームの活力が失われていきます。
職場で起こりやすい構造
ロジハラは、上司から部下への一方向的なコミュニケーションの中で起こりやすいものです。とくに成果や効率を重視する職場では、「感情を持ち込むな」という無意識のプレッシャーが強く、感情表現そのものが“非論理的なもの”として排除されがちです。この構造が積み重なることで、正しさの押しつけが組織文化として固定化していくのです。
なぜロジハラが増えているのか
ロジハラが増加傾向にあるのは、単なる偶然ではありません。社会構造や働き方の変化、そしてコミュニケーションの質的転換がその背景にあります。
成果主義と合理化の時代
現代の企業では「結果がすべて」という成果主義が広がり、合理的に説明できる人が評価されやすくなりました。この文化は一方で、「論理的であることが正義」という考えを生み出しています。上司が部下にミスを指摘するときも、「事実に基づいたフィードバック」として、厳しい言葉を正当化しがちです。
しかし、職場は人と人が協働する場です。論理だけでなく、相手の感情や状況を汲むことが欠かせません。成果主義が進むほどに、この“人間的な部分”が軽視されやすくなり、ロジハラを生む下地が整ってしまうのです。
テレワークとデジタル化によるコミュニケーションの変化
もうひとつの要因が、テレワークやオンラインコミュニケーションの定着です。非対面でのやり取りでは、声のトーンや表情といった非言語的な情報が欠けます。メールやチャットでは文面が冷たく見えやすく、意図せず相手を傷つけるケースが増えています。
また、SNS文化の影響も見逃せません。短く鋭い意見が評価される社会では、「論破」や「正論」が美徳のように扱われ、その価値観が職場にも持ち込まれています。このような背景の積み重ねが、論理を武器にしてしまう環境を生み出しているのです。
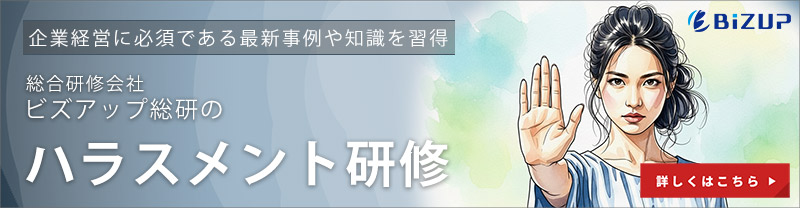
被害者・加害者双方に起こる心理メカニズム
ロジハラを理解するうえで重要なのは、「誰もが加害者にも被害者にもなり得る」という点です。お互いの立場でどのような心理が働くのかを見ていきましょう。
被害者の心理
ロジハラを受けた人は、「相手の言うことは間違っていない」と感じやすく、反論することを諦めてしまいます。理屈では正しいが、自分の感情が否定されたように感じ、徐々に自己肯定感を失っていくのです。「自分が悪いのかもしれない」「非論理的なのは自分だ」と思い込み、発言や提案を避けるようになります。結果として、職場での発信力を失い、孤立感や疲弊を深めていくケースが多いのです。
加害者の心理
一方で加害者は、自分の発言を「指導」や「改善のため」と信じています。多くの場合、悪意ではなく使命感からくる行動です。特に成果プレッシャーが強いリーダー層ほど、「論理的でなければ成果が出ない」と考え、相手の感情よりも結果を優先してしまいます。
このすれ違いは、どちらかが悪いという問題ではありません。
「正しさ」と「やさしさ」のバランスをどう取るか――
そこに気づくことこそが、ロジハラ防止の第一歩となります。
組織が今すぐ取り組むべきアクション

ロジハラの防止を掲げても、理念だけでは現場は変わりません。ここでは、企業が今日から実行できる具体的なアクションを紹介します。
1. 社内でロジハラの定義を共有する
まずは、「ロジハラとは何か」を明文化し、社内に共有すること。指導とハラスメントの境界を言語化することで、誤解やグレーゾーンを減らします。例えば、「相手の意見を一方的に論破する」「感情を無視した指摘を繰り返す」といった行為を具体例として示すと、認識がそろいやすくなります。
2. コミュニケーション研修の導入
次に、管理職・若手社員を問わず「伝え方」「受け止め方」を学ぶ研修を取り入れることです。ロジハラは意識の問題であり、スキルの問題でもあります。研修では、ロールプレイやケーススタディを通じて、相手の気持ちを汲み取る対話スキルを磨きます。
また、ハラスメントの知識を得るだけでなく、感情を尊重したコミュニケーションの実践がポイントです。研修後には参加者同士の対話会や定期的なフィードバックを行い、学んだ内容を職場に定着させましょう。
⇒ 社内のコミュニケーションを強化する|コミュニケーション研修
3. 対話の文化を根づかせる
会議や1on1での発言機会を均等に設け、「意見を出しても大丈夫」という心理的安全性を高めます。また、部下のミスや感情的な反応をすぐに否定せず、「何がそう感じさせたのか」を尋ねる姿勢を持つことが重要です。対話が積み重なることで、論理と感情がバランスを取り戻します。
4. データをもとに改善を継続する
ストレスチェックやエンゲージメント調査などを活用し、組織の健康状態を可視化します。ロジハラが起きやすい部署やタイミングをデータで把握し、早期に対応することで被害を防げます。
ロジハラを防ぐための文化づくり
ロジカルハラスメントを防ぐ最も確実な方法は、「正しさよりも信頼を優先する文化」をつくることです。論理は人を導く力を持ちますが、信頼がなければ、それはただの圧力にしかなりません。
意見が異なるときこそ、「相手の意図を理解しようとする」姿勢が問われます。ロジハラを防ぐ組織は、単にハラスメントをなくすだけでなく、人が安心して意見を交わせる創造的な職場を実現します。
まとめ
ロジカルハラスメントは、“正しさ”の裏に潜む新しい職場課題です。背景には成果主義やリモートワーク、SNS文化など、現代社会の構造的要因があります。
企業が取るべきは、教育・制度・文化の三位一体での取り組みです。特に、ハラスメントを理解し、対話力を育む研修は効果的な第一歩です。
論理を磨くだけでなく、人を尊重しながら伝える力を養うこと。それこそが、ロジハラのない健全で強い組織をつくる鍵となります。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。