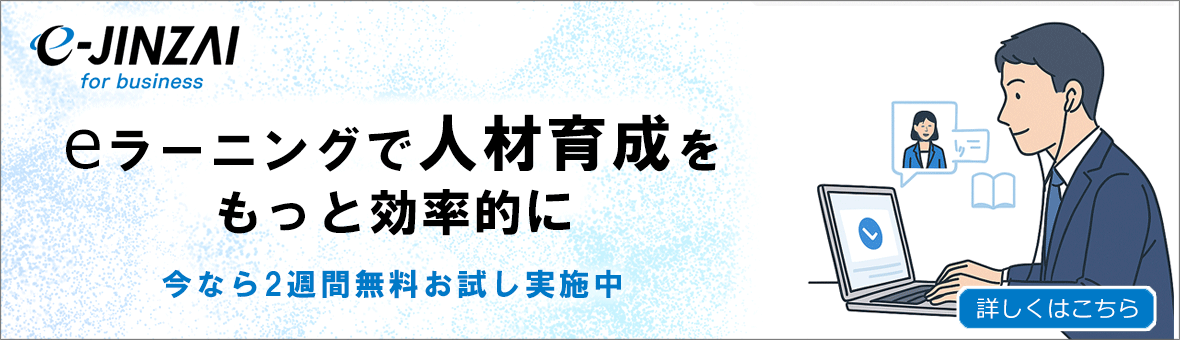派遣元責任者になるには?選任の要件や職務の役割・講習について解説!

人材派遣業務の分野では「派遣元責任者」と呼ばれる資格が必要です。
派遣元責任者とは、特定の要件を満たしていることと、厚生労働省が制定する講習機関によって実施される講習、「派遣元責任者講習」修了者が取得できます。本記事では、派遣元責任者の資格についての特集です。実際の資格取得のための要件、派遣元責任者のおもな職務内容、派遣元責任者講習受講に関する流れを解説します。
現在人材派遣での会社設立を考えている人や、派遣元責任者になるにはどうすればいいのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
⇒ 派遣法について学ぶなら自己研鑽『労務』研修 | e-JINZAI for Business
目次
派遣元責任者とは?

派遣元責任者とは、派遣労働者に関する雇用管理・保護をする責任者のことです。派遣元事業主である派遣会社から選任され、配置する義務が発生します。
では、さらに詳しく解説していきましょう。
派遣元責任者の概要
派遣先責任者とは、派遣先企業によって、自社に所属する派遣社員の就業管理を担う責任者を指します。派遣した社員が勤務先で安心・安全に仕事ができるために、雇用管理と安全衛生管理をおこなうための責任者です。
また、派遣先企業との、さまざまな連絡調整なども業務の一環としています。
派遣先責任者の役割はおもに以下のような概要です。
- 労働者派遣契約の遵守状況確認
- 労働関係法令や労働者派遣契約の内容の周知
- 派遣の受け入れ期間の管理
- 派遣先管理台帳の作成・記録・保存・通知
- 派遣社員からの苦情受理と対応
- 派遣先での均衡待遇の確保の管理
- 安全衛生管理
- 教育訓練実施
派遣元責任者の配置は義務
派遣元責任者には、自社所属の派遣社員から万が一苦情を受けた場合の対応、派遣先との連絡調整、派遣元管理台帳作成と管理などが職務として義務化されています。
派遣法や労働基準法にて業務上の留意点などを理解し、一定の要件を満たした人物を選任するよう定められた資格です。
要件の中には、「派遣社員数100人ごとに1人以上の配置」など含めた12項目があります。また、派遣元責任者になるのは、「派遣元責任者講習受講後3年以内」という規定もあり、必ず遂行することになっているものです。
派遣元責任者を配置する理由
派遣元責任者の配置は、派遣元企業・派遣先企業・派遣労働者の3者の関係性が、円滑に進展するために重要な役割を持っています。
派遣元責任者を配置する理由は、おもに以下のとおりです。
法令遵守のため
現在の人材派遣とは、労働者派遣法に基づいてルール化されています。派遣元企業は派遣先企業に対して責任を負う必要があり、派遣元責任者は法令を遵守するための監督的な役割を担うからです。
自社から派遣させた労働者の就業状況・契約内容を確認し管理し続ける義務があります。
派遣労働者の安全・健康管理のため
派遣労働者が適切な職場環境で働けるように、健康面と安全面の管理が必要だからです。
派遣労働者が、不適切な環境に派遣されて労働を強いられないように、管理する業務とされています。
派遣労働者の指導・支援のため
派遣労働者が派遣先でスムーズに業務をこなせるための指導の実施や、万が一の問題に対するサポートをするのに必要だからです。
労働条件や待遇に関する問題が発生した場合も、適切な対応をすることになるでしょう。
契約の適正管理のため
派遣契約内容が、法律に基づきながら適正に実施していることを確認する業務です。
派遣元企業・派遣先企業、派遣労働者の3者間で、トラブルが発生しないように未然に防ぐためにも有資格者を選出します。
労働環境の向上のため
派遣元責任者は、派遣労働者が働きやすい環境で業務ができるように、労働環境の改善を目指す必要性があるからです。
派遣元事業者としての要件
派遣元事業者になるには、労働者派遣事業の許可申請が不可欠です。さらに、派遣元事業者は、一定の要件を満たした人物から選任するように義務付けられています。
では、派遣元責任者になるには、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
労働者派遣事業の許可要件
派遣元事業者になるには、大元である労働者派遣事業の許可を受けることから始まります。
その際には、以下の許可要件をクリアしなければなりません。
- 欠格事由に該当しない
- 専ら派遣を目的としない
欠格事由とは、禁錮以上の実刑、あるいは一定の労働法等に違反して罰金刑以上に処せられ、5年を経過しない状態です。
具体的には、最近目立つのが、不法就労の外国人雇用です。この場合、罪に問われてから5年を経過していない状況では認められません。
専ら派遣(もっぱらはけん)とは、派遣労働者を特定企業・複数社だけの限定で派遣する状態のことで、労働者派遣法で禁止されています。
事例としては、ある会社が出資した子会社が派遣事業をする場合、親会社にだけ派遣社員を送り込み、その他の会社には派遣をしないという体制は、法的に認められなくなったということです。
派遣元責任者の要件
2015年(平成27年)9月30日より、労働者派遣法の改正に伴って、派遣事業において特定派遣事業(届出制)および一般派遣事業(許可制)の区分がなくなり、全ての派遣事業は「許可制」となりました。
その際に、派遣の許可要件も変更となり、派遣元事業主及び派遣元責任者の配置は義務となっています。
派遣元責任者になるには、以下の要件のすべて満たさなければなりません。
- 3年以上の雇用管理経験があること
- 派遣元責任者講習を許可申請の受理日前に3年以内に受けていること
- 職務代行者を選任すること
- 労働者または役員で、派遣元責任者として業務に専念できること
上記の「雇用管理経験」とは、人事・労務担当者、支店長、工場長、労基法上の管理監督者としての評価に該当することで、それらに属した経験者です。
また、「職務代行者」とは、派遣元責任者不在時の代行として対応できる人物を指します。
派遣元責任者に選出される者の要件
その他にも、派遣元責任者としてふさわしい人物に該当する要件として、以下の内容も定められています。
- 住所及び居所が一定しないなどの生活根拠が不安定なものでないこと
- 適正な雇用管理をおこなう上で支障がない健康状態であること
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為をおこなうおそれのない者であること
- 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
- 外国人は、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること
- 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣をおこなうものであること
派遣元責任者のおもな仕事内容

ここでは、派遣元責任者が常におこなっている職務内容について解説していきます。
派遣労働者であることの明示
派遣元責任者は、派遣社員として雇用する人物へ、雇用契約書を明示する義務があります。
また、紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣である旨も明示しなくてはなりません。
就業条件などの明示
派遣労働者に対して、就業条件と派遣受入期間の制限に抵触することになる最初の日を通知することを指します。
派遣先への通知
派遣先企業へ、派遣労働者に関する氏名・性別・年齢などの事柄などの、個人情報を通知します。
派遣先および派遣労働者に対する派遣停止の通知
派遣受入期間の制限に抵触する場合、1ヶ月前から前日までに、派遣先企業と派遣労働者へ労働者派遣をおこなわない旨の通知をします。
派遣元管理台帳の作成、記録、保存
派遣労働者の氏名・派遣先の名称・派遣期間・就業時間といった法令で定められた事項を記録した「派遣元管理台帳」の作成をします。派遣元管理台帳は、派遣終了日から3年間保管が義務です。
フォーマットに規定はありませんが、項目が揃っていることが条件となっています。なお、台帳の媒体は、電子記録などでも可能です。
派遣労働者に対する助言や指導の実施
派遣元責任者は、派遣労働者に助言や指導をすることも業務の一つです。
その内容としては、以下のようなものが考えられます。
- 労働者派遣事業制度や労働者派遣契約の趣旨や内容
- 派遣会社や派遣先企業が講じるべき措置
仮に、労働者派遣法に改正があった場合、改正点の説明会や文書配布などで周知する義務も発生します。また、2021年1月の派遣法改正にて、キャリアアップ教育訓練とキャリアコンサルティング実施を説明する義務も追加されました。
派遣労働者からの苦情処理
もし、派遣労働者から派遣先などについて苦情を受けた際、派遣先企業への通知や適切な措置を実行する義務があります。
派遣先との連絡・調整
派遣就業に関するトラブルが生じた場合や、その他の諸事情などは、派遣先企業と連絡を交わして調整をしていく業務が発生します。
派遣労働者の個人情報の管理
派遣労働者の個人情報の管理をする業務です。不要な個人情報は破棄や訂正をして刷新します。
また、個人情報への不正アクセス防止のための管理が求められるでしょう。
派遣労働者への教育訓練実施と職業生活設計相談の機会
派遣労働者のキャリアアップの教育訓練は、年間で8時間・入職後3年間の実施義務があります。キャリアコンサルティングの窓口を設置し、希望によってはコンサルティングの実施も義務です。
キャリアアップ教育訓練は、毎年6月の事業報告書の提出をし、派遣許可更新時には訓練計画を提出します。キャリアアップ教育訓練は、段階的かつ体系的に実施しなくてはなりません。
安全衛生に関する業務
派遣労働者の安全衛生に関する管理業務もあります。
安全衛生教育の実施・健康診断・労災事故などが発生した際の対応と確認などです。
派遣元責任者講習とは
派遣元責任者になるには、派遣元責任者講習を受講することになります。労働者派遣事業を開始するにあたっても、派遣元責任者の選任のために受講する講習です。雇用管理能力や事務手続きなどの知識を習得する目的になっています。
では、派遣元責任者講習についてさらに解説していきましょう。
概要
派遣元責任者になるには、派遣元責任者講習を3年以内に受講することが要件です。講習は1日で終了します。
複数箇所の講習機関によって実施されていますが、その内容は厚生労働省による策定に準拠するため、大差はありません。
目的
派遣元責任者講習の目的は、派遣元事業所の雇用管理や事業運営の適正化にあります。労働者派遣法や派遣元責任者の職務、事務手続きなどのカリキュラムです。
対象者
講習の対象者は、派遣元責任者に選任されている人物・その予定の人物です。
その際は、派遣元責任者としての選任要件が設けられています。
ただし、講習そのものに受講要件はありません。例えば、労働者派遣事業の知識習得のための目的でも受講が可能です。
日程および申し込み方法
各講習機関のホームページの入力でおこなえます。
おもに東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・岡山・福岡などで実施され、派遣元事業所の住所地を問わず、どこの講習機関・会場でも受講が可能です。
東京の場合は、月20回〜30回前後(同日開催も含めて)実施されています。また、オンライン開催と対面式開催のいずれかの選択制です。
おもな講習内容
- 労働者派遣法や個人情報保護の取扱いに関する法令遵守
- 公正な採用選考の推進
- 労働基準法等の適用に関する特例
- 派遣元責任者の職務
- 事務手続きの内容
まとめ
労働者派遣法によって、派遣が適切におこなわれるための規定が設けられています。派遣元責任者・製造専門派遣元責任者の選任は、すべて法的な施策です。
派遣労働者による業務委託のためには、労働者派遣法に準じた派遣元会社、および派遣先企業として成立していなくてはなりません。これから派遣社員を目指す人は、派遣元責任者の存在に着目しておきましょう。
労務の知識を動画で学べるe-JINZAI for Business
組織のバックオフィス業務の中で、最も高い比率を占めるのが「労務」。そのフィールドは幅広く、労働に関する事務処理のみならず、ハラスメントやメンタルヘルス対応、労働トラブル対応なども含まれます。 ビズアップ総研の労務研修では、労働者派遣法を含む労務の基本的な知識、業務について学習した上で、労働に関する様々なリスクとその管理方法や予防策を動画でわかりやすく学ぶことができます。
2週間無料お試しはこちら