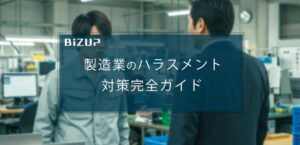医療データの力!病院経営にどう活かす?

病院経営において、データの活用は不可欠な要素となっており、患者数の推移や診療科ごとの稼働状況を分析することで、病院の経営戦略を最適化し、より質の高い医療を提供することが可能になります。また、地域医療機関との連携強化や患者満足度の向上にも、データの適切な活用が大きく貢献します。本記事では、病院経営におけるデータ活用の具体的なメリットや方法、成功のためのポイントについて詳しく解説します。
目次
医療データの活用が病院経営にもたらす影響

医療データ活用のメリット
病院がデータを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 診療の質の向上
患者の診療履歴や治療データを活用し、最適な治療方針を立案できる。 - 経営の効率化
診療の稼働率やベッド利用率を把握し、無駄のない病床管理が可能になる。 - 患者満足度の向上
患者の待ち時間や治療成績を分析し、サービスの向上につなげることができる。 - 地域連携の強化
紹介・逆紹介のデータを活用し、地域の医療機関との連携をスムーズに行う。 - マーケティング戦略の最適化
どの地域・年齢層からの患者が多いかを分析し、ターゲットを明確にする。 - 経営リスクの軽減
財務データや診療報酬の分析により、赤字部門の見直しやコスト削減が可能になる。
これらのメリットを最大限に活かすには、適切なデータ収集と分析が必要になります。
データ活用が求められる背景
医療機関がデータ活用を進める背景には、以下のような要因があります。
1.医療の高度化と専門分化
医療技術の進歩に伴い、より専門性の高い治療が求められるようになっています。しかし、病院単独で高度な医療を提供することは難しく、地域の医療機関との連携が不可欠です。データを活用することで、地域ごとの医療資源を最適に分配し、効率的な医療提供が実現できます。
2.地域完結型医療の推進
近年、医療提供体制は「地域完結型医療」へと移行しています。これは、急性期治療だけでなく、回復期・慢性期医療、在宅医療までを地域全体で担う仕組みです。データ活用により、患者の治療経過や退院後のフォローアップを一元管理し、適切な医療サービスを提供することが可能になります。
3.診療報酬制度の変化
日本の医療制度では、診療報酬が細かく設定されており、経営の収益構造に大きく影響を与えます。データを分析することで、どの診療科が収益性が高いのか、どの治療がコスト効率が良いのかを把握し、経営戦略の最適化が可能になるのです。
4.患者中心の医療の必要性
従来の医療は医師主導で治療方針が決定されることが一般的でしたが、現在では患者の意思を尊重し、共に治療方針を決める「患者中心の医療」が求められています。患者満足度調査やフィードバックデータを分析することで、医療サービスの質を向上させ、より良い治療環境を提供することが可能になります。
病院経営におけるデータ活用の具体例

地域連携の強化
病院が単独で患者を抱えるのではなく、診療所や介護施設との連携を深めることが経営の安定につながります。地域の医療機関とスムーズに連携するためには、紹介・逆紹介のデータを活用し、どの医療機関との関係を強化すべきか分析することが重要です。
例えば、紹介患者数の推移を分析し、特定の診療所からの紹介が減少している場合、その原因を探り、関係改善の施策を講じることができます。また、紹介元医療機関を「A・B・C」に分類するABC分析を行い、重点的に対応すべき医療機関を明確にすることも有効です。
患者の満足度向上
患者満足度を高めるためには、アンケート調査や診療データの分析が役立ちます。たとえば、患者がどの医療機関を選ぶかの要因を調査することで、どのような点を改善すべきかが明確になります。
患者は、治療成績だけでなく、医師や看護師の対応、施設の清潔さなども重視します。そのため、患者のフィードバックを定期的に収集し、データに基づいた改善策を講じることが必要です。
病院のマーケティング
病院経営にもマーケティングの概念を取り入れることが求められています。フィリップ・コトラーが定義する「マーケティング」とは、価値を創造し、提供し、交換することによって人々のニーズや欲求を満たす過程です。病院も、自院の強みを明確にし、ターゲットとする患者層に向けて適切な情報発信を行うことが重要です。
マーケティングのフレームワークである「4P(Product, Price, Place, Promotion)」を活用し、病院のサービス内容や価格設定、広報戦略を考えることで、より多くの患者に選ばれる病院を目指しましょう。
経営分析と改善
病院の経営状況を正確に把握し、課題を抽出するためには、SWOT分析が有効です。SWOT分析とは、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの視点から現状を分析する手法です。
例えば、自院の強みが「専門医の多さ」「高度医療機器の充実」である場合、それを活かした差別化戦略を立てることが可能です。一方で、「在宅医療部門が弱い」「特定分野の専門医が不足している」といった弱みがある場合は、外部の医療機関と連携することで補完する戦略が考えられます。
また、診療圏分析を行い、自院のシェアを把握することも重要です。どの地域からの患者が多いのか、競合医療機関の動向はどうかといったデータをもとに、ターゲットエリアを明確にし、重点的に広報や連携活動を行うことで、効率的な患者獲得につなげることができます。
e-JINZAIで学ぶ『地域医療』
深刻な少子高齢化が進む日本で今推し進められているのが、「地域医療」です。地域医療とは、地域全体で住民の健康をサポートする体制のことです。地域医療を実現するためには、医療機関を機能ごとに分化し、連携を推進することが重要であり、地域医療の実践には、医療機関が地域包括ケアシステムに参加することが必須です。 この研修では、地域医療の活性化に必要不可欠な地域医療連携や地域包括ケアシステムの構築などに関する取組みについて学びます。
詳細・お申し込みはこちらデータ活用のポイント
病院経営におけるデータ活用を効果的に進めるためには、単にデータを集めるだけでなく、そのデータを 適切に整理・分析し、経営判断に活かすことが重要です。ここでは、データ活用を成功させるためのポイントとして 「データの見える化と見せる化」、「長期的なデータ分析」 の2つの視点について詳しく解説します。
データの「見える化」と「見せる化」
データを適切に活用するためには、 「見える化」 と 「見せる化」 の両方を意識することが大切です。
「見える化」とは何か?
「見える化」とは、病院の経営状況や診療の実態を数値やグラフなどで分かりやすく可視化することを指します。データを整理し、視覚的に表現することで、現場スタッフや経営陣が問題点や改善点を直感的に把握できるようになります。
「見える化」の具体例
-
病床稼働率の可視化
病棟ごとの稼働率をリアルタイムでモニタリングし、ベッドの最適な運用を実現する。 -
紹介患者数の分析
紹介元ごとの患者数をグラフ化し、どの医療機関との関係を強化すべきか判断する。 -
平均在院日数のトラッキング
過去のデータと比較しながら、在院日数の傾向を分析し、退院支援の改善につなげる。
「見える化」によって、病院の課題を誰でも理解しやすい形で共有できるため、迅速な改善策の立案が可能になります。
「見せる化」とは何か?
「見える化」がデータを可視化することであるのに対し、「見せる化」はターゲットに応じた最適な伝え方を工夫することを意味します。病院経営においては、経営層、医師、看護師、事務スタッフなど、関係者ごとに必要な情報が異なるため、それぞれに適した形で情報を伝えることが重要です。
「見せる化」の具体例
-
経営層向け
診療報酬や病床利用率などの 経営指標 をまとめた報告書を作成し、意思決定を支援する。 -
医師向け
診療科別の患者数や診療時間のデータを分析し、医師の負担を軽減するための調整を行う。 -
看護師向け
患者満足度調査の結果を共有し、サービス向上のためのフィードバックを行う。
「見せる化」を工夫することで、単なるデータの羅列ではなく、意思決定につながる情報として活用できるようになります。
また、「見える化」と「見せる化」を組み合わせることで、データを実際のアクションにつなげることができます。例えば、病床稼働率のデータを「見える化」するだけでなく、経営層やスタッフ向けに 「なぜこの病棟の稼働率が低いのか?」 という分析を加えて「見せる化」することで、改善策の立案につなげることが可能になります。
長期的なデータ分析
病院経営では、短期的なデータだけでなく長期的なトレンドを把握することが重要です。過去のデータを蓄積し、傾向を分析することで、一時的な変動に左右されず、 経営の安定化や診療の最適化に役立ちます。
長期的なデータ分析のポイント
| 分析の視点 | 内容 | 活用例 |
| 季節変動の把握 | 時期ごとの患者数や疾患の傾向を分析 | 冬場のインフルエンザ流行に備えた診療枠の調整 |
| 診療科ごとの推移 | 各診療科の患者数や収益の変動を把握 | 診療体制や人員配置の最適化 |
| 収益とコストの管理 | 経営データを長期的に分析 | 高収益の診療科へリソースを集中 |
| 競合との比較 | 地域内の医療機関と診療動向を比較 | 病院の強みを活かした差別化戦略 |
長期的なデータ分析の手法
長期的なデータ分析を行うことで、経営の安定化やサービス向上につなげることができます。
- 移動平均の活用
- 12ヶ月移動平均を算出し、季節変動を除いたトレンドを把握する。 - 過去データとの比較
- 前年比や3〜5年単位の推移を分析し、経営の方向性を判断する。 - 異常値の分析
- 患者数や収益の急激な変化があれば、その要因を特定し対策を講じる。
まとめ
病院経営におけるデータ活用は、単なる数値管理ではなく、経営戦略の重要な要素です。地域連携の強化、患者満足度の向上、病院のマーケティング、経営分析など、さまざまな分野でデータを活用することが可能です。
今後、医療の質を維持しながら経営の効率化を図るためには、データの収集・分析・活用が不可欠です。病院経営者や現場のスタッフがデータを活かした意思決定を行うことで、より良い医療サービスを提供し、持続可能な経営を実現していきましょう。