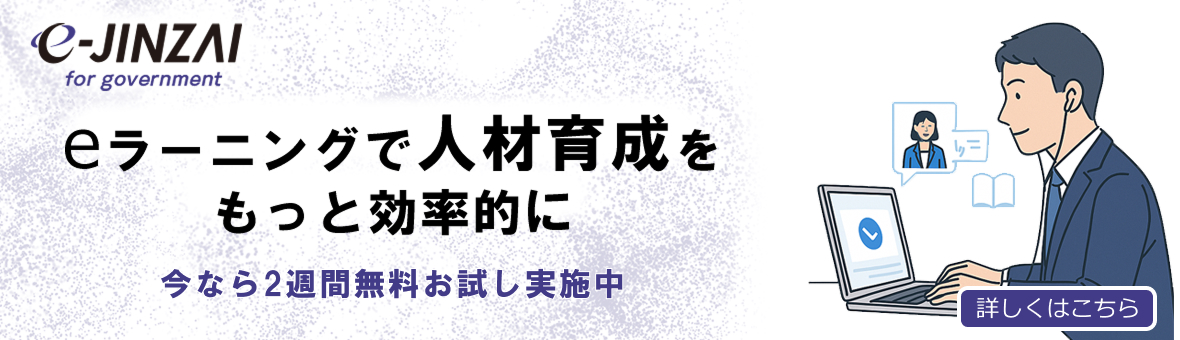「関係人口」とは?新しいまちづくりを促すシティプロモーション

KEYWORDS 自治体
地方における人口減少や少子高齢化が加速する中、地域経済の活性化は喫緊の課題となっています。観光誘致や移住促進といった従来の取り組みでは限界が見え始め、地域との関わり方に新たな発想が求められています。
こうした中で注目されているのが「関係人口」という考え方です。これは、観光客や移住者とは異なる形で地域に関与し続ける存在であり、地域の担い手として多様な形で貢献していくことが期待されています。
本記事では、関係人口をテーマに、地域が抱える課題、その解決に向けたシティプロモーションの再設計、さらに関係人口がもたらす地域経済への波及効果までを詳しく解説します。
⇒今、自治体に求められるスキルや地域活性化の最新トレンドを学ぶなら「e-JINZAI for government」
目次
人口減少時代の地域課題と情報発信の限界
地域が抱える課題の根底には、人口減少に伴う担い手不足や経済の縮小があります。しかし、それだけではありません。地域資源を十分に活かしきれていない現実や、情報発信が届かないという構造的な問題も存在します。ここでは、地域の現状と広報における課題を整理します。
地域資源が活かされずに埋もれている現状
全国各地には、自然や文化、歴史、伝統産業など、魅力的な地域資源が数多く存在しています。しかし、それらは必ずしも外部に伝わっておらず、地域住民にさえ十分に認識されていないことがあります。
地域資源の価値は、誰かに伝えられて初めて“資源”としての機能を持ちます。現場では、イベントや観光キャンペーンを通じて交流人口の拡大を試みていますが、リピーター化や継続的な関係づくりにはつながっていないケースが多く見られます。
さらに、地域内においても自分たちのまちの魅力に気づかず、無関心な状態が続いているという課題も見逃せません。地域を語れる人がいなければ、外部とのつながりは築けません。
伝わらない広報活動とコミュニケーション不足
地方自治体や地域団体の広報活動は、情報発信の姿勢こそあるものの、受け手に響いていないという問題が顕著です。たとえば、観光案内やイベント告知が一方通行になっていたり、誰に届けたいのかが明確でなかったりと、戦略性に欠けるケースが少なくありません。
また、SNSやWebサイトを活用していても、効果測定を行わず、発信の目的や成果が曖昧なままになっていることもあります。さらに、双方向の対話が生まれにくく、地域と外部との「つながりの起点」として機能していない例も多く見受けられます。
このように、情報発信の在り方自体を見直す必要があるのです。
関係人口という持続可能な地域との関わり方

人口が減少する中で、「定住人口」を増やすことだけを目指すのではなく、地域と関係を持ち続けてくれる「関係人口」を育てることが重要です。ここでは、関係人口の概念と、地域経済におけるその役割を解説します。
「関係人口」の定義と構造的役割
関係人口とは、地域外に居住しながらも、継続的に地域と関わる人々を指します。「観光以上、移住未満」という言葉で説明されることもあります。
関係人口のタイプ(関与の深さによって分類)
- ライト層:SNSでの情報拡散、特産品の購入など間接的な関与
- ミドル層:地域イベントへの継続参加、滞在・ボランティア活動など
- コア層:副業・プロジェクト参画・起業など積極的な関与と価値創出
これらの人々は、定住はしていなくとも「この地域と関わりたい」「貢献したい」という意思を持ち、地域の未来づくりに参加するパートナーです。
地域経済にとっての関係人口の可能性
関係人口は、地域経済にとって非常に重要な役割を果たします。彼らは単なる消費者ではなく、地域の課題解決に主体的に関わる“担い手”でもあります。地域での副業やプロジェクト参画を通じて知識やスキルを提供し、外部のネットワークを地域に持ち込む存在でもあります。
また、関係人口は定住者に比べて流動的でありながらも、関係の質が深まれば、移住や起業に発展する可能性もあります。このような持続的な関係性が、地域に新たな活力をもたらすのです。
地域プロモーション再設計に向けた研修の役割
地域が関係人口を戦略的に育てるためには、まず内部の人材が変わる必要があります。ここでは、地域内の職員や団体を対象とした研修の意義と、どのような力を育むかを解説します。
情報発信スキルと地域内リーダーの育成
地域の魅力を外に伝えるためには、まず「何を」「誰に」「どうやって」伝えるかを整理する力が求められます。研修では、地域資源の棚卸しからスタートし、ターゲットに応じた情報設計、SNSや動画、パンフレットといったツールの効果的な活用方法を学びます。
特に重視されるのは、「地域を語れる人材」の育成です。住民や職員自身が地域の魅力を再認識し、自分の言葉で伝えることができるようになることで、発信の質と信頼性が大きく向上します。
研修で身につける広報スキル
- 地域資源の棚卸しと「語れるコンテンツ」への再構築
- SNSや動画・チラシなど各媒体に適した発信手法
- ターゲット別に訴求力を高めるストーリーテリング技術
このような地域内リーダーが複数育つことで、地域全体の情報発信力も強化されていきます。
関係人口との接点づくりを支える企画力
研修ではまた、単に発信するだけでなく、外部の人と関わる“仕掛け”をつくる企画力も育てます。たとえば、都市部の住民との交流イベントや、地域資源をテーマにしたワークショップ、地域企業と連携したプロジェクト設計などです。
こうした取り組みによって、関係人口と地域の間に継続的なつながりが生まれ、地域の課題解決にもつながっていきます。さらに、関係人口との接点が増えることで、新たな経済的波及効果も期待できます。
関係人口がもたらす地域経済の好循環

関係人口は、単なる応援者ではなく、地域の担い手であり、経済に直接・間接のインパクトを与える存在です。この章では、地域経済への具体的な効果と、その広がりについて紹介します。
地域外の人材が地域にもたらす価値
関係人口の中には、スキルや資金、人脈といったリソースを持つ人が多く存在します。彼らが地域のプロジェクトに関与することで、課題解決に向けた実践的な知恵が注入されます。
また、地域の商品を継続的に購入したり、クラウドファンディングに参加したりといった経済的な支援も期待できます。このように、関係人口は地域にとって「外からの資源を呼び込む窓口」としての役割を果たしています。
関係人口が支える分散型経済・関係資本
現代社会では、「どこに住むか」よりも「どこと関わるか」が重視される傾向があります。関係人口の拡大は、地域における関係資本(人とのつながり)を増やし、多拠点型の経済活動を可能にします。
これは、都市と地域を循環する新たなライフスタイルとも一致しており、今後の地域社会のあり方そのものを変えていく可能性を秘めています。関係人口は、単なる人の数ではなく、関係の質と深さを測る指標でもあるのです。
- 多拠点的な人の流れ:都市と地方を行き来する暮らし方
- 関係資本の蓄積:信頼・共感・協働を基盤とした人間関係の構築
- 外部知・外部資本の導入:新たな発想・事業の創出
このように、関係人口の存在は、地域の可能性を広げる大きな起爆剤となります。
まとめ
人口減少が続く時代において、地域に求められるのは、新しい関係を築く力です。関係人口の創出は、定住を前提としない柔軟な地域との関わり方を可能にし、持続的な経済活動や社会参加を促進します。
そのためには、地域自らが自分たちの資源を見直し、誰にどのような形で魅力を伝えるのかを再設計する必要があります。そして、その実行を担う人材を育てることが、シティプロモーションの再構築において欠かせません。
情報発信を通じた「共感」から始まり、継続的な関わりを生む「関係構築」へと転換することで、地域は外部と手を取り合いながら、新たな未来を切り拓いていくことができるでしょう。
自治体職員向けのスキルや最新トレンドを学ぶ
自治体職員がキャッチアップしておくべき情報は膨大ですが、必要な情報を取捨選択し、インプットしていくのはとても時間がかかります。そこで、行政分野で話題のテーマをいち早くフォローできる研修をご用意しました。この研修では、今の時代に必要とされるスキル、気になる他の自治体の取り組みや事例など、法律や制度改正、住民ニーズを踏まえた最新のテーマを学習し、行政のトレンドを的確に読み解く能力を養成します。
2週間無料お試しはこちら