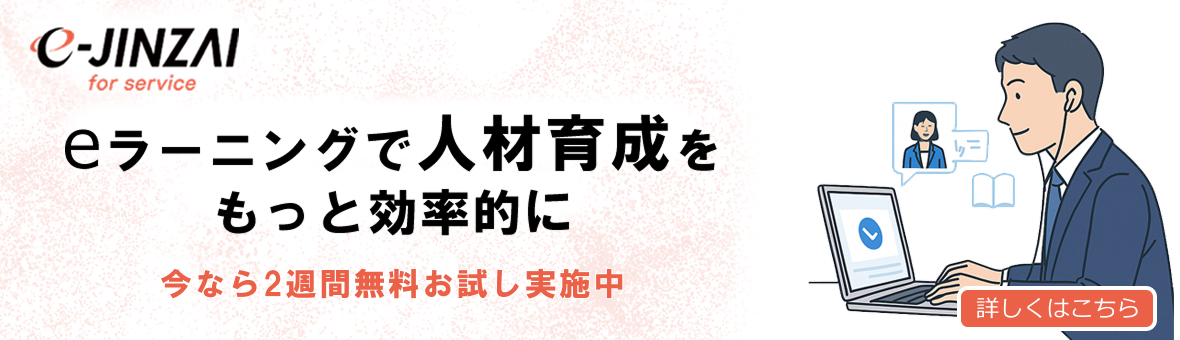店舗運営って何をすればいい?外食産業の基本を徹底解説

「飲食業界に入ったけど、何から学べばいいかわからない」「売上が伸び悩んでいるけど、原因が見えない」――そんな悩みをお持ちではないでしょうか。
飲食業界は、参入しやすい反面、実は非常に奥が深い業界です。基礎知識が不足していると、どれだけ現場で頑張っても結果が出にくいということが少なくありません。
この記事では、飲食業界で働くすべての方に向けて、「まず知っておくべき基本事項」を解説します。そして、その課題をどう乗り越えるか、効果的な研修方法についてもご紹介します。
⇒外食ビジネス、まずはここから!|e‑JINZAI for service
目次
外食産業とはどんな業界か
飲食業界は、1970年代に「外食元年」を迎えて以降、日本経済の発展とともに急速に成長してきました。特に、1970年に「すかいらーく」が、翌年に「マクドナルド」が日本で初出店を果たしたことは、外食文化の転換点として象徴的な出来事です。
現在の外食市場は、惣菜や弁当といった中食との競争もありながら、年間24兆円を超える巨大産業へと成長しています。
この業界の大きな特徴は、初期投資が比較的少なく、技術的ハードルが低いため参入しやすい点にあります。飲食業に強い思いがあれば、小規模資本であってもお店を開業することができるのです。その一方で、競合が多く、生存競争は非常に激しいという現実も見逃せません。
実際、10年後に営業を継続している飲食店は約1割程度というデータもあり、多くの店舗が数年以内に閉店へと追い込まれています。これは、単に料理の味が良い、雰囲気が良いといった要素だけでなく、「経営」に関する基本知識と実行力の差が大きな要因となっています。
さらに、SNSやデリバリーの普及、コロナ禍での営業制限など、飲食業界を取り巻く環境は変化し続けています。このような変動の大きな業界においては、時代に適応する力とともに、業界の構造を理解したうえで「勝てる経営」を実践することが不可欠なのです。
飲食業の収益構造の基本
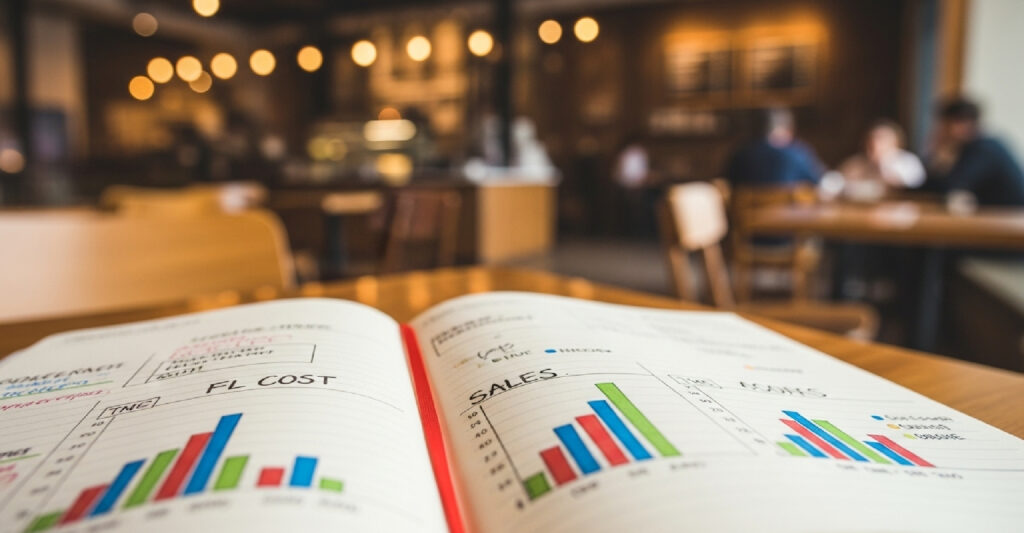
お店を経営するうえで「儲かっているかどうか」は最大の関心ごとです。しかし、売上が上がっているのに利益が出ない、という悩みを抱える店舗も少なくありません。ここでは、飲食店の利益構造を左右する「FLコスト」や日常業務の工夫について、わかりやすく解説します。
FLコストと損益の関係
飲食店経営において、最も基本的でありながら見落とされがちなのが、「損益構造の理解」です。経営者はもちろんのこと、店長やスタッフレベルでも、損益の基本を理解しているかどうかで、現場での判断力に大きな差が出ます。
飲食店の経費構造を理解するうえで中心となるのが、「FLコスト」と呼ばれる考え方です。これは、Food(食材費)とLabor(人件費)の合計を指し、これらが売上の50〜55%に収まっていれば、健全な経営が可能とされています。
この数字はあくまで目安ではありますが、これを大きく超えてしまうと、いくらお客様が入っていても赤字ということになりかねません。売上を増やすだけでなく、コストを意識した営業が求められるのです。
店長や現場スタッフが、注文の取り方や調理工程の効率化、人員配置を調整するなど、日常的にFLコストに対する意識を持つことが、収益の改善に直結します。
日々の工夫が利益を生む
FLコストの管理が必要とはいえ、「数字を意識することが難しい」「どう実践すればいいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には毎日の業務の中に改善のヒントが隠れています。
たとえば、以下のような工夫が利益に直結します。
- 開店前の仕込みを効率化し、必要最小限の人員で準備を完了させる
- 高利益率の商品をメニューの目立つ場所に配置し、スタッフからの推奨を強化する
- 食材の廃棄を減らすために、在庫を日々チェックしてロスを最小限に抑える
これらはどれも派手な施策ではありませんが、実行の積み重ねが数十万円規模の利益差となって現れます。
特に、スタッフが「なぜこの業務を行うのか」を理解して取り組むことで、無駄な動きが減り、店舗全体の生産性が向上します。利益を生む店舗は、裏側の業務にも「考えて動く姿勢」があるのです。
売上を上げるための基本戦略
飲食店の経営において、利益と並んで重要なのが「売上」です。来店してくれるお客様がいなければ、いくらコストを抑えても意味がありません。ここでは、売上を伸ばすために必要な考え方と、実際に現場で実践できる具体的な対策をご紹介します。
来店動機を高める要素とは
「売上を上げたい」と考えるとき、まず着目したいのが「お客様の来店動機」です。
なぜその店に足を運ぶのか、どのような期待を持っているのかを掘り下げることで、具体的な売上対策が見えてきます。
飲食店の来店動機は、大きく以下の2つに分類されます。
- 衝動来店型:通りがかりで気になって入る。立地や看板の目立ちやすさが重要。
- 目的来店型:味や雰囲気、接客などを求めて「わざわざ来る」。体験の質が鍵となる。
目的来店型の店舗では、リピーターが売上の安定化に直結します。そのためには、「また来たい」と思ってもらえる体験を提供することが不可欠です。
QSC(クオリティ=商品品質、サービス=接客、クレンリネス=清潔さ)の水準を常に高く保ち、期待を上回るサービスを実践することが、リピート率の向上に繋がります。
また、SNSや飲食店検索サイトを活用した定期的な情報発信も有効です。店舗の「想い」や「強み」を伝えることで、共感したお客様の心を動かすことができます。
ピークタイムに全力を注ぐ理由
売上改善のために、「暇な曜日や時間をどうにかしたい」と思うことは自然です。しかし、実はそれは非効率な努力になりがちです。
なぜなら、需要が少ない時間帯では、いくらプロモーションや人員を増やしても大きな成果にはつながりにくいからです。
一方、売れる曜日・時間帯に最大の成果を出すという発想は、非常に効果的です。週末やランチ・ディナーのピークタイムにおいて、店舗として最高のパフォーマンスを発揮できれば、多くの新規顧客に「また来たい」と思ってもらうことができます。
例えば、
- 優秀なスタッフをピークタイムに配置する
- 提供スピードを上げて回転率を高める
- おすすめメニューを積極的に提案して単価を上げる
などの工夫によって、売上効率が一気に改善されます。「売れるときに売る力」こそが、繁盛店とそうでない店の明暗を分けるのです。
本気で成長したい方におすすめの学び方

ここまでご紹介してきた内容は、飲食店経営におけるほんの基礎にすぎません。
実際には、スタッフ教育や数値管理、商品開発、マーケティングなど、さらに多くの知識やスキルが必要になります。
「自分の店舗でどう活かせばいいか分からない」
「店長として何から始めるべきか悩んでいる」
「スタッフの意識を変えたいが方法が分からない」
こうした悩みを抱えている方には、現場に即した知識を体系的に学べるeラーニング研修が効果的です。
外食ビジネスにおけるeラーニング研修のメリット
飲食業界では、営業時間が長く、シフト勤務が一般的です。そのため、全員が一堂に会して研修を行うことが難しい場面も多くあります。そんな中で注目されているのが、eラーニング形式による研修です。
この学習スタイルは、忙しい現場のスタッフにとっても取り入れやすく、実際の業務にも直結しやすいという点で、大きな効果を発揮します。
以下に、eラーニング研修の主なメリットを表で整理しました。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 時間と場所を選ばずに学べる | 営業の合間や自宅など、自分のペースで学習可能。シフト制でも受講しやすい。 |
| 習熟度に合わせた学びができる | 初心者は基礎から、経験者は応用へ。段階的にステップアップできる。 |
| 均一な教育レベルを実現できる | 店舗間で教育のバラつきがなくなり、組織全体のレベルアップにつながる。 |
| 繰り返し学習で知識が定着しやすい | 苦手な部分は何度でも見直せるため、理解が深まりやすい。 |
eラーニングは、知識を得るだけでなく、実際の業務課題の解決に活かせる“実践的な学び”が可能です。
たとえば、以下のような効果が期待できます。
・お客様の満足度を高めるためのQSC改善ポイントを自発的に見つけられる
・マネジメントや接客で、他店舗の成功事例を参考にした行動変容が生まれる
飲食業界では「人材の質=店の質」と言っても過言ではありません。eラーニングという選択肢は、その人材育成を無理なく、かつ効果的に進めるための強力な味方になるはずです。
まとめ
飲食業で成功するためには、感覚や経験に頼るだけでは限界があります。まずは、業界の仕組みや利益構造といった「基本の型」を理解することが、最短ルートとなります。
本記事で紹介した内容を踏まえ、より深く学びたい方は、eラーニングを通じて効率的にスキルアップを図ってみてはいかがでしょうか。
学びの積み重ねが、確かな結果へとつながります。
外食ビジネスの基礎知識
外食業は、店舗運営の手法や事業展開の仕組み、売上向上の工夫など、さまざまな知識が求められる業界です。また、多様化する顧客のニーズに応えるためには、経営の視点と現場での柔軟な対応力の双方を身につけることが欠かせません。 この研修では、外食ビジネスを理解するための基本的な考え方を解説。業界の特徴から、売上向上の原則、店舗運営における工夫までを幅広く取り上げ、変化の激しい環境で活かせる知識を学びます。
2週間無料お試しはこちら