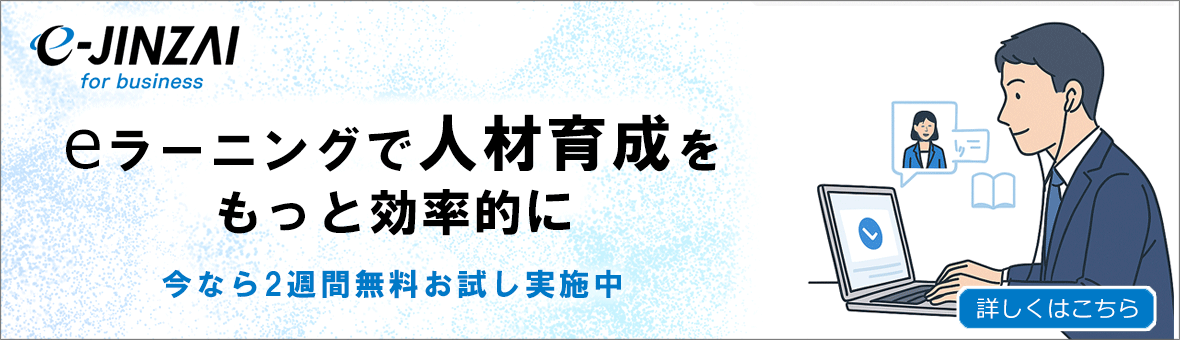退職代行って何?費用やメリット・デメリットを解説

退職代行とは、その名の通り「会社を辞めたい人」に代わって、退職の意思を勤務先へ伝えてくれるサービスです。利用者本人が上司や会社に直接連絡せずに退職できる点が特徴で、精神的な負担を減らせる手段として注目されています。
主に弁護士が行う「法律対応型」と、民間企業が提供する「一般型」があり、退職に伴う手続きや交渉の範囲が異なります。未払い残業代の請求や損害賠償などの交渉は、弁護士にしか対応できないため、サービス内容に応じて選ぶことが大切です。
⇒ 働く人のストレスとセルフケアを学ぶなら『e-JINZAI for Business』
目次
- 退職代行を使う理由
- どんな人が利用しているのか?
- 退職代行の費用相場はどれくらい?
- 退職代行を使った際の一般的な流れ
- 退職代行を使うときのポイント
- 退職代行を使う前に考えておきたいこと
- まとめ:退職代行は“逃げ”ではなく、選択肢のひとつ
退職代行を使う理由

退職代行の利用者が増えている背景には、「辞めたいけれど、自分で言い出せない」という心理的ハードルがあります。特に、パワハラや引き止め、精神的ストレスによって、円満な退職の意思表示が困難なケースで多く利用されています。
また、退職の意思を伝えた後に強い圧力をかけられたり、退職届を受け取ってもらえないといったトラブルを未然に防ぐ目的でも利用されます。
最近では、「もう会社に行きたくないけれど、引継ぎや荷物の整理を考えるだけで憂うつになる」という声や、「退職を伝えたら評価や人間関係が悪くなりそうで怖い」と感じる若手社員の利用も増えています。
どんな人が利用しているのか?
退職代行を利用する理由は人によってさまざまですが、共通するのは「自分から会社に退職を切り出すことが難しい」という点です。
特に次のような事情を抱えている人に選ばれる傾向があります。
上司に強く引き止められている
「今辞められたら困る」「次が決まってないなら考え直せ」など、圧力をかけられた結果、退職の話を切り出せなくなってしまうことがあります。
本来、退職の意思は個人の自由ですが、権力関係によってその判断が封じられてしまうケースが見られます。
退職を申し出たが受け入れてもらえない
退職届を提出しても「考え直せ」と突き返されたり、話を先延ばしにされたまま数ヶ月が経過することもあります。
制度上は退職の意思表示から2週間で辞められますが、現実には妨げられることも多いのが実情です。
パワハラや長時間労働で精神的に疲弊している
上司からの高圧的な指導や、終電までの勤務が常態化しているなど、心身に限界を感じていても、会社に話す気力すら残っていない人もいます。
このような状況では、退職の手続きを自分で進める余裕がなく、外部のサポートに頼らざるを得ないことがあります。
自分の口から退職を伝えるのが怖い
「怒られるかもしれない」「否定されるのが怖い」という不安が大きく、自分で伝える勇気が持てないケースも多くあります。
特に若手社員や社会人経験が浅い人ほど、退職の場面での緊張や恐怖感が強く、第三者の力を借りたくなるものです。
このように、精神的ストレスや職場での人間関係に悩み、自分の意思だけでは円滑に辞められないと感じた時の“最後の手段”として利用されるケースが多いのが特徴です。
他にも、「家族に辞めたことを知られたくない」「再就職の準備を優先したい」という理由で、あえて手続きを外部に委託する人もいます。
退職代行の費用相場はどれくらい?
退職代行の費用は、依頼するサービスの種類によって異なります。
大きく分けて、民間業者型・労働組合型・弁護士型の3種類があり、それぞれ対応範囲や費用に違いがあります。
民間業者型
比較的安価で、即日対応してくれる場合が多いです。
費用は2万円〜3万円程度が一般的ですが、法的な交渉(未払い残業代請求など)はできません。
労働組合型
労働組合が運営するサービスで、会社との交渉(退職日や引き継ぎ条件など)が可能です。
費用は2万〜3万円台で、交渉力のある点が特徴です。
弁護士型
弁護士が対応するため、未払い給与や有給休暇の請求など法的な交渉が可能です。
費用は5万〜10万円程度と高めですが、トラブルが予想される場合には安心です。
退職代行を使った際の一般的な流れ
退職代行サービスは、利用者の負担を最小限に抑えつつ、スムーズに退職できるよう設計されています。ここでは、依頼から退職完了までの一般的な流れをご紹介します。
相談・問い合わせをする
まずは退職代行業者の公式サイトやLINE、メール、電話などを通じて問い合わせます。
自分の勤務状況や悩み、希望する退職日などを伝えると、担当者がヒアリングを行い、サービス内容や料金を案内してくれます。
無料相談を実施している業者も多いため、複数社に相談して比較するのもおすすめです。
正式に依頼・料金の支払い
サービス内容に納得したら、契約に進みます。
依頼にあたっては、基本的に前払いでの料金支払いが必要になります。支払いが完了すると、退職代行が正式にスタートします。
業者が会社に連絡し、退職の意思を伝える
利用者に代わって、業者が会社に退職の意思を伝えます。
この時点から、利用者が会社に直接連絡を取る必要はありません。必要に応じて、業者が本人に代わって退職日や書類のやり取りについても調整します。
会社からの書類が届く(自宅でのやり取り)
退職が受理されると、健康保険証や社員証の返却、離職票や源泉徴収票などの書類が郵送されてきます。
会社に出向くことなく、自宅で完結する場合がほとんどです。制服などの私物返却も郵送で済ませることができます。
退職完了・アフターフォロー
すべてのやり取りが終わると、正式に退職完了となります。
弁護士が対応するサービスを利用した場合には、未払い残業代の請求や有給消化交渉など、法的サポートも含まれることがあります。
アフターフォローとして、転職支援を行う業者もあるため、次のステップに進むサポートも受けられます。
退職代行を使うときのポイント
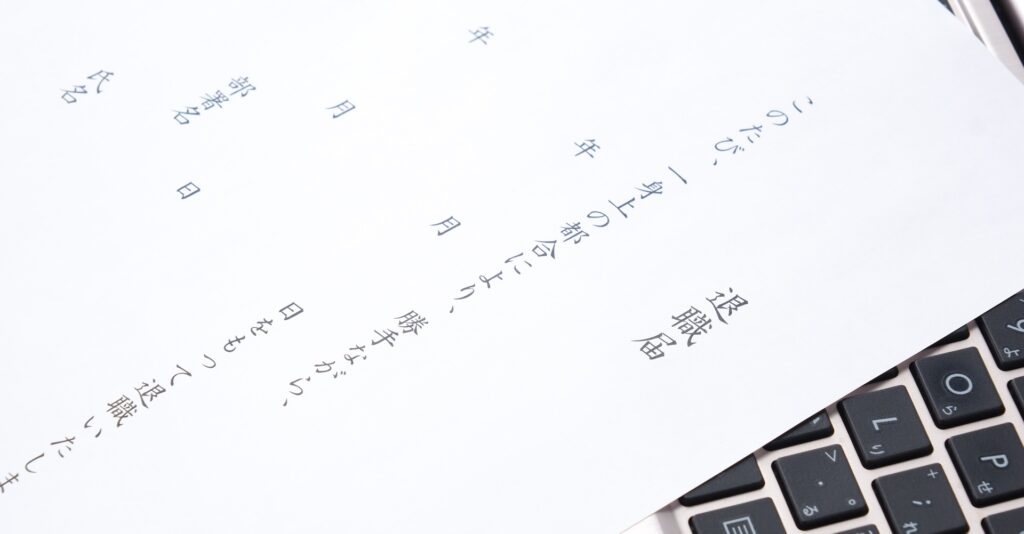
退職代行を検討する場合は、まず自分の状況や希望を整理することが大切です。
「本当に退職する覚悟があるか」「会社に伝える勇気は本当にないか」などを一度考えてみることで、後悔のない選択がしやすくなります。
また、業者を選ぶ際には、対応実績、口コミ、明確な料金体系、サービスの範囲などをよく確認しましょう。
可能であれば、無料相談などを活用して、自分のケースに合った提案を受けると安心です。
退職代行を使うメリット
退職代行を利用する最大のメリットは、精神的ストレスを大幅に軽減できることです。
退職を伝えることに抵抗がある人でも、代行業者が間に入ることで、トラブルなく退職できるケースが多く見られます。
また、即日退職に対応してくれる業者が多いため、「明日から出社したくない」といった切羽詰まった状況でも迅速に対応してもらえるのも大きな魅力です。
さらに、有給休暇の消化や退職書類の受け取りなど、手続きのサポートも受けられるため、初めての退職でも安心して進めることができます。
退職代行のデメリットと注意点
一方で、退職代行にもいくつかのデメリットや注意点があります。
まず、お金がかかるという点。自分で退職を伝えれば無料で済むところを、数万円支払う必要があります。
また、代行業者によってはサービス内容が不明確な場合もあり、トラブルに発展する可能性もあるため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
さらに、直接コミュニケーションを取らないことによる誤解や摩擦が残ることもあります。
職場との関係を一切断ちたい人にとっては問題にならないかもしれませんが、将来的に再会する可能性がある業界の場合は慎重な判断が求められます。
加えて、民間業者では法律行為ができないため、給与や残業代の請求などには対応できません。必要に応じて弁護士への相談が必要になる点も理解しておくべきです。
退職代行を使う前に考えておきたいこと
退職代行は便利なサービスですが、まずは信頼できる上司や人事担当者に相談できないか、可能性を探ることも重要です。冷静な話し合いで退職できる環境があれば、代行を使わずに済むかもしれません。
また、利用にあたっては、退職理由を明確にし、必要書類や引継ぎの準備を進めておくことがスムーズな手続きにつながります。代行を使ったからといって、すべてを任せきりにするのではなく、最低限の責任感は持つようにしましょう。
まとめ:退職代行は“逃げ”ではなく、選択肢のひとつ
退職代行は、「自分で言えないから恥ずかしい」「逃げていると思われたくない」といったネガティブな印象を持たれることもあります。
しかし、心身の健康を守るために必要な手段であることも事実です。
自分にとって今の職場が限界だと感じたら、退職代行という選択肢を前向きに捉えてもよいでしょう。
大切なのは、「どう辞めるか」よりも、「次にどう進むか」です。退職をきっかけに、よりよい働き方や自分らしいキャリアを築くことができるよう、冷静かつ丁寧に選択肢を検討することが求められます。
メンタルヘルスケア研修
日々の多忙な業務や社内での人間関係など、様々な要因からストレスを抱え、心身の不調により休職や離職に発展するケースは増加傾向にあります。ビズアップ総研のメンタルヘルスケア研修では、メンタルヘルスの向上や組織で問題が発生した際の対応方法など、一般向け・人事向けそれぞれのメンタルヘルスケア研修を用意しています。ストレス社会を健康的に過ごす知識を身につけましょう。
2週間無料お試しはこちら