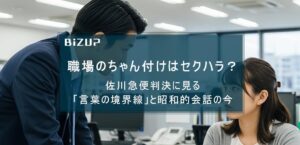あなたは大丈夫?職場の香害・スメハラに注意

「良かれと思ってつけた香水や柔軟剤の香りが、実は周囲を不快にさせている」そんなケースが職場で増えています。香りの強さや好みには個人差があり、なかには頭痛や吐き気を訴える人も。知らず知らずのうちに“スメルハラスメント(スメハラ)”の加害者になってしまう可能性があるのです。
本記事では、職場における香害(香りによる公害)・スメハラの実態や原因、企業としての対策、そして個人が注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
目次
スメハラとは?香害との違いは?

スメハラの定義
スメルハラスメント(略してスメハラ)とは、香水や柔軟剤、整髪料、たばこ、体臭など、においによって他人に不快感や健康被害を与える行為を指します。意図的でなくても、周囲に強いストレスや体調不良を引き起こすことがあるため、近年「ハラスメント」の一種として認識されるようになりました。
香害との違い
「香害」とは、強すぎる人工的な香り(香水、洗剤、芳香剤など)による健康被害や不快感を訴える人が社会的に問題視する言葉で、スメハラはその中でも特に“職場における迷惑行為”にフォーカスした概念です。
なぜ今、職場で問題になるのか
近年、職場におけるにおいのトラブルが急増しています。背景には、働く環境や価値観の変化、そして香りに対する感受性の高まりがあります。
働き方の多様化と密閉空間
オフィスワークでは換気が不十分な会議室やフロアで長時間過ごすことが多く、香りがこもりやすい環境にあります。マスクの着脱により匂いへの感覚が敏感になった人も増え、わずかな香りでも不快に感じるケースが増加しています。 また、リモート勤務から出社に戻ったことで、他人の「におい」に久しぶりに触れ、違和感を抱く人も少なくありません。これまで気づかなかった香りへの反応が顕在化しているのです。
「清潔感」の過剰演出
「いい香り=身だしなみ」という意識から、香水や柔軟剤、デオドラントスプレーを過剰に使用する人が少なくありません。しかし、香りの強さには個人差があり、「爽やかさ」を演出したつもりが、周囲には「刺激臭」として伝わることもあります。 柔軟剤や香料入り製品の香りは衣服や髪に長く残るため、気づかぬうちに職場全体に拡散し、周囲のストレスや体調不良の引き金になることもあります。
化学物質過敏症(CS)の存在
香料などに含まれる化学物質に過敏に反応し、頭痛・めまい・吐き気・呼吸困難などを引き起こす「化学物質過敏症」の方もいます。本人の体質によるものであり、軽視できる問題ではありません。 CSは一度発症すると完治が難しく、再発や悪化のリスクも高いため、職場では特に配慮が求められます。誰にでも起こり得る症状であることを、組織全体で共有しておく必要があります。
具体的な事例
「香害」は他人事ではありません。実際に職場で起きた事例を通じて、問題の深刻さを見ていきましょう。
- 香水をつけすぎた社員の近くに座った同僚が、毎日頭痛と吐き気に悩まされるようになり、最終的に部署異動を希望した。
- 芳香柔軟剤の強い香りが原因で、社内の一部メンバーが化学物質過敏症を発症し、時短勤務やリモートワークを余儀なくされた。
- 「口臭」や「たばこ臭」を理由に、社内で陰口やパワハラに発展したケースも。
こうした問題が放置されると、職場の人間関係や生産性に悪影響を与える可能性があります。
法的責任や企業の対応
スメハラ自体に明確な法律は存在しないものの、労働安全衛生法に基づく職場環境の配慮義務や、民法上の不法行為(損害賠償)などが適用されるケースもあります。
法的な位置づけとリスク
スメハラ自体を直接規制する法律は現時点では存在しませんが、職場環境への配慮義務を定めた労働安全衛生法や、故意または過失による他者への損害を対象とする民法上の不法行為責任(709条)が、間接的に関係してくることがあります。例えば、香料による体調不良を放置した結果、健康被害が深刻化した場合、企業や加害者が責任を問われる可能性もあります。
企業が果たすべき対応義務
厚生労働省が定めるハラスメント対策指針において、企業は「職場におけるあらゆるハラスメント防止に努める義務」があるとされており、スメハラも例外ではありません。具体的な対応としては、下記のような対応が企業に求められます。
- 就業規則への明文化(香水・香料の使用に関するガイドライン等)
- 全社員向けのハラスメント防止研修でスメハラへの理解を促す
- 被害申告・相談をしやすい窓口の整備と、相談者のプライバシー保護
組織文化としての「香り配慮」づくり
香りは非常に主観的な要素であり、全員にとって「快適」であるラインを見極めるのは困難です。そのため、制度化と同時に、日常的な配慮や声かけがしやすい職場文化の醸成も重要です。たとえば「無香料推奨デー」を設けたり、「香料に関する社内アンケート」を定期的に行うことで、個人の意識改革と職場全体の空気づくりの両面から対策を進めることができます。
個人ができるスメハラ対策

スメハラ(スメルハラスメント)は加害者に自覚がないまま起こるケースが多く、無意識のうちに周囲に負担をかけてしまうこともあります。だからこそ、日々の行動を見直す意識が大切です。ここでは、個人がすぐに取り組める3つの対策を紹介します。
香りの強さを見直す
香水やヘアスプレーはワンプッシュでも十分な香りが広がります。自分では気づきにくい“香りの残り香”を意識し、TPOに合わせて無香料や微香性の商品を選ぶことが推奨されます。
特にオフィスや公共交通機関などの閉鎖空間では、香りを抑えた選択がマナーとされつつあります。洗濯用洗剤や柔軟剤も香りの持続性が高まっているため、使用量の見直しも効果的です。
他人の反応に敏感になる
「何か匂いする?」「この柔軟剤どう思う?」といった会話の中に、ヒントが隠れていることも。他人の仕草や距離感から「気づかないスメハラ」に気をつけましょう。
鼻を手で覆う、さりげなく席を移動するといった行動は、においへの不快感のサインかもしれません。定期的に家族や親しい人に、自分の香りについてフィードバックをもらうのも有効です。
相談・報告しやすい職場づくりを
においの問題は非常に主観的でデリケートな話題です。無理に指摘するのではなく、相談窓口を活用したり、第三者を介して伝える方法も有効です。企業のサポート体制も整いつつあるため、一人で悩まないことが大切です。
社内で「においに関するガイドライン」が共有されている場合は、それを活用して冷静に伝える工夫も必要です。また、自分が指摘された場合も素直に受け止め、改善の姿勢を見せることが信頼につながります。
まとめ
職場における香害・スメハラは、本人に悪意がなくても加害者になってしまう繊細な問題です。誰もが被害者にも加害者にもなり得るからこそ、日頃のちょっとした配慮と、職場全体での理解促進が欠かせません。
今一度、自分の身だしなみや香りのマナーを見直し、働きやすい職場環境づくりに貢献しましょう。香りは好みが分かれるだけでなく、体調に影響を及ぼす人もいるという認識を持つことが重要です。
組織としても、スメハラを「小さな問題」と捉えず、ルール整備や相談体制の強化を進める必要があります。一人ひとりの意識と企業の取り組みが、快適で安心な職場をつくる第一歩です。