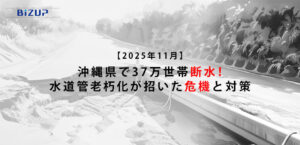クセ強社員の対応術|部下を強みに変えるマネジメント法
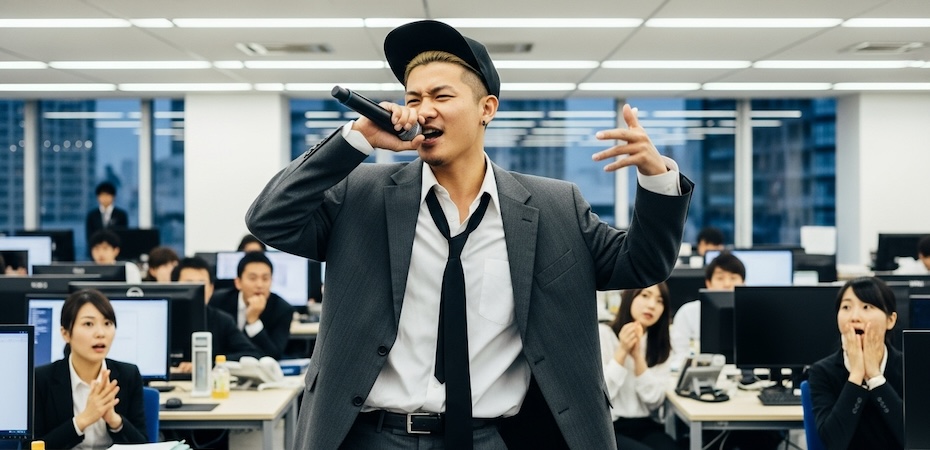
「またあの人か……」。会議でいつも意見がぶつかる部下に、ため息をついた経験はないでしょうか。
チームには必ずと言っていいほど、個性の強い、いわゆる“クセ強社員”が存在します。独自の価値観や行動パターンを持つ彼らは、マネジメントにおいて悩みの種となりがちです。しかし見方を変えれば、組織に新しい風を吹き込む貴重な存在でもあります。
本記事では、クセの強い部下との関わり方に悩む中間管理職に向けて、「クセ」を「強み」へと変換するマネジメントの考え方と、チーム全体の力を引き出すためのヒントを紹介します。
目次
- クセ強社員との日常的な摩擦
- 「クセ」を「強み」に変える視点
- チームの見える化がマネジメントを変える
- e-JINZAI lab.のタレントマネジメント研修で得られる3つの効果
- マネジメントの変化が組織を変える
- まとめ
クセ強社員との日常的な摩擦
どんな職場にも、個性の強い部下はいるものです。自分の意見を曲げない、上司の指示に疑問を投げかける、あるいは協調性が低く感じられるなど、行動や思考が“普通”と異なるために、マネジメントが難しく感じられることがあります。
一方で、こうした部下は高い専門性や独自の発想力を持っているケースが多いのも事実です。問題は「クセ」そのものではなく、その扱い方にあります。上司側が彼らを理解しようとせず、「厄介な存在」と決めつけてしまうと、チームの信頼関係は崩れてしまうでしょう。
さらに、マネージャー自身が「自分のマネジメントが悪いのでは」と悩みを抱え込み、ストレスをためることも少なくありません。感情的な対応をすれば状況は悪化し、双方にとってマイナスになります。重要なのは、部下を変えることではなく、部下を理解し、活かすことです。そのためには、コミュニケーションの土台を整え、互いの価値観を「見える化」することが不可欠です。
クセ強社員との価値観のズレを理解する
クセ強社員との衝突の多くは、能力ではなく価値観のズレから生まれます。上司が「結果重視」、部下が「プロセス重視」であれば、当然ながら意見はかみ合いません。
このズレを放置すれば、仕事の方向性がブレるだけでなく、部下のモチベーション低下を招きます。まずは、どのような価値観を持っているのかを理解することから始める必要があるでしょう。
感情ではなく構造で見るマネジメントの姿勢
感情的に「合わない」と判断するのではなく、行動特性や強みの構造を分析してみましょう。
例えば、自己主張が強い部下は「責任感が強い」「自分の考えに自信を持っている」タイプかもしれません。反発的な態度の裏には、組織をより良くしたいという意識が隠れていることもあります。
表面的な行動ではなく、背景の意図を読み取ることで、マネジメントの精度は大きく変わります。


タレントマネジメント研修
動画数|8本 総再生時間|127分
組織の競争力を高める人材戦略のひとつである「タレントマネジメント」について、基本的な考え方から実践的な運用方法までを学ぶプログラムです。現場マネージャーや人事担当者が果たすべき役割、優秀な人材の発掘・育成・配置・評価といった実務レベルの活動を整理し、自社の現状と課題を見つめ直します。
動画の試聴はこちら「クセ」を「強み」に変える視点

クセの強さを単なる「問題」と捉えるのではなく、「組織の多様性を生み出す資源」として捉える発想が求められます。多様な個性が存在するチームは、同質的な集団よりも創造性が高く、イノベーションを起こしやすいといわれています。
マネージャーに求められるのは、クセを抑え込むのではなく、強みとして生かす仕組みを作ることです。その第一歩は、部下の特性をデータとして客観的に把握することにあります。感覚ではなく事実ベースで「誰が何に向いているか」を整理することで、無駄な摩擦を減らし、適材適所の配置が可能になるのです。
以下の表は、クセの強い部下によく見られる特徴と、それを強みに転換する視点を整理したものです。
| 特徴 | 上司が感じる課題 | 強みに変える視点 |
|---|---|---|
| 自己主張が強い | 指示に従わない・協調性が低い | 主体性が高く、リーダーシップを発揮しやすい |
| こだわりが強い | 柔軟性に欠ける・時間がかかる | 品質意識が高く、専門分野で力を発揮できる |
| 感情の起伏が激しい | 周囲との衝突・雰囲気の乱れ | 感受性が豊かで、顧客対応や創造的業務に適する |
このように、「クセの裏にあるポジティブな側面」を見つけ出すことで、マネジメントの難しさは驚くほど軽減されます。
クセ強社員の強みを活かす配置のコツ
人は環境によってパフォーマンスが変わります。苦手な業務でストレスを抱えるよりも、得意な分野に集中できる環境を整える方が、成果につながりやすいのです。
上司がその人の強みを理解し、役割やタスクを最適化するだけで、チーム全体の動きがスムーズになります。クセを変える必要はなく、活かし方を変えるだけでいいのです。
見える化で進化するマネジメント手法
部下の個性や能力を“見える化”することで、上司の主観に頼らないマネジメントが可能になります。
可視化されたデータを共有すれば、本人も「自分の強みを理解してもらえている」と感じ、信頼関係が深まります。これにより、従来のような“上からの指導”ではなく、“共に成長する関係”が築けるでしょう。
チームの見える化がマネジメントを変える
マネジメントを根本から変える鍵は、チーム全体の情報共有と見える化にあります。
部下一人ひとりの強み・弱み・適性を整理し、チーム全体のバランスをデータで把握することで、配置や業務分担がより合理的になります。特にクセの強い部下が複数いる場合、見える化の仕組みがないと、感覚的な判断に陥りやすく、結果として不公平感を生んでしまうのです。
また、見える化は上司だけでなく、メンバー同士の相互理解にも効果的です。「あの人はこういう考え方をする」「この人はこういう強みを持っている」と共有されることで、不要な衝突が減り、チームの雰囲気も改善されます。
データをもとに人を理解するという考え方は、今後のマネジメントの基本になるでしょう。後半では、この“見える化”を実践的に学べるe-JINZAI lab.のタレントマネジメント研修について詳しく紹介します。
e-JINZAI lab.のタレントマネジメント研修で得られる3つの効果
「クセの強い社員を活かす」ためには、感覚や経験だけに頼らないマネジメントの仕組みが必要です。
e-JINZAI lab.が提供するタレントマネジメント研修では、社員一人ひとりの特性や行動傾向をデータで可視化し、科学的にチーム運営を改善するノウハウを学べます。
この研修の特徴は、単なる知識提供ではなく、実際の職場に落とし込める「実践設計力」が身につく点にあります。強みを中心に人材を理解し、チームの相互作用を最適化することで、マネージャーの負担を軽減しながら成果を最大化する仕組みを構築できるでしょう。
ここでは、その具体的な効果を紹介します。
強みと課題を見える化するマネジメント力
研修では、個々の性格特性や行動傾向を分析するフレームワークを活用します。これにより、感覚ではなくデータをもとに部下を理解できるようになります。
「なぜこの人は反発的なのか」「なぜこの人は意見を言わないのか」といった疑問を、科学的に紐解けるようになるでしょう。結果として、指導の方向性が明確になり、無用な摩擦を防ぐことができます。
クセ強社員を活かすマネジメント配置設計
クセの強い社員を“扱いづらい存在”と見るのではなく、“適した場所で力を発揮できる人材”と捉えることが研修の中心テーマです。
研修を通じて、各メンバーの得意分野を可視化し、役割を再設計するスキルを習得します。これにより、チーム全体のパフォーマンスを高め、離職防止にもつながるでしょう。


タレントマネジメント研修
動画数|8本 総再生時間|127分
組織の競争力を高める人材戦略のひとつである「タレントマネジメント」について、基本的な考え方から実践的な運用方法までを学ぶプログラムです。現場マネージャーや人事担当者が果たすべき役割、優秀な人材の発掘・育成・配置・評価といった実務レベルの活動を整理し、自社の現状と課題を見つめ直します。
動画の試聴はこちらマネジメントの変化が組織を変える

「人が変わればチームが変わる」とよく言われますが、実際には“上司の見方が変わることでチームが変わる”ケースが多いのです。
タレントマネジメント研修を受けたマネージャーの多くが、「自分が変わることで、部下との関係が驚くほどスムーズになった」と口を揃えるでしょう。
研修で得たデータ活用のスキルを使えば、感情的な判断を排除し、誰にどんな業務を任せるべきかを冷静に決定できます。結果として、部下も「自分の強みを認めてもらえている」と実感し、モチベーションが上がるのです。
さらに、個々の強みが連携し合うチームは、変化に強く、イノベーションを生み出す土壌を持ちます。クセの強さを恐れず、個性を戦略資源として活かす姿勢こそが、次世代マネジメントの鍵になるでしょう。
まとめ
クセの強い社員との関係に悩むマネージャーは多いものです。
しかし、その「クセ」は裏を返せば、組織に欠かせない多様性の表れです。マネジメントの目的は、部下を均一化することではなく、個々の強みを最大限に活かすことにあります。
そのためには、直感や経験に頼らず、データと仕組みで人を理解する力が不可欠です。e-JINZAI lab.のタレントマネジメント研修は、まさにその力を身につけるための実践的なプログラムです。
研修を通じて、「クセ強社員」という言葉の裏にある可能性を再発見し、チーム全体のパフォーマンスを引き上げてみてはいかがでしょうか。