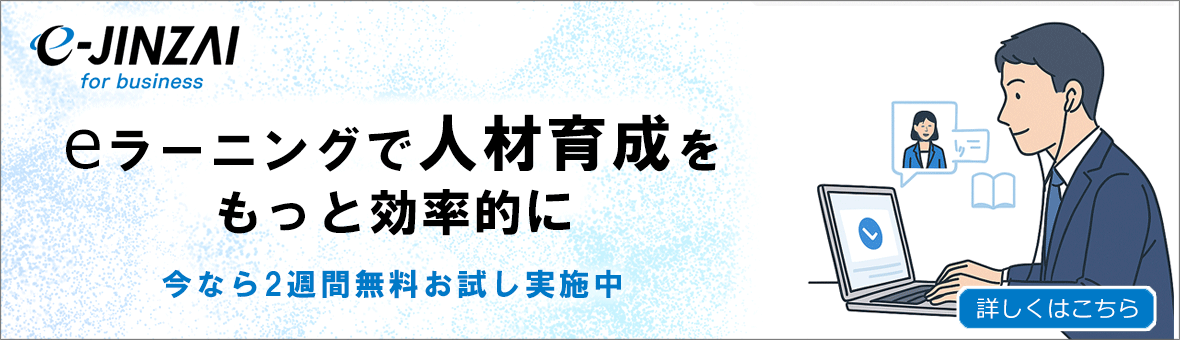人材派遣業をはじめるのに資格は必要か?申請のための要件、開業での注意点を解説!

人材派遣事業としてスタートアップするには、派遣元責任者講習の受講資格が義務とされ、基準資産額の準備などさまざまな手続きを要します。一般企業とは異なった特有な許認可が必要とされ、かかる費用についても考慮することになるでしょう。ただし、人材派遣事業には将来的な見込みがありメリットも考えられます。
本記事は、人材派遣事業を始めるにあたっての必要な資格や申請方法、開業のための注意点を解説する内容です。人材派遣事業への関心や興味がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 人材派遣業の基本的概要
- 人材派遣業での雇用形態と派遣形態
- 人材派遣業に必要な資格とは
- 人材派遣業の許可に必要な要件
- 人材派遣業の許可申請に必要な書類
- 人材派遣事業の開業で考えられるリスクや注意点
- まとめ
人材派遣業の基本的概要

人材派遣業とは、派遣会社が雇用した派遣社員やスタッフを、企業へ出向させて業務に従事してもらう仕組みを指します。
おもな、人材派遣業の基本的な概要としては、以下のような内容です。
- 派遣社員は雇用契約を派遣会社と締結
- 業務の指揮命令権は派遣先企業
- 給与支払いや福利厚生の提供は派遣会社
- 派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を締結
- 一人当たりの派遣期間や業務は制限付き
- 労働者派遣法が適用
派遣元企業が雇用する派遣社員やスタッフを、条件に合致した人物として派遣先企業へ紹介します。
派遣元企業と派遣社員やスタッフの間では、雇用関係が成立していますが、各スタッフの日常業務については、派遣先の指示に基づきながら遂行することが通常です。
人材派遣業のおもな流れ
人材派遣業の基本的な仕事の流れは、まず、派遣元会社が派遣スタッフを派遣先企業に出向させます。その際の派遣スタッフの給与については、派遣元会社が支払いますが、社会保険料などのコストを差し引いた残り(手取り)の額面です。
派遣契約期間は最長3年と定められ、派遣スタッフとの雇用契約は原則終了となります。その後の派遣スタッフについては、派遣元会社の正社員に登用されるケースや、派遣先企業に改めて正社員として採用される可能性も考えられますが、必ずしもそうとは限りません。
労働者派遣法
人材派遣業務では、労働者派遣法(派遣法)と呼ばれる法令が適用されます。労働者派遣法は、派遣元会社および派遣先企業も厳守すべきルールです。
おもに以下の10項目が制定されています。
- 労働者派遣契約に関する措置
- 適正な派遣就業の確保等のための措置
- 派遣先による均衡待遇の確保
- 派遣先の事業所単位の派遣期間の制限の適切な運用
- 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用
- 派遣労働者の雇用の努力義務
- 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進
- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
- 派遣先責任者の選任
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知
労働者派遣法は、派遣社員やスタッフの保護を主旨とし、人材派遣業の適正な運営のため、1985年より制定されました。この法令が施行された背景には、労働市場の変化による非正規雇用の需要増加があります。
派遣で働く人々の待遇や権利についての問題が、社会的に注目されてきたためです。労働者派遣法は、すべての派遣労働者を不当な待遇から保護し、トラブルなどの抑制を図るのに重要な役割を持っています。
⇒ 『e-JINZAI for Business』で労働者派遣法を詳しく学ぶ
人材派遣業での雇用形態と派遣形態
人材派遣業では、雇用の形態と派遣の形態がいくつかに分類されています。
以下のような内容です。
- 雇用形態・・・登録型派遣、常用型派遣
- 派遣形態・・・有期雇用派遣、無期雇用派遣、紹介予定派遣
各々にはどのような違いや特徴があるのでしょうか。ここでは、雇用形態と派遣形態ごとによるそれぞれの違いを解説します。
人材派遣業での雇用形態
派遣元会社の雇用形態には、「登録型派遣」と「常用型派遣」の2タイプがあります。登録型派遣とは、「求職者」より派遣元会社へ登録し、仕事を紹介されて就業開始する際に雇用契約を結ぶ形態です。
派遣期間が満了した段階で雇用契約も終了します。その後は、派遣会社が新たな派遣先の紹介をした場合、雇用契約を再締結する方式です。
一方、常用型派遣とは、派遣会社に元々属している「社員」が派遣される形態を指します。最初から社員として登用されているので、派遣期間満了後も派遣元会社との雇用関係が継続中です。
その後に新しい派遣先が決定するまでの期間も、給与支払いの対象となります。
人材派遣業での派遣形態
人材派遣業での各スタッフの派遣形態は、大きく「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」の3種類に分類できます。
有期雇用派遣は、上述した登録型派遣と同じ意味合いです。求職者が派遣会社へ登録し、派遣先企業で一定期間の就労をします。それとは違って、無期雇用派遣の場合は、上述した常用型派遣と近い意味合いです。
派遣元会社にて無期雇用された正社員が、派遣先企業にて就労します。とくに、専門職として必要性があるケースで発生する形態です。これらとは違ったタイプが、紹介予定派遣と呼ばれる形態になるでしょう。
派遣先企業への人材派遣までは一緒ですが、そのスタッフが将来的に直接雇用されることを前提としています。派遣期間中において、派遣スタッフと派遣先企業の双方が直接雇用で合意すれば切替える仕組みです。
ミスマッチが少なく、お互いに納得できるメリットがあります。
人材派遣業に必要な資格とは
人材派遣業を始めるには、どのような資格が必要になるのでしょうか。人材派遣会社は、誰でも自由に開業できる業種ではありません。事前に必ず取得すべき資格取得と許可が要ります。大きく捉えれば、「派遣元責任者」の資格取得と、「労働者派遣事業許可」が必要です。
では、この2つの内容を中心に詳細を解説していきましょう。
派遣元責任者の資格について
人材派遣事業のスタートに欠かせない資格は一つだけです。「派遣元責任者講習」を受講し「派遣元責任者」の資格を取得する必要があります。
また、実際に派遣元責任者の資格を得て職務に就くためには、3年以上の雇用管理の実務経験も必要です。管理経験を積むには、一般企業などで人事や労務の担当を3年以上経験する、もしくは職業安定行政や労働基準行政にて3年以上の業務経験が必要となります。
これらの経験年数については、20歳を迎えた時点より起算されるのが特徴です。仮に20歳未満での実務経験はカウントされないルールになっています。
労働者派遣事業許可について
派遣元責任者の資格を取得した後に、厚生労働省より「労働者派遣事業許可」という認可を取得します。これは、2015年より労働者派遣法が改正されたことで、すべての派遣事業者が許可を得ないと事業展開ができない決まりになったからです。
初回では3年、以降5年ごとに更新をすることが義務となっています。労働者派遣事業の許可を受けるためには、主たる事務所を管轄する都道府県労働局への申請が必要です。
また、許可を取得するための要件も決められています。
人材派遣業の許可に必要な要件

人材派遣業務を開始するためには、資格取得後に労働者派遣事業許可を得ることになりますが、そのための要件が決められています。ここでは、人材派遣業務の開業で不可欠な要件について解説しましょう。
必要な基本的要件
労働者派遣事業許可を希望する事業主は、まず「未成年者でないこと」および「欠格事由に該当しないこと」が基本的な要件です。
中でも、欠格事由としては以下の項目が該当します。
- 暴力団の構成員
- 破産している
- 禁錮以上の刑や一定の労働法等に違反、罰金刑以上に処せられ5年経過していない
これらに該当しないことが最低限の要件で、さらに別な要件が発生します。
財産や資産上での要件
人材派遣業を開業するには、一定の財産基準をクリアしている必要性があります。理由は、派遣社員への保護対策、派遣先企業への安定した供給がおこなえる基盤を担保する意味合いからです。
その基準は、以下のようになっています。
「基準資産額 ≧ 2000万円 × 事業所数」
- 基準資産額とは、資産の総額から負債の総額を控除した額(貸借対照表上での基準資産額)のことで、その額面が2000万円×事業所数以上あること
「基準資産額 ≧ 負債 ÷ 7」
- 基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
「自己名義現金預金額 ≧ 1500万円 × 事業所数」
- 事業資金として自己名義の現金・預金額が、1500万円×事業所数以上であること
事業所の広さと立地
人材派遣業務を開業する場所に関する立地条件にも決まりがあります。
以下の内容をクリアしている必要があるでしょう。
- 事業使用面積が概ね20㎡以上あること
- 使用目的は賃貸借契約書の目的と一致し事務所用途であること
- 事業所の独立性が保たれていること
- 風俗営業や性風俗特殊営業などが密集する好ましくない位置にないこと
個人情報管理
人材派遣業では、個人情報保護法に基づいた適正な管理と、労働者情報の保護措置を制定することも義務とされています。個人情報の取り扱い対象の職員の範囲、教育、取扱規定、苦情処理窓口設置、苦情への確実な処理、といった規定も必要です。
専ら派遣の禁止
人材派遣業では、「専ら派遣(もっぱらはけん)」が禁止となっています。
専ら派遣とは、派遣先企業での派遣スタッフの割合が異常に多くなって大部分を占める場合です。具体的な定数は決められていませんが、およそ8割程度を超えてはなりません。
このような状態に陥るのは、特定の会社のみに労働者を派遣してしまう場合が考えられるでしょう。例えば、とあるグループ企業に派遣する場合でも、割合を全派遣労働者の総労働時間8割以下への制限があります。
また、7割に達した場合、その時点より行政指導が入ることになるでしょう。
その他の要件
他にも、人材派遣業の管理要件には以下の項目などがあります。
- 労働保険・社会保険の適用など、派遣社員の福祉にも増進を見込むこと
- 派遣社員への、不当による精神および身体の自由を拘束しないこと
- 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせないこと
- 派遣元事業主が名義貸しでないこと
- 外国人には、一定の在留資格を有すること
- 教育訓練施設の設備、実施責任者の配置など、能力開発体制があること
- 教育訓練上での派遣社員からの費用徴収をしないこと
人材派遣業の許可申請に必要な書類
人材派遣業の許可申請の際には、事業所についての書類をはじめ、派遣元責任者としての書類、財務に関する書類といった、数種類の書類提出が必要となります。宛先は、主たる事務所を管轄する都道府県労働局です。
では、それらのおもな必要書類について解説していきましょう。
法人と個人事業主に共通した必要書類
人材派遣業務の形態として法人・個人事業主の双方で共通に提出すべき書類は、以下のとおりです。
- 事業所の使用権を証する書類
- キャリア形成支援制度などを証する書類
- 派遣元責任者の住民票の写し
- 個人情報適正管理規程
- 就業規則
- 事業所のレイアウト図
法人の場合の提出書類
法人として開業するにあたって、その特有の提出書類は以下のとおりです。
- 定款または寄付行為
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写しおよび履歴書
- 直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書
- 直近の事業年度における法人税の確定申告書の写し
- 法人税の納税証明書
個人事業主の提出書類
個人事業主として開業する場合に、特有の提出書類は以下のとおりです。
- 住民票の写しおよび履歴書
- 直近の納税期での所得税の確定申告書の写し
- 納税証明書
- 貸借対照表と損益計算書
- 不動産の登記事項証明書および固定資産税評価額証明書
- 預金残高証明書
人材派遣事業の開業で考えられるリスクや注意点
人材派遣業をスタートさせるには、さまざまな手続きがあることで複雑化しやすいことがデメリットです。その際のリスクや注意点についても、あらかじめ考慮する必要があります。
ここでは、開業に向けての考えられるリスクと注意点を解説します。
人材派遣業の開業でのおもなリスク
人材派遣事業を開始した際に考えられる代表的なリスクとしては、やはり資金繰りに関する悩みです。例えば、派遣先企業からの入金遅れ、派遣先企業の経営状況悪化、競合他社との関係性などで、思ったよりも経営が上向かない状態に陥るリスクです。
また、派遣社員の求人が上手くいかず人材不足になることや、派遣期間制限や派遣禁止業務との折り合い、育成コストなど人事的な問題点が起こりやすいことも考えられます。
人材派遣業の開業での注意点
人材派遣業のスタートでの注意点も、考えられるリスクとともにクリアしておく必要があります。
まず、労働者派遣事業の許可を取得する際には、事務所ごとの基準資産額2000万円以上の準備が必要です。そのための準備金を確実に確保できているかどうかにかかってきます。また、フルタイム勤務で1年以上の雇用見込みがある派遣労働者には、毎年8時間以上の教育訓練実施が義務となっています。
派遣スタッフへの教育訓練の提供とその資金も必要です。教育訓練は、有給であり無償でおこなう必要があるでしょう。
さらに、派遣先としてふさわしくない業務もあります。港湾、建設、警備、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などの「士業」は、派遣法の適用範囲から除外視され、派遣が禁止されていることを念頭に入れておきましょう。
まとめ
人材派遣事業の市場規模は、2023年度の事業者売上高ベースで9兆2,800億円とされています。(出典:人材ビジネス市場に関する調査を実施(2024年)| 矢野研究所)
年々増加傾向にあり、派遣事業は今後も広がる予想です。事業のスタートアップには、資格や厚生労働省の認可を取得する必要があります。認可を得るためのステップを理解し、入念な事前準備が必須です。手続きで慌てないためにも、確実な準備をしていきましょう。
労務の知識を動画で学べるe-JINZAI for Business
組織のバックオフィス業務の中で、最も高い比率を占めるのが「労務」。そのフィールドは幅広く、労働に関する事務処理のみならず、ハラスメントやメンタルヘルス対応、労働トラブル対応なども含まれます。 ビズアップ総研の労務研修では、労働者派遣法を含む労務の基本的な知識、業務について学習した上で、労働に関する様々なリスクとその管理方法や予防策を動画でわかりやすく学ぶことができます。
詳細・お申し込みはこちら