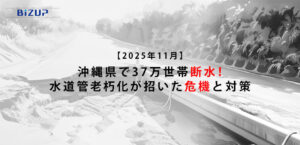【2026年1月施行】取適法とは?下請法改正のポイントと背景

KEYWORDS コンプライアンス
2026年1月、「取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)」が施行されます。
この新しい法律は、長年中小企業を守ってきた「下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)」を抜本的に見直し、名称・用語・制度体系を大きく変えるものです。今回の改正は単なる法律名の変更ではなく、「取引関係の考え方そのものを時代に合わせて再定義する」大きな制度改革と位置づけられています。
この記事では、法改正の背景と新旧制度の違いを中心に、押さえておくべきポイントを整理します。
目次
- 下請法とは:従来の目的と構造
- 改正の背景:時代に合わなくなった「下請」という構造
- 新法「取適法(中小受託取引適正化法)」の概要
- 実務への影響:委託・受託双方の対応が必要に
- eラーニングで法改正やコンプライアンスを学ぶ
- まとめ


コンプライアンス研修
動画数|27本 総再生時間|310分
企業不祥事やSNS炎上など多様なリスクに対応するため、法令遵守にとどまらず企業倫理や社会的規範まで含めた広義のコンプライアンスを実践的に学ぶ研修です。全階層で必要な行動基準を実例とともに身につけ、コンダクト・リスクやESG経営にも対応します。
動画の試聴はこちら下請法とは:従来の目的と構造
1956年に制定された下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、主に「親事業者」と「下請事業者」という立場の非対称な関係を前提とした法律です。
製造業などを中心に、大企業が中小企業に対して不当な取引を行うことを防ぐ目的で運用されてきました。
禁止行為には、たとえば次のようなものがあります。
- 受注後の一方的な値引きや返品
- 納品後の支払い遅延
- 理由のない取引内容の変更
これらは公正取引委員会と中小企業庁によって監視され、勧告や指導の対象となってきました。
ただし、制度上は「資本金の大きい発注者」と「比較的小規模な下請側」という構図を前提としており、現代の多様な取引形態には十分に対応できていませんでした。
改正の背景:時代に合わなくなった「下請」という構造
本改正の出発点は、社会全体の取引構造の変化にあります。経済のデジタル化や働き方の多様化が進む中で、旧来の「下請」という概念が現実にそぐわなくなってきました。
ここ数年で、企業間取引や働き方は大きく変化しました。クラウドソーシング、業務委託、副業・兼業など、個人や小規模事業者がオンラインで受注する形態が増加しています。こうした新しい取引では、従来の「元請-下請」という上下関係ではなく、対等なパートナー契約が一般的です。
このような社会構造の変化に合わせ、下請法を「時代に合う形で再設計する」必要が生じました。これが、2026年1月に施行される新法「中小受託取引適正化法(取適法)」の誕生につながっています。
新法「取適法(中小受託取引適正化法)」の概要

ここでは、新法の目的や変更内容を具体的に整理します。旧下請法から何が変わり、どんな理念で再構築されたのかを理解することがポイントです。
今回の改正では、法律名が「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託取引適正化法」に変更されます。名称変更には、「上下関係を前提としない新しい取引モデルを法制度として支える」という明確なメッセージが込められています。
新法は、旧下請法の基本的な仕組みを引き継ぎつつ、次の3つの観点で構造を再設計しています。
法律の目的を「保護」から「適正化」へ
旧法では「下請事業者の保護」という性格が強く、特定の力関係を前提とした制度でしたが、新法では視点を広げ、取引全体の公正性と透明性を確保することを目的としています。優越的な立場にある委託事業者による不当な行為を規制し、中小受託事業者の利益を守るとともに、委託側にとっても健全で持続可能な取引環境を整える意義が重視されています。
法律用語の見直しと立場の再定義
旧法で使われていた「親事業者」「下請事業者」といった上下関係を示す表現は廃止され、「委託事業者」「中小受託事業者」といった中立的な言葉に置き換えられます。また、「下請代金」は「製造委託等代金」となり、契約の本質を明確に示す表現に改められます。
対象取引の拡大とデジタル取引への対応
新法では、従来の製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託に加え、特定運送委託も対象になります。
さらに、電子契約やクラウド上での業務委託など、デジタル取引も正式に法的対象とされます。これにより、書面ではなく電子的記録で契約を結ぶケースも、明確に法の保護下に置かれるようになります。
・改正前後の比較 一部抜粋
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 名称 | 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
| 通称 | 下請法 | 取適法 |
| 主要用語 | 親事業者/下請事業者/下請代金 | 委託事業者/中小受託事業者/製造委託等代金 |
| 対象取引 | 製造委託/修理委託/情報成果物作成委託/役務提供委託 | 特定運送委託も加わる |
| 契約形態 | 書面契約が中心 | 電子契約・クラウド契約も可能に |
このように、法律名・用語・制度の方向性すべてが見直されます。特に注目すべきは、「下請」という言葉を排除し、取引の対等性を法的に明確化した点です。
実務への影響:委託・受託双方の対応が必要に
委託事業者が取り組むべきこと
- 契約書面の整備(電子契約を含む正式な条件提示)
- 委託業務の支払い条件・修正対応範囲の明文化
- 内部統制・コンプライアンス研修の実施
委託側は、形式的に契約を交わすだけでなく、条件変更や納期調整を公正に管理する体制づくりが求められます。
受託事業者の備え
- 契約内容の確認と履歴の保存(電子証跡を含む)
- 不当要求への相談体制(中小企業庁・商工会議所等)
- 自社の取引慣行を見直し、法改正に沿った運用へ
受託側も契約条件を自ら把握し、適切に管理する姿勢が求められます。
eラーニングで法改正やコンプライアンスを学ぶ
法改正が続く中で、企業や事業者には「必要な知識を自分のペースで確実に身につける仕組み」が求められています。その点で、eラーニングを活用した学習は非常に有効です。時間や場所にとらわれず、重要なポイントを体系的に学べるため、業務の合間でも無理なく継続できます。
また、コンプライアンスは一度学べば終わりではなく、定期的なアップデートが欠かせません。eラーニングなら、最新の法改正や実務に必要な知識を継続的にキャッチアップでき、組織全体のリスク管理にも大きく貢献します。
企業の社内研修や、フリーランスの自主学習の一環として取り入れることで、公正取引の意識定着やトラブル防止に大きく役立ちます。
まとめ
2026年1月から施行される「取引適正化法(中小受託取引適正化法)」は、単なる下請法の延長ではなく、取引の在り方そのものを変える法律です。
下請構造から脱却し、発注者・受託者が対等な立場で取引を行うことを制度的に支える点が最大の特徴といえるでしょう。今後、契約の電子化や委託業務の多様化がさらに進む中で、この法改正は「取引の透明性」を確保する重要な基盤となります。
企業も個人も、これを機に取引ルールを見直し、より健全で持続的なビジネス関係を築いていくことが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、最新の法令を参照のうえ専門家にご相談ください。