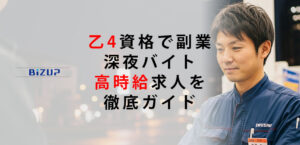商標登録が難しい…と悩むあなたへ|自力で進められる力が身につく!

KEYWORDS 法務・コンプライアンス
新商品やサービスを立ち上げるとき、まず考えるのが「名前をどうするか」。
キャッチーで覚えやすく、かつ競合とかぶらない名称を見つけるのは簡単ではありません。
ですが、実はそこで終わってしまうケースが多いのです。
「思いついた名前でサイトを作って、SNSで広報もして…」
ところがある日、似たような名前で販売している他社を見つけたり、
「その名称は当社の登録商標です」と警告を受けたりすることも。
こうした事態を防ぐカギとなるのが、商標登録です。
この記事では、
- 商標登録の基本
- 登録できるもの・できないもの
- 手続きの流れと所要期間
- 費用感や必要書類の概要
などを、知識ゼロからでもわかりやすく整理していきます。
登録の判断は早いほど安心です。まずは、基礎をしっかり押さえておきましょう。
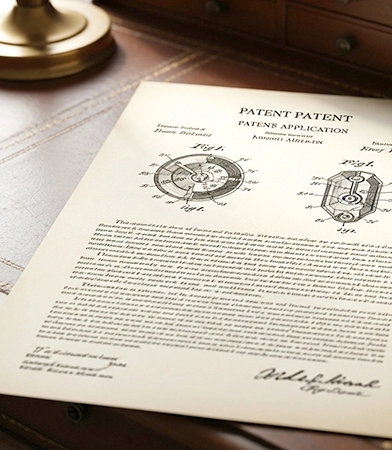

特許調査・特許取得実践研修
動画数|12本 総再生時間|183分
特許の収集・分析から出願・権利化までを体系的に学ぶ実践講座です。技術動向調査や明細書の読み解き方、審査情報の活用に加え、発明発掘や共同研究時の注意点も学べ、企業の特許戦略に役立ちます。
動画の試聴はこちら目次
- 商標登録とは?中小企業が最初に知っておきたいこと
- 登録できるもの・できないものの境界線
- 実はシンプル?商標登録の流れと期間
- 費用はいくら?申請に必要な書類とは
- 「自分でできるか不安…」という方へ
- まとめ|商標登録はブランド保護の“先手”
商標登録とは?中小企業が最初に知っておきたいこと
ブランド名やロゴを“守る仕組み”が商標権
商標とは、商品やサービスの「名前」「ロゴ」「マーク」などの目印です。
商標登録をすることで、それを法的に保護し、他人に勝手に使わせない権利=商標権を得られます。
たとえば、飲食店名、化粧品のブランド名、商品のパッケージロゴなど。
こうした「識別される名称」は、今や大企業だけでなく、中小企業にとっても重要な経営資産です。
競合が多い市場ほど、ネーミングやブランドが持つ価値は大きくなります。
それを守る手段として商標登録は欠かせません。
| 権利名 | 守る対象 | 登録の必要 | 権利期間 |
|---|---|---|---|
| 商標権 | 名前・ロゴ・マーク | 必要 | 登録日から10年(更新可能) |
| 特許権 | 発明・技術 | 必要 | 出願日から20年 |
| 意匠権 | 形状・デザイン | 必要 | 出願日から20年 |
| 著作権 | 文書・音楽・映像などの創作物 | 不要(自動で発生) | 作者の死後70年(法人は公表後70年) |
「登録しなくても使える」は大きな誤解
「自分が先に使っているから問題ない」と思う方も多いのですが、
実際には、先に出願して登録した人が権利を持つ(先願主義)というルールが原則です。
そのため、たとえ先に商品化していても、他社に商標を取られてしまえば、
「使えなくなる」可能性もあり、最悪の場合は使用差止請求や損害賠償請求に発展することもあります。
また、無意識に他人の登録商標と類似する名前を使ってしまった場合、
知らなかったでは済まされない法的トラブルに発展することも。
こうしたリスクを避けるためにも、早めの知識武装が必要です。
登録できるもの・できないものの境界線
商標登録の相談でよくあるのが、「会社名と商品名、どちらを先に登録すべきか?」という疑問です。
結論から言うと、ビジネスの軸になるほうを優先するのが基本です。
- 自社のブランドを前面に出す戦略(例:無印良品、ユニクロ)→ 会社名(ブランド名)を優先
- 個別の商品シリーズで認知を拡大したい(例:iPhone、ポカリスエット)→ 商品名を優先
また、最近ではSNSアカウント名やドメイン名とも重複・衝突が起きやすいため、全体のネーミング戦略と照らし合わせて判断することが重要です。
登録できる商標のバリエーションに驚く
商標登録の対象は多様です。文字やロゴだけではなく、以下のような形でも登録が可能です。
商品名・ブランド名
例:無印良品
ロゴ・アイコンなど
独自のパッケージ形状など
例:キットカットの形
メロディ、ジングルなど
例:企業のサウンドロゴ
特定の配色
例:Tiffanyの青
動きのある映像・視覚効果も対象
意外と幅広いと思われるかもしれませんが、すべては「識別力があること」が前提です。
登録できないものもある
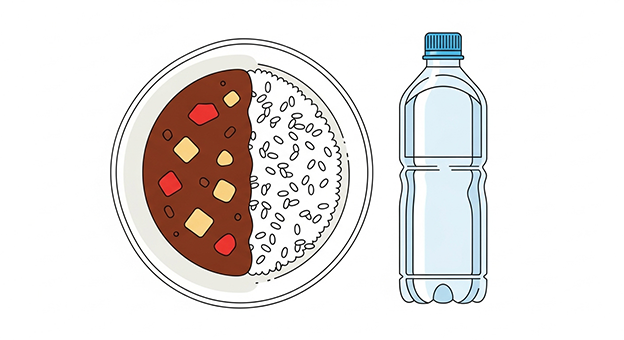
一方で、登録が難しいケースもあります。
代表的な例がこちらです。
- 一般的すぎる言葉(例:「カレー」「水」など)
- 単なる説明文(例:「おいしいお弁当」など)
- 地名や人名のみ(例:「大阪商店」「田中食品」など)
また、他社がすでに似た名前で登録している場合は、類似商標として却下される可能性もあります。
たとえば、「東京ばな奈」と「大阪プチバナナ」の商標訴訟のように、混同を避ける判断がされるケースもあります。
登録の成否は微妙な表現や業種区分でも変わってきます。
先に登録状況を調査するだけでも、リスクを大きく減らせます。
実はシンプル?商標登録の流れと期間
手続きと聞くと「面倒そう」と思われがちですが、全体の流れは比較的シンプルです。
以下が一般的なステップです。
- 出願内容を決定(商標・商品区分など)
- 特許庁に出願
- 審査(約9〜14ヶ月)
- 登録査定 → 登録料の納付
- 商標登録完了・公告
ここまでの期間は平均して1年前後。
もちろん、内容が明確であれば半年ほどで登録されることもあります。
すでに使用している実績がある場合や、模倣リスクが高いと判断される場合には「早期審査制度」も利用できます。これは、出願から数ヶ月で審査が行われる制度で、特にスタートアップや新規事業では活用価値が高いと言えます。
費用はいくら?申請に必要な書類とは
商標登録には「出願するだけ」では済みません。登録にかかる費用は大きく3つに分かれます。
| 費用項目 | 金額(1区分あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 出願料 | 12,000円 | 願書提出時、印紙代として支払い |
| 登録料 | 28,200円(5年) 55,200円(10年) |
審査通過後に選択して支払い |
| 更新料 | 登録料と同額 | 10年ごとに再納付 |
これに加え、複数区分を登録する場合は費用が加算されます。たとえば飲食と雑貨で使いたい場合、区分が2つになるため、全体費用も倍になります。
書類は意外とシンプル。でも記載ミスは命取り
必要書類は以下のとおりです。
- 商標登録願(書式あり)
- 商標の図案(ロゴなどがある場合)
- 商品・サービスの区分の指定
- 手数料(印紙)
見た目はシンプルでも、「どの区分にするか」「表記をどう記載するか」で審査結果が大きく変わるため、実務経験がないと迷いやすい部分でもあります。
商標出願では「商品・サービスの区分(=クラス)」を指定する必要があります。
これは、自社の商標をどの業種分野で使うかを明確にするステップです。
たとえば「パン屋」を運営する場合、以下のような区分に該当します。
- 第30類:パン、ケーキ、菓子類
- 第43類:飲食店、カフェ
商品だけでなく、サービスとしても展開するなら複数区分の登録が必要になります。
また、アパレル事業で「服」と「靴」の両方を展開する場合、それぞれ別の区分になります(第25類など)。
この「区分選び」を誤ると、「守りたかった商品に商標権が及ばない」という事態にもなりかねません。
「自分でできるか不安…」という方へ
「手続きは難しくなさそう。でも、ミスが怖い」「弁理士に頼むには予算が厳しい」
――そんな声を多く聞きます。
実際、商標登録は個人で出願することも十分可能ですが、初めての場合は
- 「この表記でいいのか?」
- 「区分を間違えてないか?」
- 「すでに類似登録がないかどうか」
など、細かな判断が必要になります。
まずは基本を知ることで「何を相談すべきか」が見えてくる
専門家に丸投げする前に、最低限の知識を自分で持っておくことは、出願の成否だけでなく、コストの最適化にもつながります。最近では、動画やスライド形式で商標登録の基本や失敗事例を体系的に学べる教材も増えています。いきなり出願するのではなく、「知ってから決める」ことで、時間もお金も無駄にしなくて済みます。
商標登録を怠ったことで起きた実例
▶ 事例1:「白い恋人」に似た商品名が訴訟に
「白い恋人(石屋製菓)」に類似した名前として「面白い恋人(吉本興業・サンタプラネット)」が販売され、商標権侵害で訴えられました。最終的には和解となりましたが、パロディや言葉遊びであっても訴訟リスクは存在することが明確になった事例です。
▶ 事例2:商標を後出し登録されて使えなくなった
個人事業主Aさんが販売していたオリジナルアクセサリーブランド。SNSで人気が出たタイミングで、第三者にそのブランド名を出願されてしまいました。商標権は先願主義のため、本人が使用していても登録されていなければ権利を主張できないのです。
このようなトラブルは、年間を通じて少なくありません。
まとめ|商標登録はブランド保護の“先手”
名前やロゴは、商品やサービスの「顔」です。その顔が他社に奪われてしまったら、信用も売上も大きなダメージを受けることになります。商標登録は、単なる手続きではありません。将来の安心を買う“知的財産への先行投資”でもあります。
- 自社の商品やサービスに名前をつけた
- SNSやネット販売を始めた
- 類似ブランドを最近よく見かける
このような状況にひとつでも当てはまるなら、「自社の名前を守る準備」を早めに進めてみてください。まずは、商標登録の基本と流れを正しく知ることが最初の一歩です。商標登録が完了しても、5年以内に使っていなければ、取り消し審判を請求される可能性があります(不使用取消審判)。そのため、登録後も実際のビジネスで継続的に使用していくことが大切です。
また、商標に「®マーク(登録商標)」や「™マーク(商標)」をつけて使うことで、第三者へのけん制効果も期待できます。ただし、「®」は実際に登録されていなければ使えませんので、誤使用には注意しましょう。