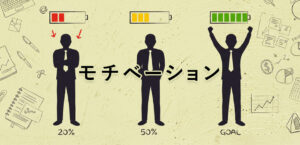大学の歴史と制度改革|職員が押さえておきたい基礎知識

KEYWORDS 教育機関
大学は、教育と研究の中心として、長い歴史を持つ機関です。その起源は中世ヨーロッパにさかのぼり、時代とともに進化しながら、現在の多様な高等教育の形へと発展してきました。日本の大学もまた、独自の変遷をたどりながら現代の制度を築いています。本記事では、大学の歴史を中世ヨーロッパ、近代ドイツ、アメリカ、日本の順に追いながら、その変遷と制度の変化を紹介します。
目次
中世ヨーロッパの大学の誕生
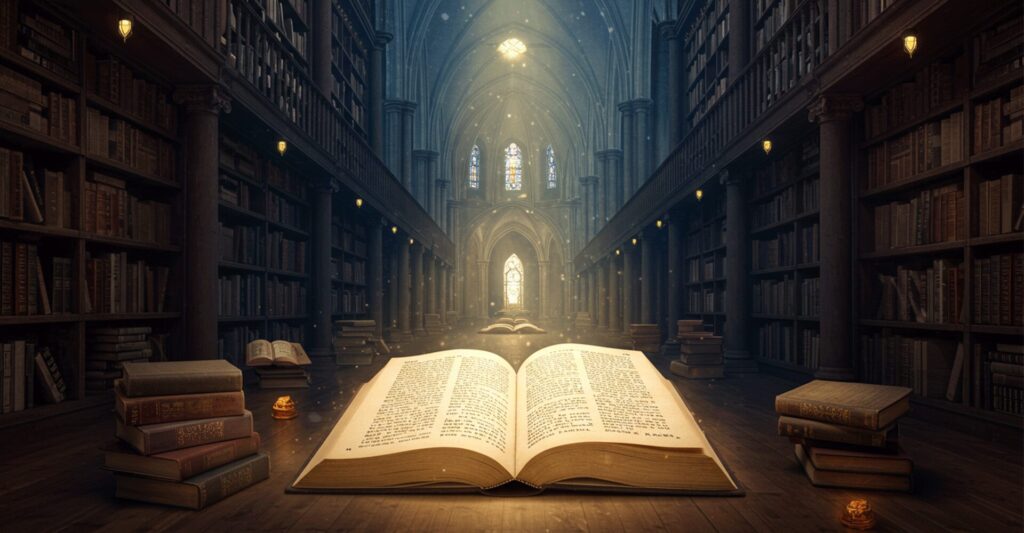
大学の起源:キリスト教と学問の発展
大学の起源は12世紀頃の中世ヨーロッパにさかのぼります。当時、キリスト教の影響が強く、学問の中心は修道院や大聖堂付属学校でした。ここでは、ラテン語を用いた神学や哲学が学ばれていましたが、次第に都市の発展とともに、より体系的な教育機関としての大学が形成されていきました。
ヨーロッパ最古の大学
中世ヨーロッパの大学は、学生と教師の共同体として誕生しました。その中でも特に有名なのが以下の大学です。
- ボローニャ大学(1088年設立・イタリア)
ヨーロッパ最古の大学とされ、法学の研究で知られています。ボローニャ大学は「学生が教師を雇う」という特徴を持ち、学生主体の大学運営が行われました。 - パリ大学(1150年頃設立・フランス)
神学の研究で有名で、学問の自由を重視しました。パリ大学は、教師たちの共同体として形成され、教授陣が大学の運営を主導しました。このモデルは後の大学制度に大きな影響を与えました。 - オックスフォード大学(1167年頃設立・イギリス)
イギリス最古の大学で、文法、修辞学、論理学などの自由七科を中心とした教育が行われました。
自由七科とリベラルアーツの起源
中世の大学では、教育の基本として「自由七科(リベラルアーツ)」が重視されました。これは、
- 三学(文法学・修辞学・論理学)
- 四科(算術・幾何学・天文学・音楽)
から構成され、特に哲学部(学芸学部)で教えられました。これが現在の「リベラルアーツ教育」の起源となっています。
学位制度の確立
中世大学では、現在の学位制度の原型も作られました。
- 学士(Baccalaureus):基礎教育を修了した者に与えられる
- 修士(Magister):より高度な学問を修め、教鞭をとる資格を持つ
- 博士(Doctor):専門分野で最高の学位として認められる
これらの制度は、現在の大学の学位体系の原型となりました。
近代ドイツの大学の発展
18世紀から19世紀にかけて、大学は単なる教育機関ではなく、「研究機関」としての役割を強めていきました。その転換点となったのがベルリン大学(現在のフンボルト大学・1810年設立)です。ベルリン大学の創設者であるヴィルヘルム・フォン・フンボルトは、「教育と研究の統一(Bildung)」という理念を打ち出しました。この理念の下で、大学は単に知識を伝える場ではなく、新しい知識を生み出す場として位置付けられました。
フンボルト型大学の特徴
- 研究重視
学生は受動的に学ぶのではなく、教授とともに研究に参加し、知識の創造に貢献することが求められました。 - 専門化の進展
各学問分野が細分化され、哲学、自然科学、社会科学、人文学などの領域が確立されました。 - 学術論文と学会の発展
研究成果を論文として発表し、学術雑誌や学会が発展しました。これにより「科学者」という職業が確立しました。
フンボルト型大学のモデルは、ドイツ国内にとどまらず、フランスやアメリカの大学にも影響を与え、研究大学の基盤となりました。
アメリカにおける大学制度の発展
ハーバード大学と単位制度の導入
19世紀後半、アメリカの大学制度は大きく変革を遂げました。その中で特に重要なのが、ハーバード大学による「単位制度」の導入です。従来のヨーロッパの大学では、固定されたカリキュラムに基づいて学ぶスタイルが一般的でしたが、ハーバード大学は選択科目制度を導入し、学生が自由に履修科目を選べるようにしました。これにより、学生の興味やキャリアに応じた柔軟な学習が可能になりました。
ジョンズ・ホプキンス大学と大学院制度
アメリカの大学制度をさらに進化させたのが、ジョンズ・ホプキンス大学(1876年設立)です。ジョンズ・ホプキンス大学は、大学院(Graduate School)の概念を導入し、博士課程の研究を重視するモデルを確立しました。この大学院制度により、アメリカの大学は高度な研究を行う場としての地位を確立し、多くの研究者を育成することに成功しました。
一般教育の導入
アメリカの大学は、専門教育だけでなく、市民としての教養を身につけるための「一般教育(General Education)」を重視しました。これは、学生が幅広い知識を学び、批判的思考力を養うことを目的としています。この一般教育の考え方は、日本の戦後の大学制度にも影響を与え、教養教育の基盤となりました。
e-JINZAI for universityで学ぶ『大学の歴史と政策・制度』
この研修では、まず、戦後以降の大学の歴史をおさらいし、つぎに、設置認可、法人制度、質保証などの大学の制度について学びます。さらに、学校教育法、大学設置基準、学位規則などの大学の関係法令をおさえた上で、文部科学省などによる大学政策の基礎知識を習得します。
詳細・お申し込みはこちら日本の大学の歴史
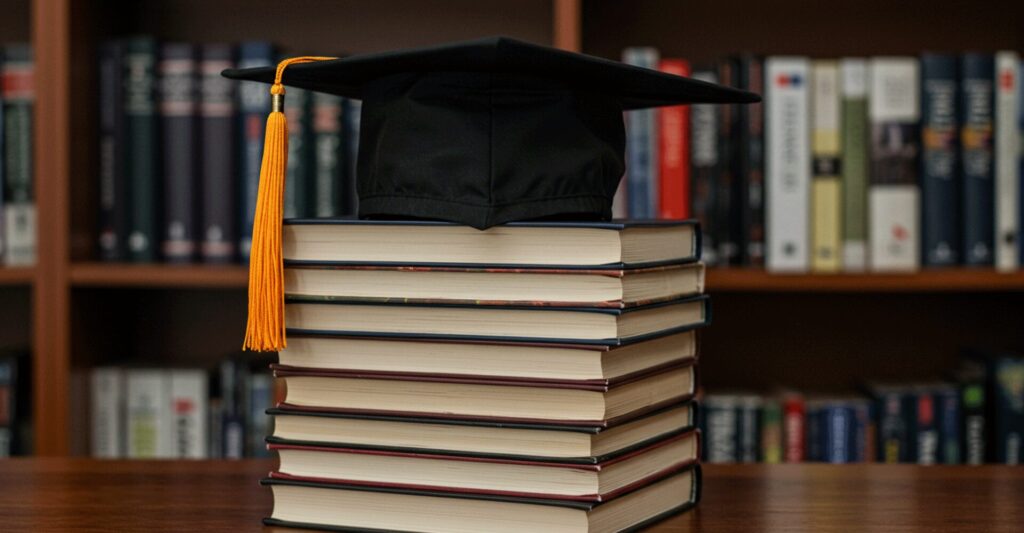
明治時代の大学制度の確立
日本における近代的な大学制度は、1877年の東京大学の設立によって始まります。江戸時代の藩校や私塾とは異なり、明治政府主導で創設された東京大学は、国家の発展に貢献する人材を育成する機関としての役割を担いました。
明治期の大学制度は、主にドイツの高等教育制度を参考にして整備され、専門教育を重視する特徴がありました。特に、法学・医学・工学などの実学が重視され、大学は官僚や専門職の養成機関としての性格を強めました。また、講座制を導入し、教授ごとに独立した研究や教育が行われる仕組みが確立されました。こうした制度のもとで、日本の大学は近代国家の発展を支える知的基盤として成長していきました。
戦前の大学制度
帝国大学制度の確立
明治時代後半には、日本各地に大学が設立され、帝国大学制度が確立されます。東京大学は1886年に「帝国大学」に改称され、その後、京都帝国大学(1897年)をはじめとする計7つの帝国大学が設立されました。帝国大学は、当時の日本における最高学府として位置づけられ、特に以下の3つの役割を果たしました。
- 官僚・専門職の育成
国家の指導者となるエリートを育成することが目的でした。これは、明治政府が強い中央集権体制を築こうとした背景に基づいています。 - 学術研究の推進
西洋の最新学問を導入し、科学や技術の発展を促しました。特に工学、医学、法学などの分野で重要な研究が進められました。 - 国際競争力の向上
日本は欧米諸国と肩を並べるために、学問の発展を国家戦略の一部として位置付けました。これにより、大学は国家主導の教育機関として強い影響を受けることになりました。
この時代には、帝国大学以外にも、私立大学(例:早稲田大学、慶應義塾大学、同志社大学)や、高等専門学校(旧制高等学校)が整備され、大学教育の裾野が広がりました。
戦前の大学の特徴
- エリート教育が中心(庶民が大学へ進学するのは難しかった)
- 学年制と講座制が主流
- 国家の強い統制下にあった
- 女子の大学進学は限定的(津田塾大学など一部の女子教育機関を除く)
戦後の大学制度改革
1949年の大学改革
第二次世界大戦後、日本の大学制度はアメリカの影響を受けて大きく変わりました。特に1949年の教育改革によって、戦前の大学制度は大きく改編されました。
この改革の主なポイントは以下の通りです。
- 旧制高等教育機関の統合
戦前には、大学、旧制高等学校、専門学校、師範学校など、さまざまな高等教育機関が存在していました。これらを統合し、「4年制大学」として一本化しました。 - 新制大学の設立
戦前はエリート層しか大学に進学できませんでしたが、戦後はより多くの人が大学に進学できるようになりました。これにより、私立大学が急増し、全国的に高等教育の機会が拡大しました。 - 一般教育の導入
戦前の大学は専門教育中心でしたが、戦後はアメリカの「リベラルアーツ」の考え方を取り入れ、一般教育(教養科目)が導入されました。これにより、1・2年次に幅広い科目を学ぶカリキュラムが整備されました。
戦後の大学の特徴
- 戦前の「専門教育中心」から「一般教育+専門教育」へ転換
- 高等教育の大衆化
- 私立大学の急増
- 女子の大学進学が一般化
事前規制から事後チェックへ
1991年の大学設置基準改正
1991年、日本の大学制度は大きな転換点を迎えます。それまで、大学は「大学設置基準」によって厳格に規制されていましたが、この年の改正により、大学の自由度が高まりました。具体的には、
- 大学が独自のカリキュラムを編成できるようになった
- 一般教育、専門教育、外国語、保健体育といった授業区分が廃止された
- 卒業要件が単位数(124単位以上)のみで規定されるようになった
この改正により、大学はより柔軟に教育内容を設計できるようになりました。
自己点検・評価制度の導入
大学の自由度が増す一方で、教育の質を保証するための制度も必要とされました。
そこで、自己点検・評価制度が導入されました。
- 1991年:「自己点検・評価」が努力義務として導入
- 1999年:「自己点検・評価」が義務化
- 2004年:「認証評価制度」が導入され、大学は第三者機関による評価を受けることが義務付けられる
これにより、大学は「事前規制から事後チェックへ」と移行し、各大学が自ら教育の質を高める努力を求められるようになりました。
まとめ
大学は、中世ヨーロッパで誕生し、近代ドイツで研究機関としての役割を強め、アメリカで自由なカリキュラムや大学院制度を確立しました。そして、日本では明治時代に大学制度が整備され、戦後の改革を経て、より柔軟な運営が可能な形へと発展してきました。
現在の大学は、教育の質を保証するために自己点検や認証評価制度を導入し、常に改善を求められています。こうした制度の変遷を理解することは、大学が果たすべき役割を考えるうえで非常に重要です。