ユーザー体験を変える!システム開発の新常識UX
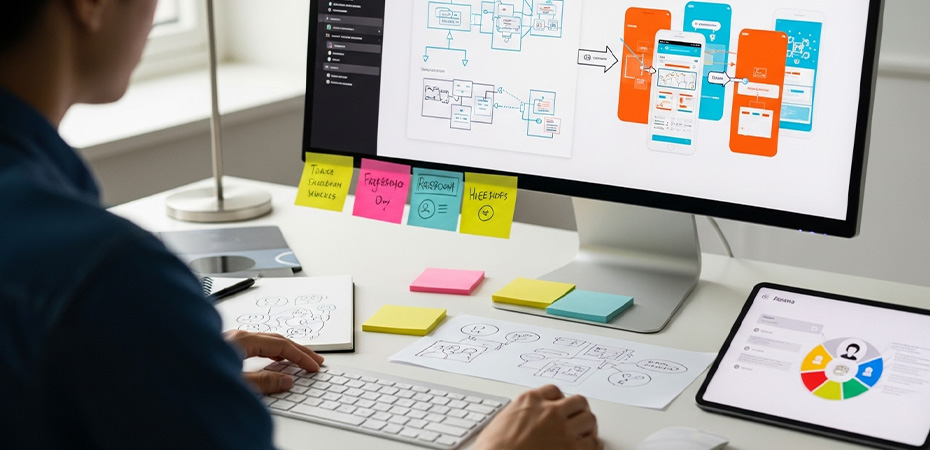
KEYWORDS UIUX
近年、情報システム部門における役割は大きく変化しています。従来はシステムの安定稼働やコスト削減が中心でしたが、今では「ユーザー体験(UX)」の質が事業全体の成果に直結するようになりました。顧客向けのWebサービスだけでなく、社内向けシステムにおいても、使いにくさが業務効率を落とし、不満を引き起こす原因となります。
特に若手社員やUXデザインに関心のある担当者にとって、「UXをどうシステム開発に組み込むか」は避けて通れない課題です。本記事では、UXの基本理解からフレームワーク、改善の進め方までを整理し、学習を加速させるeラーニングの活用法について解説します。
目次


システム化におけるユーザー体験(UX)
動画数|5本 総再生時間|44分
情報システム部門におけるユーザー体験(UX)の重要性と設計手法を体系的に学べます。基本概念からUI設計、フレームワークを活用した改善プロセスまで網羅し、プロトタイピングや評価方法も含めて実務に活かせるUXデザインを習得できます。
動画の試聴はこちらユーザー体験(UX)とは何か
基本的な定義と特徴
ユーザー体験(UX:User Experience)とは、ある製品やサービスを利用することでユーザーが得る体験や感情全般を指します。これは単なる機能や操作性にとどまらず、利用前の期待、利用中の心理状態、利用後の満足感までを含む広い概念です。
例えば、旅行に行くときに「飛行機と車のどちらを選ぶか」を考える場面を想像してみてください。移動手段を選ぶ際の基準は、時間やコストだけではなく、「空からの景色を楽しみたい」「有名なサービスエリアに立ち寄りたい」といった感情的な価値にも左右されます。このように、体験は数値化しづらい心理的な要素を多分に含んでいるのです。
UXが業務や顧客に与える影響
システムにおけるUXが悪いと、次のような問題が発生します。
- 社内システムの場合:入力が複雑で作業時間が増え、業務効率が下がる
- 顧客向けサービスの場合:再訪率や利用者数が減少し、売上や戦略目標に悪影響を及ぼす
逆に、UXが適切に設計されると、業務効率が上がり、顧客満足度が高まり、競合との差別化にもつながります。つまりUXは「快適さ」だけではなく、企業にとっての重要な競争力の源泉なのです。
UXの重要性と課題
システム開発にUXを組み込む難しさ
情報システム部門にとっての悩みは、UXをどの段階で、どのようにシステム開発プロセスに組み込むかという点です。要件定義や設計段階では、つい「機能が動けば良い」という発想に偏りがちです。しかし、後工程でUXを考慮しようとすると修正コストが膨大になり、プロジェクト全体のリスクが高まります。
さらに、UXは「正解が一つに定まらない」点も難しさの要因です。ユーザーによって価値を感じるポイントが異なるため、単純にチェックリストで判断することができません。そのため、担当者は心理学や人間工学などの幅広い知識を参考にしながら、ユーザーの行動や感情を理解する姿勢が求められます。
UXを無視した場合のリスク
UXを軽視すると、次のような結果につながる可能性があります。
- 登録フォームが複雑で入力に時間がかかる → ユーザーが離脱する
- 業務システムが直感的でない → 社員の不満が高まり、生産性が低下する
- 顧客サポートが分かりにくい → 信頼を失い、リピーターが減少する
このようにUXを無視することは、単なる「不便さ」ではなく、売上や事業継続にまで影響を与えるリスクを含んでいます。
UX設計のフレームワーク
ハッセンツァールのUXモデル
ドイツの研究者ハッセンツァールは、UXを「実用的属性」と「快楽的属性」に分けてモデル化しました。前者は効率や有用性といった機能面、後者は楽しさや満足感といった感情面を指します。システム開発においても、この両面を意識することで「使える」だけでなく「使いたくなる」サービスを実現できます。
UX白書の期間モデル
UX白書では、ユーザー体験を時間軸で捉えています。利用前の期待(予期的UX)、利用中の体験(一時的UX)、利用後の振り返り(エピソード的UX)、そして利用を積み重ねる中で形成される累積的UXの4段階です。これにより「体験は使っている瞬間だけではない」という理解が得られます。
ISO 9241-11に基づくユーザビリティ
国際標準化機構(ISO)が定義するユーザビリティでは、「有効さ」「効率」「満足度」という3つの観点が示されています。これはUXの評価を定量的に行う際の指針となり、システム開発プロジェクトでの改善ポイントを明確にするのに役立ちます。
UX改善の進め方
ユーザー調査・モデリング
UX改善の第一歩は「ユーザーを知ること」です。アンケートやインタビュー、行動観察などの調査を通じて、ユーザーがどのような行動をとり、どんな点に価値を見いだしているのかを可視化します。
この情報を「ペルソナ」や「カスタマージャーニーマップ」といった手法で整理すると、ユーザー像や体験の流れが明確になります。情報システム部門にとっても、この段階でユーザーの声を具体化しておくことが、その後のシステム要件定義や設計に直結します。
コンセプト設計とシナリオ作成
調査で得た情報をもとに、どのような体験を提供するのかをコンセプトとして言語化します。例えば「顧客が比較検討をしやすい画面構成」や「現場作業を効率化するUI」など、シナリオ形式に落とし込むことで、実際の利用シーンに即した具体性が生まれます。
この段階では「どのユーザーが」「どんな行為を通じて」「どのような価値を得るのか」という3点を明確にすることが鍵です。
プロトタイピングと評価
| 観点 | 目的例 | シグナル例 | 指標例 |
|---|---|---|---|
| Happiness | 不満の低減と好意の醸成 | ポジティブな口コミ・問い合わせ減 | NPS、離脱数、クレーム数 |
| Engagement | 能動的な利用の促進 | 直打ちアクセス、再訪の増加 | 利用回数、投稿数、支払い率 |
| Adoption | 初回利用・導入の獲得 | 体験後の登録・導入 | 登録率、DL数、申込率 |
| Retention | 継続利用の維持 | 日常的な利用・解約の抑制 | 継続率、休眠率、解約率 |
| Task Success | タスク完遂のしやすさ | ミス・やり直しの減少 | 成功率、エラー率、完了時間 |
コンセプトが固まったら、実際に試作品(プロトタイプ)を作成し、ユーザーに試してもらいます。画面デザインや操作の流れを簡易的に見せるだけでも、改善点が浮かび上がります。
その上で、Googleが提唱した「HEARTフレームワーク」などを用い、ユーザーの幸福度、利用の継続度、タスク達成率といった指標で定量的に評価していきます。こうした検証プロセスを繰り返すことで、最終的に「使いやすく、価値が伝わる」システムが実現されます。
学習効果を高めるeラーニング講座

UX改善のプロセスは理論だけでは理解しづらく、実践的なトレーニングが不可欠です。そこで効果的なのがeラーニング講座です。
この講座では、
- UXの基本概念を整理する
- 実際の改善ワークを通じて問題点を発見する
- フレームワークを活用して改善策を検討する
- プロトタイピングや評価の流れを理解する
といった学びを体系的に得ることができます。特に情報システム部門の担当者や若手社員にとっては、単なる知識習得にとどまらず「業務で使えるスキル」として定着しやすい点が魅力です。
また、学習は自分のペースで進められるため、日常業務と並行しながら効率的に取り組めます。UX改善に挑戦したいが時間や環境に制約がある方にとって、強力なサポートとなるでしょう。


システム化におけるユーザー体験(UX)
動画数|5本 総再生時間|44分
情報システム部門におけるユーザー体験(UX)の重要性と設計手法を体系的に学べます。基本概念からUI設計、フレームワークを活用した改善プロセスまで網羅し、プロトタイピングや評価方法も含めて実務に活かせるUXデザインを習得できます。
動画の試聴はこちら受講によって得られる効果
業務効率と生産性の向上
UXを意識したシステムは入力や操作が直感的になり、社員の業務効率が格段に向上します。小さなストレスの積み重ねを減らすことが、生産性全体の改善につながります。
顧客満足度の向上と売上貢献
顧客向けシステムでUXを高めると、利用者がサービスを快適に感じ、リピーターや口コミの増加を促します。結果として、売上や戦略目標の達成率が向上します。
自身のUXスキルアップと提案力強化
eラーニングを通じて体系的に学ぶことで、UXのフレームワークや改善手法を自信を持って使えるようになります。若手社員にとってはキャリア形成に直結し、情報システム部門にとっては提案力のある人材として評価されるでしょう。
まとめ
ユーザー体験(UX)は、単なる使いやすさを超えて、業務効率や顧客満足度、さらには売上にまで影響を及ぼす重要な要素です。情報システム部門や若手社員にとって、UXを理解し改善できる力は、今後ますます求められていきます。
本記事で紹介したフレームワークやプロセスは、その一端にすぎません。実務に活かすためには、体系的に学び、実際に改善の流れを体験することが不可欠です。そこでeラーニング講座を活用することで、基礎から応用までを効率的に習得し、業務の成果に直結させることが可能になります。
「システムをもっと使いやすくしたい」「顧客に喜ばれる仕組みを作りたい」と考える方にとって、UXを学ぶことは確実に次のステップへの力となるでしょう。



