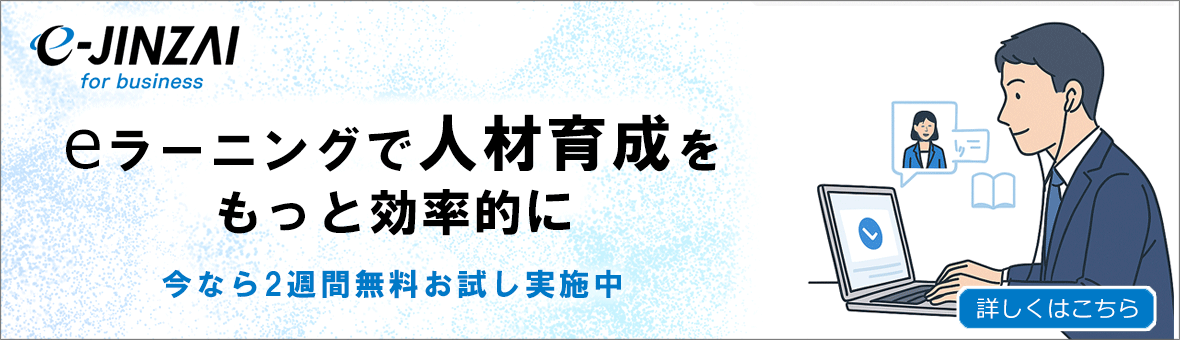伝わる言葉を選ぶ力:会社員のための言語化トレーニング

仕事の中で「なんとなく伝わっていると思った」「うまく説明できなかった」と感じたことはありませんか?
たとえば、上司に課題を報告したつもりが温度感が伝わらず放置されたり、部下に指示を出したはずがうまく実行されなかったりと、「伝わらない」ことが原因でトラブルやストレスが生まれる場面は多くあります。
こうした行き違いの多くは、「言語化力」の不足から起こります。
頭の中にある思いや考えを、相手が理解できる形に落とし込む力が不十分だと、誤解が生まれやすく、チーム内の連携にも支障をきたします。
ビジネスパーソンにとって、言語化とは単なるスキルではなく、信頼関係や成果に直結する重要な能力です。
⇒ 社会人のコミュニケーションを学ぶなら『e-JINZAI for business』
目次
- 言語化が上手い人とは?
- 上司に「問題意識」が伝わらないときに起こっていること
- 部下に「意図」が伝わらないのはなぜか
- 言語化力を高めると何が変わるのか?
- 言語化トレーニングの基本ステップ
- まとめ:言語化は一生使える“対話の筋トレ”
言語化が上手い人とは?
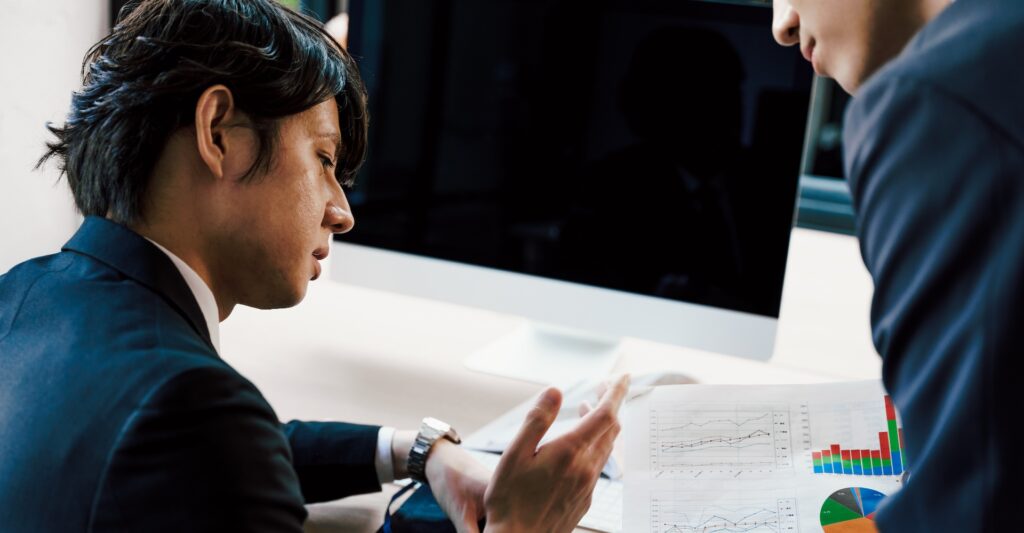
言語化が上手い人は、決して難しい言葉を使っているわけではありません。
むしろ、相手の理解を意識して、誰でもイメージしやすい言葉で伝えることに長けています。
「何が問題なのか」「なぜそう考えたのか」「どんな結果を期待しているのか」など、自分の思考や感情を整理し、相手が受け取りやすい形で説明できるのが、言語化がうまい人の特徴です。
また、言語化が得意な人は、「わからない」「迷っている」といった感情ですら、正直に言葉にする力を持っています。あいまいな表現や沈黙でごまかさず、自分の状態を適切に共有することができるため、結果的にコミュニケーションが円滑になります。
上司に「問題意識」が伝わらないときに起こっていること
「このままだとまずい気がする」「方向性が違うと思う」——こうした感覚はあっても、それをうまく言葉にできないと、上司には伝わりません。
「なんとなく危なそうです」と言うだけでは、抽象的すぎて、上司は何を判断すればいいのか分からない状態になります。
重要なのは、「なぜ危ないと思うのか」「どのような影響が出るのか」「具体的にどう変えたいのか」といった要素を整理して言葉にする習慣を持つことです。
たとえば、「〇〇の業務が遅れており、このまま進めると□□の納期に影響が出そうです。△△のような対応が必要ではないでしょうか」と言えるだけで、状況が一気に共有され、建設的な話し合いが可能になります。
部下に「意図」が伝わらないのはなぜか
逆に指示を出す立場に立つと、「ちゃんと言ったはずなのに、どうしてやってくれないの?」と感じる場面があります。
その原因は、言葉に「背景」や「目的」が欠けているからかもしれません。
たとえば「来週までにこの資料まとめておいて」とだけ伝えると、部下は「なぜ急ぐのか」「何を重視すればいいのか」が分からず、期待外れのアウトプットになってしまうことがあります。
「来週のプレゼンに使うから、読み手がパッと見て理解できるようにまとめてほしい」などと、“目的”と“意図”を言葉で補足するだけで、行動の精度が格段に上がります。
言語化力を高めると何が変わるのか?

言語化力を高めることで、コミュニケーションのズレが減り、無駄な確認作業やトラブルを未然に防げるようになります。
また、自分の考えや立場を明確に表現できることで、社内外での信頼や説得力も増し、仕事の成果にも直結します。
さらに、自分の感情や状態を言葉で説明できるようになると、ストレスの軽減にもつながります。
「なんとなく疲れている」ではなく、「複数の案件を同時に抱えていて、集中力が落ちている」と言えれば、適切な対応も取りやすくなります。
言語化トレーニングの基本ステップ
「うまく説明できない」「なんとなくは分かっているけど言葉にできない」——そんな悩みを解消するためには、日々の思考を“見える形”にする練習が大切です。言語化力は、意識してトレーニングを積むことで誰でも鍛えることができます。
ここでは、ビジネスシーンですぐに実践できる3つの基本ステップをご紹介します。
1. 曖昧な感覚を「具体的な言葉」に変える
最初のステップは、「もやもや」「違和感」といった曖昧な感覚を、具体的な言葉で表現する練習です。
たとえば、「この資料、なんか分かりづらい」と思ったときには、「構成が論理的につながっていない」「専門用語の説明が不足している」と細かく言い換えてみることがポイントです。
日常の中で湧き上がる感情や気づきを、「何が、なぜ、どこでそう感じたのか」という視点で分解して言葉にしてみる癖をつけましょう。
■ 感じたこと(そのまま)
この企画、なんかピンとこない…
■ 自分用メモ:なぜそう思った?
・ターゲット(20代社会人)のニーズにマッチしていない気がする
・メインの訴求ポイントが曖昧で印象に残らない
・他社と差別化できている点が見えにくい
■ 言語化してみたコメント案
「この企画、20代の社会人にとっての“メリット”が伝わりにくく感じます。比較対象があまりないので、もう少し具体的な事例や数字を入れて、違いを明確にしたほうがよさそうです。」
2.「目的」と「理由」を常にセットで話す
言語化が苦手な人ほど、行動だけを伝えてしまいがちです。
「やっておいてください」ではなく、「明日の会議で使うので、この資料を今日中にまとめてほしい」といったように、“何のために”それをお願いするのかを明示することが大切です。
理由を添えることで、相手が納得しやすくなり、指示や提案の伝わり方が大きく変わります。
■ 指示したい内容
「資料、今日中に出してほしい」
■ 自分用メモ:なぜ?何のために?
・明日9:00から部長への報告がある
・前回の報告で指摘された点を改善したことを見せたい
・できれば今晩チェックもしたい
■ 言語化してみたコメント案
「明日朝一で部長に提出する資料なので、今日中に出してもらえると助かります。前回の指摘事項を反映したところがポイントなので、仕上がりを一度確認させてください。」
3. 話す前に、一度「書いて」みる
頭の中だけで整理しようとせず、いったん紙に書き出してみることで、言語化の精度がぐっと高まります。
メモでも箇条書きでも構いません。話したい内容や伝えたい結論を、文字にして視覚化することで、論点のズレや飛躍にも気づきやすくなります。
特にプレゼンや会議発言の前などは、要点を「ひとことで言うとどうなるか」を意識してまとめてみましょう。
■ 相談したい内容
「今のタスク管理のやり方、見直したい」
■ 自分用メモ:構造化して書いてみる
1)課題:
- 現在の進捗管理がExcel+口頭なので属人化していて分かりづらい
- メンバー間で情報の共有漏れが起きている
2)理想:
- チーム全員がリアルタイムで確認できるようにしたい
- タスクの期日や担当が一目でわかるようにしたい
3)提案:
- Trelloなどのツール導入を検討したい
- 週1の振り返りでタスクレビューの時間を設ける
■ 言語化してみたコメント案
「今のタスク管理方法だと、進捗が把握しづらく属人化しているように感じます。ツールを使って見える化することで、チーム全体の連携がスムーズになると思うのですが、導入を検討してもいいでしょうか?」
まとめ:言語化は一生使える“対話の筋トレ”
言語化は一朝一夕で身につくものではありませんが、日々の仕事の中で意識して取り組むことで、確実に鍛えることができます。
何をどう伝えれば相手に届くのか、自分の考えや違和感をどのように形にするのか。そうした言葉の選び方が、ビジネスパーソンとしての信頼や評価につながっていきます。
上司と円滑にやりとりをしたい、部下との意思疎通を改善したい、自分の考えをもっと明確に伝えたい——
そんな時こそ、言語化力に目を向けてみてください。日常のちょっとしたトレーニングが、コミュニケーションの質を大きく変えてくれます。
業務を円滑に進める「コミュニケーション研修」
言語化能力はビジネスパーソンにとって重要なコミュニケーションスキルのひとつです。多様な働き方が進む今、年齢や役職を問わず、互いに尊重し合うコミュニケーションが求められています。ビズアップ総研のコミュニケーション研修では、3つの新しいコミュニケーションスキル「リバースメンター」「リモート・コミュニケーション」「アサーティブコミュニケーション」にスポットライトを当て、詳しい解説を行います。
2週間無料お試しはこちら